例えば,「吉野川」の交流学習のまとめは,次のような催しを行った。
(a)交流学習の様子や作文の展示
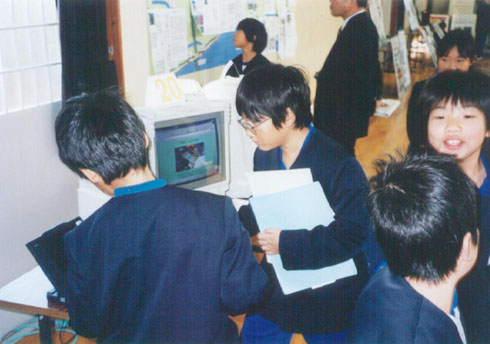
▲柿原小の展示会場でHPで情報検索
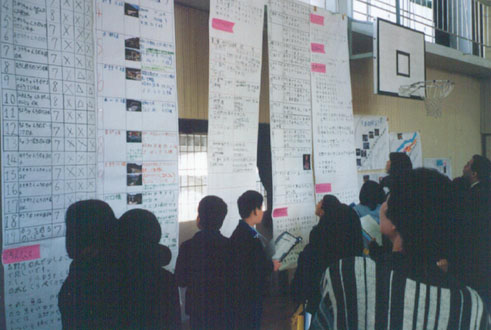
▲豊永小の発表作品の前で情報交換
児童・生徒のモチベーションを保ち,また高めることが必要である。このための手段としては,相手校の学習成果を見てその良さを認め合ったり,自分たちの学習に取り入れるなどの模倣を促進したい。また,交流の中から新たな課題を発見するなど,児童・生徒の興味・関心の方向を常に敏感にとらえる姿勢が必要である。
自分たちの学習を交流校に知らせることから始まる。具体的な方法としてはTV会議の実施やメールの交換,インターネットホームページでの公開などがある。交流相手校との距離に課題はあるが,相互訪問,オフラインミーティングなどを実施して実物を持ち寄る,発表し合うなどの方法も考えられる。相手の顔を見ながら学習成果を確かめ合うことは子ども達にとって刺激になる。また「また,いつか会える」という希望を持ち,以後の学習にも励みにもなる。
相手校の学習成果を見て,自分たちがあまり意識していなかったテーマについて,自分たちも調べてみたいという感想を持った児童がいた。また,相手校のまとめを見て,今まで気づかなかった自分たちの校区の特徴について気づいたり,同じテーマでも違った見方があることに気づいた子もいた。
こうした気づきを通して,子ども達は,相互に事前にテーマのすり合わせを始め,学校間を越えたグループを編成し,交流学習を進めていく可能性が生まれている。
まとめ方も電子掲示板「イントラバケッツ」にまとめた内容を,大きくプリント出力したり,用紙や模造紙に表や地図で表したり,また「次は,別な方法でまとめてみたい」という意欲を持った子も出てきて,さまざまな制作物ができあがる。
交流校の学習成果を認め合うことだけでなく,相手校から送られたビデオレターやメールへ返信し,さらにそれを受けてコメントしていくなどの具体的な手だてが必要である。これを継続していくことで,交流したクラスが「相手」でなく「仲間」という意識が生まれ発展していくだろう。
遠隔交流学習を展開するには,それぞれの学習グループが,その探究過程をどのようにまとめ行くかの手だてと工夫が重要である。特に,子ども達には,多様なメディアを,その特性に沿って活用させながら,課題設定から情報の収集,加工・整理,再取材,再整理,発表の見通しを持った計画的な実践を進めさせたい。
地理的に離れた学校が交流して学習を進めていくためには,情報を共有する手段として,学習したことをデジタル的にまとめる必要がある。今回の交流学習では,集めた画像や映像と,それについてまとめた文章を記録するツールとして「イントラバケッツ」を使用した。イントラバケッツを使ってHTMLの形式でまとめることによって,各グループのプレゼンテーションに使うことができ,各グループのまとめを集めて共同ホームページを作ることも可能になる。コンピュータを使ってデジタル的にまとめることは,次年度へ学習を積み重ねていくためにも必要なことである。さらに校内で他学年の学習と関係づけることにも活用できる。ただしホームページにまとめてインターネット上で公開する場合は,プライバシーや著作権について万全な配慮が必要である。
学習の成果をお互いに,あるいは保護者,地域,他学年の子ども達に発表するためには,掲示や提示のできるまとめが必要である。
例えば,「学習成果発表フェア」の開催を計画して,それぞれの学習グループごとに学習のまとめを発表し合う方法もある。
例えば,「吉野川」の交流学習のまとめは,次のような催しを行った。
(a)交流学習の様子や作文の展示
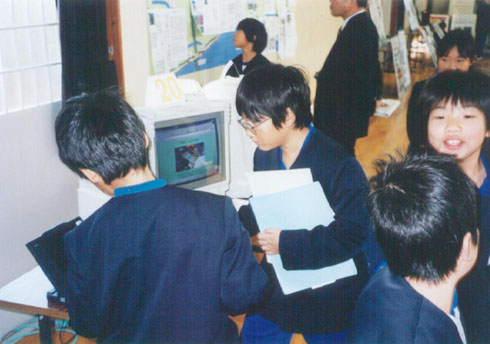
▲柿原小の展示会場でHPで情報検索
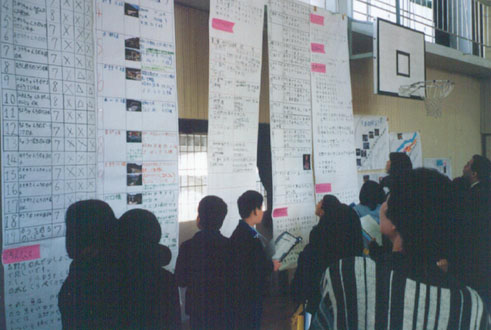
▲豊永小の発表作品の前で情報交換
(b)吉野川での活動の展示
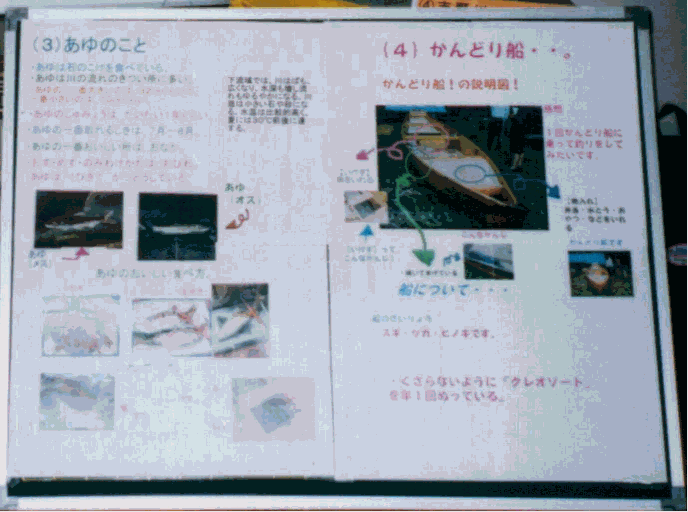
▲鮎の生態・鮎漁「かんとり舟」のまとめ
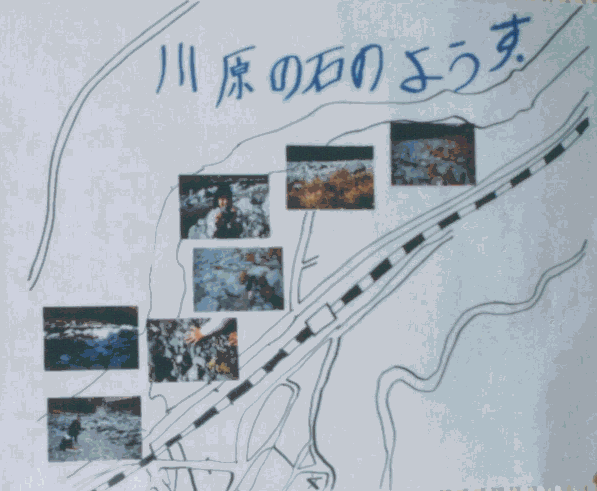
▲川原の様子のまとめ
(c)イントラバケッツでまとめた学習の展示
(d)体験コーナー(石に絵を描く・竹で工作・吉野川の植物で押し花作り)の展示
(e)吉野川マスコットキャラクターを仕上げる。
吉野川をきれいに,水を大切にしようというパンフレットを作成し,それに賛 同してもらえる方に色紙の用紙に署名をしてもらう。署名してもらった色紙を,線書きのマスコットキャラクターに貼り,キャラクターを完成させていく。
(f)吉野川俳句(標語も可)を作ろう
吉野川をたたえる,または吉野川の思い出などを俳句や和歌などにまとめる。子どもの場合は,吉野川に関する標語の形になってもよい。
来ていただいた方にも作ってもらう。(g)吉野川クイズコーナー
吉野川を知ってもらうためにクイズを出して考えてもらう。
ネットワークによる交流学習は,単年度に終わるのではなく,年度をまたいで実施できると,いっそう効果的である。ネットワークは横に広がるだけではなく,年次や学年といった縦にもつながることが望ましいと考えよう。
しかし,同じことの単なる繰り返しではいけない。学習の継続はマンネリズムとは異なることを肝に命じる必要がある。真の継続は,繰り返しの中に発展があってこそである。ネットワークにおける交流を継続させるために,次のような計画を立てて,実行するとよい。
まず,子ども達が共有する課題,学習テーマを再考し,そのレベルアップを図るとよい。交流の必然性,共同への価値が学習素材に大きく依存するのは万人が認めるところである。だから,交流の初年度の素材をどう広げていくか,いかに深めていくかが,交流学習継続・発展の決め手になる。
例えば,河川を題材とする場合には,自然,歴史,暮らしなど,それに迫るアプローチは多様であるから,2年度目以降に,最初の年度に扱えなかった視点を導入するとよい。また,最初の年に子ども達の活動が河川の汚染状況に関する実態調査にとどまっていたなら,次は改善への努力を学習の主柱に据えるのもよかろう。さらには,自分たちだけの調査や行動に終始するのではなく,他者への発信活動,普及・啓蒙活動へ展開するのも,テーマをステップアップするひとつの視点となろう。
新しい情報技術の利用も,子ども達の交流の継続・発展を促す。
現段階では,子ども達のネットワークへの関わりは,そこで必要とされる能力によって,いくつかの層に分かれている。最も簡単なのは,電子メールの交換である。あるいはホームページの閲覧である。交流学習の最初の年では,子ども達がネットワークの利用に慣れていないことが多く,彼らのネットワーク利用の術もそうした方法に限定されがちである。しかし,ネットワークを通じて繰り広げられる共同作業はそれだけにとどまるものではない。電子掲示板の利用やサイトの共同開発などの仕事もネットワークならではの営みである。高度情報通信社会を生きる子ども達には,そうしたコミュニケーションもぜひ体験してもらいたい。
だから,子ども達のネットワーク上での交流では,その手段を可能な限り多様化すべきである。換言すれば,ネットワーク上で展開されるコミュニケーションの方法は,交流の時期や相手によって,使い分けられたり,組み合わせて利用されたりすることが望ましい。それが,子ども達の追究意欲や仲間意識を,いっそう高めてくれるだろう。
ネットワークによる交流学習は,一種の学習コミュニティの形成を意味する。しかも,できるだけ広範囲に及ぶことが望ましい。だから,交流の継続・発展が新たな学習のパートナーを見つける方向へ進むよう,教師は学習を計画・実施すべきである。
例えば,ある年度に同一河川流域内の学校がオンライン上で集った場合なら,次の年には,彼らが,他地域の子どもともコラボレーションを繰り広げられるとよい。もちろん,他地域の学校,子どもとの交流学習には,ひとつの地域の子ども間で進める場合に比べて共通項が少なくなるから,その過程にもさらに工夫が必要にはなる。しかし,他地域との比較によって,自分たちの取り組みを評価したり,相対化したりすることが可能になるという利点は大きい。
交流の相手が,外国の子ども達にも広がるとなお好都合である。言葉の壁を心配する向きもあろうが,例えば,自動翻訳システムなどの先端技術を導入することによって,それらはある程度カバーできる。それらによって,今や小学校段階においてさえ,交流相手を外国に求める方向の見通しは明るい。
なお,交流学習のパートナーの広がりはなにも地理的・空間的なものに限られるわけではない。異世代がネットワーク上で交流を展開するのも,生涯学習時代にふさわしい姿である。小学生と中学生の意見交換,子どもと専門家の共同作業など,はその代表例である。たとえ同一地域内であっても,異校種とか異年齢といった視点で学習のパートナーを拡張し,子ども達と他者のコミュニケーションやコラボレーションを質的に高めることが可能である。
交流学習の成果を,校内のいわゆるイントラネット上に,交流校間とのイントラネット上に,さらに,インターネット上にホームページを構築して,成果を共有することが期待される。
調べたことを文章と画像,音声等を用いて,子どもHPを作る活動も,情報教育の具体的な実践の場を提供でき,学習の意欲と継続への誘因となる。
合わせて,電子掲示板を利用すると,文字中心ではあるが意見の交換もホームページ上で可能となる。また,各校で作成したサイトをまとめてひとつのホームページにすれば共同ホームページも構築できる。
複数の学校が必要なときに必要とする情報をインターネットを介して,お互いに確認することができる。ただ,一度に成果をまとめるという形よりも,各交流校がさらに詳しく発表したい内容を掲示板やホームページを利用して継続的に行うのが好ましい。
留意点としては,インターネット上への公開に際しては,グループの子ども達の顔や氏名などを除くこと,非公開のページにするかということも検討する必要がある。
学校に交流学習を定着させることを考えるときに,交流を続けるための環境作りという面と,交流を続けていく人作りという面の2面から考える必要がある。さらに,児童・生徒からと教師からの二つの視点からも考えていく必要がある。これらを考慮してまとめると次のようになる。
交流学習の効果を高めるためには,交流の方法や活動の方法を広げることが重要である。そのためには,コンピュータの整備が重要な要素となる。
例えば,交流をより効果的にするためには,校内LANが組まれ,インターネットに接続できるコンピュータが,クラスの最大人数分設置され,一人1台ずつ利用できることが望ましい。そして,児童・生徒用の情報交換のためのアプリケーションソフトが導入されていることが望まれる。さらには,TV会議のシステムもぜひ整備したい。
以上のように,よりよい環境を整えることが,交流を容易にし,より効果的な交流を実現することにつながるとともに,児童・生徒に交流学習の楽しさを味わわせることになる。
児童・生徒が交流学習へ積極的に取り組めるようにするためには,児童・生徒が学ぶ楽しさを味わえるような学習を,教師がいかに構成できるかが基本である。それに併せ,児童・生徒の意欲と交流の技術を高めるような方策をとることが大切である。そのためには,次のようなことを考えていきたい。
1) 児童・生徒の情報メディア活用の技能を高める。
児童・生徒の情報メディア活用の技能が高まれば,それを生かそうとする意欲も高まるし,活動の幅が広がる。学年に応じて,育てたいメディア活用の技能を明確にした指導計画を作成し,計画的に高めていくことが必要である。
2) 児童・生徒の中で学習成果を継承させる。
実践の中で,上級生の児童が,下級生の児童に対して,交流学習で学んだことを教えさせたり,パソコンの使い方を指導させたり,また,下級生の学習テーマを,上級生が一緒に学習する場を設ける。
これらは,下学年の児童達に交流学習の一端に触れさせることになり,学習の成果を継承する事につながる。そのために効果的な方法として次のようなものがある。
(a)異学年どうしの共同学習を構成する。
(b)交流学習題材の一部を共同調査する場を設定する。
(c)上学年児童・生徒が下学年児童・生徒にコンピュータの使い方など,交流学習に役立つ学習方法を教える場を設定する。
(d)学年内だけでなく,他学年や学校全体に学習成果を発表する機会を作る。発表会では,学習内容だけでなく,交流学習の有効性や「学習してよかった」という気持ちも合わせて発表したい。
(e)学習成果を蓄積し,学校内共有の学習データベースを構築する。
せっかくの学習成果も,その年度だけの1年で片づけてしまっては,次の年度も1からのスタートになってしまう。前年度までの学習の成果は,誰もが見られるように整理・保管し,閲覧できるようにしておくことが重要である。学習してまとめたことは,次の学年の児童・生徒達の有効な資料となり,学習の手引きとなる。
学習成果の電子ファイル化も,有効な方法である。電子ファイルかとは,調べたことをWeb化したり,児童・生徒用のソフトを使ってデータベース化したりすることである。ここまでできなくとも,紙にまとめたものをデジタルカメラで撮影し,ファイル化しておくだけでも,学習成果を継承していくうえで有効である。
また,学習成果というのは,調べてまとめたものだけではないことも考えていきたい。学習している最中に気付いた学習方法や技能も,大切な学習成果である。
例えば,
(a)実験器具の使い方
(b)コンピュータの生かし方
(c)ビデオの撮影のポイント
(d)TV会議をするときの留意点
等である。
これらもまとめておけば,後輩にとって大変有効な情報になる。後輩達がこれらを見ることは,先輩からアドバイスを受けたことと同じであり,それを生かしてより質の高い学習を進めることができる。そして後輩達は,一歩進んだ学習成果を,新たな情報として学校のデータに付加することができる。こうして,学習成果が深化しながら,年々,後輩に継承されることにより,交流学習が学校に定着していく。
また,これらは,指導する教師にとっても有効な情報になる。
教師間でも,交流学習のノウハウを継承していかなければ,学校全体に継続していくことはできない。つまり,校内のすべての教師にも,交流学習の意義・方法・成果を理解してもらえるようにすることが大切である。そのためには,児童の発表会を見ることにより,児童の学習成果を通して,実際に成果を感じ取ってもらうことが一番であるが,その他に,次のようなことを進めていきたい。
1) T・Tを意図的に導入して理解者を増やす。
T・Tを積極的に導入し,多くの教師に,経験豊かな教師が支援しながら交流学習を経験させ,交流学習のよさを体得させ,自分で交流学習を行う意欲と自信を持たせる。
2) 校内研修会の実施理解者を増やす
授業研修や成果発表会などの校内研修を実施し,交流学習のノウハウを教師間に広める機会を作る。
これらのことをよりうまく進めるためには,前にも述べたようにコーディネータが必要である。できれば,コーディネータは,市町村で学校ごとに配置することが理想だが,それがまだ望めない現在では,少なくとも学校から他の研修会や大学の講座等に派遣し,校内のリーダーを養成していく必要があろう。
成果の公開・啓蒙活動は,交流学習に従事した子ども自身にとって,非常に重要な活動となる。というのも,ひとつは,他者への発信を通して,子ども達が自己の学習を内省することができるからだ。
異なる学校の交流学習は,交わりの密度が増すと,その学習共同体が閉鎖的になる危険性をはらんでいる。だから,成果の公開・啓蒙活動のもうひとつの意義は,それを通じて,ネットワーク本来の持ち味である,開放性を実現できることにある。
それゆえ,次のような方法で,学習成果の公開・啓蒙活動を広く展開できるとよい。
最も身近な公開・啓蒙活動は,それぞれの学校の下級生や上級生に対して,学習成果を発信することである。学校の仲間に向けての発信であるから,子ども達も肩肘をはらずに,自らの学習の過程を語り,その成果を伝えることができる。
もちろん,それにも工夫が必要である。例えば,下級生に対しては,言葉を選ぶ必要がある。学んだこと,分かったことをそのまま伝えようとしても,難しい言葉が続いたら,聞き手は理解してくれないだろう。興味さえ示してくれなくなるかもしれない。
また,形式にも配慮しなければならない。成果の公開・啓蒙場面でよく用いられる形式は,発表会である。しかしながら,発表会だけでは,学習の過程や成果を聞き手に理解してもらうことは難しい。情報を瞬時にしてつかまなければならないからである。だから,発表会に加えて,学習の実際をじっくりと,時間をかけて眺めることができるような仕組みを整えるとよい。例えば,校内に展示や掲示形式のゾーンを設けて,成果を示すこともできるし,校内のホームページ内に交流学習に関するサイトを構築することもできよう。もちろん,それらを組み合わせると,いっそう効果的であることは言うまでもない。
なお,学校内における成果の公開・啓蒙活動には,学習の伝承という側面もある。すなわち,下級生による学習の継続・発展のための布石としての性格を有していることも補足しておこう。
ネットワークにおける子ども達の交流学習は,多くのケースで,地域の人々との交わりを基盤としている。それぞれの学校で,子ども達は,地域人材に聞き取り調査を展開したり,そうした人々のインストラクションのもとで活動を繰り広げている。お世話になった人々へのお返しとして,あるいは学習成果に関する評価を受けるために,地域に向けて学習の過程や成果を公開することは大切な作業である。
その方法であるが,学校内における発信作業と同じく,直接的なものと間接的なものに分かれよう。直接的な方法としては,社会教育活動との連携が効果的な手段であろう。例えば,地域のボランティア団体が催す会合での発表,活動への参加などである。また,間接的な方法としては,ポスター等の制作と掲示,新聞の発行,そしてホームページの作成による情報の発信などを試みるとよい。特にネットワークによる成果の公開・啓蒙活動は,学習の過程や成果を受け手にゆっくりと味わってもらえるし,その後,フィードバックをもらうことも可能であるから,最も効果的である。
ネットワークを舞台とする営みは開放性を前提としているので,その成果は,広く社会に提供できることが望ましい。したがって,交流学習の成果も,社会一般に対して広く公開されるべきである。
そのための手段は,もちろん,ネットワークである。理想的には,参加校の成果が一堂に会する形で,すなわち共同のホームページが開設されて,成果の公開・啓蒙が実現するとよい。子ども達の合同会議の模様が紹介されたり,彼らが作成した共同宣言が示されたりすると,他地域の学校の子ども達の交流学習への参加も促されるだろうし,大人たちの取り組みの刺激にさえなるだろう。
なお,以上のような学習過程の紹介,学習成果の公開,それを通じた啓蒙活動は,学習の最後に実施するものだと思いこまない方がよい。いやむしろ,学習の中間段階でも試みられる方がいい。情報の受け手から子ども達へのリアクションがあれば,児童・生徒の活動の見直しが喚起され,学習の軌道修正が施されるからである。ネットワークを通じた交流学習の成果は,常に進行形で示されるべきである。
地域に交流学習を定着させるためには,まず学校で交流学習が継続され,その成果があがっていくことが必要である。そのうえで,保護者,地域の人々,地域の先生方,教育行政に携わる方々に,成果や展望を理解してもらうよう働きかけていくことが,地域に交流学習を定着させるとにつながる。
1) 交流学習の内容や成果を公開する
(a) 授業参観や成果発表会を実施する
学校の様子を保護者に知らせるために,学校通信や学年通信等を家庭に配布している学校は多いが,交流学習の様子もそれらを利用して知らせるべきである。また,交流学習の場面を実際に参観できる機会を作ることも必要だと思う。やはり,「見ると聞くとは大違い」であり,「百聞は一見に如かず」である。見ることにより,交流学習のよさを肌で感じてもらうことができるはずである。
学習の成果発表を「学習成果フェア」の形で実施し,保護者はもとより,地域の方や市町村内の教職員・一般の方々にも学習成果を広く公開することは,地域の人々に交流学習のよさを理解してもらう上でも有効であるし,児童達のモチベーションを高める上でも有効である。
(b) ホームページを使って交流学習の様子を公開する。
ホームページを利用して交流学習の学習内容や成果を公開すれば,保護者だけでなく,より多くの人々に交流学習を理解してもらえ,地域に交流学習を定着させることにつながる。そして,さらにこの効果を高めるためには,できるだけ児童・生徒が自分でつくったものをホームページに掲載するのがよい。なぜなら,児童・生徒からの生の情報は,大人に感動を与えるからである。
しかし,これを実現するためには,児童・生徒が容易にホームページを作成できるようにすることが必要であり,そのためにも,児童・生徒用のホームページ作成ソフトの導入が切に望まれる。
2) 交流学習への参加を促す
保護者や地域の人々に,交流学習に参加してもらうことも,交流学習のよさを理解してもらう上で有効である。参加してもらう一つ目の方法は,(1)で述べたように,学習の状況や内容を公開しながら,それについて,協力者を広く募集し,児童・生徒の指導者(教育ボランティア,ゲストティーチャー)として参加してもらうことである。
柿原小では,児童が調べ学習を進める際,保護者にも必ず聞いて調査することを条件にした。このような方法も,保護者の理解を図るために,有効であろう。
保護者や地域の人々に交流学習に参加してもらう二つ目の方法としては,子ども達とともに学習する場を設定することが考えられる。保護者が指導者になるというのではなく,保護者も一緒に学習を進めていくという形態のものである。これは,保護者の誰もが参加でき,保護者も楽しく学ぶことができるので,交流学習の理解を広めるのに有効な方法であると考える。
さらに,今後は,情報活用環境の進展と共に,保護者や地域の人々を巻き込んで共同学習のためのメーリングリストを開設する事も有効な方法となるであろう。
学校長を通じて,教育委員会の方々や教育長・市町村長に授業を参観してもらうように働きかけることも必要である。これらの方々に授業参観していただき,交流学習のよさを理解してもらうためである。これらの方々に交流学習のよさをわかっていただければ,他校や地域の人々に,その良さをPRしてもらえるはずである。行政に携わる立場の方からの紹介は,影響力が大きく,地域の人々の交流学習への関心は,一層高まることであろう。
また,これらの方々の理解を得られていれば,効果的な交流学習を実施するための学校の環境整備についても便宜を図っていただける可能性が高まる。
実際にT校では,教育委員会の指導員による参観が実現し,その成果が認められたことにより,今後もTV会議システムを継続して利用できる環境整備が実現することになった。
マスメディアを通しての宣伝効果は大きい。
今回実践された交流学習は,写真入りの記事としてK地方新聞に掲載された。また,K新聞には,子ども記者が書いた記事が,内容によって新聞に掲載されるという子どもHPを設けている。今回の交流学習について児童が書いた記事が3回も掲載されて,反響を呼んだ。これらは学校で広報活動するよりも,地域の方々にPRするという意味では,効果が大きい。
交流学習は,普段,経験できない多くの児童との共同学習を実現し,子どもに多くの効果をもたらすことが報告されている。特に,都市部から離れた学校や,小規模の学校では,普段,どうしても情報や交流が狭く学習が固定しがちになってしまうが,交流学習はそれらを補ううえで大変効果的である。子どものよりよい成長のために,地域をあげて交流学習を支え,継続できるようにしていくことが必要なのである。そのためには,地域の人々の理解を広く得られるように,実践を続け,子どもの変容を示し,地道な広報活動を積み重ねていかなければならないのである。
ただし,外へアピールすることを意識するあまり,形を作ることに目を奪われ,子どもの意識や関心等をおろそかにすることは,避けなければならないことを、最後に述べておきたい。
以上
◆協働企画「同一河川流域内学校交流学習」研究開発委員
委員長 水越 敏行 関西大学教授・大阪大学名誉教授
副委員長 木原 俊行 岡山大学助教授
委 員 森田 充 茨城県つくば市立吾妻小学校教頭
委 員 中川 斉史 徳島県三加茂町立三庄小学校教諭
委 員 長尾賀代子 徳島県三加茂町立三庄小学校教諭
委 員 鶴田眞由美 徳島県三加茂町立三庄小学校教諭
委 員 吉岡 健一 高知県大豊町立豊永小学校校長
委 員 難波 成行 高知県大豊町立豊永小学校教諭
委 員 小倉 信之 徳島県吉野町立柿原小学校教諭
委 員 瀬尾美保子 徳島県吉野町立柿原小学校教諭
委 員 岡田 八重 徳島県吉野町立柿原小学校教諭
委 員 二宮 典子 NTT西日本会社マルチメディア推進部
委 員 原田 静男 (財)コンピュータ教育開発センター
委 員 貞本 勉 (財)才能開発教育研究財団
委 員 秋山 久義 (株)学習研究社・教育ビジョンセンター
◆謝 辞
今回のEスクエアプロジェクト協働企画「同一河川流域内学校交流学習」研究開発を推進するに当たり,実践校をお引き受けいただいた
高知県大豊町立豊永小学校校,
徳島県三加茂町立三庄小学校,
徳島県吉野町立柿原小学校,
の校長先生はじめ,教職員の方々,また,児童のみなさん,ご家庭のみなさんに心から御礼を申し上げます。
またこの研究推進に,多面にわたりご支援いただいた各実践校所轄の教育委員会,各地域の教育ボランティアの方々に感謝申し上げます。
研究開発委員長
|
|
次へ → |