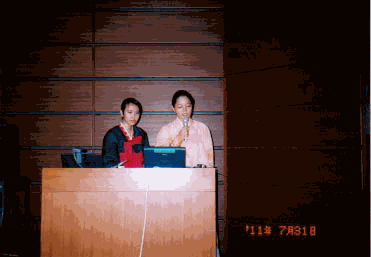
1994年よりCECの主催する100校プロジェクトに参加することができた。
1992−3年の間は1台の端末から内線電話を通して東京のISPまで接続し、電子メールを行っていた。通信速度も2400bpsのものであった。
それでもインターネットの電子メールの運ぶ異文化の風に教室はどよめいた。
当時から比べると環境は格段とよくなった。
第一ステージとして100校プロジェクトへの参加があった。64kの専用線が提供され、24時間アクセス可能となった。
フィンランドなどの学校とリアルタイムチャットをたのしみ、核の問題などを話し合ってきた。
1997年からは新100校プロジェクトがさらに発展的に展開され通産省の「高度情報化」の施策は現場に広がっていった。
一点の炎も荒原を焼き尽くすの言葉通り、すべての先生、生徒がインターネットの機能、働きについて理解するまでになった。2001年にはすべての学校にインターネットが導入される施策が打ち出されるまでになっている。高校においては2003年より新しいカリキュラムが実施される。このような動きはまさに100校プロジェクトの葛藤の第1波の後に続く第2波ということもできる。
このような大きな歴史的な転換の中、「国際化」「情報化」が高校レベルにおいては情報教育推進のための両輪の輪である。
小学校レベルであれば国内の離れた地域、さらに形態の異なる地域との交流が単元でも設定されており、そのようなインターネットの使い方がまず模索されるべきであろう。
しかし、高校レベルにおいては「英語」の日常的な利用の場、英文電子メールが「相手」に届くことが必要である。
このような状況をバックボーンに持ってこのプロジェクトに参加できた意義は大きい。
1999年は本校生徒にとっては大きな一年であった。
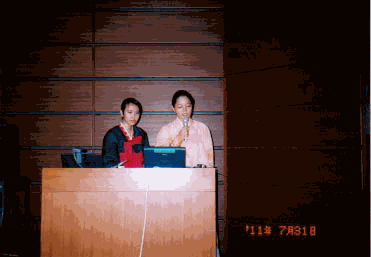
7月30日にCEC共催の「ワールドユースミーティング」に参加することができた。
これまで本校では国際コミュニケーションコースの生徒が主にプロジェクトに参加してきたが、今回は他のコース、情報処理科、会計科の生徒の参加が目立った。
これもインターネットの広がりと関心の深化であると思われる。
さらに夏には同じくCEC共催の「アジア高校生インターネット交流」に 参加することができた。生徒30名とともにアジアの地「ソウル」を訪れ、現地でのホームページづくりをおこなった。
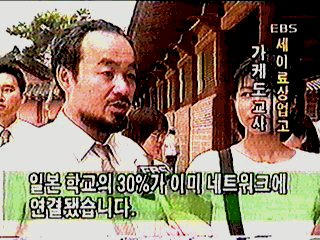 |
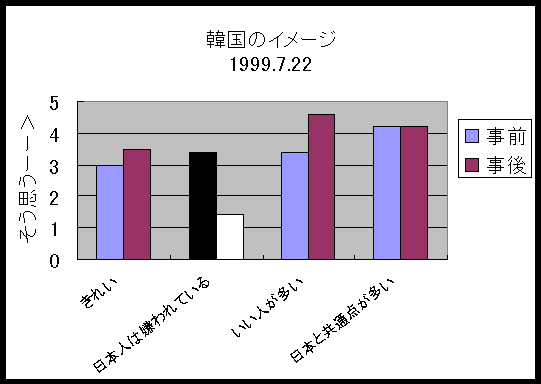 |
インターネット上でこれまで交流してきた国ではあったが「直接体験」は生徒のイメージを大きく変えた。
またこのことが以後の交流のバネとなっている。
これら一連のプロジェクトを経ながらさらに参加意欲と人数の増加を経ながらこのプロジェクトに参加することとなった。
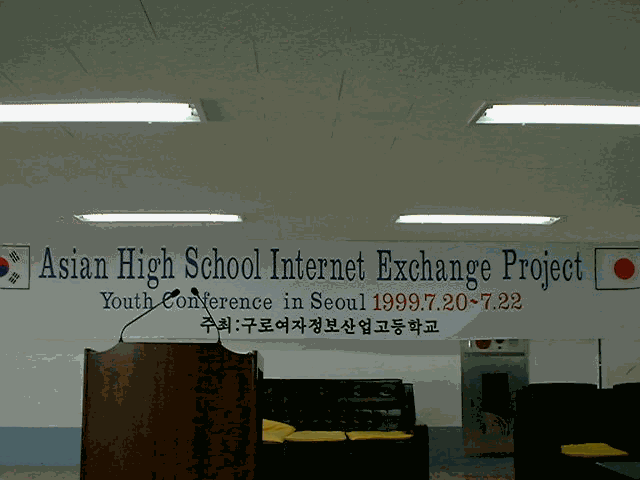
本校は1994年の100校プロジェクトによって設置された専用線を発展的に利用している。
当初64kであった接続も1998年秋に光専用線128kに切り替え快適な運営をしている。
DNS、MAIL、proxyサーバなどすべてSUNのOSで運用し24時間運用している。
SUNは難しいとの声もあるが、学校の運用は
授業で使う
セキュリティーを強化
メールアカウントの発行
チャット・CGIなど学校用のシステムの必要性
が重要である。
これらをクリアするためにはSUNのOSは必要なものであり、100校より貸与されたSUNマシーンは7年を経て未だに快適に動いている。
すべての教科での利用
本校は商業高校であるがすべての教科でインターネット利用の推進を中心課題としている。
事実、普通科の数学、国語の準備室にも光の配線がなされており、ノートのパソコンをつないでほしいとの要望が非常に多い。
日常的なサポートを心がけ全職員の利用を推進している。
生徒はこれまでの国際交流の先輩たちの活動を夢見てきた。
今年度は特にCECのサポートを受けながら、早稲田高等学院、神奈川大学付属高校との連携をとりながらプロジェクトを推進してきた。
生徒の意識の変容
本校は商業高校である。受験英語を苦手とする生徒が多い中、実際にCu-seemeなどのソフトで海外の大学、高校とのやりとりは「使う」体験と「通じた」という喜びをもたらす絶好の機会となった。
参加したI君は次のような文章を書いている。
生徒感想――――
――(英語と僕)&(学校の授業だけでは英語はしゃべれない)――
僕は前から英語の授業に興味がなく、英語が嫌いでした。「日本人は日本語だけで十分。英語は話せなくていい」と考えていたからです。なぜかというと、学校で英語を勉強しても国際交流の機会がなく、英語で会話することがないからです。しかも、高校になると英語が格段に難しくなり、会話をすることとのバランスが崩れていると思います。僕はCECのプロジェクトに参加して、英語は使わなければ身につかないこと、英語の必要性をすごく感じました。
交流校の国の人と話をしていると、英語が聞き取れず何を言っているのか、どのように答えればいいかわからない。単語を使って話したものの、自分の思っていることをうまく伝えることが出来なかった。自分の英語力のなさにとてもくやしく思いました。それから僕は英語を話せるようになりたい、そしていろいろな人たちと話をしてみたいと思うようになりました。そのために、これから英語を勉強しようと思いました。どうやって勉強すればいいのだろう?そこで役に立ったのが、電子メールでした。韓国のKimとKwangとメールの交換をしています。初めは読めない単語ばかりで、辞書を使って何とか訳していました。自分がメールを書くときも辞書を使いながら書いていました。何回もやっているとだんだん英語に対してなれてきて、読んだり、書いたりするスピードが速くなりました。
最近はキムとICQをやっています。ICQとは、相手のコンピュータがオンライン(インターネットにつないでいる状態)かどうかがわかり、オンラインであれば、リアルタイムでメールのやりとりができます。PHSや携帯のメール機能と同じようなものです。キムとはその日の出来事や音楽などについて話しています。しかも、英語でやりとりするのでとても英語の勉強になります。
英語を勉強して思ったことは、何事にもやる気が一番必要だということです。やる気さえあればどんなこともできると思います。これからも英語を話せるように努力して、このような国際交流の機会にもっと参加していきたいです。
このようになによりも海外につながったインターネットの線は生徒のモーティベーションを大きく育てている。
他校との連携
12月12日に名古屋において活用事例発表会が開催された。
その中で名古屋校の取り組みを本校生徒が発表した。
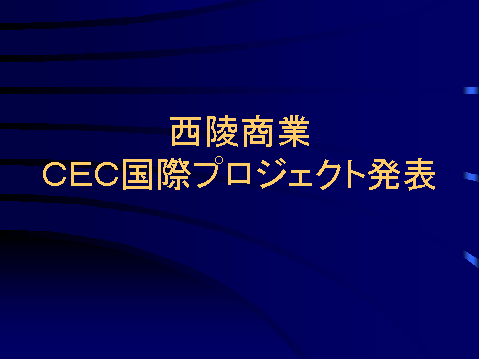 |
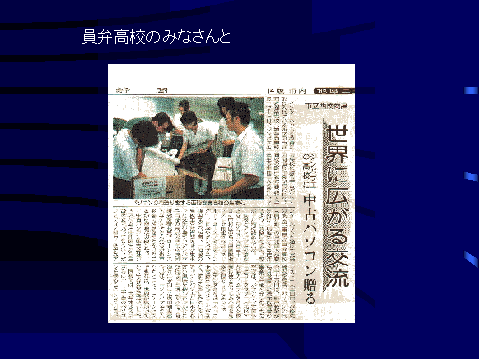 |
午後の発表の中で他校の生徒のプレゼンテーションに接し大きな刺激を受けたようである。
これまで継続していた生徒用メーリングリストst@seiryo.ed.jpを活用しイベントだけに終わることなくその後の情報交換を行った。このメーリングリストは主に高校の生徒間で行われた。
メール例
Reply-To: st@seiryo.ed.jp
To: st@seiryo.ed.jp
家田です。
>MLって名前だけだから、誰が誰なのか分かりにくいです
>(分かんなくていいのか)
>自己紹介に写真載っけませんか?ぼくたち準備できたら載せたいと思います。
>ご検討お願いします!ごめんなさい〜。挨拶が出来なかったから顔がわかんないですね。
実は、この前のために西陵参加者の自己紹介のHP(写真付き)を
つくったんですけど、まだサーバーに上げてないんです。
これから急いで上げようと思ってます。そのときは早稲田のみなさんのも
一緒にっておもってるんですが・・・。
そのことについてはまた連絡します。
ネットワークでの交流――直接会う――交流というこれまでのインターネット活用の体験が大きく働き、生徒の生活を豊かにしていった。
この会への参加の後生徒たちは次のような感想を寄せている。
|
生徒感想
|
名古屋市立西陵商業高等学校3年 吉澤朋子
1.大学の先生の話
普段では、滅多に会うことが出来ないような偉い方々の話を聞くことが出来て良い体験をさせていただきました。先生方のような人がいるからこそ、私たちの教育にパソコンが有効利用されることがわかりました。私たちは高校を卒業してしまうので、もう学校での教育を受けることはないけれど、これからの子供たちのために役立てていって欲しいと思います。もう少し遅く生まれていたら、小学校からパソコン教育を受けることができたと思うと少し悔しい気もしますが。
2.学校の先生方の実際に授業で活用した話
いろいろな先生方のお話を聞きましたが、一番印象に残っているのは員弁高校の先生のお話です。環境が整っていないにもかかわらず、生徒のために大変な努力をしてくれているのがすごく伝わってきました。ぜひ、最後までがんばっていただきたいなと思いました。
3.生徒の発表
東京校の皆さんの発表がとてもすばらしかったです。人数が多いとなかなかうまくまとまらないと言いますが、みなさんそれぞれが自分の仕事をこなしうまくまとまっていました。とても前日までがテストで会場に来る途中や会場で準備したとは思えませんでした。英語の発音が上手で感動しました。英会話を勉強している私としてはうらやましかったです。後から聞いたところによると帰国子女だそうで納得いたしました。
4.全体の感想
このような講話に初めて参加しましたが貴重な一日だったと思います。私も名古屋校として研究発表に参加できていたらと悔やまれてなりません。お偉い方々が影戸先生の名前を講話の中でずいぶん出されるのと聞いてあらためて先生のすごさを実感しました。私はもう授業を受けることは出来ないけれど、これからもどんどんコンピュータを教育の現場に取り入れていって欲しいと思います。今回のみなさんのお話や研究結果を聞いて今後の私の生活に役立てていきたいと思っています。
技術的なレベル
生徒はネットワークの機能を国際交流の中で生かす中で、今回のプロジェクトがマルチメディアの活用があったことがあり、積極的に今回は動画のwebへの掲載に取り組んだ。
このファイルは生徒がデジタルカメラでaviファイルを作成し、自らグループに分かれrmファイルを作成した。
さらにこれらに評価を得たいとCGIファイルを活用し、一般からの評価をえた。 現在台湾の高雄市の学校との交流に利用している。
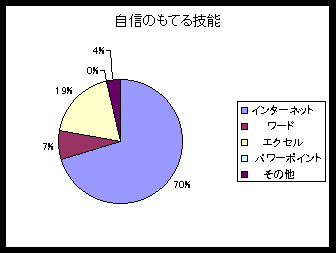
ハワイとの交流において
このプロジェクトに参加した生徒たちは同時にハワイ大学、さらにはハバーフォード大学戸の交流にも積極的に参加した。
チャットを活用し「理想の学校」をテーマに話し合いを続けた。
電子メール、メーリングリスト、さらにはテレビ会議システムを多用しプロジェクトを推進した。
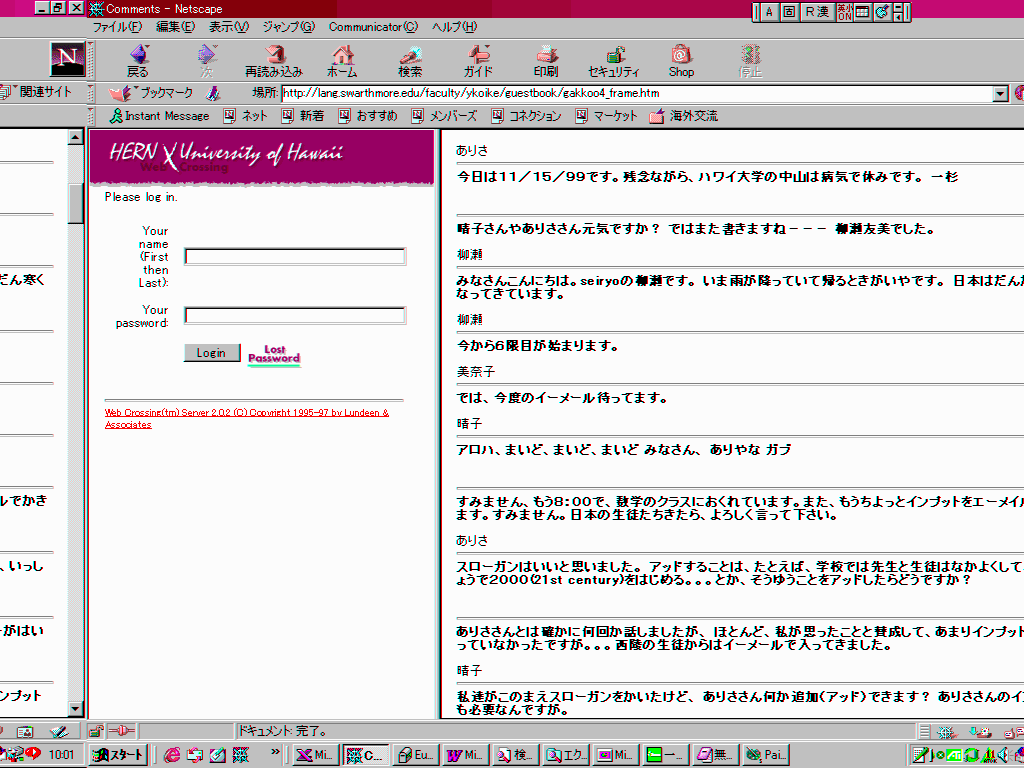
参加教諭・交流への意欲は技術力に比例
「これまでやりたかったのだがなかなか実現しなかった」そんな声を受けての研修会であったが、かく先生方が自信を持ってそれぞれの学校の交流校とマルティメディアを活用した実践を行うこととなった。
またインターネットの新しい機能をしり、これからのそれぞれの授業をより豊かにイメージすることができるようになった。
来年度への継続の意欲もよりいっそう高くなっている。
生徒においても、先生の技術研修がそのまま授業に活かされ、
授業での取り組みを目指しながらプロジェクトを推進して来たが、インターネットを使った授業は生徒の評価も高い。
卒業後も英語学習を継続する生徒も表のごとく高いパーセンテージを示しており、学習に連動したインターネットの効果が現れている。
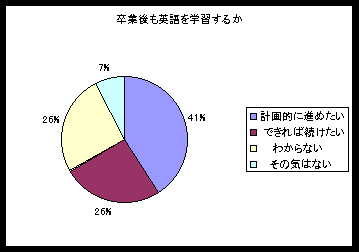
研修の成果の利用
2003年より教科「情報」が開始される。
インターネットがどのように授業に利用できるか多くの先生方が不安を持ちながらこの課題に取り組んでいる。
インターネット活用には技術が必要である。教育センターの官製研修では非常に基礎的な研修しか行われておらず、今回のようなマルチメディア研修は目的にかなったものと評価できる。
しかしながら、数からみるとまだまだ少数である。
Webに研修内容を掲載はしているが、あまり知られていない。
ポータルサイトのデータ提供などの方法を検討していきたい。
今回のプロジェクトのイベントとしては名古屋で行われた活用事例発表会がある。この会場には200名もの参加がありCECプロジェクトの紹介が中心的な役割を果たした。
参加の教員アンケートからは「このような利用もあるものかと」大きな評価を得た。このような実践の共有の場として発表会が機能した。
今後もこのような企画を継続していただきたい。
ネットワークの活力は人的ネットワークにある。
CECのプロジェクトに参加することによって、技術、交流相手だけでなく、「よりよい教育を」というエネルギーを得ることができる。
多くの人の支えのなかで授業実践していって欲しい。
この1年間、様々なイベント、研修会に暖かいご配慮と、ご支援をいただいたCEC担当者、CECのみなさまに心よりお礼を申し上げます。
|
|
↑ 目次へ |