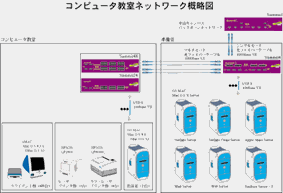 |
 |
学校内の学習環境で、パソコンやインターネットが身近な存在となった今、生徒達は自由にWebページ検索やWebページ制作を行っている。また、WWWとメールを使うことによって、世界の人々と交流し、共同研究できることは、インターネットの持つ大きな魅力である。
本校では、1996年よりAT&TバーチャルクラスルームやThinkQuestなどにインターネットを活用した海外校との交流および共同研究を実践してきた。AT&Tバーチャルクラスルームでは、インターネット上に仮想教室(バーチャルクラスルーム)を作り、世界の小・中・高校生が共同研究を行うというものである。学校単位で参加し、異なった国の3校が1組となってチームを編成し、活動するというものである。本校は4年連続で参加しており、毎年、中学1年〜3年生の生徒を30名程募集し、学年を越えたクラスを作ります。毎週1回放課後活動を行っている。
ThinkQuestシンククエストは、1996年に米国で始まった教材Webページコンテストである。2〜3名の中・高校生が一つのチームを組み、半年?1年かけて他の生徒が学習に利用できるWeb作品を英語で制作する。同じ学校の生徒でチームを組んで参加することもできるが、異なる国の生徒同士がチームを組み、協力しながら作品を制作する事が奨励されている。作品制作は全て生徒自身が行うが、各チームには1?3名までコーチと呼ばれる大人(多くの場合教員)が制作上の指導役・相談役として付く。作品のテーマによって「科学・数学」、「芸術・文学」、「社会科学」、「スポーツ・保健」、「学際(複数の学問分野にまたがるもの)」のいずれかの部門に応募する。これまでに本校から10組以上のチームが参加しており、今年度の参加では社会科学部門で銀賞を受賞した。
情報教育とは、コンピュータやインターネットを活用することだけが重要なのではない。国際理解教育とは外国の子供たちと出会っておしゃべりすることが重要なのではない。情報教育も国際理解教育も子供たちにとっては身につけなければならない学問である。重要なことは、その学問を体系的に実施し、習得されることなのである。
インターネットを活用した国際交流を行うにはいくつか解決しなければならない問題がある。
日本に興味を持っている学校、教師を見つける
交流を継続的に行う上で共有できるテーマが必要である
メールのみの交流では全体の動きが見えない
活動がスムーズに進むようにサポートできる人が必要
Webサーバーやビデオ画像のストリーミングサーバーが必要
一つ一つあげていけばきりがないが、コンピュータやインターネット設備の整備がなされ、実践を行いたい教師、生徒がいてもこのような問題を解決しない限り、実践を行うことは難しいといえる。
そこで本校でも、Eスクエア・プロジェクトの協働企画である「国際交流の継続的実践企画」に参加することとした。
96年にインターネット専用回線を導入し、各種サーバーを設置するとともにすべての生徒用コンピュータからインターネットが利用できるようになった。97年に学校全館の校内LANを構築し、専用回線を光ファイバーに切り替え1.5Mbpsの速度が得られる環境になり、98年からATM回線に切り替え、回線速度が3Mbpsとなりインフラ整備がほぼ完成した。今年度より、生徒用コンピュータとしてiMacを48台導入した。コンピュータ教室は7:30?18:00まで開放しており、生徒が自由に使えるようになっている。朝早く登校してコンピュータ教室に駆け込んだり、休み時間、お昼休み時間に授業で制作している作品を作り込んだり、インターネットで情報を集めるといったことがごくごく自然に行われている。コンピュータ教室はいつも生徒で溢れ、コンピュータの順番待ちが日常の光景となっている。
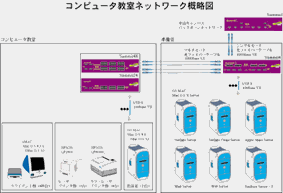 |
 |
98年7月に、本校に在籍する全生徒を対象に、各家庭でのコンピュータの有無、活用に関するアンケートを行った。結果は下の表の通りである。
| 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | 合計 | 割合(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
生徒数
|
196 |
189
|
190
|
194
|
183
|
185
|
1121
|
|
|
家にパソコンがある
|
142
|
135
|
135
|
155
|
148
|
126
|
841
|
75.0
|
|
所有台数
|
198
|
159
|
216
|
197 |
229
|
182
|
1181
|
1.40
|
|
インターネット接続
|
84
|
71
|
88
|
78
|
74
|
54
|
449
|
40.0
|
|
自分も使っている
|
118
|
110
|
126
|
118
|
114
|
71
|
657
|
58.6
|
この結果から、全生徒の75%の家庭がコンピュータを所有しており、40%の家庭がインターネットを利用できる環境にある。この数値は全国的な平均値よりも明らかに高い。このことは、本校が私立学校であり、保護者の年収も大きな要因として考えられる。このアンケートで注目すべき点は中学3年と高校1年のコンピュータの所有である。中学3年が約71%に対して高校1年は約80%である。
本校では中学3年時に本格的にWebを中心としたインターネットを活用した授業を行っている。ここで仮説をたてるとすれば、前年度の中学3年時での学習を終えた高校1年の生徒が学校でコンピュータ、インターネットの活用方法を身につけ、家庭において保護者に願い出て購入してもらったといえるのではないか。
4月からネットワーク環境が整備されコンピュータ機器が新しく導入されたこと、そして、コンピュータ教室を7:30?18:00まで開放していることによって生徒の行動に変化が見られた。生徒は学校で生活する時間のほとんどは授業で過ごすことになるが、休み時間は教室で友人との会話を楽しんだり、体育館でバスケットをしたり、グラウンドでサッカー、野球をするというのが主なものであった。しかし、4月から学校行事以外の平常授業を行っている日では、次のような割合いでコンピュータ教室に生徒が集まるようになった。
7:30〜8:20 平均10名程度、課題提出前は30名程度
12:30〜13:00 平均40名程度 課題提出前は60名程度
15:30〜18:00 平均40名程度 課題提出前は60名程度
コンピュータ教室に集まる生徒は特定の生徒ではなく、本校に在籍する生徒のほとんどが、それぞれ目的を持ってコンピュータ、インターネットを活用するために集まってくる。昨年度までの機器の入れ替え前もコンピュータ教室を7:30〜18:00まで開放していたが、平均してこれだけの生徒が集まることはなかった。
生徒のほとんどは、コンピュータやインターネットを活用した授業に興味を持ち、真剣に取り組む姿勢がみられている。しかし、授業での取り組みにおいては、生徒よりも教師の変化が大きかったと言える。生徒がコンピュータやインターネットを活用した授業を望んだとしても、当然決定するのは授業計画を立てる教師である。
今年度は週35時間中17時間コンピュータ教室が年間計画で埋まっており、イレギュラで週平均で2時間ほどコンピュータ教室が稼動した。普通教室での授業が週23時間くらい稼動していることを考えると、コンピュータ教室の稼動率は他の特別教室よりも多く、普通教室の次に多いことになる。コンピュータ教室を活用した授業の多くは、Web検索、教材webサイトの活用、CD-ROM教材の活用、そして研究のまとめとしてwebページ制作を行った。これらも高速なネットワーク回線と高速な処理速度を持つコンピュータ、生徒用ファイルサーバー、作品提出用サーバーの設置による大きな変化と言える。
一斉授業ではまだ実現できない国際交流や海外の子どもたちとの共同研究は、課外活動として行った。今年度本校で取り組んだ、授業外での活動はすべて生徒の自由意志によるもので、各プロジェクトごとに生徒を募集した。活動時期、時間、参加生徒はそれぞれ異なっているが、約100名の生徒が各プロジェクトに参加した。これも昨年までと比較すると倍以上に増えたことになる。
9月から始まった「国際交流の継続的実践企画」は全国24校の小中高等学校が参加している。大阪、名古屋、東京の3地域に分かれ、東京校の幹事校として本校の中学生、高校生が10名程度参加した。東京校では、海外の子供たちと交流する前に、日本を紹介するwebページを制作することとなり、題材として「日本のアニメとゲーム」「日本の昔話」を選ぶこととなった。「日本の昔話」を紹介する方法として、マクロメディア社のFLASHというソフトを使ってアニメーション絵本を制作した。イラストを描き、物語の日本語の読み、英語の読みを入れ、インターネットで配信できるメディアコンテンツである。
それとともに、参加している子供たち、先生が打ち合わせができるバーチャル会議室を構築することになり、Web Xというサーバーソフトを使って会議室を立ち上げ、ユーザーはブラウザを使って会議室に入れるシステムを作った。このサーバーの管理は本校の高校生が行っている。
11月に本校で東京校研修会を開催し、参加校の先生、子供たちが30名集まり、交流とともにアニメーション絵本の制作方法やバーチャル会議室の使い方、活動の展開について話し合った。
12月7日に名古屋で中間報告会が開催され、発表では、本校の高校生が日本語と英語で司会を行った。早稲田大学高等学院の生徒たちで「日本のアニメとゲーム」の発表を行い、本校の生徒と東林小学校の児童たちで「はなさかじじい」のFLASHアニメーションと日本語の読みと英語の読みの発表を行った。どの発表もすばらしく、特に子供たちが自分たちの活動を自分たちの言葉で発表できたことはすばらしい経験であるとともに、これからの活動の大きな自信となった。
この企画の活動はまさに始まったばかりであり、これからの展開が重要となってくる。しかし、交流を行うためには何が必要で、どのような活動を行う必要があるか見えてきた。そして子供たちの活動が予想以上に活発に行われ、充分成果をあげることができたことは、何を物語っているのだろうか。それは、子供たちにとってはコンピュータやインターネットは決して異文化ではなく、物事を解決するためのツールとして位置付けられているということである。
次年度には外国の子供たちとの交流が実際に行われ、様々な活動が行われることになる。しかし、子供たちにとって、この活動は決して異文化体験ではなくなっているのかもしれない。
|
|
↑ 目次へ |