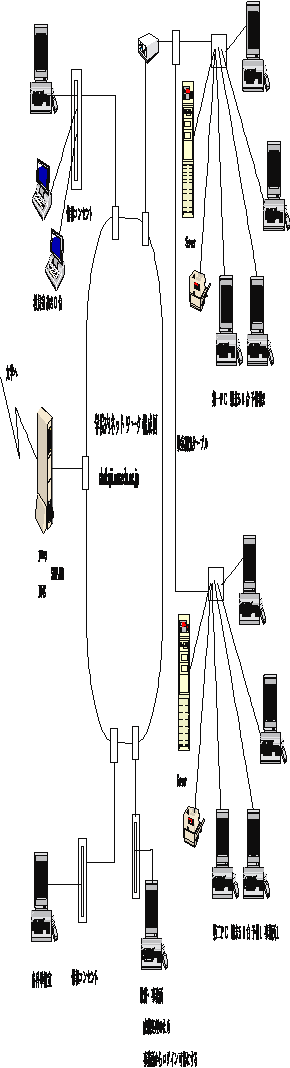
私たちが国際交流の継続的実践プロジェクトへの参加をはじめてから約4ヶ月が経とうとしている。この間、ネットワーク上でのコミュニケーションのありかた、コミュニティ形成の具体的方法、そしてインターネットを利用した学習環境のデザインを検討してきた。これまでの成果を通じて、今後国際交流を具体的に展開していくための、達成目標、テーマ設定の方法、分散協調環境における連携作業のありかた、意思決定の手法などを確認することができた。また、本校ではこのプロジェクトを課外活動として位置づけているが、今後正規カリキュラムに国際交流プログラムを導入していく際に参考となるいくつかの重要な視点を確認できた。
キーワード: 国際交流 学習環境 分散協調環境 コミュニケーション
Abstract: Four month has passed since we have participated in the CEC International Project. So far, we have learned the basic skills on launching out an international project on the Internet such as; communication among the participating students on web crossing, how to select an appropriate theme for international projects, how to set goals of each activity. Our next target is to adopt the skills into the course design of regular school classes.
Keywords: International project, Learning environment, On-line communication
1)国内外の小・中・高等学校との交流のチャンスをつくり実践研究を重ねること。
2)インターネットを利用した国際交流のありかたを探り、問題点を認識すること。
3)参加生徒の情報処理技術・情報倫理のスキルを高めること。
4)活動成果を新しい学習観に基づくカリキュラム作成に導入すること。
大学付属校としての立場から、今後の教育カリキュラムに資するものとして今回の活動を位置づけている。とくに初等中等教育から高等教育に至る一貫した教育カリキュラムのなかで、今回の成果をどのように取り入れていくかが課題となっている。
早稲田大学の付属高校であるため、ネットワーク環境は基本的に大学の管理下に置かれている(下図参照)。インターネット利用の環境には恵まれているが、一方で授業形態に応じた柔軟な環境作りが困難であるというデメリットがある。
早稲田大学とは、専用線で接続。コンピュータ教室 2教室:サーバーマシン2台、クライアントマシン120台、OS:WindowsNT4.0。
国際交流プロジェクトへの参加に伴い、全普通教室に情報コンセントを開設し、普通教室からインターネット接続できるようになった。
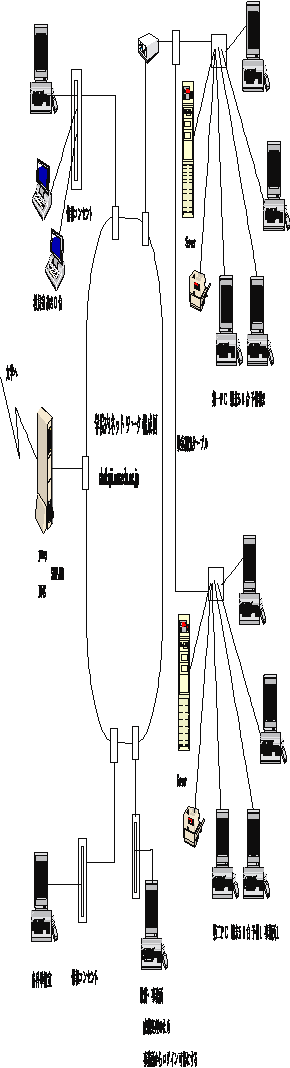
今回の国際交流プロジェクトは本校の正規カリキュラムのなかに位置づけることができなかったため、課外活動としておこなった。課外活動とはいえ参加した生徒全員がほとんどの作業を自宅でおこない、放課後にミーティングのかたちで集まったのはせいぜい3〜4回程度である。教員を含めた参加者どうしのコミュニケーションはほぼすべてネットワーク上でおこなった。
このことはむしろ生徒たちにとって、ネットワーク上でのコミュニケーションの難しさを体験できたという意味において有益であった。分散環境におけるコミュニケーションは、通常の対面コミュニケーションとは異なり、相応のマナーとルールが求められる。ネットワーク上での共同作業や意思決定のあり方を、参加生徒のあいだで模索しながら、一定のルールを共有していく過程がみられた。
活動の内容としては、国際交流の場となるWebページの作成を当面の目標とした。そのコンテンツ作成に向けて、いくつかの方法でリサーチを進めた。おおきく分けて、次の5種類に及んだ。
図2学院BBS
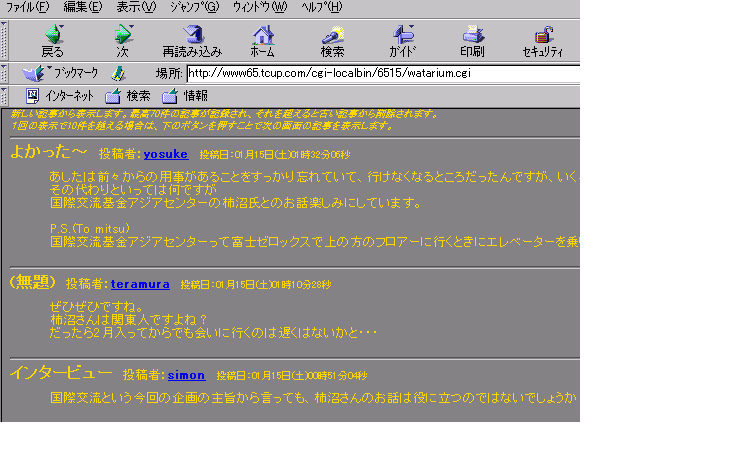
1)BBSの役割として、メンバー同士のコミュニケーションツールであり、同時に意思決定ツール。そしてアイディアの創出場所。
1)テーマ設定: アニメ・ゲーム・漫画
2)コンテンツの詳細の決定と役割分担の決定
(ア)日本アニメの発達史
(イ)最近のアニメ動向
(ウ)小学生による描画作品の掲載
(エ)漫画に関する二択ゲーム
3)小学生対象アンケート(好きなアニメ)
アニメ・ゲーム・漫画が、小学生にどのように受容されているかということをテーマに、アンケートを実施。
参加生徒がそれぞれの得意分野や興味に基づいて、自主的に役割を分担。コンテンツ作成のための調査・制作活動を開始。HTML知識の自主学習。
約1ヶ月の活動内容を、生徒自らが教育関係者を前に発表する機会を得た。生徒にとって、同じプロジェクトに参加している仲間とオフラインで初めて顔を合わせる機会であり、またプレゼンテーションを体験する機会でもあった。
発表内容一部(図3)
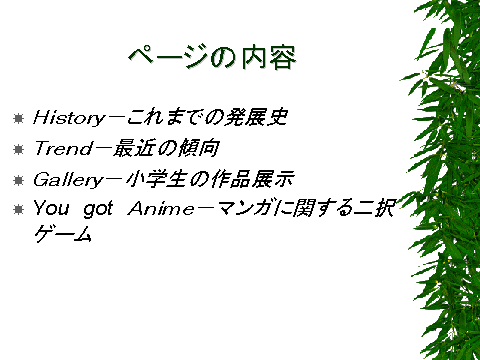 |
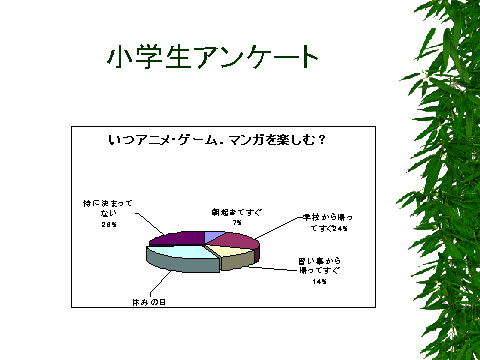 |
1) 民話の平易化
昔話の通釈 → 池袋に伝わる民話を易しい表現に改め、低学年の児童にも容易に読み取れる文章に直す。直した作品を、こんどは小学生が絵画作品にテキスト変換していく試みである。
1)東京校第1回ワークショップ開催時に、テーマおよび各校の役割を分担
2)生徒たちの役割内容の理解度を確認し、BBSの開設を提案
3)生徒の自立的役割分担と活動内容を承認
4)BBSの活動内容の確認及びアイディア等の提案
5)活動促進のための動機づけ
6)Webページ内容の確認
7)東京校他校との連絡・調整
8)活動の方向性の修正
教員が生徒に、課題の実施方法、活動内容及び方向性などの具体的な指示を与えることは一切なかった。そのため、活動当初は生徒達に戸惑いが多く、BBSを通してのコミュニケーションにおいても、指示を待つ質問や活動方法を確認する会話が多く見られた。しかし、そのうち、「何をやってもいいのなら自分たちで自主的に考えなければ、前に進んでいかない」事がわかってきた。しかし、BBS上のコミュニケーションでは、最終的に、誰がどのように、意思決定を行うのかが、問題になる。しかし、これも時間の経過やネットワーク利用の慣れとともに、会話の中から相手の心境を読み取ることができるようになった。その後、自立的に自分の役割や位置づけが決まっていった。それぞれの話題やテーマに応じて、意思決定者が自然に決まっていった。
このような活動が可能であった原因は、メンバーが7人と小人数の限定された環境であったこと、同じ学校の生徒であったこと、友人同士のメンバーでであったことが考えられる。しかし、相手を十分認知しているにもかかわらず、BBS上で意思決定が可能なレベルに達するには、2ヶ月以上の時間を要した。
全員が「参加してよかった」と回答した。
校外との交流も出来、また普段考えたことの無いことを仲間同士で話し合えた。
Web環境をより身近に感じ取ることが出来た。
月並みな言い方だが、実りのある経験になった。人に課されずに仕事をする事あるいは、前からの友人もそれまで出会った事の無い人もひっくるめて仲間として付き合って行く事の難しさを感じた。また、新しい自分、それまで知らなかった自分の能力を知る事が出来た気がする。
他校の同じような生徒とかかわりをもつことができた、また、自分の才能を生かせそうな場所が見つかったから。
教育の現場にいる人たちのインターネットに対する考え方がわかったような気がする。
プレゼンテーションのための準備、話し合い、調査、結果を会場の人たちに分かりやすく発表するという一連の流れ。
小学生へのアンケートをとる際、アンケートの内容を作成する難しさを知った。
e-メールでのコンタクトを取る便利さと難しさを体感できた。
「国際交流」の内容・目的を掴み難かった。
主催者側がインセンティブに欠けていた印象を持った。
他校との連絡の取り方や方法が不十分だった。
資料の収集が困難だった。
時間が結構取られる割に、コミュニケーションが取れない。
他校との連絡の取り方の改善。
各学校の代表者同士だけで連絡を取らず、せっかく全員がWebで繋がっているのだから全体用の掲示板を有効活用すべき。
高校生として関わるのなら、もっと新しくおもしろいもの、ホントに必要なものを作らなければならないと思う。
自分の目的をはっきりと持って、具体的なプランを練っていけば、もっと実のあるものになったと思う。
自立的に、自然に、なんとなく、やりたいものを自分で提案して作っていった。
僕がこの企画に期待していたのは、学生が「教わる」チャンネルから「教える」方にもなることができるチャンスだと思ったからです。教育の方向が先生から生徒への縦でなく、色々な意味でもっと「横」に向けばおもしろいと思います。このことが学習の目的化の一端になるのではないかと思うからです。とにかく、この企画で生徒がイニシアティブを取っていってほしい。先生が引っ張っていく形にはしてほしくないです。そのためにこの企画に関わる生徒数を増やして欲しい、アンケートでも意見を聞くだけでも、多くの人間が集まればきっと何かしら方向が出てくると思います。
参加校の年齢層がばらばら過ぎて活動し難かった。小学校部門と中・高校部門に分けるとよい。
完成度の高い、充実したコンテンツを作りたい。やる気のある集団の集まりにし、連絡を逐一とり、進行状況、意見交換など確認を取り合わなければいい物は出来ないと思う。楽しくやることが大前提だが、けじめが必要だ。
1)交流相手と適切なテーマの設定が急務。
A)継続するための方策。
現時点では韓国の大学・高校をターゲットとしている。
B)指導者チャンネルの体制作りが重要。
1)ネットワーク環境の整備・統一
指導者が相互に目的・手段を理解し共有することが必要。
2)情報共有化の方策
WEBページのアップロードが急務。
学習者の自主的な姿勢を尊重し、状況を確認しながら、活動目的・スケジュールを共有することが必要。
3)モチベーションの持続のために
学習者が、明確な目標(週単位、月単位、学期単位)の設定を自主的にさせていくことが重要。さらに、学習支援者は、目標の達成度を管理していくことが 必要。
活動を通じて最も困難であったことは、東京校の参加校が、小・中・高にわたっていたため、児童・生徒どうしのコミュニケーションを確立する方法であった。また、ネットワーク環境の学校間格差が大きいため、ネットワークを利用した積極的な交流ができなかったことは残念である。
今後、文部省等が進めている初等中等学校への情報インフラの早期整備・確立を願うとともに、活動をしていくための環境についてもさらなる支援を期待したい。
|
|
↑ 目次へ |