�Ȋw���̊����Ƃ��ăt�B�����P�[�X�Ƃ뎆��p�����Ǝ��̊����쐬���A�������x�v�ŋz���x�����߁A���ʐ�����Z�x�����߂���@��4��̑�������{�����B
���̌��ʂɂ��Ă͈��Q�������w�Z�H�ƉȐ��k�������\��Ŕ��\�����B
�ȉ��ɔ��\�v�|�������B
�@
��C���̒��f�_�����m�n�w�����ɂ���
���Q�����V���l�H�ƍ����w�Z�@�H�Ɖ��w�ȁ@�ɓ��U�u�@�x�J���u�@���䕐�u
�P�@�͂��߂� �@
���f�_�����̓m�b�N�X�i�m�nx�j�ƌĂ�A��_�����f���_�����f���܂Ƃ߂ČĂԌ��t�ł��B���̂�R�₷�Ƃ��ɔ������A��Ɏ����Ԃ̔r�C�K�X��H��̉��̒��Ɋ܂܂�Ă��܂��B�Q�Ƃ��Ă͌ċz��n�ɕϒ�������������A���z�������Č����w�������N�����u�����w�X���b�O�v�������N��������A�_�ɂƂ肱�܂�ďɎ_�Ȃǂ̕����ɕω����u�_���J�v�ƂȂ��Ēn��ɍ~���Ă��܂��B
���w�����u�_���J�^���f�_����(�m�nx)�����v���W�F�N�g�v�ɎQ�����A�w�Z���ŗ��p�ł���L�p�Ȋϑ��f�[�^���W�߂���A�Q���Z���m�̌𗬂Ȃǒʂ��Ċ��������l���邽�߂̃l�b�g���[�N����ڎw���Ă��܂��B�܂��A���w�������삵����������g���ċ�C���̒��f�_�����Z�x�̑�������݂Ă��܂��B
�Q�@�u�_���J�^���f�_����(�m�n�w)�����v���W�F�N�g�v�ɂ���
�i�P�j�ϑ����ԁ@�P�X�X�X�N�P�O���`�Q�O�O�O�N�W��
�i�Q�j�Q���Z�@ �S�� �Q�T�Z
�i�R�j������@�u��C����(�m�nx)�����L�b�g�v�@ �i���{�t�@�C���P�~�J���А��j
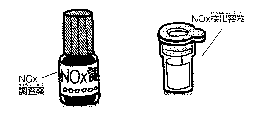
�i�S�j�ߏW���@�@���o�e��˓�����������ꏊ�ɂQ�S���ԊJ��
�i�T�j��������@�P�X�X�X�N�P�O���`�P�P���̌��j���E�Ηj��
�i�U�j����n�_�Ɣ�F�l�i��g�^ml�j
| ���@�� |
11/17
|
11/24
|
11/30
|
|---|---|---|---|
| 1�j�s�����O�����_ |
0.25
|
0.3
|
0.3
|
| 2�j�a�@�����H |
0.2
|
0.2
|
0.2
|
| 3�j�w�Z���։� |
0.25
|
0.3
|
0.25
|
| 4�j�E���� |
0.35
|
0.3
|
0.3
|
| 5�j�z�[�����[������ |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
| 6�j�^�����[ |
0.25
|
0.25
|
0.3
|
| 7�j���H���w�Z�~�n |
0.3
|
0.2
|
0.3
|
| 8�j���̑����_�� |
0.2
|
0.2
|
0.2
|
| 9�j���`�̂��� |
0.2
|
0.1
|
0.2
|
| 10�j�H����� |
0.2
|
0.2
|
0.25
|
��F�l�i��g�^ml�j �Ƒ�C���̒��f�_�����Z�x�ippm�j�̊W
|
��F�l
|
�`0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.4
|
0.5
|
0.6
|
|
�Z�x
|
�`0.019
|
0.019�`0.038
|
0.029�`0.056
|
0.039�`0.075
|
0.048�`0.094
|
0.058�`
|
�i�V�j�f�[�^����M�@�C���^�[�l�b�g�Ńf�[�^�𑗐M���A���[�����O���X�g�Ō𗬂��܂��B
�R ���w��������ɂ�鑪��
�i�P�j������@�ʐ^�t�B�����P�[�X�̒��ɂ뎆������������B�뎆�̑傫���c3�p�A��2.5 �p�ɐ�B
�i�Q�j�ߏW�t�@�뎆�ɂP�O vol ���g���G�^�m�[���A�~���E�A�Z�g���n�t�����ݍ��܂��Ă����B
�i�R�j���F�t�i�U���c�}������j�@�`�t�Ƃa�t���ʍ����t�Q�Oml
���`�t�@�P���X���t�@�j���_�@ ���T�O�Oml�ɃX���t�@�j���_�Tg�������āA�}�O�l�`�b�N�@�X�^���[�łR�O���قǂ��������ėn������B
���a�t�@�O.�O�P���m�|�i�P�|�i�t�`���j�G�`�����W�A�~�����n�t �@���T�O�Oml�ɐ|�_�S�Oml�������A����ɂm�|�i�P�|�i�t�`���j�G�`�����W�A�~���_���T�Omg��n������B
�i�S�j��������@�P�X�X�X�N�P�P���`�P�Q���̐��j���E�ؗj��
�i�T�j�ߏW���@�@ �뎆���邵���t�C�����P�[�X�J�����A�Q�S���Ԍ�t�^�����ĉ������B
�i�U�j���́@ �z���x����@�g���T�S�T nm�@ ���Ɏ_�i�g���E���W���t�@�P.�Tg�^���P�O�Oml�@���Pml �̂�1�O�Oml�Ɋ�߂���B������e�Z�x�ɍ̂蔭�F�t�őS�ʂ��Q�Oml���ċz���x�����߂�B
�z���x�i�~�P�O-3�j���ʐ�
ppb �z���x
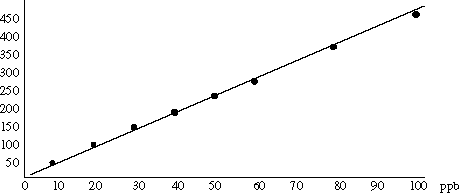
�i�V�j����n�_�Ƒ���Z�x
| ���@�@�@�@ �� | �P�Q�^�V | �P�Q�^�X | �P�Q�^�P�U | �P�Q�^�P�S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �߁@�W�@�t�@�� |
0.10 ml
|
0.08 ml
|
0.06 ml
|
0.04 ml
|
||||
| ���@�@�@�@�@�� |
�z���x
|
ppb
|
�z���x
|
ppb
|
�z���x
|
ppb
|
�z���x
|
ppb
|
| 1) �s�����O�����_ |
0.239
|
51
|
0.160
|
35
|
0.194
|
35
|
0.147
|
32
|
| 2) �a�@�����H |
0.225
|
48
|
0.161
|
35
|
0.112
|
34
|
0.089
|
19
|
| 3) �w�Z���։� |
0.138
|
30
|
0.177
|
38
|
0.116
|
24
|
0.074
|
17
|
| 4) �E���� |
0.112
|
24
|
0.101
|
23
|
0.123
|
26
|
0.111
|
25
|
| 5) �z�|�����[������ |
0.043
|
10
|
0.047
|
11
|
0.044
|
9
|
0.028
|
7
|
| 6) �^�����[ |
0.159
|
35
|
0.145
|
32
|
0.150
|
32
|
0.073
|
16
|
| 7) ���H���w�Z�~�n |
0.224
|
48
|
0.225
|
48
|
0.212
|
45
|
0.094
|
21
|
| 8) ���̑����_�� |
0.077
|
18
|
0.051
|
33
|
0.095
|
20
|
0.072
|
17
|
| 9) ���`�̂��� |
0.143
|
31
|
0.170
|
37
|
0.154
|
33
|
0.106
|
23
|
| 10) �H����� |
0.166
|
36
|
0.168
|
37
|
0.132
|
30
|
0.082
|
18
|
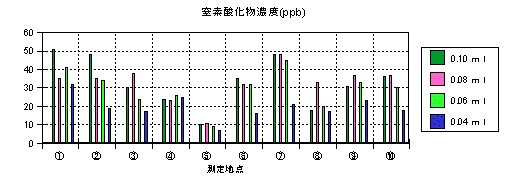
�S�@�܂Ƃ�
�ϑ��n�_���߂����ߊe�n�_�ł̑傫�ȍ��͏o�Ă��܂���B�������A�ǂ̏ꏊ�ł����H�̋߂��͍����Z�x�Ȃ��Ă��܂��B���f�_�������o�邱�Ƃ��Ȃ��z�[�����[�������ł͖�����ɏ������l�ɂȂ��Ă��܂��B�H����ӂł͕��ʂ̏ꏊ�ƕς�肹��A�������˂ȂǂōL����܂���Ă���悤�Ɏv���܂��B
��F�@�Ƌz���x�@�̔�r�ł́A�z���x�@�̕��������ȔZ�x�̍����͂�����ƌ������邱�Ƃ��ł��܂��B
��������g���������ł́A�뎆�ɂ���ߏW�t�̗ʂ��O.�O�S�����Ƃ���ƁA�s�̊��̔�F�@�ɂ��Z�x�ƈ�v����Ƃ��낪�������Ƃ�������܂����B
���̊ϑ���������Ƃ����Ď��������ċz���Ă����C�̉���ɋ����S�����悤�ɂȂ� �܂����B