今、全国各地で環境教育に関する取り組みが行われています。その取り組みの意義は、自分たちで調べた結果が、そのまま実際に役立つものになっていくことにあると思います。ただ、自分たちの結果だけでは他との比較ができません。本校でも、以前より、大気中のNOxの調査を大阪府教育センターの先生を中心に行ってきました。しかし、中心になる先生が転勤のため、そのプロジェクトが停止してしまいました。そんなときに、この企画を見つけました。
ネットワークを組むことによる利点は、身近な取り組みが、大きなネットワークになり、全国規模で比較することにより地域の特性を知ることが出来る事にあると思います。そのことにより、環境に対する興味関心がさらに深まると考え、この企画に参加しました。
2-1.教育活動の中での位置づけ
(1)プロジェクトを実施した具体的な教育活動( 1)
- 理科の授業(特に選択授業)
- 理科以外の授業
- クラブ活動
- ホームルーム活動
- その他の活動
(2)測定を行ったのは誰ですか。 (1)
- 生徒
- 教師
- 生徒と教師の共同作業
(3)データの送信は誰が行いましたか。 (2,3)
- 生徒
- 教師
- 生徒と教師の共同作業
2-2.プロジェクトを教育活動の中で実施するとき、ネットワークの具体的な利用場面(1,2)
- データの送信
- 他校のデータの収集
- 他校との交流
- 他のホームページを使った資料の収集
- その他( )
2-3.プロジェクトの実施にあたり利用できたネットワークの環境。
該当するものを全て選び、その他のものがある場合は具体的にお書き下さい。(1,2)
- ホームページ
- 電子メール
- 電子掲示板
- テレビ電話
- チャット
その他
本校で行っている、選択教科の理科で実践を行いました。以下が、その取り組み内容です。
[選択教科(理科)]
(テーマ) 身のまわりの環境を知ろう
我々人類の生活は、長い生物の歴史と、現存の他の生物の生存によって支えられているといえるでしょう。ところが困ったことに、人類は、文明の発達とともに、我々の生存を支えてくれているこの地球の自然を破壊しています。環境破壊や環境汚染は、今や地球規模で広がり、直接間接に人類の生活を脅かすようになってきています。生活を豊かにするための努力によって作り出された文明が、逆に生活を脅かすというのは何とも皮肉なことではないでしょうか。
それを受けた形で、国際的に環境教育の必要性がうたわれたストックホルムでの国連人間環境会議(1972年)からすでに25年余りが過ぎました。この間に環境教育に関する多くの取り組みが行われてきましたが、我が国の状況をみますと、1990年代に入ってから環境教育への取り組みが活発化し、環境教有への取り組みはその多くが比較的最近のものであり、まだまだ手探りの状態にあるといっても過言ではないと思います。
そのような中、本校では、今年度と来年度にかけて「環境のための地球学習観測プログラム」のモデル校として、「GLOBE」の活動にも参加することになりました。
そこで、後期の選択理科では、前期に取り組んだ「化学を楽しむ」を一歩進化させる形を取り、色々な実験観察を行いながら、身のまわりの環境を知ろうという取り組みをしていきたいと考えました。自分たちの身のまわりの環境がどのようになっているのか、今どのような取り組みが人類として必要なのかを、この選択理科を通じてつかみ取ってくれることを期待しています。
今回のテーマは、「think globaly,act locally」です。
環境を調べるのですから、実験が中心です。必修の理科の授業中に行うものより最寄り専門的な実験になります。 実験に興味のある人には、ぴったりです。
自分の身近な環境は、自分の足で調べる必要があります。また、調べた中身は自分だけしかわからない地域の実体でもあるのです。
自分たちの調べた情報をネットワークを通して、いろいろな仲間と交流し、日本規模、地球規模への取り組みへと発展させていきます。
今まだ継続中ですので、レポート提出までの取り組みを紹介します。 実験は、すべて、2〜4人のグループで行っています。
(1時間目)選択理科・NOx測定オリエンテーション
- これから、選択理科で行うことの説明
- 酸性雨/窒素酸化物調査プロジエクトの概要説明
- 測定班を決める。
- 測定場所を決める。(地域の地図を参考にして)
- 第1回測定開始 (今後、選択理科のない週も6週間測定をする)
(2時間目)NOxについての説明、測定結果の閲覧(HP上で)
- NOxとは、(物性、環境に及ぼす影響など)
- 大気汚染の原因、酸性雨について
- 自分たちの測定結果をHP上で確認する
(3時間目)空気を調べる
- マツの気孔の観察を通して空気の汚れについて調べる。(下図参照)
図1(実験 マツの葉で空気の汚れを調べよう)
図2(結果 マツの葉の汚れ)
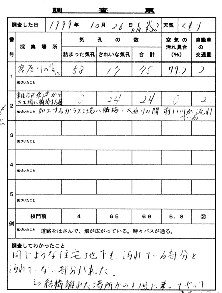
(4時間目)水を調べる
- 水質調査の方法を紹介する(採集方法、測定項目など)
- 自分たちの身のまわりの水を(あらかじめ家からもってくる)パックテストを利用して簡単に水質調査をする。
〈調査項目:PH、COD〉- 水質について簡単に解説をする。
(5,6時間目)土を調べる
身近にある土を採取し、色々な観点で土の性質を調査する。
- 土の感触を調べる。
- 土に含まれているものを調べる。
- 土の中にいる生物を調べる(ツルグレン装置を使って)
- 土のPHを調べる
以上の実験どのような順序でもよいから、グループごとに調べる。(図参照)
(7時間目〜)環境について自分たちで課題を見つけて調べよう。
今までに行った、色々な環境を調べる実験を元にして、自分たちで課題を見つけてそれについて調べていく。
(最後には、発表会をする予定)
(1)実践で得られた成果
このプロジェクトを選択理科の「身のまわりの環境を知ろう」というテーマの一環として取り組みました。必修の理科の学習も、基礎・基本という意味においては重要なものですが、選択、特に環境について調べることは、先にも述べたように、即自分たちの生活にかえって来るという意味においても、大変大事な取り組みであると考えます。生徒たちも、そのあたりが興味深かったようで、前向きに取り組んでいました。また、このプロジェクトに参加することにより、自分たちの調べた結果がホームページに載ることになったので、取り組んでいることに対する自信や誇りが生まれさらに前向きに環境について考えるようになったと思われます。
環境に対する取り組みだけでなく、どのようなことでも、それを認めてくれる何かがあるということは、生徒たちにとって大きな自信になると思います。 その意味で、今回のプロジェクトの参加は、環境に積極的にアプローチをかけるきっかけになったと思われます。
(2)反省・課題
まず第一に、今回は環境教育の一環として、大気中の窒素酸化物を調査し、それを報告するというところまでで終わったので、HPを利用してさらに色々な学校との交流も行えばよかったと考えます。さらに、今後の実践(課題研究)の中に今回の取り組みがどのように活かされていくか、そのあたりの検証が時間的な問題でできていないので、その検証を行うことも大きな課題です。せっかくの実践も生徒たちの活動に生きてこなければなにもならないと思われるからです。
(3)今後の実践にあたってのワンポイントアドバイス
せっかくの取り組みなので、もっともっと交流することが発展につながると思います。これは私たちの反省でもあるのですが、交流に対する取り組みの弱さを、プロジェクト全体を通して様々な形で補っていければいいのではないかと考えます。
(4)このプロジェクト実施にあたって利用した資料・ホームページ等
(資料)
- 大阪教育大学附属天王寺中学校実践事例「土を調べる」
- 「誰にでもできる環境測定マニュアル」 左巻健男・市川智史(東京書籍)
- 「身近な環境を調べる」梅埜國夫・下野洋・松原静郎(東洋館出版社)
(ホームページ)
- 鳴門教育大「環境のページ」
- 環境庁のHP
- 「酸性雨/窒素酸化物調査」のHP
| 目次へ↑ |