
Subject:養護学校のみなさんへ
Aちゃんの絵を、見せていただきました。
とても素晴らしいプレゼントですね。どうもありがとう。
私達も、早くホームページを作ってみんなにプレゼントしなくてはいけないのに、遅くなってしまってこめんなさい。
あとちよっとで仕上がる予定ですので、もうしぱらくお待ち下さい。(後略)
本節から6.4節までは視覚障害、肢体不自由及び知的発達障害について述べる。
重複障害については、6.5節で述べる。
(1) 体制
活動計画を具体化するため、以下の委員による研究グループを設置した。
| 所属 | 氏名 | |
| 主査 | 神奈川県立第二教育センター | 田村順一 |
| 委員 | 東京都立光明養護学校 | 伊藤守 |
| 委員 | 福井大学教育学部附属養護学校 | 水野雅人 |
| 委員 | 福井県立盲学校 | 渡辺雅彦 |
(2) 研究会の実施
研究会の開催は以下の通りである。継続して討論が必要な事項についてはメーリシグリストで行った。
表6.2.1.2会議の実施状況
| 会議名 | 開催日 | 議事 |
| 高度化教育合同会議 | 平成9年9月7日 | ・高度化教育企画の内容確認、今後の進め方 |
| 第1回検討会議 | 平成9年10月30日 | ・視覚障害生徒が参加する企画「オンラインディベート」実施内容の検討 |
| 第2回検討会議 | 平成9年12月12日 | ・インターネット利用実践の分析と今後の進め方について |
| 第3回検討会議 | 平成10年2月10日 | ・報告書について |
(3) 討議された課題
・視覚障害、肢体不自由及び知的発達障害各企画の進捗状況と実践内容
・視覚障書:健常者とのオンラインディベートをメールで実施
・肢体不自由:Cu-SeMeeによる在宅支援を行う際の回線速度の問題
・知的発達障害:タッチパネル用Webぺージを作成するボランティアの組織化
(1) 1OO校プロジェクトにおける研究の成果
平成7年度、100校プロジェクト発足に際し、特殊教育諸学校8校がこれに参加することとなった。これらのうち、視覚障書では福島県立盲学校が、運動障害では東京都立光明養護学校、知的障害では福井大学付属養護学校が中心となり、それそれ地域や様々な機関等の支援を受けて実践と研究を深めていった。とりわけこれらの学校は、心身に障害のある子どもたちがコンピュータやインターネットをはじめとする広域ネットワークにどのようにアプローチし、どのような学習成果を上げうるかにういて試行錯誤を重ね、障害児のアクセシビリティについての研究成果を残した。
アクセシビリティとは、情報(または情報機器)にアクセスする上で、身体・感覚機能的な不利(ハンディキャップ)がある場合、それを補い、円滑な情報アクセスをできるようにする(アビリティ)ことを言う。そのためには、機器あるいは周辺装置
(ハードウェア)の工夫やソフトウェアによる操作系列や認知的なわかりやすさ、さらには障害児が快適に学習活動ができるような環境的な整備を行うなど多様な要素が含まれている。
これらの実践をとおして明らかになったことは、障害のある子どもたちも適切なアクセシビリティの手だてを考慮することで、ネットワークを通した学習活動が十分に展開できることと、こうした活動が、障害児にとって今まで得難かった大きな学習効果を上げるという事実であった。
インターネットをはじめとする広域ネットワークは、どうしても移動や人的交流に困難を生じがちな障害児にとって、そうした社会的不利を補ってあまりある教育効果を上げた。
情報アクセスの拡大は、我々の日常生活にも大きな恩恵を与えてくれるが、社会的弱者ともいえる障害のある人々にとっては、適切な情報アクセスのできる環境は豊かな社会参加の上で、健常といわれる人々より切実な要求なのである。中でも、障害ゆえにどうしても介助や支援されることに慣れてしまい、自ら積極的な社会参加や自己主張の意欲を育てにくかった特殊教育の対象児童・生徒においては、自らの能動的な情報発信ができるインターネットの活用は大きな学習効果が期待できる分野であることがわかった。
これらの学習を効果的に展開していくためには、現在の技術で普及可能なアクセシビリティ機器の活用や、新たな技術的、教育的工夫などを積み重ねて実践的な研究を進める必要がある。もとより障害の状態や程度は一人ひとり大きく異なり、アクセシビリティのあり方も多様な道筋が必要となる。そこで導入後のフィッティングや支援も含めた研究と組織的な支援体制も併せて検討を進めることが必要であるといったことが、これまでの研究の中で見いだされた課題であった。
(2) 各校の実践
<福島県立盲学校>
福島県立盲学校では、視覚に障害のある子どもたちがインターネットプラウザの特徴であるはずのGUI(グラフィカルユーザインターフェース)がかえって妨げとなり、画面情報を読みとることが困難であったり全くできないため、それを克服する手だてについての研究を行った。
視覚障害には大きく分けて、視力が低くものが見えにくい状態にある「弱視」という障害状況と、ほとんど視覚情報が入らない「盲」という状況がある。
弱視という状況も、単に視力の高低だけではなく視野の問題や色による見え方の個人差が大きく、極めて個別的な対応が必要である。具体的には大きな画面サイズのディスプレイを使うほか、個に応じた色調の変更やカーソルの形状の工夫などが行われている。
一方、盲児については、これまでコンピュータを利用するにあたって画面の視覚的な情報を音声に置き換える「音声合成」という手法と、触覚に置き換える「ピンディスプレイ」という手法がある。これらは感覚器官の障害を他の感覚器官で補う手だてであり、「感覚代行」と呼ばれている。
ところがインターネットプラウザで見るWebサイトコンテンツ画面の多くはGUIであるため音声に置き換えることが困難となっており、大きな研究課題となっている。
福島県立盲学校では、音声変換がたやすいテキストのみのホームページを立ち上げてその必要性を訴えると共に、Web画面を音声化できる技術について研究を進めた。
その手だてのひとつが「Lynx mail gateway system」である。このシステムはWeb画面の情報をいったん別のサーバーにある翻訳システムに転送し、リアルタイムでメールの形式で返送してもらうというものである。メールはテキストの形式であるため、そのまま音声合成装置にかけて聞き取ることができる。当然ながら写真や図は読みとれない上、不要な情報も読み上げてしまうため決して万能というわけではないが、現時点において視覚障害者がインターネットを利用する上で有用な手だてのひとつである。
<東京都立光明養護学校>
東京都立光明養護学校では、後述のように特殊教育に携わる教師や関係者によるインターネットの活用とテクノロジーについてのメーリングリスト、「edhand」を運営し、質の濃い討論と情報の共有化をはかっている。平成9年度現在100名前後の参加者があり、日々活発な議論と情報交換が進められている。
また光明養護学校では、子どもたちからの積極的な情報発信を引き出し、それらをWeb画面上で実現化することによってインターネットの持つ情報コミュニティとしての意義を前面に提案した。
情報を受け身に利用することばかりではなく、障害の有無をも含めた自分自身を自発的に表現し、自己発信していくことは、運動障害のある子どもたち自身にとっても新しい経験であった。
これらの活動は、子どもたちの学習意欲を高め、当初予測できなかったほどの子どもたちの力を引き出す結果につながった。自己発信することの新鮮な喜び、それに対して思わぬところから寄せられる暖かい励ましや評価のメール等に、さらに意欲を刺激されたものと思われるが、インターネットの持つ大きな側面である情報発信と情報コミュニティの成立が障害のある子どもたちの新しい社会参加の一形態となりうることがわかった。とりわけ運動障害のために移動に困難があり、社会参加経験の機会が乏しくなりがちな子どもたちにとっては、ネットワーク上の間接的な関わりとはいえ、居ながらにして世界と交信できるメディアは教育的に大きな意義を持っていることを、これらの実践を通じて教えられた。
この活動に参加した子どもたちの中には、手指だけではなく、全身的に大きな運動障害のある子どもも含まれている。光明養護学校では手指の障害を補うためのアクセシビリティ機器として、マウスの代わりをするポインティングデバイスの試行や、ポインティングをキーボードや1-2キーのスイッチ・センサー等、その子どもが少しでも随意に動かせる部位に対応させたキーインターフェースの試行などを行ってきた。重度の運動障害のためほとんど寝たきりに近い状態を余儀なくされている高等部のI君は、はじめは光学マウスを用いて入力していたが、.気管切開後は呼気スイツチ
(息を吹き込むことで作動するセンサースイッチ)を使用し、さらに現在てば指先のわずかな動作だけで作動するスイッチを使って童話や情感豊かな文章を書き、卒業後も引き続き情報発信を続けている。
<福井大学附属養護学校>
福井大学附属養護学校では、知的障害の子どもたちの情報活用と交流にインターネットを活用してきた。一口に知的な障害といってもその能力差は極めて大きく、単に知的なレベルだけではなく意欲や社会経験の多少に応じた、自らの積極的な意思の引き出し方によって学習効果も大きく異なってくる。
これまで知的障害(精神薄弱)教育は歴史的にも社会適応や身辺処理に力を入れてきた経緯があり、機器を活用することより実体験を重んじ、「身体で覚える」という観点で指導が計画される例が多かった。それは精神薄弱児(知的な発達において障害をもつ児童・生徒)の認知特性や心理過程からして理にかなったものではあったが、最近ではこうした一辺倒な経験主義教育に対して批判の声もある。社会や人の生き方の価値観が多様化し、個に応じたQOL(Quality
of life:生活の質的向上)と幸福が追求される社会において、精神薄弱児だけが旧来の障害児観に縛られ、新しいメディアや社会コミュニティから隔離されるようなことがあってはならないという考え方からである。
福井大学附属養護学校では、子どもたちの意欲を引き出して自らの興味に結びつく情報を探し出す楽しさを教え、ネットサーフィンを自発的にできるまでに機器利用の力量を高めることに成功した。また、電子メールを利用して関係者や他校の児童・生徒との交流を行い、コミュニケーションそのもののルールを学習していった。その延長として、知的障害児を中心としたインターネット上で運営されているクローズされたコミュニケーションネットワークであり交流フィールドでもある滋賀大学附属養護学校が運営する「チャレンジキッズ」に参加して交流を深めた。
さらに、自校のWebサイトコンテンツ上でも工夫を重ね、ひらがなだけのページで知的障害児が読みやすいぺージ作りの試行も行ってきた。
(1) 視覚障害における実践研究
福島県立盲学校では、新100校プロジェクトに呼応して、これまで試行錯誤してきたLinx mail gateway systemを活用して、一般の高校生と電子メールによるオンラインディベートを行うことを試みた。
リアルタイムのディベートでは、いったんこの翻訳システムや音声合成装置を通さねばならない視覚障害児には即時性という点では不利であることはいうまでもないが、電子メールを利用することによって可能な限りのバリアフリー(障壁となっている事象を取り除くことで、よって立つところを均一にしようとすること)をはかり、同一のフィールドで共同学習ができるようにする極めて意義の大きい試みといえる。
(2) 運動障害における実践研究
都立光明養護学校では、これまでの100校プロジェクトの成果をふまえ、さらにその延長として在宅になっている子どもに対する支援として、PHS(簡易携帯電話)とCU-SeeMeを組み合わせ、家庭と学校とのあいだの遠隔学習や情報交換の実践的な研究を行うこととした。
回線速度の制約から専用線接続の場合や専用のテレビ会議システムのようには行かないまでも、現時点で比較的安価に提供できる技術を用いて、在宅による情報過疎に陥りかねない状況を改善するには大切な研究といえよう。
(3) 知的障害における実践研究
福井大学附属養護学校では、校内LANを利用して教室からのインターネットアクセスを可能にし、日常の学習場面や放課後の部活動等でも子どもたちがたやすく利用できるように環境を整えた。また、大学生ボランティアの積極的な協力の下に、知的障害児が学習にも利用できるWebサイトコンテンツの開発にも着手した。知的障害児の場合、いかに日常の教育活動にさりげなくとけ込ませるかも大きな研究課題といえる。
(4) 特殊教育メーリングリストにおける実践研究
都立光明養護学校が運営を務めている特殊教育メーリングリスト「edhand」は、当初はこれら一連の研究の調整と連絡を行う目的もあって発足したものだが、各障害種別ごとの教員の参加と実質的にsysop(システムオペレータ)を努めている光明養護学校伊藤教諭の努力により、大変活発な意見交換の場となってこれら一連の研究の基礎を支えてきた。このメーリングリストのやりどりの中には、将来の特殊教育やインターネット活用のために重要なキーワードがたくさん含まれており、現時点の我が国における最も先進的な「論壇」のひとつであることは疑いがない。
(1) 視覚障害児を対象としたオンラインディベートの実践
はじめに
これまで「100校プロジェクト」を通して、視覚障害者のインターネット利用を考えてきた。その中で幾つかの実践を積み、ある程度のインターネット利用を実現してきたが、さらに今年度の初めには音声ガイドを利用した全盲生のメール利用環境を整えることができた。
前年度までの実践は視覚障害児のアクセシビリティの向上に力を割くことが多く、教育実践までには手が回らなかった。しかし今年度の初めに当初の目標であった機器環境整備にめどがついたことで、本来取り組むべき教育実践に集中することが出来るようになった。そこで、コミュニケーション能力の向上と論理的思考を高めるために一般の高校生とのオンラインディベートに取り組むこととした。
なお、ディベートとは、一つの論題に対して、肯定側・否定側に分かれ、ある一定のルールに従って議論を進め、最後に勝敗を審判によって決めるというものである。
○ ディベートを行うことによる教育的な意義とメリット
・客観的分析力が身につく
・論理的思考力が身につく
・発表能力が身につく
・より良い聞き手になれる
・情報収集力が身につく
○ ディベートをインターネット上で行う意味(オンラインディベート)
オンラインディベートとは、通常のディベートは一般に肯定派、否定派のグループに分かれ同じ会場で直接対面しながら行うものであるが、これをメール等を用いネットワーク上で行うものである。
○ オンラインディベートの特徴
・発言かテキストに残る。
・発言がテキストで残るため、思考を進めていく上で有効である。
・発言の整理や記録を残すのに便利である。
○ ハンディキャップの克服につながるオンラインディベート。
オンラインディベートはネットワーク上で行うため、障害等のために直接対面してはコミュニケーションが困難なケースでも意思の疎通を図ることができる。参加者双方が、お互い障害の有無等を意識することなくコミュニケーションをはかることができる。
例えば、視覚障害者と聴覚障害者が直接対面したケースではそれぞれの言語や意思の表現方法が違うためコミュニケーションは困難である。視覚障害者は音声言語であり聴覚障害者は視覚言語(手話)である。お互い障害がある部分がコミュニケーションに直接つながる使用言語に関わるものであるため、正確に意思を伝えることは難しい。しかし、ネット上では電子的な信号を介したものになるため、それそれアクセスしやすい言語形態に変換することによってコミュニケーションが成立する。
a. 福島県立盲学校のオンラインディベートの実践
対象生徒
| ・本校対象生徒 | 高等部普通科1年生 |
| ・相手校生徒 | 清泉女学院高校 |
障書の程度によるコンピュータ利用上の配慮
| ・弱視生への配慮 | フォントを大きくする。マウスポインターに軌跡を付ける。 |
| ・全盲生への配慮 | 音声合成装置を使用する。 |
機器
| ・パソコン本俸 | NEC9800シリーズ DOS/Vマシン(FJITSUFMV) |
| ・OS | Windows95MS-DOS/6.2 |
| ・メールソフト | tsworksver2.25 D-Mailver2.2(DOS汎用) |
| ・補助危機 | 音声合成装置FMVS101 音声ソフトVDM |
| ・LANボード | TDKLAK-98025 |
| ・TCP/IPドライバ | アライドテレシスTCP/IPver6 |
オンラインディベートの進め方
立論:自分の立場を明確にし論題に対しての意見を明らかにする。
尋問:立論に対して疑問と思う点を質問する。
反駁:相手側の立論、尋問のやり取りをふまえ最終的な自分たちの意見を述べる
オンラインディベートの実践
オンラインディベートのテーマ「予定外の妊娠」
A子は「妊娠3ヶ月に入ってますね。」医者からそう告げられたとき目の前が真っ暗になった。自分に限って妊娠しないだろうとたかをくくっていたのが失敗だった。A子は就職がすでに決まっている大学4年生、彼は、大学院2年生、そのまま博士課程に進む予定である。つき合い始めて一年になる。A子は妊娠の事実を真っ先に彼に伝えた。その時のA子の気持ちは正直言って産もうとも、おろそうとも決めかねる、白紙の状態だった。ずるいようだが、彼の反応を見て考えようと思っていた。ところが、彼は「ええっ!・・・でも、安易に生むわけにはいかないじゃないか・・・これからのことを考えるとおろした方か・・・」と言った。彼の気持ちも分かる・・・。しかし・・・どうしよう・・・。彼を説得して産もうか・・・それぞれの将来の夢を考えれば、今は子どもを産まないほうがよいのだろうか・・・A子の気持ちは次第と支離滅裂に・・・。 論題:この状況でA子は A 産むほうがよい B 産まないほうがよい |
上記の説明に対して、以下の質問があった。
〉質問:A子と彼は、避妊をしていたのでしようか?
〉→避妊をしていたとするならば、どのような方法だったのでしょうか?
〉彼等の行為に関する責任の度合について、上記のことで検討したいと考えました。
どんな避妊法も失敗率がともなうので、「コンドームによる避妊はしていた」ということにいたします。
本校はG-ROUND、福島盲学校 一 清泉女学院高校P組否定
立論
肯定側立論
以下メールからの引用-----------------
全盲生が書いた文章
|
世の中には子供がほしくても何らかの理由で産むことができない人もいるのです。それにもかかわらず自分たちの将来が心配だからと言って子供を堕すなどという考えはまったく身勝手なことだベつに子供を堕さなくてもいいのではないかとおもいます。家族の力を借りて育てていくと言う方法も意味のある豊かな生き方ではないのでしょうか? |
--------------ここまで--------------
否定派立論
以下メールからの引用------------------( )内は筆者注釈
清泉女学院高校否定側立論
清泉P組「産まない側」立論です。どうそよろしく。
私達は産まない方に賛成です。この場合、A子と彼が結婚して子どもを産んでも、幸せにはなれないだろうと思うからです。
まず第一に、A子の就職が決まっていることです。この就職難の時代に、せっかく勝ち取ったものなのに子どもを産むということで、その仕事をあきらめざるを得ないし、もし産休をとると、今後その会社でやっていくのにたくさんの支障が生じてくると思います。そのようにして、仕事をあきらめてしまうのは、社会に出ないまま残りの人生をすごす、視野の狭い人間になる可能性がある。もし子どもを産んでから、仕事をやり始めるといっても、今の日本の社会では、子どもがいるというのは、女性の社会進出の妨げにもなるだろう。
次に、これは第一に挙げたものと近いが、二人はまだ、将来の夢への道の途中にいるということです。彼は、博士になって、それを活かした仕事をするために勉強しているところである。そして、A子は多分、理想とする会社に入り、将来的にはこんな事業をしようなど、たくさんの夢を抱えているはずである。このまま、結婚して子どもが産まれても、夢を打ちやらないと(うっちゃらないと)いけないから、後々問題
が生じてくるだろう。
第三に、A子と彼には、子どもを養うだけ後から(の力が)がないと思われるからである。まだA子も彼も学生だから、親の保護を受けているだろうし、またそうでないにしても、自分一人養っていくのが精一杯だろう。そんな二人を親に持っても、子どもは経済的な援助をしてもらうことが出来ないとおもう。
そして、彼が、乗り気ではないということだ。もしA子が、産むことを決意したとしても、A子と彼の心には、彼がいった、おろしたほうがいい、という言葉が残り、わだかまりが残るだろう。彼にして見ても、自分が若いのに父親になってしまったら、責任も重大だし、しかも、まだ学生だから嫌だろうし、二人にとっても今これからの人生を決めてしまって、子どものために未来の望ましい生活を諦めてしまうのも、早すぎると思うのだ。
もし、A子が彼の反対を、押し切って子どもを産んだとしよう。彼もA子も望んだわけではないから、結婚しても子どもがつなぎ会わせた(合わせた)家族であって、そこに幸せが生まれるとは限らない。そして、彼もA子も子どもを養い教育するために疲れ果てて、いつも、子どもがあのとき生まれていなかったら、と後悔するかも知れない。
それに、A子が医者から妊娠を告げられたとき、目の前が真っ暗になったように、彼もA子も今はまだ子どもを受け入れる用意も準備も出来ていないのではないか。
彼もA子も望んでないのに、産んだとしても二人は、子どもを幸せに育てていくことが出来るだろうか。二人はまだ学生で、自分が子どもを産む前に一人前の大人になれていないのだ。そんな二人が子どもを育てるのは無理である。
後悔しながら生きるよりも、今勇気を出して、輝く未来を手に入れたほうが良い。
子どもを作るのは、一人前になって他人の面倒も見れる様になってからでもおそくはない
--------------ここまで--------------
肯定派からの尋問
以下メールからの引用--------------
全盲生が書いた文章
|
福島県立盲学校 おんらいんでいベーと肯定派 |
--------------ここまで--------------
否定派尋問
以下メールからの引用--------------
清泉女学院高校否定側尋問
清泉P組産まない側質問
福島盲学校さんへの質問です。
子どもを責任だけで育てていっても、そんな形の愛で育てられて、子どもは幸せになれるのでしようか。
--------------ここまで--------------
報告書を書いている時点ではここまでのやりとりであるが、この後それぞれの尋問に対する回答、反駁、審判と進みオンライディベートは終了する。
本校生徒のこれまでの実践を通じての感想
・「内容が濃かった」
・「ディベートで話し合うテーマはもっと簡単な方がよい」
・「ディベートを行う前にメールの交換をしたかった」
オンラインディベートの成果
・他校の同年代の生徒と交流できた。
・今回のテーマはやや難解であったが、生徒はめげることなく取り組み論理的思考の進め方を学習できた。
・文字入力に慣れ、文書作成が出来た。
b. オンラインディベートの課題
・文字入力が遅い
全盲の生徒は普段は点字を利用しているが、メールを書くときには墨字(一般の文字、この場合は漢字仮名交じり文)を利用する。点字によって表現できる文字はひらがなだけで漢字がなく、その概念と適切な使用が全盲生徒には十分には理解出来ていない。そのため文章を書くのに大変時間がかかる。また、音声ワープロを利用しての漢字の選択は慣れと時間が必要である。
例「コウテイ」のように同音異語がある場合の音声ワープロにおける漢字選択は
肯定コウテイテキノコウサダメルノテイ
皇帝コウタイシノコウテイコクシュギノテイ
と音声合成装置が漢字を読む音を聞き分け、選択して使いこなしていかなくてはならない。この 選択が正確に出来るようになるには経験と時間が必要である。
・墨字の文章に不慣れ
墨字の文章の書き方と点字の文章の書き方はルールが異なっており、全盲生が書いた文章は少し読みにくい点がある。
点字では読点を省略する事が多く生徒が書いた文章を見ると読点がない。今後一般の生徒とコミュニケーションを図るには、墨字の文章表現に慣れる必要がある。
・視覚情報が少ない
週刊誌等のグラビアやビデオなどの視覚情報で多くの性情報が流されているが、視覚障害者はその情報を取り入れることが難しく、性についての知識は普通校の生徒と比べて遅れがちである。今回参加した本校の高等部普通科1年生にもこのことを強く感じた。
おわりに
オンラインディベートでの学習内容は文字の入力、論理的な思考、考えをまとめ文章を作成すると多方面にわたったが生徒は真剣に取り組み、一定の成果をあげた。
この取り組みは今後の盲学校でのインターネット利用のあり方を示唆している。オンラインディベートで用いた電子メールは、書き手と読み手が構えることなく交流できるという障害児にとって適切な道具である。障害を持つ者も持たない者も意識することない自由な空間を作り、多くの人たちとの交流を深めることのできる優れた性質を持っている。
今後、さまざまな技術を活用しながら、更なるメールの利用法を検討し実践を深めることが必要である。
(2) 肢体不自由児を対象とした在宅支援学習の実践
はじめに
肢体不自由教育における在宅学習支援については、100校プロジェクトが始まった当初から課題としてあげられてきた。95年度の報告書の中では以下のように記述されている。(原文のまま)
・・・ティーンズねっとわーくの「インターネットって何?」という特集に参加する中で、インターネットを使ったテレビ会議機能をテストするチャンスにも恵まれた。
電話とかパソコン通信などでは難しかった<在宅学習支援システムの構築>の可能性を調べてみたかったのである。具体的には、QTCとCU-SeeMeを使った実験をした。
QTCについては、もともと「LANか専用線(128kbps以上)を使用したインターネットで接続しないと使用出来ない。」という事ではあったが、少しは・・・という期待から実験してみたのであるが、結果的には、やはり無理であった。QTCの方が、カラーで、共有ボードがあり、そのボードを使って共同作業が出来るなど・メリットが大きいのだが、土台、専用回線とはいえ、28.8kbPsのモデムで接続しようというのが無理のようだ。(本校の回線は、アナログの28.8k)
CU.SeeMeについては、実験・リハーサル段階ではそれなりに相互に見る事は出来たが、番組の収録の時は、悲惨であった。静止画像を送るのに10分以上かかる有り様だった。土曜日の午後の収録だったので、お昼過ぎから徐々に回線が混みだしただろうか。
その後、学校とI君の自宅をつなぐことを想定して、お互いにアドレスを直接入力する方法でつなげてみたら、14.4kbPsのモデムでもなんとかつながったα学校のサーバーにつながっている方が、6から7fps、プロバイダにPPP接続している方が、0.0から0.5fpsなので、お世辞にも快適とは言えないが・静止画像十画面に文字を書き込むなどの工夫をすれば、現状でも、なんとか使えるかな・・・というか、パソコン通信の文字情報だけ・・・という状況に比へれば、「少しは使えるかな」という感じだと思う。
結果的には、<現状の28.8Kのアナログ回線では厳しいものがある>という事を再認識する結果とはなってしまったが、問題点とその打開の方策がより明確になった事も確かではある。
先進的教育システムの開発における特殊教育共同利用企画の実施」調査報告書
3.1.3 東京都立光明養護学校におけるI君の利用事例について
7) 在宅学習支援システム構築の可能性について
http://www.koumei-sfh.setagaya.tokyo.jp/~koumei/kenkyuu/kikakuhtml
96年度の末には、100校プロジェクト事務局のお骨折りによって、Enhanced CU-SeeMeとカラーQcamを導入する事ができた。しかし、「在宅学習支援のためのテレビ会議システムの利用についても、平成8年度も引き続き検討を加えてきたが、回線の太さからくる制約などがあり、検討課題が積み残されている。」という報告書の記述に見られるように、.実質的な進展は見られなかった。
http://www.edu.ipa-gojp化youiku/100/project/prjlist/joint/jugyou/koumei.htm
しかし、97年度に入ると、光明養護では回線が64kbpsと高速化されるなど、環境整備も整ってきたという事もあって、注目すべき成果が報告されるようになってきた。以下、二つの事例について報告する。
a. 佐賀県立金立養護学校におけるチャレンジキッズを使った在宅学習支援
http://www.saga-ed.go.jp/school/kinrytu-sfh
・昨年度までの経過
本校高等部のMくんは、高等部2年生の5月に病状の進行により気管切開を行い、病院での生活、また退院後は在宅での生活を余儀なくされている。以前より本児のような生徒がでてくる可能性が考えられたため、学校でもスイッチ入力で操作でき、コミュニケーションエイドとしても使用可能な機器をそろえる必要性を感じていた。
そこで、96年12月にマッキントッシュとその上で動作するキネックスという入力装置を購入し、冬休みの問、自宅で使用してもらうこととした。マッキントッシュにはモデムも内蔵してあり、インターネットにも接続することができる。また佐賀県は、佐賀県教育センターに接続することでインターネットを使用することができるため、学校のIDでセンターに接続しWebサイトコンテンツも見ることもできるよう
にした。
その後本人がノート型のマックとキネックスを購入し、また佐賀県教育センターより本人のインターネットIDの発行を受け、現在まで使用している。
・今年度の取り組みについて
97年2月にノートパソコンを購入し、キネックスという代替入力装置に親指で押せる小さいボタンスイッチをつないで操作練習を行っていたが、3月中旬に肺炎のため短期入院となり練習が滞っていた。4月に入り、自宅での学習が可能となり、今年度から週2回の家庭訪問の形で火曜目は主要5教科、金曜日にコンピュータを使ったコミュニケーションという内容で在宅学習を行うことになった。以下に今年度のコンピュータ利用の指導内容をあげる。
(指導計画)
・エディタの起動と終了
・キネツクスのスキャンモードの操作
・編集(コピー、ぺースト)
・ファイルの保存
(学習状況)
コンピュータ操作に慣れるために、ワープロによる入力練習から始めた。画面にキーボードが表示され、その上をボタンが動き、必要な文字のところで押すといった入力方法のために時間がかかり、また、自力での排痰が困難なため20分に1回の吸引が必要となり、どうしても疲れやすく、あまり興味関心は示さなかった。
(単元)ホームページをみよう
(教材名)NetscapeNavigator
(指導計画)
・インターネットの接続方法
・ブラウザについて
・学校のホームページ
・検索エンジン
(学習状況)
雑誌等に掲載されているホームページを紹介してみたがあまり興味は示さなかったが、検索エンジンを説明する際に例としてキーワードを「養護学校」で検索した時に、全国の同じ養護学校のホームページで生徒が紹介している作品や自己紹介には目を輝かせていた。
(単元)電子メールを使おう
(教材名)Eudora-Pro、クラリスメール
(指導計画)
・メールの受信
(学習状況)
複数の教師が訪問前にメールを送信しておき、本人に受信させてみた。はじめは楽しんでいた。しかし、訪問日以外に自分だけで受信したり、メールを送ってくれた人に返事を書くことは無かったので、火曜日の担当者と川柳を題材にメールのやり取りをしようと試みたが自分から送信することはやはりなかった。しかし、学校の同級生がワープロで打った文章を教師が代理で送信した時は今までになく嬉しそうだった。
その時は自分から返事を書いて送ることが出来た。やはり教員より同年代の友達とのやり取りを望んでいることがはっきりと分かった。でもこのやり取りも教師を介してのやり取りのため長くは続かなかった。
(単元)CD-ROMの利用
(教材名)雑誌付録のCD-ROM,PhotoDe1uxe
(指導計画)
・ソフトのインストール
・作品の鑑賞
(学習状況)
興味を示した内容は、絵やデザインの作品と毎回掲載されている小説だった。その小説には文字の他に挿し絵があり、絵の部分をクリックすると絵が動き出すものだった。作品を作ってみようかの問いかけでカレンダーを作ってみた。出来上がった作品を見て嬉しそうだった。
・チャレンジキッズに参加して
コンピュータを使ったコミュニケーションを主に学習を進めてきたが、本人からの自発的な発信はあまり見られなかった。そこで、現在、本校が参加している「チャレンジキッズ」(注1)を一週間ほど自由につないで見せることにした。その後、97年10月3日に放送された「メディアと教育」でチャレンジキッズの内容が紹介されていたのでビデオを見せ、その上で滋賀大学教育学部附属養護学校が出版している「チャレンジキッズダイジェスト96」を読ませた。本人もチャレンジキッズの内容が少し理解できたらしく、頻繁に自ら接続するようになった。母親の話ではうまく繋がらない時でも、2時間もいろいろと操作していたという話を聞いた。そんな時に、「一度チャレンジキッズに自己紹介をしてみようか」との問いかけに、彼は次の訪問指導の時に以下の文章を書いていた。
「はじめまして、僕は佐賀県の金立養護学校の3年M.Mといいます。18歳になります。在宅で、週二回訪問教育を受けています。金曜は、パソコンを習っています。
今日は初めてメールを出しました。これからよろしくお願いします」
その後、チャレンジキッズの良いところは、すぐに返事が来るところで、本人も「初めてのメールなのにこんなに返事が来た」と嬉しそうだった。彼のこのような前向きな姿勢は、チャレンジキッズが養護学校や小・中学校の障害児学級の仲間が自由にのびのびと会話ができる世界と感じとった結果だと思う。彼の世界は確実に広がっている。昨年は載せることができなかった本校のひまわり文集にも次のような文章を書くことができた。
「僕は、高校2年の5月から呼吸器を使っています。声を出すことができなくなりました。学校にも行けなくなりました。でも、校長先生や先生方のおかげで訪問教育を受けることができるようになりました。勉強の問に、学校のことや、友達のことを聞くと懐かしく思います。そして、金曜日には、F先生から、パソコンを習っています。メールを見たり送れるようになりました。これからは、パソコンを通して友達をつくりたいと思います」
b. 東京都立光明養護学校におけるCU-SeeMeを使った実践
http://www.koumei-sfh.setagaya.tokyo.jp/~koumei/
全国各地で肢体不自由養護学校部高等部の訪問教育の試行か始まっている(注2)。
光明養護学校高等部でも、現在、来年度中学部から進学が予想されている訪問籍の生徒の受け入れ体制を検討中である。その一方で、光明養護学校は97年の秋、28.
8kbPsのアナログ回線から64kbPsのデジタル回線に変更された。こういった状況を受けて、かねてから懸案であったCU-SeeMeを使った在宅学習支援の実験を行った。対象は2学期後半から長期欠席している生徒であり、自宅にノートパソコンと通信機材を持っていき、生徒の自宅と学校をつないでみた。使用機材は以下の通りである。
| 学校側 | :ApP1eMacintoshLC630/EnhancedCU-seeMe・カラーQcam/64kデジタル専用回線 |
| 生徒の自宅 | :PowerBook5300cs/EnhancedCU-seeMe・カラーQcam /パルデイオ312S・32KパルデイオデータカードDC-1S |
今回の実験は、「インターネットと障害児教育」というメーリングリスト(注3) に逐一報告したので、その書き込みの一部を紹介することで実践の様子を報告する。
・98年1月23日
生徒の自宅から文化祭の会場に戻って一息ついたところです。
学校の様子を聞くために電話を入れてみたら・・・普段軽口しか言わないM教諭が・・・
「いやあ、いい授業でしたよ。感動してしまいましたよ」ですって・・(^^)
(長期欠席の生徒に、学校の方から色々呼びかけてもらったんです)
「ちよっと音声が、衛星放送が始まったときのような・・・」
だったので、電話と平行しておこなったのですが・・・
たかがインターネット・されどインターネット・・・ですねえ。
(CU-SeeMeのちっちゃな画面・・・客観的には、どってことないというか・・・でも、「つながり」ですかねえ。(^^))
思い起こせば長い道のりだった・・・
回線を太くして下さったIPA・CECさんはじめ幾多のアドバイスなど、精神的支援も含めて、ここのメンバーのみなさんには色々助けていただきましたし感謝の念にたえません。ありがとうございました。m(_)m
p.s. 送信しようとしてPHSを見たら・・・電池切れ・・・
大活躍だったんですねえ。グレー電話で送信してみます。
と思ったのですが、うまくいかないので自宅から・・・
・98年1月24日
・・・学校に来たら、机上に以下のようなメモがおいてありました。
伊藤丁へ
**君と一緒の授業、みんなとても楽しんでました。
なんかワクワクする時間でした!
現場にいてよかったというか・・・いいでしよう。(^^)
・98年1月25日
・・・なぜワクワク出来たか・・・
もしかしたら、耕しもの好きの先生(と子どもたち)だったからかも知れませんが、逆に、見えそうで見えない・見えなそうで見える・・・
そんなような状況があったからかも知れない・・・
***ティーズの世界ですね。(^_-)
そんなような事を考えたりしています。
以前、ある場所で1.5Mbpsのケーブルで直結したテレビ会議システムを見せていただいたことがあるんですが、なんだか・・・だったんです。
負け惜しみかも知れませんが、このシステムでやっても・・・
といった感想・予想が、少し頭をよぎったんです。
今回のCU-SeeMeを使った実験の意味を整理してみると
・相互(長欠の生徒(家庭)と学校の生徒(含む教員))の問に伝えたいものがあった(相互の存在を気にしていた)
・伝えたいものがあるにもかかわらず、なかなか伝わりにくかった (かろうじて伝わった・・・どきどき・スリルの世界?)
・PHSの電波が届く家庭なら、どこの家からでも可能である。
つまり、伝えたいものがあまりない状態で環境整備の方はかり整えても感動的なコミュニケーションにはなりえない・・・
コミュニケーションの本質を考えると、当然のことだと思うのですが。
来週というか今週は、来年度高等部に進学が予想される訪問籍の生徒の家への家庭訪問があります。教育相談の先生が管理職と訪問する予定ですが、その場所に、パワーフックを持っていってもらう・・・
そんなような話もしています。そこでどうなるか・・・また楽しみです。
・98年1月27日
・・・今連絡が入りました。PHSが使えないようです。^_^;
アンテナを買わないといけないかな・・・
C. 肢体不自由教育における在宅学習支援の現状と課題
以上、二つの異なった環境における在宅学習支援についての事例について紹介してきたが、以下のように整理できるのではないかと思う。
・在宅学習支援をするにあたって一番重要なのは、在宅を余儀なくされた児童・生徒のコミュニケーション意欲を如何に引き出し育てるかにある。そのために支援する側はどのような環境を整えればいいのか。金立養護の事例は、貴重な教訓を提示している。
・テレビ会議システムを使った在宅学習支援の試みには電話回線を使った専用テレビ電話を使うケース、ISDN回線で双方のパソコンをつなぐケース、インターネット上で動作するテレビ会議システムを使うケースなどいろいろな方法が考えられる。ここで紹介した光明養護の事例は、インターネットを利用したケースであるが、この実験結果によれば、回線速度は最低でも32kbPsくらいないと、実用にはならないということであった。工SDN回線が普及してきたとはいえ、一般家庭の中でISDNを利用している所はまだまだ少ない。
全国各地で肢体不自由養護学校の高等部の訪問教育の試行が始まっていることをあわせて考えたとき、現段階では、ノートパソコン十PHSという環境か最も現実的と言える。今回、光明養護の実験では、PHSについては教員個人のものを利用してみたが、公費で購入できている学校は多くはないと思われる。早急な対応がのぞまれる。
しかし、教育利用ということを考えたとき、それ以上に重要だと思われるのは、在宅学習支援=子どものコミュニケーション支援だということだと思う。それさえ忘れなければ、最低限の環境でも大きな教育効果をあげられる。光明養護の実験はそんな事を示唆しているようにも思われる。
注1:チャレンジキッズ
滋賀大学教育学部付属養護学校内に設置された、インターネット経由で接続できるパソコン通信のネット局。/インターネットのWebサイトコンテンツが、基本的に公開されたものであるのに対して、会員制なので、児童・生徒のプライバシーが保ちやすい。/ファーストクラスというGUI(GraphicalUseresInterface)環境のソフトを利用しているため、児童・生徒にとっても操作がわかりやすい。/インターネット経由で接続が可能であるため、遠距離電話をする必要がなく電話代を気にしないで安心して利用することが可能である。/などの利点がある。
インターネット上に設けられた障害児教育のためのインドラネット=パソコン通信とインターネット、それぞれの利点をいかした広域ネットと言うことか出来る。
注2:教育課程の基準の改善の基本方向について(中問まとめ)
http://www.monbu.go.jp/singi/00000128/index.html参照のこと
注3:「インターネットと障害児教育」というメーリングリスト
100校プロジェクト「特殊教育共同利用企画」推進のためのメーリングリストとして、95年12月14日に発足した。その当初の目的は、「1OO校プロジェクトの特殊教育諸学校8校における活用研究と実践が円滑に進むよう、各学校・先生方への支援と検討の場を提供する。また、子どもたちの積極的な企画が実現できるコミュニケーションの場として活用し、様々な試行を行いながら障害児教育から様々な発信
ができるよう、準備を整える」ことにあった。
参加者は、100校プロジェクト参加校のうちの特殊教育諸学校担当者にアドバイザーグループなどが加わって、15名でスタートしたが、その後、いくつかの紆余曲折を経て、小・中・高等学校教員・教育委員会指導主事・障害児教育研究者・リハビリテーション工学研究者・地域の施設職員など100校プロジェクト参加校以外からも参加を得て、98年2月現在で約100名の規模になり、<「障害児教育」と「インターネット」・・・二つの(andあるいはor)キーワードに関するフリーディスカッションの場>として続いてきている。
このメーリングリストの活動と課題については、6.4.2で述べる。
(3) 知的障害児童・生徒を対象としたWeb利用等の実践
-タッチパネルの利用を中心として-
本校の児童・生徒の障害の状態は多様であり、中でも発達の遅れが大きい者の中には、マウスが使えないなどインターネットの操作が難しい場合も決して少なくない。
この子どもたちにも画面上に張り付けた透過型のタッチパネルを利用することでWebサイトコンテンツにアクセスできるようにすることは、今後ますます増加するであろうWeb資源の利用をとおして学習や生活に役立てたり、自分から対象に働きかける力を育てたり、生活を豊かにし、生活の質を高めることにつながるのではないかと考えた。その際、既成のWebサイトにアクセスするだけでなく、大学生にインターネットボランティアとして、本校の子どもたちが楽しめるような、わかりやすく、生活にも役立てることができるWeb教材を作成してもらった。そして子どもたちが試した結果をフィードバックしながら、より学習に利用の可能性が高いWeb教材作威を目指している。また、こうしたWeb教材作成にあたっては、本校や子どもたちのことを知ることが重要であるため、学生と子どもたちが会う機会を設けたり、オンラインでの交流も平行して行っている。
a. 方法
本校の児童・生徒が楽しめるWeb教材を作成していくには、本校の児童・生徒について知ること、できれば本校の児童・生徒と直接会うことが重要である。
さらに日常的にWeb画面やメールにある程度接しており、時には会って打ち合わせすることができ、何よりもWeb教材を掲載できる環境を持っているという点で、福井大学教育学部情報文化社会課程の学生さんたちに依頼することにした。
また、子どもたちが良く知っていてなじみが深いと思われる既成のホームページ (Webサイトコンテンツ)にもアクセスしてみることにした。その際、そのホームページの管理者の許諾を得て、そのホームページ内にある画像を、本校のホームページには公開していない、本校内だけで使うローカルなWebサイトコンテンツに貼り付け、その画像をタッチすることでWebにリンクできるようにした。
b. 利用環境
<本校>
タッチパネル、パソコン(Macintosh7300/180)両機器は借用物品。
〈インターネットボランティアヘ>
デジタルカメラQV-10と接続機器一式(貸与)
福井大学教育学部技術科の塚本先生に研究室学生のインターネットボランティアのために、WebサーバとしてWindows95マシンを1台用意して頂く(平成9年11月21日)。これは、1日式のマシンを改造したものであるが、学内LANに接続され、終日電源を入れている機器である。
またWebサイトコンテンツによる情報提供だけではなく、オンラインでの音声交信やお絵描き等の共同作業をして頂くためにマイクとスピーカを接続したコンピュータを1台用意して頂いた。(平成9年12月10日)CPUはMMXPentium
(200MHz)、ハードディスクの空き容量は、2パーテーションで合計約1.8GB。メモリは64MB.10Base-Tで学内LANに接続。
| 10月21日(火) | 来校、ビデオ視聴、クラブ見学、生徒と対面 3時に来校して4時まで在校 |
| 10月23日(木) | 本校教育研究集会参加 9時から10時30分まで。 |
| 10月28日(火) | 2時15分-3時まで来校 チャレンジキッズについての説明 |
・オフライン・オンライン交流の様子
10月21日
実際には少し、自己紹介をするぐらいだったが、自己紹介できたのは、A生徒ぐらいで、B生徒は、與味があるものとして手芸と絵も言うことができた。学生さんの中には、絵を描くことが好きな人やみんなのことを知りたいという人もいた。
10月28日
学生さんが作った既存の学生さん自身のホームページを見てみる。最近繰り替えし見ているお気に入りのホームページを見ようとしていた子も、それなら見たいと言いだしていっしょに見る。生徒たちの中には長いURLを入力して自分で見る子もいる。学生さんの作ったレポートのページなど、何これと言った感じで興味深そうに見ていた。
・オフラインで会った学生さんからの感想のメールから
Date:Thu,6Nov9717:51:43JST Subject:fukudai saitou
水野先生へ
福井大学のSです。この間の教育研究集会に参加させていただき、はじめて授業風景をみせていただいたのですが、一人一人が自分の得意なことを楽しんで勉強していることをしりました。
また、パソコンクラブの4人のみなさんがたいへい上手にパソコンを使かっていたのをみて驚きました。それにみなさんすごくパソコンに興味があるんですね。
自己紹介した時はみんなあまり私達のほうをみてくれなかったので少し不安になったけれど、きっと恥ずかしがっていたのでしょうね。メールのやりとりをしているうちに仲良くなれたらいいなと思います。
| A生徒 | 手芸、絵 |
| B生徒 | ゲーム、アニメ、有名人 |
| C生徒 | 声優さんのホームページ、動物、ファッション |
平成9年12月18日学生へのWeb教材作成依頼内容
(タッチパネルを使う子どもたち向けに)
アニメのキャラクターの画像や真似て使うことは著作権の関係で避けて頂き、自由に気楽に「マンガチック」に描いて欲しい。例えば、デジタル紙芝居?風に1ページずつボタンをクリックして頂くと物語が展開するという構成で。
(パソコンクラブの子どもたちたちへ)
学生さん自らの生活や経験から「衣食住や余暇、交通、旅行、日常の出来事」など身近な話題でできれば役に立つような(すぐには役に立たなくても良い) 情報で、子どもたちが学生さんの情報を基に実際に体験できるとか、生活上の身近なことで本校のような障害を持った子どもたちにとって「生きた生活情報」となるようなもの。
平成10年1月
学生さんの作成途中のページを見たA生徒が学生さんたちにお礼のつもりで絵を描いた。それに対してお礼のメールが来た。
 |
Date:Wed,21Jan9811:50:15JST Subject:養護学校のみなさんへ Aちゃんの絵を、見せていただきました。 とても素晴らしいプレゼントですね。どうもありがとう。 私達も、早くホームページを作ってみんなにプレゼントしなくてはいけないのに、遅くなってしまってこめんなさい。 あとちよっとで仕上がる予定ですので、もうしぱらくお待ち下さい。(後略) |
<作成したWebの内容について>
トップページ----目次----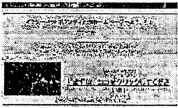 |
*福井大学だよ *ふだんの私たちは... *絵であそぶ *えであそぶ(ひらがなバージョン) *おすすめページへのリンクしてみては? *あたらしい情報 |
*ふだんの私たちは...-----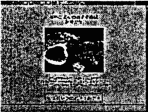 |
*授業のあとは...(サークルやバイト) -おすすめのお店 お天気のいい日は *旅行しました ------九州に行きました スキー(菅平)に行きました さくらは「韓国」にも旅しました 東京に行きました |
おすすめのページの内容
とてもお勧めできるリンク *福井大学教育学部附属養護学校*
Aちゃんは絵が好きだから *美術館のページヘご招待します*
Bちゃんは *声優さんのページへご招待します*
Cちゃんは***どんな歌がすき?***
Dちゃんは***占いは好きかな?***
「そのほか私たちのおすすめページですよ」
*サンリオのキャラクターたち*
*安室奈美恵なんてどう?**ただ今大人気の”V6”*
*フジテレビにもいってみよう*
*日本テレビにもいけるぞ*
*行きたい遊園地を見つけよう!*
そのほか興味のあることは
これらのサーチエンジンで探ってください。*おなじみのYAHlOO!だよ*
*私達のページヘリンクします*
d. タッチパネルの利用
<既成のホームページヘのアクセス>
インターネットボランティアである学生さんがWebを作成するまでにタッチパネルに慣れ親しむことやホームページにアクセスするおもしろさを経験させるためにタッチパネルを用いて既成のホームページヘのアクセスを試みた。
(事例)
子どもたちが興味を持っているキャラクターの一つであるアンパンマンのホームページにアクセスすることにした。その際、ホームページの管理者や著作権を持つ、日本テレビ及び、日本テレビ音楽部の了解を得て、アンパンマンのホームページのトップページに使われている比較的大きめの画像を用い、その画像をクリック(触れると)するとアンパンマンのホームページ内のなかまたちの紹介のページにリンクするようなローカルな(本校のホームページに組み入れない)
Webサイトコンテンツ(HTML文書)を作成し利用することにしてアクセスしやすくした。
対象児童・生徒
マウスがうまく使えない小学部児童2名・中学部生徒1名
結果
小学部児童のうち、一人は、週1回のべースで2回、合計40分程度の指導でWeb内のキャラクターの画像をクリックすれば、見たい画像を見ることができることやWWWブラウザ(今回は、NetScapeCommuinicator4.01)の左上にある「戻る」ボタンを押すと元の画面に戻ることを理解し、1回押しても戻らない時はもう一度押すことがほぼできるようになった。また、キャラクターの画像が出てくることを楽しむだけではなく、文字に興味を示し、アンパンマンのホームページの別のページの漢字交じりの文やひらがなの文を良く読むことができた。
考察
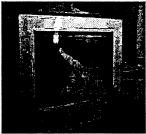 |
本児童は、マウスをファミコンのゲームを操作するように両手で宙に持ち上げて操作しようとする状態で、まだマウスは使うことはできない。今回、タッチパネルを用いることで教師が支援する中で自分の力でホームページ見ることができ楽しむことができた。 今後、学習を重ねることによって、おそらく普通にマウスを使うことができるようになるのではないかと思われるが、タッチパネルがあれば、直感的で操作しやすいためにタッチパネルも平行して使い続けるものと思われる。 |
反省と課題
まだ現在は対象とする児童・生徒を限定した実験的なものだったが今後は、できれば生活する教室や遊戯室等に置いて学級や学部のみんなで使うようにしていきたい。その中で、情報に接することやパソコンを操作することだけではなく、きれいな手でタッチパネルに触れるというような基本的生活習慣に関わること機械を乱暴に扱わないということやパソコンを使う際には、順番を守って使うことなどのルールも教えていけるのではないかと考えている。
<インターネットボランティアが作成したWebの利用>
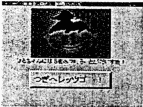 |
タッチパネルの利用を前提としたWeb作成の件が学生さんに十分に伝わらなかったためか、最初に出来上がって来たものは、文字の色(テーブルで囲まれた文字を含む)の部分だけで、次のぺージへにリンクするものであった。そこで、とりあえず利用しやすいと考えられた絵本のページの中のイメージをクリックすることで次のぺージにリンクできるやり方でホームページを修正するように依頼した。 |
ところで、当Webについては幾つか改良して欲しい点があった。そこで、平成10年2月の新100校プロジェクトの事務局の方々の視察に合わせて、インターネットボランティアに本校に来校してもらい、学生さんが作成したWebについて話し合った。そこで浮かんできた問題点は、次のような点である。
・文字をクリックすることでリンクするだけではなく、ボタンの画像を利用してよりわかりやすくする必要があること。またその画像はできれば大きくはっきりしたものが望ましい。
・ボタンに使用する画像は、同じ働きを持たせる場合、画像は統一し、児童
・生徒が操作に迷わないようにすること。
・ボタンに利用する画像は、児童・生徒が作成した画像を用いると親しみを持つことができる。
・単に画像だけではなく、音声がある方がイメージを広げることができたり、親しめ、楽しめるWebにすることができる。
今後、これらの点を修正したWebを作成して頂き、本校での利用を図っていきたい。
ところで、学生さんが作成したWebは、パソコンクラブの生徒たちの利用を念頭に置いたぺージが多い。生徒たちは、自分の興味のあるページや学生さんの日々の生活のページを見ることを楽しんでいる。
e. 反省と今後の課題
今回のWeb作成は、最初は電子メールに画像や音声等を添付するというかたちで、学生さんから子どもたちにとって役に立つ身近な、あるいは楽しめるような情報提供を考えていた。ただ、データのサイズも関係するのだろうが、メールに添付することはネットワークトラブルの恐れがあることを大学関係者から指摘され、Web利用に切り替えた。また、以前からタッチパネルを用いれば、今まではマウスを使うことができずに自分でネットワークを利用することができなかった子どもたちの多くも利用できるようになり、利用が増えるのではないかと考えていた。
ただ、今回の学生さんは自分のWeb作成の経験はあるものの年末、年始の時期を含めた大学の休業期間と重なったこともあり、Web作成のための企画、情報収集、作成に手間取った様子で、実質1か月余りかかった。また、できたものから少しずつ公開するのではなく、全部できてから公開というかたちになったため、例えば、学生さんからのメールが来ていないかを期待して待つというようにネットーワークを生活の楽しみにするという姿は残念ながら見られなかった。もっと手軽に情報を提供して頂く方法がないかと考えている。
こうして出来上がって来たWebを子どもたちは楽しんでみている。なぜならばWeb画面はマルチメディア性に優れ、情報を手軽に集中してみることができるという点が優れているからであろう。
今後は、Web教材だけではなく手軽で即時的な情報提供であるメールやNetMeethgなどのネットワーク会議ソフト等と併用していくことがより望ましいのではないかと考えている。
また、情報提供を依頼するインターネットボランティアの方が、十分な利用環境を持っているわけではない場合は、ネットワークにこだわらず、VTRなど別のメディアと併用することを含めて、児童・生徒の興味・関心やイメージを豊かにし、よりわかりやすく、身近で役に立つネットワークにするためにボランティアの人に動画像を提供していただけないかと考えている。
また最近、全国的な障害児学校・学級のネットワークであるチャレンジキッズにアクセスするために、サーバー校である滋賀大学教育学部附属養護学校よりインターネットボランティアの学生さん用にIDを発行して頂き、利用できる環境を用意した。まだ利用はこれからという段階のようだが今後は本校の子どもたちとのメール交換だけではなく、利用する中で個人情報の保護を念頭に置き、障害児教育、ネットワーク利用の様子を知り、そこで行われる参加している全国の教師から障害を持つ子どもたちへのメールを良い手本にしてメールの送受信を行っていくことで、よりオンラインでの交流が深まると考えてい孔ところで今回は、作成してもらわなかったが、例えば福井大学のボランティアサークルのメンバーでもホームページを持つ学生がいる。また教材研究や教育実習等、学校に来て本校の児童・生徒と接している養護課程の学生さんの協力が得られれば、より身近でわかりやすい親しみやすく、子どもたちの障害や特性に応じたWeb作成が期待できると共に学生さんとの学習にも役立てることができる。またWeb等を通して情報提供や交流等が期待でき、とかく閉鎖的になりがちな養護学校における、子どもたちを支援する人々や社会との新たで今後の成長が期待できる窓口になる可能」性を秘めていると思われる。
また学生さんのみならず、例えば福井県のある接続業者のホームページにある
ホームページであるボランティアのページも利用可能だという。
(例http://www.mitene.or.jp/vo1unt/index.html)
また福井県の公共施設の一つである生活学習館では、来年度、児童・生徒が知りたいことを調べるというサービスを開始することを構想中と聞いている。
今後は、前述のように本校以外のWebを利用して本校の児童・生徒を支援する情報の提供を求めたり、インターネットの講習を行っているカルチャセンター等を通して本校の児童・生徒を支援する情報を提供して頂くような地域に根ざしたインターネットボランティアを募集していきたい。そうすることで単なるインターネットボランティアからインターネットボランティアネットワーク(仮称)の形成を目指していきたい。