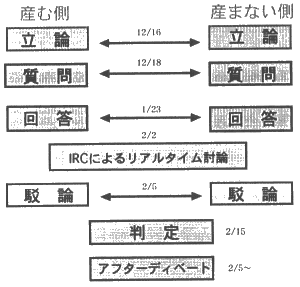
図1 オンDの流れ |
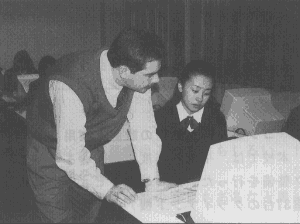
図2 IRCでチャットをする生徒たち1 |
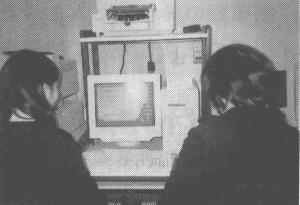
図3 IRCでチャットをする 生徒たち2 |
| 活動計画 | 活動内容 | |
| 5月 | 交流の開始 | 「倫理」の授業で行った「青年文化」についての生徒のアンケートやディスカッションを東北学院でも実施してみる。アンケート結果やディスカッションの結果をメールで送り,それを東北学院の高校2年生のホームルームで扱い,その結果を送ってもらって比較する。 |
| 6月 | IRC (インターネットリレーチャット)を使ったチャットによる交流 | 生徒たちに「インターネットを通じて仙台の男子校と交流してみよう」と呼びかける。月曜日と木曜日の放課後,4時から5時までを定例のチャットの時間とする。CU-SeeMeによる画像転送も試みる。 |
| 7月 | 倫理の論題による第1回オンD(参加校:東北学院高校,宮城県立泉高校,清泉女学院高校) | チャットによる交流が定着した頃オンDをすることを生徒に提起する。論題は「茶髪,ピアス,ルーズソックス等のファッションは高校生らしい文化である」である。有志の生徒が行う。 |
| 9月 | 教員・技術者のオンD | 生徒にオンDの楽しさやその”妙”を伝えるたに,教師もオンDを体験する。論題は,「日本の教育に,飛び級制度・飛び級選抜制度(例えば高2→大学)を導入すべし」である。 |
| 10月
30日 |
福島盲学校参加に当たっての会議 | CEC ,福島盲学校,東北学院により,第2回オンDに盲学校の生徒が参加するにあたり考慮すべき点について話し合う。 |
| 12月
〜 2月 |
家庭科の論題による第2回オンD(参加校:東北学院高校,宮城県立泉高校,福島盲学校,松山東雲高校,高校生同盟,清泉女学院高校) | 論題は,以下の利用場面に示すとおり。同論題による教室ディベート後,オンDを行う。全4クラスの生徒が関わる。 |
3 利用場面(第2 回オンD,家庭科における取り組み)
| 活動内容 | 留意点 |
| ・教室ディベート,オンD開始に当
たり,グループごとに作戦を練る。 |
それぞれのグループ(7,8人)に別れ,いろいろな視点(倫理面,経済面,精神面,この女性の将来,相手の男性の将来,子どもの将来,子どもの命について等)からA,B両方の立場を考えさせる。A,Bを比べて,一方よりもよいと思われる点はどんなことか気付かせる。 |
| ・同論題で教室ディベートを行う。
・オンDを行うための準備をする。 |
オンDを行うグループとは別のグループに担当させる。 |
| 1.参加する生徒のグループ,担当教員,支援者,判定者それぞれがメールアカウントを持つ。
2.担当教員,支援者,判定者のメーリングリストにより企画や技術上の問題を話し合う。 |
生徒のアカウントは以下の例のように設定する
例) umu-b@ 〜 ,umanai-b@ 〜 立場 クラス 立場 クラス |
| 3.運用に関しての質問を受け付ける メーリングリストを用意する。 | 例)ond-c@ 〜 |
| 4.肯定側,否定側それぞれにメーリングリストを設け,学校を超えてそれぞれの立場で情報交換や作戦をたてる場を与える。
5.ディベートの立論や質問などは東北学院の担当者がプールし,対戦相手に同時に送る。また,それを随時ホームページに公開することとする(図1参照) ・対戦相手の決定
|
例)
肯定側 ond-koutei@ 〜 否定側 ond-hitei@ 〜 対戦相手の組み合わせ A-ROUND 清泉B 組肯定 - 東北学院否定 B-ROUND 東北学院肯定 - 泉高校否定 C-ROUND 泉高校肯定 - 清泉N 組否定 D-ROUND 清泉N 組肯定 - 松山東雲高校否定 E-ROUND 高校生同盟肯定- 清泉J 組否定 F-ROUND 清泉J 組肯定 - 東北学院否定 G-ROUND 福島盲学校肯定- 清泉P 組否定 H-ROUND 清泉P 組肯定 - 福島盲学校否定 I-ROUND 東北学院肯定 - 清泉B 組否定 |
| ・オンDの開始
立論を送る(図2)。 公開質問を送る。 回答を送る。 |
おもに放課後の時間を用い,グループで協力,分担させる。
35文字×60行または句読点も含め1700文字以内 1 質問は100文字以内,質問は全部で5つまで。 1 回答は150文字以内。 |
| ・授業でオンDの様子を確かめる。
IRC によるリアルタイム討論(図3) 反駁作成(現在進行中) |
この時点までの流れをプリントにし,クラスでオンDの流れや他の学校の意見を分かち合う。
チャットによる質疑応答。 否定側反対尋問10分。肯定側反対尋問10分。 35文字×30行または句読点も含め850文字以内 |
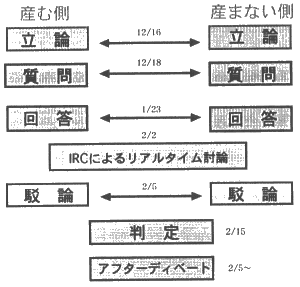
図1 オンDの流れ |
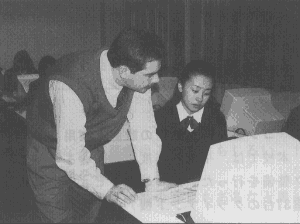
図2 IRCでチャットをする生徒たち1 |
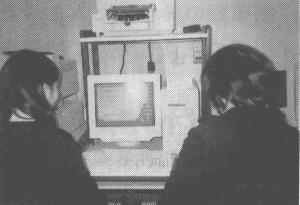
図3 IRCでチャットをする 生徒たち2 |
| ワンポイントアドバイス
1つは,オンDに費やす日にちについて。第1回オンDは,夏休み前に2週間ほどで終わらせ,生徒たちにとってはかなりきつい日程だった。第2回オンDは,冬休み前に始まり,冬休みを挟んで再開し,2カ月ほどかけて行っている。余裕がある日程ではあるが,生徒たちにとっては,反応が遅く,じらされている感を持ったようだ。 長期の休みを挟まず,1カ月ほどの期間をかけるのが理想といえる。 2つ目は,各校におけるオンDの扱い方の違いについて。今回は,すべての学校の担当者が異なる教科を担当し,オンDの扱いも,授業,部活,放課後の個人参加とバラエティーに富んでいた。同じ教科の授業と授業の結びつきができると,論題に対する考えも互い学校で深まり,より教育効果が高いと思われる。 3つ目は,方法としてのディベートについて。ディベートの技術の追求に走ると相手をやりこめることばかりが先決となってくる。家庭科の授業では,あくまで自分の考えを深めること,考え方の多様性に対する認識ができることを目的とした。 |
 インターネットを利用した授業実践事例集2 平成9年度
インターネットを利用した授業実践事例集2 平成9年度