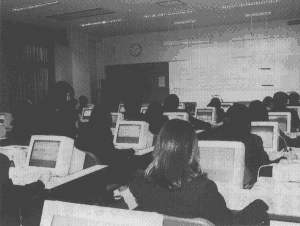 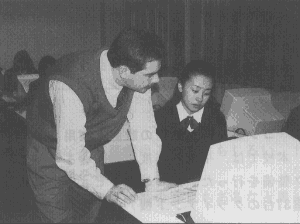
図1,2授業風景(Web での検索) |
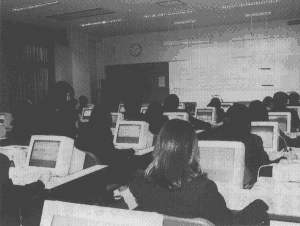 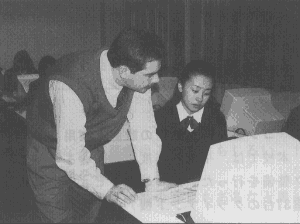
図1,2授業風景(Web での検索) |
| 時期 | 内 容 |
| 2 年次
1 学期 |
・自己紹介:家族,好き/嫌いなもの,趣味,興味,将来の職業などについて
・人の体,個性など,周りの人について紹介 ・家や家の周りの様子について話す ・地図上の建物の場所などを説明 ・日本について: 日本語の単語の意味を英語で説明・地理,歴史,文学,文化の紹介 ★オーストラリアについて知る: 歴史,自然,地理,文化,その他6週間のホームステイに関する準備 |
| 2 学期 | ・カカドゥー国立公園でのキャンプ生活を経験した後,オーストラリアのゴー
ルドコーストで6 週間のホームステイ ・日本とオーストラリアの生活の違いについてレポート ・オーストラリアでの経験についてのスピーチ ・オーストラリアでの経験についてのエッセイ |
| 3 学期 | ・オーストラリアでの経験についてのエッセイ(推敲,完成)
★スピーチ(物語の暗誦) ★リサーチペーパーのトピックを選択 検索の仕方を学び,リサーチを開始 |
| 3 年次
1 学期 |
★3 学期に引き続き,リサーチペーパー作成
・スピーチ ★ニュースのレポート ★ディベート ★時事問題についての議論 ★リーディングのテスト |
| 2 学期 | ・即興でスピーチ
★電子メールの使い方 ★ビジネスレター ・履歴書作成 ・模擬入社面接 ★リサーチペーパー完成 |
| 生徒の感想
高校三年生のとき,英語で日本のものを紹介し,論文にするようにと課題が出されました。1年間,その論文に時間が与えられたので,自分の選んだ分野に関して,深い知識と出来るだけ多くの資料が必要となりました。そんな時に,インターネットの活用が非常に有効になりました。 例えば,僕の選んだトピックは「相撲」だったので,インターネットの検索エンジンに「すもう」と入れます。そして,検索ボタンをクリックすると相撲に関する,日本中あるいは世界中のホームページが一覧になって出てきます。それは,全日本相撲協会から,一般の相撲愛好家までの幅広い資料をのぞくことが出来ます。ページによっては,写真が豊富に使ってあったり,ビデオを見ることができたりと,視覚的にも楽しく調べることができました。そして,各ホームページの最後には,そのページを作った団体あるいは個人へメールが出せるようになっており,質問や意見をやりとりすることも出来ます。 このように,インターネットはその手軽さ,図書館では決して得ることのできない数々の情報,そして,その道の専門家などと直接質問をやりとりできるという点などで,これからの高校生には有効に使っていってもらいたいと思います。僕は,麗澤高校のコンピューターを使い,自分でも満足のゆくリサーチを書きあげることができました。(平成8年度卒業生) |
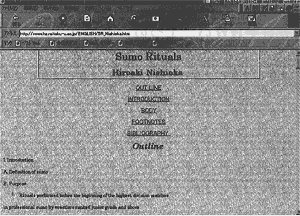 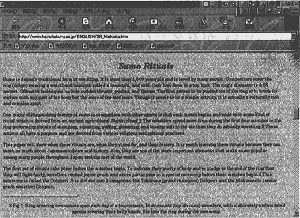
図3,4 麗澤高校のページより リサーチペーパー |
4 Web 活用の利点
| ワンポイントアドバイス
インターネットというと,Web で好きなアイドルのページを開いたり,新しい音楽を探して聴いたりといった,趣味の範囲での利用に留まっていることが多いように思う。また,E-mailも使われているが,ただ単なるおしゃべりだけで終わっていないだろうか。Webのページにしても,E-mailにしても,有用な情報を得ることができる非常に便利なものである。特に,Webでどのような情報がどれほど手に入れることができるか,気付いていない場合が多いのではないか。検索エンジンといえば日本ではYahoo!JAPAN が有名だが,検索エンジンはそれだけではない。1つの検索エンジンで検索できなくても,他から見つけることができることもある。 インターネットは,趣味の範囲で終わるものではない。まだまだ意義のある利用ができるということを知り,活用をしていきたい。事実,ただ情報を得るだけで終わらず,生徒の学習成果を海外に発表する機会としても位置づけることができるのだ。今後もさらなる利用価値を求めていきたいものだ。 |
利用したURL
 インターネットを利用した授業実践事例集2 平成9年度
インターネットを利用した授業実践事例集2 平成9年度