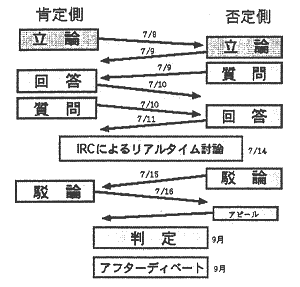
図1 第1回オンラインディベートフォーマット(引用3) |
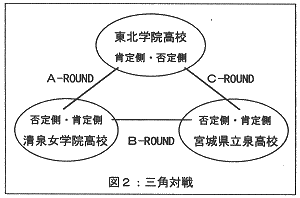 |
| 指導計画 ★全てインターネットの利用 | 留意点 |
| (1) 共同実践者の連絡手段の確保
メーリングリストが望ましいが,同報メールでも可能である。 ディベートの運営側用と参加者連絡用が必要である。 |
・特に遠隔地を結んでのディベートを実施する際には,実施計画を作成にするにあたって多くの連絡・確認が必要となるので,十分に運用されるような配慮が必要である。
・自己紹介をさせるなどをして,メールの送受信の仕方について指導する |
| (2) 論題の確定
メーリングリストを用いて,取り上げたい論題を募集し,選択・決定する |
・生徒たちの興味・関心・意欲を配慮し,できれば参加者の意向を尊重したいが,授業への導入のため,教員側で設定する場合もある。
・ディベートの成立のため,肯定側・否定側のどちらかが有利になるような論題は避ける。 |
| (3) 参加者・対戦相手の確定
肯定側・否定側が同数になるように調整をして確定する。 確定後, 対戦相手を決定して参加者に伝える |
・参加者を配慮して,偏りがなく,なおかつ作為的ならないように対戦相手を決定する。 |
| (4) ディベートのフォーマットと日程の確定
ディベートのフォーマットを決め,要する日数を計算する 各学校の行事日程等とも照らし合わせて,日程を決定する |
・各学校の生徒が,どのくらいパソコンを利用できるかによっても,必要な日数が異なる。
・生徒からも日程に関する要望が出る場合があ るので,参加者連絡用のメーリングリストを用いて確認する。 |
| (5) ディベートを行う | * 詳細はコンピュータの利用場面にて |
| (6) ディベートの勝敗判定を行う
口頭のディベートと同じく,フローチャートを作成し,論理的な勝敗判定を行う。 観戦者の意見を参考にしても良い。 |
・良かった部分を取り上げて高く評価し,その部分をみて勝ちを決めるのが望ましい。
・負けたチームにも,至らなかった部分を分かりやすく示し,今後に生かしてもらうように促す。 ・生徒は勝敗判定に対して真剣である。ディベートの内容を十分に把握し,生徒の努力が認められ,かつ判定に納得が行くよう,明確な勝敗提示が求められる。 |
| (7) アフターディベートを行う
メーリングリストを用いて,ディベートを振り返り,勝敗のない部分での意見交換を行う。 実践の反省のために,参加者に対してアンケートを行う。 |
・ディベートが単なる勝ち負けで終わらないように,生徒へ働きかける。
・勝負のために言えなかった“本音”の部分を生徒から引き出し,より深く,論題について意見交換を進める。 |
3 利用場面
(1) 今年度のオンラインディベート実施要項
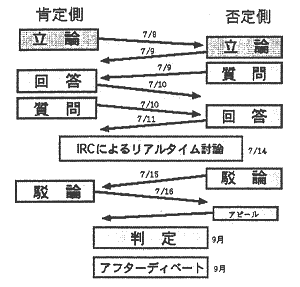
図1 第1回オンラインディベートフォーマット(引用3) |
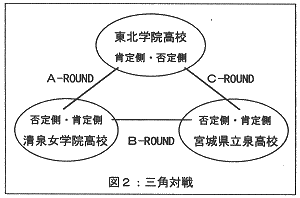 |
(2) 教員+技術者間オンラインディベート 11月11日(火)~11月27日(木)
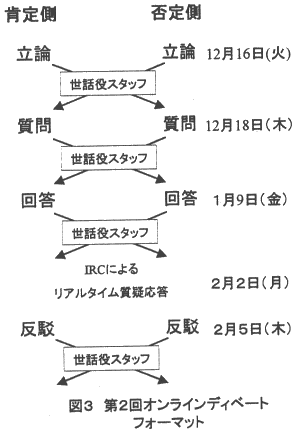 ・参加者・参加校
・参加者・参加校| ワンポイントアドバイス
最も大切なのは,生徒と教員が「共にやってみよう!」と思うことである。生徒はインターネットを用いる場面で困難を感じ,ディベートをする場面では自分の考えを整理するのに苦労する。そこで教員が傍らに立つことで,生徒は解決の糸口を見出し新しい自分を確立させていく。その成長には目を見張るものがある。 次回のオンラインディベートには,秋田和洋女子高校から参加希望がある。本報告をご覧の方で参加を希望される方は,学校,個人共に,ご連絡頂きたい。また,企画の更なる向上のため,ディベートに取り組んでいる方々からのお知恵を拝借したい。 他校との交流ができるのと同時に,一つのテーマについて深く考える好機になる。生徒・教員・ネットワーク環境・企画…全てが成長するきっかけとして頂きたい。 |
参考・引用Web ページ
 インターネットを利用した授業実践事例集2 平成9年度
インターネットを利用した授業実践事例集2 平成9年度