4.4 ヘルプデスクの成果と課題
1.事業内容
(1)平成12年度(以下、12年度)
取扱う質問項目や利用者の対象が違う3つのヘルプデスクサービスを運営し、総合的な教育用ヘルプデスクの要件について調査研究を行った。
3つの調査研究の対象と研究を実施したヘルプデスクサービス名を表1.1に示す。
表1.1 調査研究対象とヘルプデスクサービス名
|
|
調査研究対象 |
ヘルプデスクサービス名(実施団体名) |
|
1 |
教育活動に係る ヘルプデスクサービス |
JERICインフォメーションデスク (早稲田大学) |
|
2 |
情報技術に係る 教員向けヘルプデスクサービス |
学校ヘルプデスク ((財)コンピュータ教育開発センター, 委託先:富士通株式会社) |
|
3 |
情報技術に係る 一般向けヘルプデスクサービス |
パソコン初心者相談所 ((社)パーソナルコンピュータユーザ 利用技術協会) |
(2)平成13年度(以下、13年度)
全国ヘルプデスクサービスとして、12年度同様、「学校ヘルプデスク」を運営し、全国からの問い合わせを対象としたヘルプデスクサービスにおける要件について調査研究を行った。
また、全国から任意の地域を選定し、地域訪問や教員研修との連携により、その地域での地域ヘルプデスクサービスに関する調査研究、および全国ヘルプデスクサービスと地域ヘルプデスクサービスの連携の在り方に関する調査研究を行った。
本調査研究にあたり選定した地域と調査研究方法を表1.2に示す。
表1.2 選定した地域(調査研究方法)
|
1 |
千葉市教育センター(訪問) |
6 |
長野市教育委員会(訪問) |
|
2 |
岡山県情報教育センター(訪問) |
7 |
輪之内町教育委員会(訪問) |
|
3 |
三重県総合教育センター(訪問) |
8 |
鳥取県教育研修センター(訪問) |
|
4 |
西遠総合教育センター(訪問) |
9 |
大分県教育センター(訪問) |
|
5 |
長野県教育委員会(訪問) |
10 |
さいたま市大宮地区(教員研修実施) |
2.成果
2.1利用登録者数/アクセス回数
学校ヘルプデスクの利用登録者数について、12年度、13年度、および合計を表2.1に示す。
表2.1 利用登録者数
|
所属機関 |
12年度 |
13年度 |
合計 |
|
小学校 |
114人 |
42人 |
156人 |
|
中学校 |
75人 |
27人 |
102人 |
|
中高一貫校 |
2人 |
1人 |
3人 |
|
高校 |
64人 |
23人 |
87人 |
|
特殊教育諸学校 |
12人 |
4人 |
16人 |
|
教育委員会等 |
36人 |
8人 |
44人 |
|
その他教育機関 |
30人 |
17人 |
47人 |
|
合計 |
333人 |
122人 |
455人 |
12年度はヘルプデスクセンターを開設したこと(H12.10)や毎日教育メール(H13.1)による広報により、利用登録者の大幅増加があった。しかし、平成12年2月以降の利用登録者数に大きな増減はなく、一般的な推移であった。なお、13年度の利用申請者数は216人で、うち40人が本人確認中、31人が申請却下となった。
12年度、および13年度に開発したFAQコンテンツ数を表2.2に示す。
表2.2 FAQコンテンツ数
|
|
12年度 |
13年度 |
|
登録数 |
804件 |
201件 |
|
総数 |
1810件 |
2011件 |
12年度、および13年度のメニュー検索/自然語検索/よくある質問のアクセス回数を表2.3に示す。
表2.3 メニュー検索/自然語検索/よくある質問のアクセス回数
|
|
12年度 |
13年度 |
|
メニュー検索 |
961回 |
3585回 |
|
自然語検索 |
4845回 |
8714回 |
|
よくある質問 |
891回 |
3839回 |
12年度、および13年度のメニュー検索/自然語検索/よくある質問の時間帯別アクセス回数を図2.1に示す。
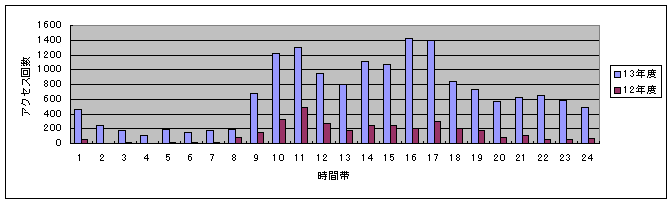
図2.1 メニュー検索/自然語検索/よくある質問の時間帯別アクセス回数
12年度と13年度の調査研究期間に違いがあるものの、利用登録者数とは反対に、アクセス回数は大幅に増加している。しかし、アクセス回数の多い時間帯、少ない時間帯に大きな変化はなかった。
また、12年度、および13年度の学校ヘルプデスクのアクセス数を表2.4に示す。
表2.4 学校ヘルプデスクのアクセス数
|
|
12年度 |
13年度 |
|
総数 |
8642回 |
25866回 |
|
平均(/月) |
1440回 |
2587回 |
検索機能のアクセス数増加に伴い、学校ヘルプデスク全体のアクセス数も増加していることが分かる。アクセス数のさらなる増加のためにも、FAQコンテンツの精査、充足が重要と考える。
2.2 質問内容
質問内容別質問数について、12年度、13年度、および合計を表2.5に示す。
表2.5 質問内容別質問数
|
所属機関 |
質問内容 |
12年度 |
13年度 |
合計 |
|
JERICインフォメーションデスク |
教育的な質問 |
3件 |
− |
3件 |
|
学校ヘルプデスク ※ |
技術的な質問 |
39件 |
69件 |
108件 |
|
教育的な質問 |
3件 |
4件 |
7件 |
|
|
パソコン初心者相談所 |
技術的な質問 |
0件 |
− |
0件 |
|
合計 |
技術的な質問 |
39件 |
69件 |
108件 |
|
教育的な質問 |
6件 |
4件 |
10件 |
※学校ヘルプデスクには、技術的な質問、教育的な質問のどちらにも該当する質問が、12年度2件、13年度2件含まれる。表に示した以外に、回答対象外が12年度3件あった。
学校ヘルプデスクに限って見ると、技術的な質問、教育的な質問、どちらも対象としたが、教育的な質問は全体の1割未満であった。カテゴリ別に見ると、12年度と比較して13年度はネットワークについての質問が急増しており、コンピュータに関するスキルレベルの高い教員からのヘルプデスクコールであることが予想される。
2.3 運営
学校ヘルプデスクとしては、12年度、13年度とも同様のルールで運営を実施した。主な運営ルールを表2.6に示す。
表2.6 ヘルプデスクの主な運営ルール
|
検索およびヘルプデスクコールの質問の受付 |
24時間(年末年始を除く毎日) 質問はWeb上から入力し、送信する。 |
|
ヘルプデスクコールの回答 |
9:00〜17:00(祝日を除く平日) 回答方法はE-Mail、電話、FAXから選択できる。 |
|
利用者登録 |
利用者IDの申請に対し、申請者の存在を確認のうえ、利用者登録を行う。企業関係者からの申請や入力内容に不備がある場合は、その申請を却下する。 |
許可/却下の判断が難しい利用者登録や回答範囲が微妙な教育的な質問等、運営ルール外の事象については、組織内での検討、確認により、迅速かつ適切な対処を行った。
また、12年度調査結果により、運営に対する要望であったヘルプデスクコールの回答時間の拡大については、13年度も24時間または17:00以降の運営を望む声が多かった。教員がコンピュータを利用するのは放課後や自宅であることを考慮すると、本要望については今後検討が必要と考える。
2.4 地域ヘルプデスクサービス
表1.2の1〜9に示した9ヶ所の教育委員会を訪問し、1)環境、2)実施している教員支援体制、3)現在の問題点、4)ヘルプデスクの導入計画、5)全国ヘルプデスクサービスへの期待についてヒアリングを実施した。結果を以下に示す。
1)環境
・学校間で接続台数、接続方法の違いはあるものの、インターネット接続はほぼ100%。
・指導主事(2〜3人程度)で管轄学校全教員をサポートしている。
2)実施している教員支援体制
・ほとんどの地域で、指導主事を中心に、地域ヘルプデスクサービス、または同等の支援を実施している。
・地域ヘルプデスクサービス利用者のほとんどは、学校の情報教育リーダ。
・指導主事、またはSE派遣による教員研修を実施。
3)現在の問題点
・指導主事の作業負荷が高い。
4)ヘルプデスクの導入計画
・電話、メール、来所、訪問による対応を実施している。
・Q&A実績はExcelで管理している地域が数ヶ所あるのみで、コールトラッキングのような管理システムの導入やFAQのシステム化はされていない。
5)全国ヘルプデスクサービスへの期待
・FAQコンテンツの公開。
・指導主事やリーダでも解決できないときの対応。
また、表1.2の10に示した地域で実施している教員研修と連携し、ヘルプデスクの活用モデルの作成を行った。実施した取組みとその結果を以下に示す。
1)取組み
・教材にQ&Aボタンを用意し、即座にヘルプデスクコールが利用できるようにした。
・テレビ会議で受講者とヘルプデスク担当者の顔合わせを行った。
・初心者研修のため、ヘルプデスクを円滑に利用できるように、SEによる訪問指導(月1回)も実施した。
2)結果
・SEによる訪問指導をあわせて行ったため、ヘルプデスクよりも訪問SEへの質問が多くなった。
・SEが対応した質問は、Windowsやインターネットの基本操作に関するものが15件、研修内容に関するものが25件であった。また、Q&Aボタンの操作性は特に問題なかった。以上のことから、研修を継続すればヘルプデスクコールの利用は増えていくものと予想される。
・情報教育リーダ向けにネットワークに関する研修を実施する等、受講対象者や研修内容を変えることでも、ヘルプデスクコールの利用は増えていくものと予想される。
2.5 利用者アンケート
12年度と13年度に実施した学校ヘルプデスク利用者アンケートの結果を以下に示す。なお、人数は12年度と13年度の合計である。
1)メニュー検索/自然語検索/よくある質問を利用するのはどんな時ですか。
分からないことがあればすぐに利用する 9人
インターネット、マニュアル、雑誌で調べても分からない場合に利用する 32人
身近な人に聞いても分からない場合に利用する 25人
2)ヘルプデスクコールを利用しない理由は何ですか。
質問の仕方が分からない 20人
身近な人に質問した方が早い 27人
Web上からの質問分の入力による質問が面倒 11人
メニュー検索/自然語検索/よくある質問で目的の回答が得られる 24人
3)利用者登録制度についてどう思いますか。
現在のままでよい 112人
ヘルプデスクコール利用時毎に名前や連絡先等を伝える方がいい(利用者登録制度はなし)15人
無記名で質問できる方がいい 33人
メニュー検索/自然語検索/よくある質問を利用する前に、インターネット、マニュアル、雑誌で調べる人が多かった。また、ヘルプデスクコールをしなくても、FAQコンテンツで目的の回答が得られるという回答も多かった。以上のことから、FAQコンテンツを充実させること、目的のコンテンツを探しやすくすることが、FAQコンテンツのアクセス回数増加に繋がると考える。
一方で、ヘルプデスクコールを利用しない理由は、身近な人に質問した方が早いという回答が多く、学校では情報教育リーダに質問が集中していることが推測できる。このことから、情報教育リーダをサポートするヘルプデスクサービスを提供する必要があると考える。
利用者登録制度については、7割が現在のままでよいと回答しており、特に問題はないと考える。しかし、2割が名前を名乗って質問することに抵抗を感じていることに対し、メールの替わりに所属機関名のみを記名しての掲示板形式等での質問方法を検討する必要があると考える。
3.今後の展開
Eスクエア・ヘルプデスクプロジェクトにより得られた成果を踏まえ、ヘルプデスクサービスに関する今後の展開について記述する。
(1)地域ヘルプデスクサービスの強化
さまざまな自治体で、地域ヘルプデスクサービスを実施している。その場合、利用者や質問応答履歴を管理するシステムの導入、およびFAQの整備が必要と考えるが、予算と要員の確保の問題から、実現は難しい。
FAQコンテンツの公開は全国ヘルプデスクの役割と考え、Q&A事例のコンテンツ化に必要な項目を含めたQ&A実績管理用フォーマットを提示する等、全国ヘルプデスクが地域ヘルプデスクのQ&A事例を収集するための手立ても必要である。
(2)全国ヘルプデスクサービスの役割の明確化
全国ヘルプデスクサービスは、学校の教員、公的教育機関に所属する教育関係者を広く対象としてきた。しかし、一般の教員はコンピュータを利用して分からないことがあると、校内の情報教育リーダに質問する傾向にある。このことから、考えられる全国ヘルプデスクサービスの役割を以下に示す。
1)情報教育リーダをターゲットにしたヘルプデスクコールサービス
全国ヘルプデスクのヘルプデスクコールは、主に情報教育リーダの問い合わせ窓口として位置付ける。
2)FAQコンテンツの公開
FAQコンテンツは情報教育リーダだけでなく、一般の教員向けのものも用意する。自治体と連携し、地域ヘルプデスクに蓄積されたQ&A事例を全国ヘルプデスクに吸い上げ、それをFAQコンテンツとして公開するしくみを確立することが重要である。
3)情報教育リーダ同士の連携の強化
FAQコンテンツの更新に伴い、既存コンテンツの見直しや収集したQ&A事例の精選といった作業が発生する。教育現場に有益なFAQを提供するため、本作業には情報教育リーダの協力が求められる。利用登録者からその旨のメーリングリストへの参加を依頼する等、さまざまな地域の情報教育リーダ同士がヘルプデスクサービスを通して連携できるようなしくみを検討する。