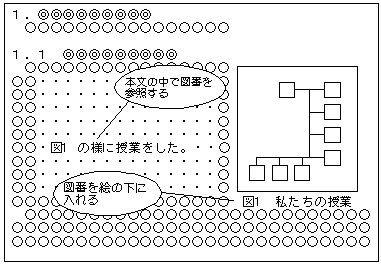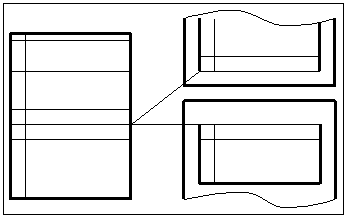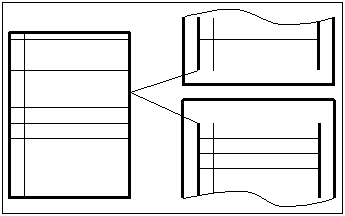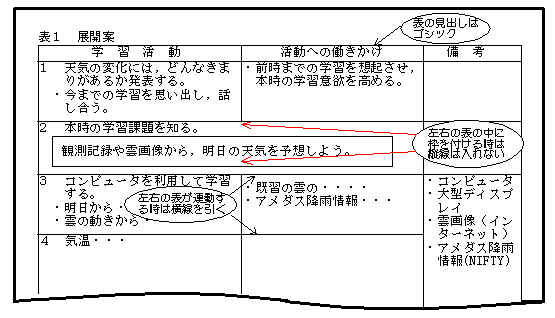原稿 執筆要領
1.原稿の提出の注意
2.提出方法
3.レイアウト
3.1 基本形式
(1) ページの基本形式
(2) タイトルの基本型式
(3) 段落の基本型式
3.2 目的に合わせた形式
(1) 授業実践事例集形式
(2) 発表会レジュメ形式
(3) 報告書集形式
(4) 実施報告集形式
4.文章表現の注意
5.図,表の注意
本原稿執筆要領の目的
本執筆要領は,財団法人コンピュータ教育開発センター(CEC)が書籍やホームページで出版する授業実践事例や研究報告を執筆していただいている先生方に向けて用意しています。
本文の中では,原稿を執筆する上での内容や体裁の注意,その原稿を受け渡しする時の注意を記載してます。
原稿を執筆する時に,本文を頭の片隅において,自由な発想で自由な表現で執筆いただきたいと考えています。
- 1.原稿作成の注意
(1) 修正,出版の等の注意
提出された原稿の著作権は,執筆者に有りますが,当財団から執筆者に許可なく下記のことを行う場合が有ります。このことをご了承下さい。
- ・原稿の内容が著しく目的に合わない場合,修正等の再提出を依頼する場合が有る。また,それが不可能な場合は,掲載をお断りする場合も有る。
- ・原稿の誤字脱字,語尾等表現の修正,レイアウトの変更をする場合が有る。
- ・原稿は,CECまたは公的な団体のホームページや,CECまたは公的な団体が発行する書籍へ掲載する場合が有る。
- (2) 気配りの注意
- 原稿執筆に当たり,第三者の権利保護に注意する。
- ・児童生徒や第三者の写真や人名等を入れる場合,個人情報や肖像権など事前の許諾や配慮をお願いする。
- ・第三者の書籍やホームページ等からの引用や転載をした場合,その引用・転載元を原稿末に記載する。
- [例]著者名,書名,論文名,出版社名,発行年,版,巻,号,引用ページ等
尚,引用・転載の許諾は,原則として執筆者各人で行って下さい。
2.提出方法
原稿は,事務局担当者が依頼する媒体で送付する。
但し,執筆者の都合上他の方法を取りたい場合,事務局担当者にご相談する。
(1) 原稿データの送付方法
原稿はデジタル・データと印刷したデータの両方を提出する。
- 1) デジタルデータの送付方法
- 原稿をHTMLテキストファイルで送る。HTMLテキストファイル以外の形式は,事務局担当者と相談しワープロやテキストで送る。(デジタル・データで送付すると印刷やホームページ化において誤りが少なくなります。)
- ・メールの添付ファイルで事務局担当者へ送付。
(ファイル添付の場合BASE64形式で添付,他のコード変換で送る場合は,事前に事務局担当者にご連絡する)
- ・メールの文章中にテキストとして書込みして送付。
- ・FDで郵送する。
- ・MOで郵送する。(DOS互換128Mバイト/230Mバイトフォーマットで送付)
- ・著作者の管理しているホームページに登録し,URLを事務局担当者に連絡する。(後ほど事務局担当者が貴サーバよりダウンロードする)
- 2) 印刷物での送付方法
- 原稿を印刷して送付する。事務局では,原稿の段落の編集,図や表の位置の編集などに利用する。
- ・ファックスで送付。
- ・郵便で送付。
- (2) デジタルデータの形式
- デジタルデータは基本的には以下の形式が受付可能です。
- ワープロ等デジタルデータ
- ・HTML形式
- ・一太郎(バージョンはVer6-Ver8の形式)
- ・MS Word(バージョンは5.0,95,97)
- ・リッチテキスト形式
- ・テキスト形式
- 今後,ホームページでの内容確認や公開が多くなるため,極力HTML形式で作成する。
- イメージのデジタルデータ
- ・ワープロに直接組み込んだデータは上記のバージョンにする。
- ・他の形式の場合,極力鮮明で,ファイル容量の小さいファイルにする。
- gif形式,tif(tiff)形式,bmp形式,pct(pict)形式,jpg(jpeg)形式
- (3) 写真や図の原稿の送付
- 写真や図は,印刷原稿として印刷紙や写真焼きされた紙を郵送で送付する。
- 但し,印刷解像度が気にならない場合は,極力デジタル・データで送付する。
3.レイアウト
3.1基本型式
(1) ページの基本型式
原稿は,ワープロで印刷した形を考慮して作成する。先に出版物の総ページ数を考慮して編集するので指定したページ数で原稿を作成する必要がる。
事務局編集の段階で,段落や改頁を行い,ページを揃えるため,若干の行数の増減は可能です。
HTMLやテキストで原稿を作成する場合は,1行文字数や1ページの行数の概念が無いため,1行の文字数,1ページの行数を指定されたレイアウトに換算して作成する必要がある。(実際の作成にあったって,改行などを40文字目に挿入する必要は,ありません)
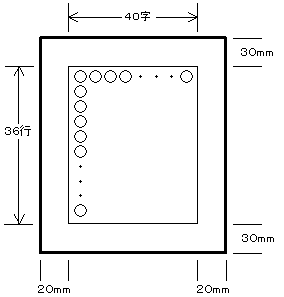
- ・ページの上下,左右の余白や文字数,行数は事務局担当者から指定される。指定されていない場合は,上記の構成を目安にする。
- ・ページの基本は,上記の様に1行40文字で,36行で1ページを構成する。
- ・原稿は,タイトルや著作者諸源,図や表を含め,指定されたページ数で作成する。
- ・本文の標準的なフォントは明朝を利用する。(HTMLの場合標準サイズのフォントとする)
- ・タイトルや項番など強調するフォントは,ゴシックを利用する。(HTMLの場合は標準サイズ太字フォントとする)
- ・テキストの場合は提出された印刷原稿を確認しながら事務局側で編集する。
- ・ワープロや機種によりフォント名が異なりますが,何れかの明朝・ゴシックフォントを利用する。
- ・文字の大きさは事務局担当者から指定された文字フォントの大きさで作成する。
(2) タイトルの基本型式
原稿の種類によって,タイトルや意図(ねらい)などが,本文の先頭に来る場合がる。
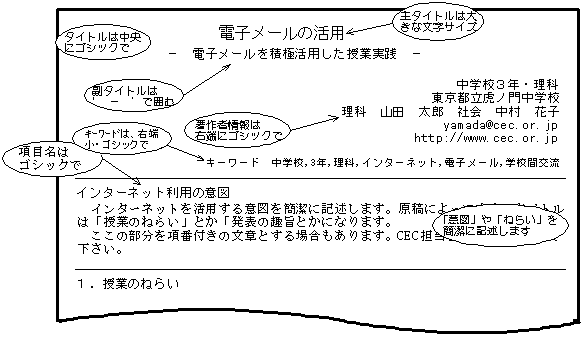
- ・タイトルは,本文より大き目の文字サイズで,中央に記入する。
- ・著作者情報(学校名・所属,執筆者氏名,メールアドレス,学校URLなど)は,タイトルの次に右端によせてゴシックで記入する。
- ・意図やねらいを続けて記入する場合がる。この場合,項目名をゴシック,本文を明朝で記入する。
- ・報告書の形態により,タイトルの形は異なりますので注意する。
- 1) 主タイトル
- 主とするタイトルを記入する。
- ・文字サイズは少し大き目(授業実践事例集の場合14ポイント,発表会レジュメ形式の場合10ポイント)で記入する。
- ・中央に揃え,30字以内を目安として記入する。
- ・HTMLの場合,文字サイズは標準+1で指定する。
- ・タイトル全体を「」で囲まない。
- 2) 副タイトル
- 副タイトルを記入する。省略可能。
- ・中央に揃え,30字以内を目安として記入する。
- ・副タイトルの前後を「 - 」を囲む。
- 3)著作者の情報
- 対象学年・教科
- 対象学年や教科を特定できる場合,記入する。
- 位置 右端
- 所属学校名 担当教科
- 氏名
- 連絡先E-mailアドレス
- 必要な場合,連絡先E-mailアドレスをや自校のホームページURLを記入する。
- 共同執筆の場合,氏名を1行で連続に記入する。所属学校名が異なる時には,複数行に分けて記入する。
- 4)キーワードの情報
- 本文をホームページ等で公開する場合,容易な検索を目指すために,キーワードを記入する。
- ・キーワードの項目には,項目名として太字で標準より少し小さいフォントでキーワードと記入する。
- ・キーワードの項目名に続けて「,」で区切った実際のキーワードを記入する。
- (3) 段落の基本型
- 本文の段落は,以下の例の様になる。
- ・項目番号は,あまり重ねると(例1.1.1.1)見にくくなる。
- ・項番付きの項目(例1.1 ABC や (1) XXX 等)は,ゴシックで記入する。
- ・項番付きの項目の直前は,1行空ける。
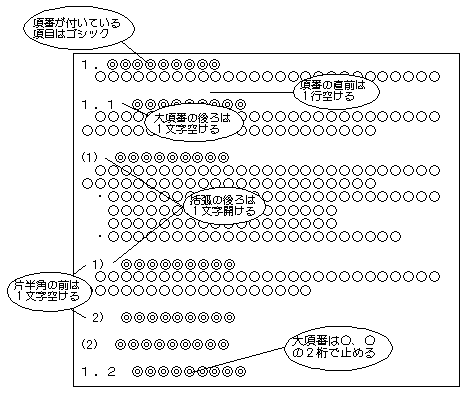
3.2 目的に合わせた形式
ページは,それぞれの執筆する書籍により異なる。
以下に4例を用意するが,事務局担当者が依頼する形式で執筆する。
本文のフォントは,明朝を標準とするが,文字サイズは個々の依頼する形式に合わせる。
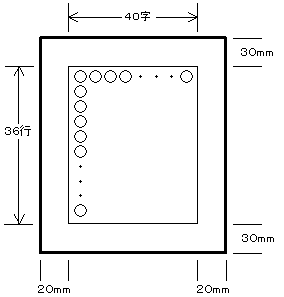 (1) 授業実践事例集形式
(1) 授業実践事例集形式
授業実践事例集のように印刷を主体に構成された執筆物。
- 標準文字サイズは,10.5ポイント
- 1ページの文字数は,横40字(半角80字)×縦36行
- 余白は,上下30mm,左右20mm
- 原稿分量は,写真,図表を含め,6ページ程度
- HTMLの場合,1行40字折り返し換算で216行程度
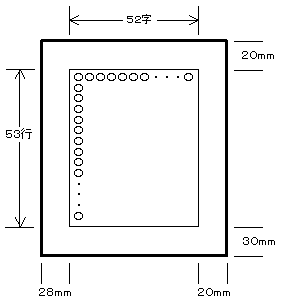 (2) 発表会レジュメ形式
(2) 発表会レジュメ形式
成果発表会で使用する発表用レジュメのように,1ページに多くの情報を盛り込む構成の執筆物。
- 標準文字サイズは,9ポイント
- 1ページの文字数は,横52字(半角104字)×縦53行
- 余白は,上20mm下30mm,左28mm右20mm
- 原稿分量は,写真,図表を含め,2ページ程度
- HTMLの場合,1行52字折り返し換算で106行程度
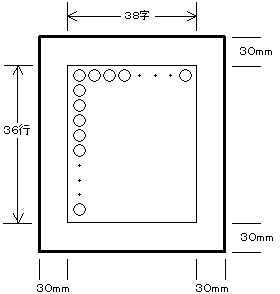 (3)報告集形式
(3)報告集形式
成果報告集で使用する報告書のように,比較的整然と見やすい構成の執筆物。
- 標準文字サイズは,12ポイント
- 1ページの文字数は,横38字(半角76字)×縦36行
- 余白は,上下30mm,左右30mm
- 原稿分量は,写真,図表を含め,CEC担当者の依頼する通り
- HTMLの場合,1行38字折り返し・1ページ36行換算でCEC担当者の依頼するページ数
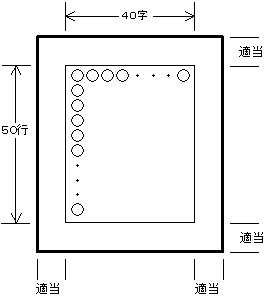 (4)実施報告集形式
(4)実施報告集形式
教育現場のインターネット利用の実施報告集で使用する報告書のように,HTMLで作成しB5サイズ書籍にする執筆物。HTMLで作成する場合,文書の量をWP換算にする。
- 標準文字サイズは,9ポイント(HTMLでは標準サイズ)
- 1ページの文字数は,横40字(半角80字)×縦50行
- 余白は,HTMLで作成する場合有りません。WPの場合適当
- 原稿分量は,写真,図表を含め,2ページ程度
- HTMLの場合,1行40字折り返し換算で100行程度
4.文章表現の注意
- 文 体
- 「・・・である」調
- 文中の英字
- 半角を用い,一般に使われている表記に従う。
- 本文がズレないようにしたい場合は,全角文字の前で調整する。
- [例]本校でのWWW サービスは,以下の項目である。
- 文中の数字
- 半角を用い,原則としてアラビア数字,必要に応じてローマ数字(英字「I」や「V」),漢数字を使う。
- [例]1 時間,2 個,3 本,一つ,数学Ⅰ
- 文中のカナ
- カタカナは,すべて全角で記載する。
- 文中の記号
- 半角,ただし「・」のみ全角。
- なお,機種依存する特殊な記号は避ける。
- [例]空白の四角,丸の中の字,ローマ数字,罫線文字,半角カタカナ(
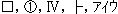 )
)
- 句 読 点
- 全角の「,」と「。」を利用する(教科書と同じです。注意して下さい)。
- 文中の修飾基本的に自由ですが,本文中のフォントサイズの変更は避ける。
- 数 式
- 通常の文より3文字空ける。
- 分数 2/3 1/10 などすべて半角にする。
- [例]
 はスペース(空白)を表す。
はスペース(空白)を表す。
- この時間では,以下の数式を学習することにした。


 y=a+2ab
y=a+2ab- 外 来 語
- 全角のカタカナとする。基本的に用語をつなげる場合でも「・」を入れない。
- ただし,長い用語の場合は,読みやすさを優先する。
- [例] システム・エンジニア(勧めない例) システムエンジニア(勧める例)
- 長音の取り扱い
- 用語内に長音(ー)付きの語が重なる時は,一般的に末尾に長音は入らない。
- 長音を付けるかどうか不明の場合は,いずれかを選択して,文書内で統一する。
- [例]コンピュータ,サーバ
- [末尾長音例]フロッピー,アダプター
- [例外]メーカー
-
- 【用 語 の 例】
- コンピュータ用語の例
- ネットワーク関連
- 10BASE-5,10BASE-T,10BASE-2,100BAST-TX,LAN,チャット
- インターネット系
- WWW,FTP,News,CU-SeeMe,E-mail,電子メール,URL
- 本体名
- PC-9801,PC-98,PC-9821,DOS/V,AT互換機,AT機,Macintosh,Mac
- メーカー名はそのままで記載
- 本体関連
- RS-232C,RS-422,フロッピー,ディスプレイ,Cドライブ,CD-ROM
- OS関連
- UNIX,OS/2,MS-DOS,DOS,Windows3.1,Windows95,WindowsNT,MacOS
- 数量表記
- 28800bps,64K,512KB
- ※ WWWやWeb,ウエブ,ウェッブなど,表記が数種類あるものはどれでもかまいませんが,文書内で統一する。
- 気を付けたい表記の例
- 出来る -> できる
- 啓蒙 -> 啓発
- メイル -> メール
- 父兄会,父母会 -> 保護者会
- HP -> ホームページ
- けじめ -> 区切りを付ける等文章にあった適切な表記にする。
5.図,表の注意
- (1) 図
- ・図を用いる場合は本文中に引用を必ず付ける。
- [例] 図1 が本校のコンピュータ室での配線である。
- [例] ・・・・というように作成した(図2 )。
- ・図を印刷物で提出する場合は,黒で明瞭に書いた物を提出する。
- ・パソコンやワープロ等で作成したデジタル・データの方がよい。
- ・図には先頭から図1,図2の様に番号を振る。
- ・図を印刷物で提出する場合には,印刷物の裏にも図番を振る。
- ・図のタイトルやキャプション(説明文)は,図の下に記入する。
- ・プログラミング言語等のテキストが細かく入ったものは、イメージとして図として扱った方がよい。もし,このテキストを読ませたい場合は,明瞭なハードコピーを用意する。
- ・図やホームページのイメージなどで大体の構成が判ればよいものはイメージとして扱う。
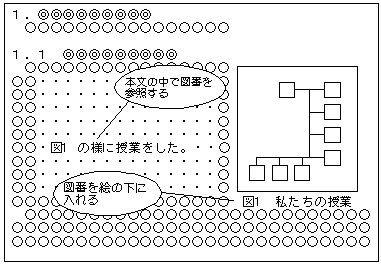
- (2) 写 真
- ・写真も図と同様に扱う。
- ・写真を用いる場合は本文中での引用をする。
- [例]図3 が本校のホームページである。
- [例]授業内で作業を行った(図4 )
- ・デジタル画像でもかまいませんが,極力明瞭なものにする。
- ・写真には先頭から図1,図2の様に番号を振る。
- ・写真を紙焼きで提出する場合は,写真の裏に番号を振る。 ただし,写真の上には直接図番などを書き込まない。
- ・第三者の肖像権やプライバシーには十分注意する。
- (3) 表
- ・表を用いる場合には本文中での引用をする。
- [例]表5 に本校のアクセスデータを載せておいた。
- [例]・・・・というような偏りがある(表6 )。
- ・表のタイトルは表の上に入れる。
- ・表には先頭から表1 ,表2 の様に番号を振る。
- ・表を別の用紙に印刷し送付する場合には,紙の裏にも表番を振る。
- ・2ページ以上にまたがる大きな表(授業計画など)の場合は,次の規則に従う。
- ・横線の区切りで終わり(改頁)にし,次のページに残りをいれる。この時,ページの最後に横線を入れ,次ページにも同じ線を引く。
- ・1枠がとても大きく,どうしても枠の途中で切れる場合は,横線は入れない。また、次ページの始めの横線は不要です。
【次ページにも横線を入れるケース】
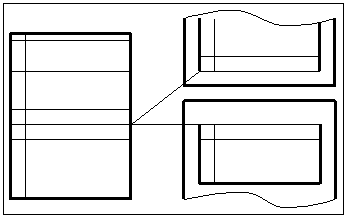
【次ページにも横線を入れるケース】
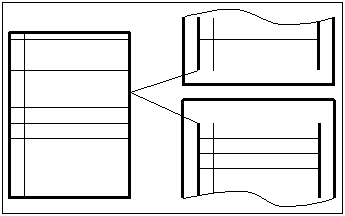
・表の中に,更に表や枠を入れる時は,入れられる欄の中に,途中で途切れる縦線や横線を入れては行けません。
・表の右欄と左の欄が関連がある時は,上下に横線を入れて示する。
【縦線,横線の利用の例】
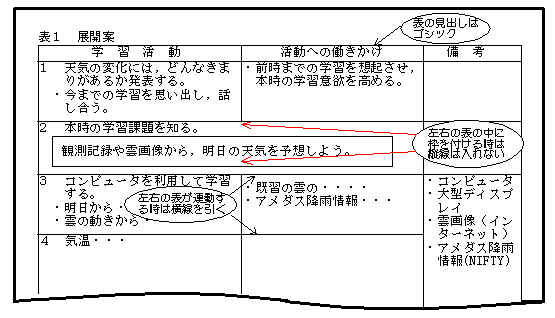
財団法人コンピュータ教育開発センター(略称CEC)
FAX 03-5423-5916
住 所 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル 3F
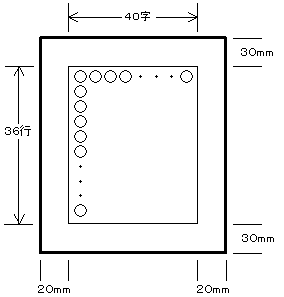
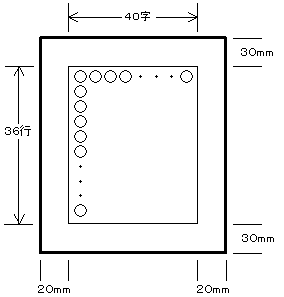
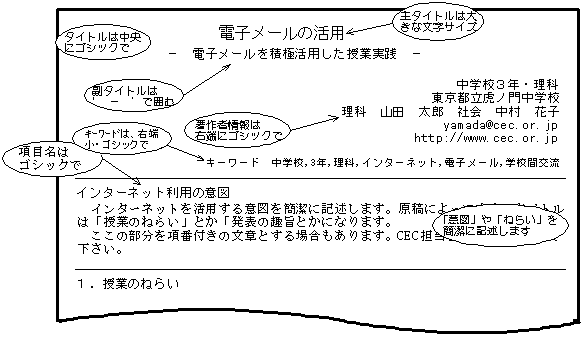
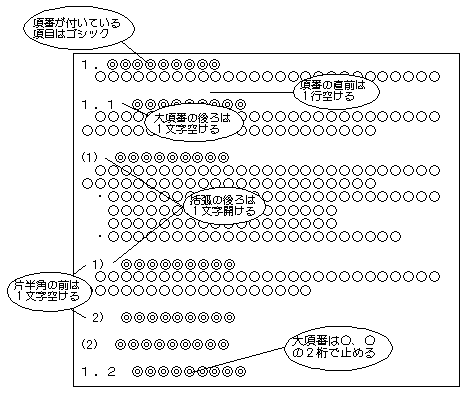
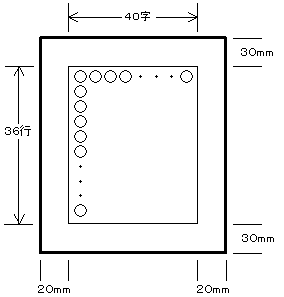 (1) 授業実践事例集形式
(1) 授業実践事例集形式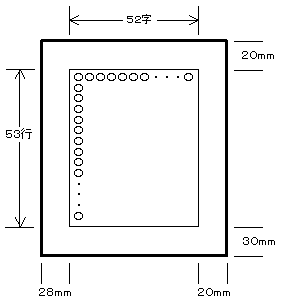 (2) 発表会レジュメ形式
(2) 発表会レジュメ形式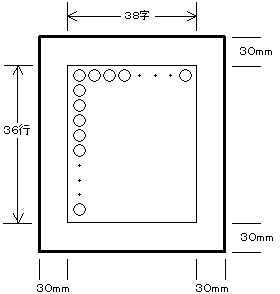 (3)報告集形式
(3)報告集形式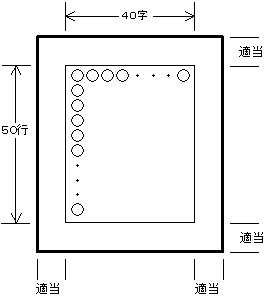 (4)実施報告集形式
(4)実施報告集形式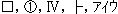 )
) はスペース(空白)を表す。
はスペース(空白)を表す。

 y=a+2ab
y=a+2ab