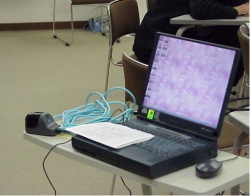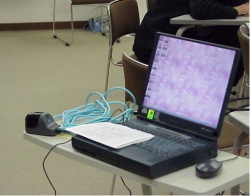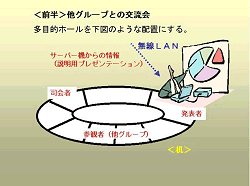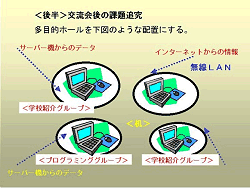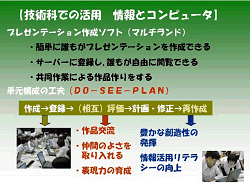Eスクエア(e2)・プロジェクト 成果発表会
自ら情報を求め,創新する生徒をめざして
− 光無線LANと,校内電子掲示板の活用 −
岐阜大学教育学部附属中学校 吉田 竹虎
taketora@fuzoku.gifu-u.ac.jp
http://www.fuzoku.gifu-u.ac.jp/chu/index.asp
キーワード 中学校,自ら求め・創造する生徒,光無線,LAN,電子掲示板,総合的な学習
1. はじめに
附属中学校では,"自ら情報を求め,創新する生徒"の育成をめざし,主体的な学習ができるような学習環境を構築してきた。"創新"とは,新しい考え方を創造していくことである。創造していく力を育成していくためにコンピュータネットワークの利用を考え,実践した。
本校は,大学と1.5メガの光ファイバーケーブルでつなぎ,校内LANを整備している。また,コンピュータ室や図書館等に,デスクトップパソコンやノートパソコンを整備し,授業等にコンピュータやインターネットを積極的に活用している。これらの利用により,"自ら調べ・自ら表現する生徒"を育成しようとしている。
ところが,例えば,総合的な学習の時間には,全校が一斉にコンピュータ室を使うので,一人一人の生徒が十分にインターネットを活用することが困難となっている。
そこで,授業中や休み時間でもノートパソコンを持ち込んで,いつでも自由にネットワークを利用できる環境を整備するために,多目的ホールに光無線LANを導入し,活用場所を増やした。光無線LANの導入により,本ホールでは移動式の机と椅子を使い,多様な授業形態を工夫し,主体的な学習ができるようになった。また,生徒用サーバーを構築し,電子掲示板により,いつでもどこからでも仲間の作品や,過去の作品を閲覧できるような環境を作り上げた。
これらの環境により,生徒は,学習形態や学習時間を自分で工夫し,仲間の作品を自分で検索することにより,自分独自の作品を創造的に創り上げていくことができるようになってきた。
2. 実践
(1) 光無線LANを活用した多目的ホールの実践
1) 多目的ホールの活用
- 校内ネットワークを構築する際に,光無線LANを多目的ホールに整備した。全校の生徒がコンピュータを活用するには,コンピュータ室や図書館だけでは場所的な問題がある。特に,総合的な学習や選択の時間には,多くの生徒が一斉にコンピュータ室を使う場合があり,一人一人の生徒が十分に活用することが困難となっている。そこで,授業中や休み時間でもノートパソコンを持ち込んで,いつでも自由にネットワークを利用できる環境を整備するために,多目的ホールに光無線LANを導入し,コンピュータの活用場所を増やした。
光無線LANの導入により,本ホールでは移動式の机と椅子を使って,多様な授業形態を工夫し,主体的な学習ができるようになった。従来の多目的ホールの活用は,演劇や合唱の練習及びその交流,椅子だけを使った学年集会,大きな物の製作学習,福祉や看護などの体験学習,PTA集会,委員会の会場等であった。光無線LANを導入したことにより,自由にノートパソコンを使っての学習も可能になった。具体的には従来の活用に加え,以下のような利用も行われるようになった。
-
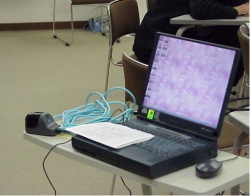
図1 ノートパソコンとMOIL |
- コンピュータ室と多目的ホールの2つの部屋で,2クラス同時にコンピュータを利用した授業を行うことができる。
- 広いスペースで,コンピュータを使い,動画を撮り,その編集を行うことができる(体育科ダンス等)。
- コンピュータを使って,動く模型を自由に制御させる学習ができる(技術科コンピュータ制御)。
- 休み時間や放課後に,自由にコンピュータを持ち込んでの調べ学習ができる。
- このように,利用状況に応じて,机とノートパソコンを自由に組み合わせることができる多目的ホールは,総合的な学習や放課後の活動において,効果的に学習できる場所になった。以下に,多目的ホールでの光無線LANを活用した総合的な学習の実践事例を紹介する。
2) 総合的な学習での実践例

図2 学習の様子 |
- 本校の総合的な学習では,"体験を重視"し,その中から生まれる「体験に基づいた課題を設定」し,「追求から主張・提言」につなげている。学習内容としては,保育園体験・病院体験・農業体験・花壇作り・国際交流・伝統文化体験・エコ活動など20程度のコースが用意されている。その中のひとつである「コンピュータを使った附属の文化向上」グループの活動を例に取りながら,光無線LANの利用について述べる。
「コンピュータを使った附属の文化向上」グループは4つのグループに分かれ,学校紹介や地域紹介のホームページやプログラミングの作品製作を行い,学校の文化向上に役立てていきたいと考えている。
このグループは,通常は各自が多目的ホールにコンピュータを持ち込み活動を行っている。
-
3) 光無線LANを用いた中間交流会
- 総合的な学習の年間計画の中に,他のグループとの中間交流会を位置付けた。これは,それぞれのこれまでの活動を振り返り,成果や悩み,今後の方向を交流することにより,自分達の今後の活動の方向へのヒントが得られるであろうと考えたからである。
中間交流会の時間には,本ホールで,前半を「プレゼンテーションにより他のグループと交流をする形態」,後半を「各小グループで活動する形態」で授業を行った。
授業前半は,移動式の机を円形にして,プレゼンテーションや実物を見せながらのグループごとの中間発表会である。生徒は光無線LANを使い,サーバー機に保存しておいた写真や動画を見せながら発表を行った。光無線LANとサーバー機を利用すると,動画などの容量の大きなデータへの対応が容易であり,発表に説得力をもたせることにつながった。授業後半は,前半の交流会での反省を生かして,机とパソコンを組み直し,自分たちの目的に応じた活動を行った。
-
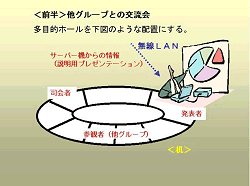
図3 交流会用配置 |
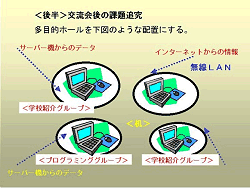
図4 課題追究 |
(2) 生徒用校内電子掲示板を活用した実践
1) 自ら情報を求め,創造していく力を育成するために
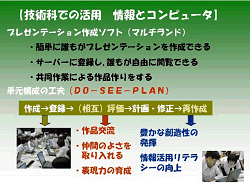
図5 単元構成の工夫 |
- 前述した,総合的な学習を含め,ほとんどのコンピュータを利用した授業において,生徒用サーバーを使った「校内電子掲示板」を利用している。これは,新しいものを創造していく力をつけるためには,「自ら問題を見つけ,自分なりに解決の見通しをもち,解決していく」授業過程が重要であると考えたためである。
そのために,ある程度作品が出来上がったら,その途中の作品を電子掲示板に登録し,誰でも,どこからでも閲覧が可能な環境を構築した。生徒は,自分の作品をより工夫するために,掲示板に登録された仲間の作品を見て,情報を得るという学習スタイルである。
完成品をデータとして残すのではなく,途中の作品を掲示板に登録しておくので,それぞれの生徒がお互いの工夫点を取り入れながら,どんどん優れた作品を創りあげていくことができた。
2) 生徒の姿から(技術科「マルチメディア作品」の授業)
- ある授業の中で,仲間の作品の掲示板を見ていた生徒A君は,「動画を使っている」B君の作品に目を止めた。そのB君の作品は「デジタルカメラを使って撮られた物」であったが,A君はその考えを応用し,「WWW上の動画を貼り付ける方法」を考え出した。そしてそれを掲示板に登録した。
こんどはB君がA君の作品を見て,「ならば,自分の作品にはさらに音声を貼り付けてみよう」と考え試行錯誤を繰り返し,ついに音声を貼り付ける方法を見つけ出すことができた。そして,B君は再度その作品を掲示板に登録し,みんなに見てもらうことにした。
これは,ごく一部の例であるが,こうしたお互いの作品を見合い,自分の作品をさらによくしていく,切磋琢磨と呼べる姿が多く見られるよになった。
3. 生徒の学びの姿の変容
光無線LANと,校内電子掲示板の利用により,学びの姿に以下のような具体的な変化が表われてきた。
- 多様化した学習時間…授業ではない昼休みや,放課後等の時間に電子掲示板を見る姿がでてきた。「あの子の作品はどんなふうだろう。」「自分の作品に取り入れられる部分はないだろうか」という姿が随所でみられるようになってきた。
- 多様な学習場所…情報コンセントが,通常教室を始め,コンピュータ室以外にもたくさんあるので,放課後などに図書館や多目的ホールなどで学習する姿が多くなった。
- 向かい合っての会話の質的な向上…基本的なことは電子掲示板を見れば理解できるので,コンピュータに向かい合う場以外での会話の質,お互いへの質問項目のレベルが具体的かつ,高くなった。
- 成長の実感…作品が順じ名前と日付時間入りでデータベースに登録されてくるので,生徒は自分の作品がどのように良くなってきたのか実感することができる。また,教師側も作品の変容を具体的に詳細に捉えられるようになってきた。
- 作品レベルの向上…最終的に完成した作品を見ると,一斉授業で行っていたこれまでの作品と比べ,はるかに見栄えがする物が多くなった。しかも,仲間の工夫点を取り入れているが,作品としては実に個性的なものが多くなったことが特筆すべきてんである。
4. まとめと今後の課題
校内電子掲示板と,光無線LANを組み合わせることにより,生徒は徐々に主体的かつ,創造的に学習を進めていくことができるようになった。生徒用サーバーに残されたデータは,年度毎に整理をし,蓄積していきたい。一部,優秀な作品は過年度のデータとして残し,次の年度の生徒が自由に参考にできるようにしていきたい。
また,多目的ホールは,現在使用する者が目的に応じて机や椅子およびコンピュータを整備して,活用している。従って,通常は,部屋の周りに机を並べ,椅子は隣の倉庫に保管してある。ところが,コンピュータを活用した授業を行うには,机や椅子及びノートパソコンを整備しなければならない。この設定時間を少しでも短くできるような工夫をしていきたい。そのためには,ノートパソコンの電源コードやハブの線などのコード類を極力少なくして,スムーズにセットし使いやすい環境にすることである。今後は,ノートパソコンを本ホールで管理し,利用目的者が必要に応じてセットすれば利用できるような環境にしておくことを計画している。