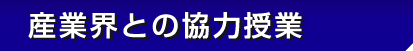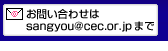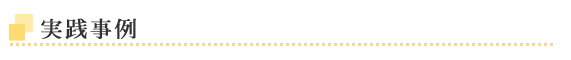|
■進行
講師の話しを聞き、生産活動・調律活動での工夫や苦労を知る。
■内容
調律師さんの仕事はどんなこと?
・音を合わせ、整える
・弾いたときの感じ(タッチ)の調整
・ピアノのお医者さん
・置き場所の相談や引越しの手配もする
きれいな音ときたない音の違いクイズ
予めわざとくるわせた音・正しい音を聞かせて ○ ×
で当てっこしてみる。
きれいな音の気持ちよさ、調律の大切さを感じさせる。
きたない音を直したり調整したりする道具が入ったカバンを見せる。
児童に持たせてみて、その重さを実感させ、中の道具を紹介。
・ドライバー
・チューニングハンマー
・針がついた道具などいろいろある
実際に弦を調整して音が変化していく様子を観察させる。音の違いを比較
音叉という道具で基本の音を決めて1本ずつ調整する。
88鍵盤 230本
もあるのに大変な仕事。ペダルの役割も紹介。
張弦力実験機で弦を引っ張る力をかえると音がかわることを実験。
みんなの体重は平均30キロぐらいだから、さっきみたいな音だけど、ピアノの弦は1本あたりだいたい90キロで引っ張っている。
全部の弦を引っ張っている力を足すとみんなが600人ぐらい必要。大型ダンプカー1台を持ち上げる20トンの力くらいになる。
そのため、ピアノはフレームという金色の部分でささえられている。
やわらかい"太鼓のバチ"、硬い"木琴のバチ"
で弦をたたいて、たたくものの硬さで音がかわることを実演し、ハンマーを針のついている道具でほぐしたりペーパーで削ったりして硬さを調整することを説明。
浜松で勉強した調律師が世界中に行って仕事をしている。中国やインドネシアの人も勉強にきている。アクトシティ(浜松)に世界中の3000人ぐらいの調律師さんが集まって勉強会もした。
浜松はピアノやそれにまつわる仕事の中心である。
目の前で調律したピアノでピアニストによるミニコンサート。
・「月光 第2楽章 」
(前回竜洋では第一楽章を演奏。暗いイメージを持った子もいたらしい。同じ曲でも明るい感じの部分もあることを知ってもらいたい)
・「エリーゼのために」(知っている子が多い)
・「千と千尋の神隠しテーマ曲」(流行の曲で、こどもに人気がある)
担任の先生より、講師への挨拶
|

知ってる。うちのピアノもなおしてもらったことあるよ。

音をよく聞いて、わかった児童が手をあげて黒板に○か×を書く。
他の児童は、口々に○だよとか、×だよと意見を言い合う。
すごい、重たい!!
ピアノの回りに集まる。
音が変わったことに、大きくうなずく。
すごいね、面白いね。

大きい子、小さい子 、一人と二人、乗る位置
をかえる などいろいろ試してみる。
音がいろいろにかわって面白い!
(担任の)先生も乗ってみて
不思議だね。すごいね。
竜洋工場でも会ったね。
ここで、1年生、2年生も参加。
知っている子が多く反応が強い。頭が自然に揺れる。
曲が始まると、ざわめき、小さい声で歌詞を口ずさむ児童もいた。
自然発生的に沖先生、中山先生に握手をもとめ、講師の周りに児童が集まった。
|