学校ホームページを中心とした交流
−クラスページの作成と活用を通して−
横浜市立飯田北小学校 横山美明
iidakita@pikaia.isminet.co.jp
http://web.isminet.co.jp/iidakita
キーワード 小学校,インターネット,クラスページ,電子メール,学校間交流,学習用リンク集
インターネット利用の意図
本校は児童数200数名の小規模校であるが,中国,ベトナム,カンボジア,ラオス,ペルー,日本という6ヶ国の子ども達が在籍しているという特色ある学校である。また,コンピュータの設置台数でも比較的恵まれた環境にあると言える。こういった環境の中で,「人との関わり合い」ということに視点を置いて2年間校内研究を進めてきた。そして,昨年11月には独立開校20周年記念としてサーバ機を立ち上げ,学校のホームページを開設した。今年度は,校内や地域の人との関わり合いだけでなく,ホームページの作成とその活用を通して,さらに子ども達の世界を広げていきたいと考えている。
1 実践内容
(1) 学校ホームページ及びクラスページの作成
(a) 利用環境
ア 使用機種 NEC PC-9821V16/SSD2(15台)
SOTEC PC STATION M246L(3台)クラスページ作成用として活用
SONY Vaio PCV-S600(1台)ホームページ作成及び管理用
SUN SPARC station5(1台)WEBサーバとして活用
イ 周辺機器 カラープリンタEPSON PM770C
カラープリンタNEC PC-PR7000PS
レーザープリンタFUJI XEROX LaserPress4150PSII
デジタルカメラ SONY digital Mavica(2台)
ウ 稼働環境 [第1コンピュータ室]
NEC PC-9821V16(15台)…64Kでインターネット接続(ISDN回線)
SUN SPARC station5(1台)…(64K専用線)
[国際教室]
SOTEC PC STATION M246L(2台)…(64K専用線)
[職員室]
SOTEC PC STATION M246L(1台)…(64K専用線)
SONY Vaio PCV-S600(1台)…(64K専用線)
エ 利用ソフト
ホームページ作成 一太郎スマイル(Justsy stem)
School-writer(富士通)
Front Page98(Microsoft)
画像処理ソフト Image composer(Microsoft)
ブラウザ Internet Explorer4.01(Microsoft)
(b) 作成経過
1999年4月 タイトル画面の作成と各学級への投げかけ。
5月 用務員室・国際教室のページ開設。
7月 5年生がクラスページを作り始める。
10月 5年生のクラスページ完成。
11月 4年生のクラスページ完成。
12月 1年生,2年生,3年生,6年生のクラスページ完成。
更新については,必要に応じて各クラスで適宜行った。
(c) 作成方法
表1 作成の手順と役割分担
|
学 学年 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
|
[計画] |
児・担 |
児・担 |
児・担 |
児・担 |
児・担 |
児・担 |
|
[作成] |
担・情 |
担・情 |
児・高 |
児・担 |
児・担 |
児・担 |
|
[組み立て] |
担・情 |
担・情 |
担・情 |
担・情 |
担・情 |
担・情 |
|
[アップロード] |
情 |
情 |
情 |
情 |
情 |
情 |
|
[活用] |
児・高 |
児・高 |
児・担 |
児・担 |
児・担 |
児・担 |
児…児童,担…担任,高…高学年児童,情…情報担当者
(d) 作成上の工夫
ア 異学年同士の関わり合い
クラスページ作成については,できるだけ児童に作らせたいと考えた。高学年の児童は自分たちで作成することができたが,低学年には難しいところもあったので,低学年の活用には高学年の児童がサポートに入った。3年生は,作成時に(図1),1・2年生は完成したクラスページを見る時(図2)にサポートしてもらった。このような活動を取り入れることで,高学年の児童には低学年の児童に自分のできることをしてあげる喜びを持ち,高学年としての自覚を育てていきたいと考えた。

図1 ページ作成のお手伝い

図2 できたページを見てみよう
イ 学校の特色を活かしたリンク集
前述の通り,本校には外国籍児童が多いという特色がある。また,そのほかにも,地域の方から借りている畑で,毎年サツマイモ作り(図3)にも取り組み,それを「いもふかし」や「収穫祭」といったさまざまな活動に活かしている。そこで,学校ホームページのリンク集にも教科の学習で役立つページだけでなく,国際(アジア・南米諸国)やサツマイモ(栽培方法や料理レシピ)についてのページなど,学校の特色を活かしたリンク集(図4)を作成した。

図3 今年もたくさんとれました
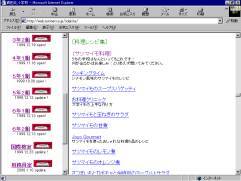
図4 サツマイモ料理のレシピが豊富
(2) 学校ホームページを中心としたインターネットの活用
(a) 検索を中心とした活用
学習の中でのインターネット活用は,主に検索が中心である。高学年以上は各教科の学習の中で必要に応じてインターネットでの資料検索を行った。検索については学校リンク集を活用することが多かったが,場合によっては既存のリンク集も活用していた。学習場面での検索は,大きく2つに分けられそのひとつは「学習内容の検索」もうひとつは「事前学習としての検索」である。この二つの活用事例は以下に挙げる通りである。
ア 教科学習での検索
教科学習の中で出てきた疑問や問題を解決するためにインターネットを活用して知りたいことを調べた。知識面での情報を補うために主に活用した。
表2 教科学習での検索の主な活用例
|
学年 |
4年 |
5年 |
6年 |
|
国 語 |
恐竜について |
オゾン層について |
ガラパゴス諸島の動物や自然について |
|
社 会 |
神奈川の水 |
農業(米作り) |
日本の歴史 |
|
理 科 |
ヘチマの栽培 |
天気(台風について) |
春の星座 |
|
家 庭 |
料理のレシピ |
料理のレシピ |
イ 事前学習としての検索
社会科見学や体験学習に行く前に,自分たちが行く場所はどういうところなのか調べたり,グループの自由行動の計画を立てたりするために検索をした。
4年生…横浜見学(ランドマークタワー,横浜マリタイムミュージアム,MM21)
5年生…体験学習(南伊豆臨海学園),社会科見学(自動車工場,製菓工場)
6年生…修学旅行(日光),東京見学(国会議事堂,NHKホール)
(b) メールの活用
本校では,職員一人一人とクラスに一つずつのメールアカウントが与えられている。また,それぞれのメールボックスも独立させているので,児童が自由に自分のクラスの受信箱を見ることができる。それらの環境を活かしてメールについても有効的な活用ができるよう努めた。
ア 問題解決のための活用
(ア) 企業宛の質問メール
|
学習活動の中で出てきた問題を児童が関連の会社にメールを出して質問した。ほとんどすべての質問に対して,小学生にもわかりやすくきちんとした形で回答をもらうことができた。また,メールだけでは説明仕切れないということで,実際に学校まで来てもらい説明をしてくれた企業(図5)もあった。 |
図5 リサイクルについての説明 |
(イ) ホームページ上での質問
|
理科学習では,科学技術振興事業団が提供している「サイエンスQAひろば」(図 6)が役に立った。ここでは,会員校になっていれば理科に関する質問にはきちんと答えてもらえるし,またそれ以外の話題でもナビゲータの方が回答をくれる。答えについては,一問一答で回答してくれるのではなく児童のヒントとなるようなものなので最終的に自力で調べることができた。 |
|
イ 想いを伝え合うための活用
(ア) 転校した友達との交流
アメリカに転校した児童とのメール交換をした。エアメールよりも簡単で,頻繁にやり取りができるので児童も進んで行った。
(イ) お世話になった先生方との交流
異動した先生方に,自分たちの作ったページを見てもらおうとメールを出した。先生方からもその感想や近況報告などが書かれたメールをもらった。これをきっかけとして現在も先生方とのメール交換が続いている。
ウ 学校間交流を目指した活用
(ア) 学習場面での活用
4年生の社会科「さまざまな土地のくらし」,5年生の社会科「米作り」の単元で交流できる学校を探すために,児童が全国の学校にメールを書いた。実際の交流についてはまだ回答がなく始められていないが,今後も続けていく予定である。
(イ) 国際教室での活用
国際教室の児童が,茨城県の結城市立結城小学校の青空教室(国際教室)にメールを書いた。国際教室の児童にとってはメールを書くこと自体が日本語の学習になる。また,自分たちと同じ外国籍の児童との交流を通して,自分の国のことや日本の国のことなどいろいろな面で情報交換ができればと考えている。
2 成果と課題
(1) 学校ホームページ(図7)の作成を通して
(a) クラスページの作成について
ア 縦のつながりの深まり
|
クラスページの作成は2年目だが,昨年に比べると大きな進歩が見られた。まず子供同士の関わり合いである。今回は,低学年が作業する時には高学年の児童がサポートに入ったが,これによって縦のつながりが強められた。4年生が2年生にホームページの見方を教えてあげたことが,2年生の秋祭りに「4年生を招待したい」ということのきっかけにもなった。他の学年でも同様の深まりが見られた。 |
図 7 ホームページのタイトル |
イ 内容の充実
ホームページを出すには,やはりそのコンテンツ(内容)が最も重要である。昨年度は,初めてということで何を載せたらいいのかがわからず,どのクラスも考えあぐねていた。今年度は児童にとっても2回目ということ,事前に他のホームページからいろいろな情報を得たということ,2学期になってからクラスページの作成を始めたので,1学期に学習したり取り組んだりしたことなど,コンテンツの材料となるものが蓄積されていたので,コンテンツはすぐに決められ,子ども達が学習したことを「誰かに伝えたい。」という想いそのものがコンテンツになった。ただし,時期的には,学校ホームページを利用した交流という点から考えると,2学期末の完成では遅すぎてしまう。来年度は,4月当初から少しずつ作り上げていきたいと考えている。
(2) 学校ホームページを中心とした活用を通して
ア 「調べる」ということ
検索は,回数としてはたくさん使ったものの,実際には既存のサーチエンジンを使って効率よく調べられるようになってはいない。結局,1単位時間の中では目的の情報がつかめず,時間だけが過ぎてしまうということが少なくない。今後も学校の特色を活かしたリンク集を使いやすく充実させていくことが必要であると思う。
イ 交流学習について
今年度の取り組みの中心にしたかったが,思うような効果はあげられなかった。現在,全国のたくさんの小学校がホームページを開設しているが,看板だけのものが多いのではないだろうか。もちろん,地道な取り組みを続けているところもあるだろうが,サーチエンジンの中ではすべてが混在しているのでなかなか見つからない。交流したい条件に合った学校を見つけてメールを書いても返信さえないといった事が続いており,なかなか思うようにいかない。交流学習は来年に持ち越されるかもしれないが,今後も「子どもの姿が見えるホームページ作り」に取り組んでいきたいと思う。
|
ワンポイントアドバイス |
参考URL
横浜市のホームページ(http://www.city.yokohama.jp/)
少年の家南伊豆臨海学園(http://village.infoweb.ne.jp/~fwkc2165/index01.htm)
NHK(http://www.nhk.or.jp/#01)
衆議院(http://www.shugiin.go.jp/index.html)
日光東照宮(http://www1.sphere.ne.jp/oh-world/oh-world/oasis/toshogu/index.htm)
株式会社エフピコ(http://www.fpco.co.jp/)
サイエンスQAひろば(http://qa.jst.go.jp/)
茨城県結城市立結城小学校(http://www.asahi-net.or.jp/~vd3s-tsk/)

 図6 サイエンスQAひろば
図6 サイエンスQAひろば