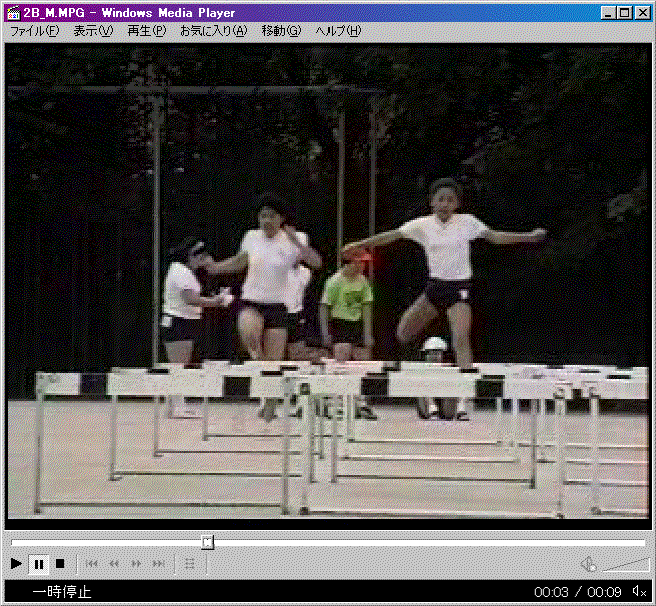
図1「ハードル」の一場面
ビデオクリップによる体育教材作り
− 教材の共同利用と共同研究の試み −
京都市立朱雀第二小学校
中嶋 弘行
jh3cqw@mbox.kyoto-inet.or.jp
キーワード 体育,インターネット,資料交流,共同研究,共同利用,
インターネット利用の意図
体育の「わざ」の学習には,視覚に訴える教材が有効であり,よくビデオが使われる。ビデオテープは巻き戻しが要るが,コンピュータの上で扱えば任意のファイルがくりかえし自由に調べられる。
この特性を利用して,動画のクリップファイルを作り,それをブラウザの上で参照できるものに仕上げる。 この教材作りに当たって,いろんな学校の子どもと先生たちに得意な,あるいは興味のある領域のビデオを撮ってもらい,ftpを通じて送りあってWebから参照できる資料にしあげ,共同利用・共同研究する。ここにインターネットが生きると考えている。
1 動きがわかる体育教材がほしい
(1) ねらい
体育教材の中には,「わざ」の名前はわかっても,実際にはどんな「わざ」なのか,その動きやポイントが文字や写真の資料からはよくわからない場合がある。その「わざ」を示すビデオがあると,児童にとっては「見ながらつかんでいく」ことができる。
私たち教員が教材研究を進めていく上でも,資料の上でしか見たことのない「わざ」に出くわすことがある。これも,やはりビデオがあれば,だいたいのことが把握できるようになる。
また,バトンを渡す瞬間やハードルを越える瞬間のように,くりかえし調べさせたり意識させたりしたいポイントがある。
そういう意味で広く体育教材ビデオが普及しているが,ユーザの側からすると,ビデオテープは戻しすぎたり送りすぎたりしがちで段取りがよくないし,テープを傷めてしまうことすらある。この点で,ポイントを絞ったビデオ教材の場合はAVIやQT,MPEGなどのファイルにしてコンピュータ上で再生するようにした方がはるかに使い 勝手がよいのではないかと考えている。
ところで,これらは「教材研究」という視点から考えたものだが,児童にとって,自分たちの姿そのものを使ったものであれば,教材としてより身近なものになり,取り組みへの意欲向上につながるのではないだろうか。
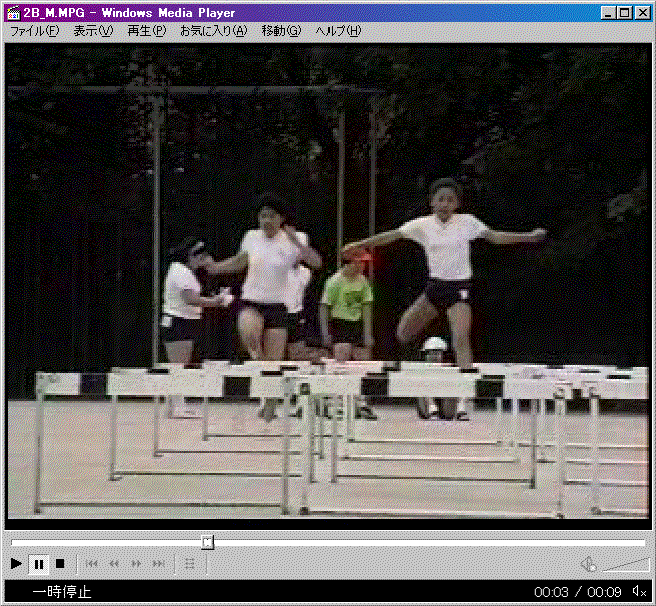
図1「ハードル」の一場面
さらに,
自分たちの姿そのものを教材化する
他地域の体育教材をしらべる・交流する
というような活動をすれば,子どもたちにとってもその教材に対する気持ちが変わってくるのではないだろうか。
そのような視点から,ビデオファイルの共有化のために本企画を策定した。
(2) ビデオクリップ作りのあゆみ
98年度のビデオファイルを使った重点企画のひとつに大津市立平野小学校の「ビデオクリップによる教材制作プロジェクト」があった。デジタルカメラの作る短い動画クリップを送り合って教材のデータベースにしようという企画で,多くの教科・領域にわたって素材が送り合われた。
また,本校の自主企画にも「マルチメディア方言辞典を作ろう」があり,やはり動画クリップを使って方言の交流をする試みに取り組んできた。
これらの取り組みの中で,動画データベースを築くことの意味がわかってきたように考えられる。資料は調べるものだが同時に作り合うものでもある。作り合う・交流するという過程は児童にとっても教員にとっても総合的な学習課程そのものだろうと考えることができた。
(3) 方法
昨年度の「マルチメディア方言辞典」や,「ビデオクリップによる教材制作」の企画にみられるように,「見てわかる教材」を作ることを主眼にしている。
いくとおりかのビデオファイルを登録して参照しあいながら共同研究を進めていくために,参加募集に平行してftpサイトを用意することにする。情報基盤センターに共有ディレクトリとして間借りしているディレクトリを使えるようにした。
また,ファイルの登録状況などについて交流できるためにメーリングリスト(以下MLと略記)も設置の方向で検討するが,当面は参加者間のメール交換という形でスタートする。
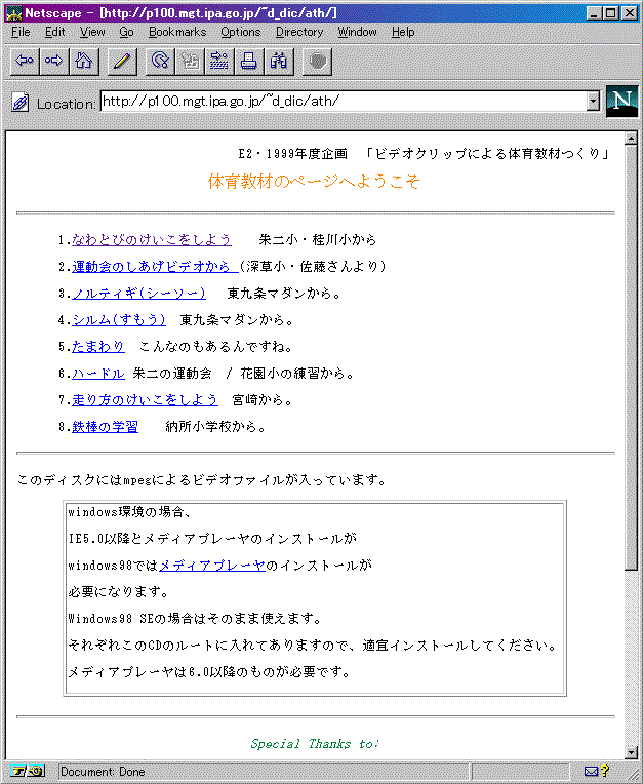
図2 Web上の「体育教材」
(4) 利用環境
[使用機材・稼働環境]
コンピュータ
・PC/AT互換機 (PentiumII-400クラス)
・Sony VAIOノート PCG-XR1G
ビデオキャプチャカード
(アナログビデオ)カノープス Power Capture Pro Power Capture SE
I/O DATA GV-VCP2/PCI
(デジタルビデオ)カノープス DV Raptor
IOI IOI-1394
VAIO内蔵1394(i-link)キャプチャアダプタ
などを利用した。
参加各校でビデオカメラ( 8ミリ,VHS,デジタル等)を用意して,任意の体育の時間に教材化したいビデオを撮影する。
上記のような機材を使い,取り込んだ素材ファイルをmpegファイル化する。
学校により接続形態はまちまちだが,インターネットに直接接続してファイルの送受信ができることは活動準備のための基本条件として必要である。
けれども,ビデオファイルは一般にかなり大きなサイズになるので,送信が負担になる学校についてはMOなどのメディアに記録して郵送してもらい,大容量の回線が利用できるところから基盤センターにある回収用ディレクトリへ送信するようにする。
集まったデータはビデオファイルであるという性格上,ISDNを含めてダイアルアップ接続している学校が多い現状ではロードにかなりの時間がかかることが予想される。そのため,データの登録(回収)にはftpを使うが,使いやすいようにデータを整理した上でCD化して配布することにする。
また,他校との交流のためには電子掲示板の利用などが適当なので,CD上のHTMLからもインターネット側へのリンクを作っておくと,シームレスな利用が可能になる。
2 リソースの制作・共有と共同研究
(1) 学校と学年を越えて「まねたい」課題に子どもが出会う
運動の美しいフォームは,見ていると「自分もやってみたい」という気持ちを起こすものである。「マット運動」の中では,ひとりの子どものフォームを獲得していく姿も浮かんでくる。
他校の美しいフォームにふれ,自分たちの姿や変化のようすにふれ,より「運動したい」という気持ちを起こすものになるのでは
ないだろうか。そういう気持ちを喚起できる機会を探しながらビデオ撮影をしてきた。
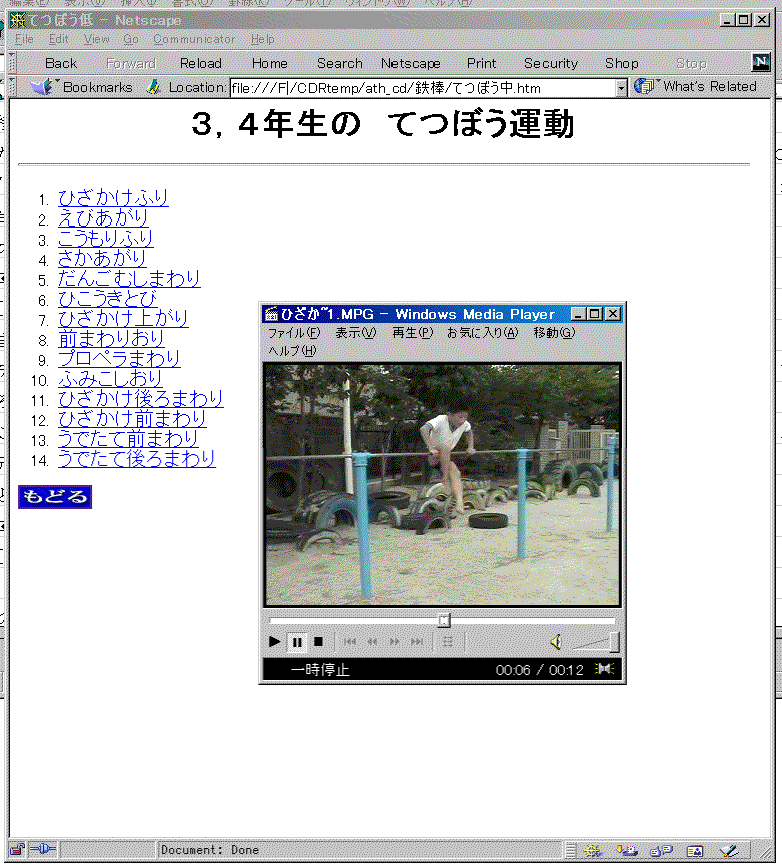
図3「鉄棒」のページ
(2) 共同研究
また,これらの教材のためのビデオファイルへのリンクをhtmlで作り,そのhtmlのあるディレクトリはメンバーが共有するものになるところから,ひとつの素材に対するいろいろな教材化のアプローチができると考えている。
ここのところはまだファイル作りに精一杯の段階なので今後の課題なのだが,ひとつの単元の中で複数の学校のビデオクリップが参照できるようになってきているのは成果としてとらえていいだろう。
[児童が地域による体育教材の違いを知ったり楽しんだりする]
ハードル走の教材では,電子掲示板を用意してみた。まだようやくファイルが教材化できた段階なので,実際に書き込みの作業をするのはこれからになる。
このパターンを使うと,室内ネットワークでCDのあるディレクトリを参照しながら,同時にインターネット上の電子掲示板にも出入りできる形になる。
回線負荷はネットワーク管理をするものにとっては常に頭の痛い問題だが,こういうかたちで動画リソースは手元にあり,話し合いのテーブルとしての掲示板がインターネットの上にあるというような形であれば,ダイアルアップ接続での学校からも参加しやすいのではないだろうか。
また,民族のあそびを体育教材として採り入れられそうなものも教材化することができた。こういうものを利用して,子どもたちが今まで知らなかったあそびを知っていくことができるだろう。
このことは,あそびを通じた民族文化の理解と交流にもネットワークが使えることを意味しているだろうと考える。
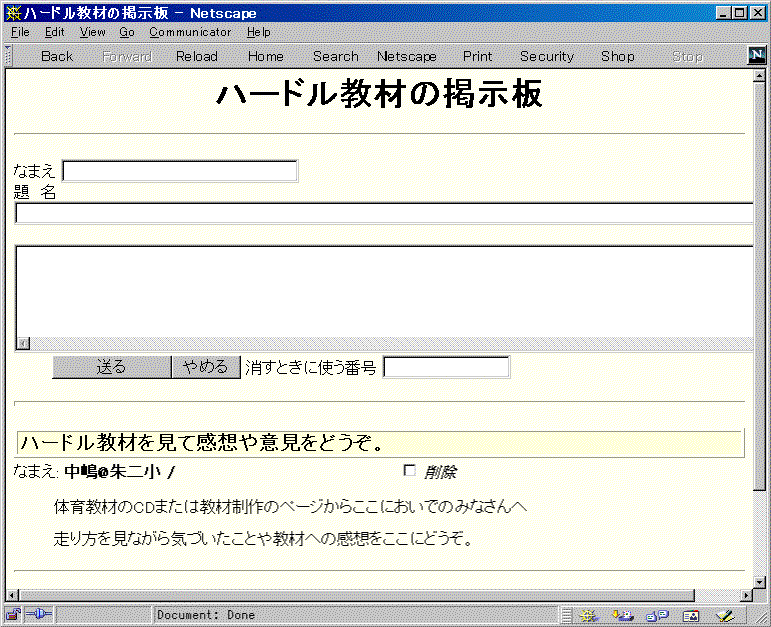
図4 電子掲示板
(4) ftp領域を用意することの意味
共同研究・共同製作をすすめていくという点では,同一ディレクトリにファイルがある方が作業がしやすいので,現在(原稿執筆の時点)では,これらのリソース類はIPAから間借りさせてもらっているディレクトリにftpして置いている。
今後は,インターネットへの常時接続が進めば,それぞれの学校の持つサーバ内にこれらのファイルを分散配置できる。
ビデオクリップという素材自体は共有・共用できるリソースとして考え,それに対するリンクを利用者が各自で自由につくることになれば,インターネットの上では敷居なく自他のサーバ内のリソースを使いあいながら,学校・学級の実態に合わせて柔軟に教材作りが可能になる。
ちょうど「先進的教育用ネットワークモデル地域事業」も始まっており,全国的に回線の高速化が進んでいる。このような事業の指定を受けることができれば,回線負荷を比較的軽減して相互に大規模なファイル転送ができる可能性を秘めている。このとき,より多くの学校からビデオファイルの参加がしやすくなるだろう。

図5 民族のあそび
3 実際にファイルを集めてみて
実にさまざまな性格のファイルが集まってきた。
(1) ふだんの学習のようすを映して課題を見つけさせようとするもの
「なわとび」のページでは,4年生と6年生の学習のようすが記録されている。児童の課題として見つけさせたい「ポイント」と「お手本」になりそうなファイルがあり,課題に沿って繰り返し参照することができる。
(2) いろんな「わざ」の「お手本」として見ることができるもの
鉄棒のページでは,美しく整ったフォームのクリップが配置されている。まだ見たことのない「わざ」も,これらを参照しあうことで,概念として把握することができるし,「やってみよう」という意欲にもつながることだろう。
また,これらのファイルへのリンクを調べてみると,同じ「わざ」に対して異なった名前のあることもわかる。そういうことから,児童どうしの交流にも利用できるだろう。
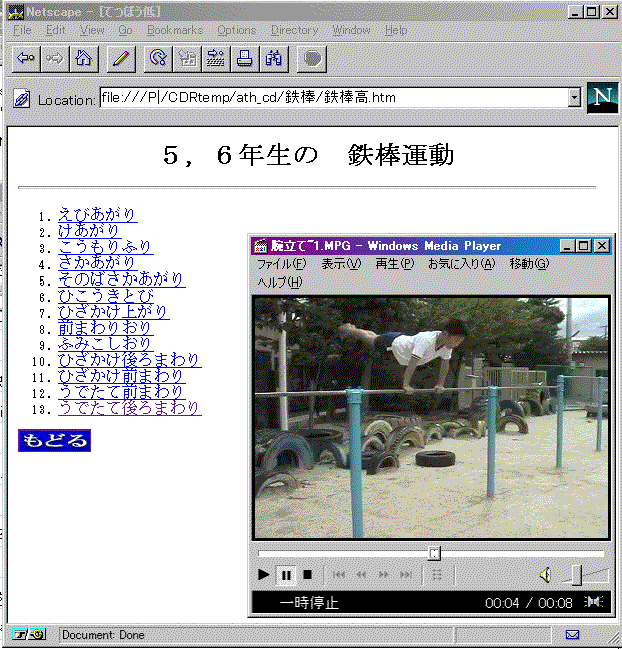
図6「お手本」として使える例
4 授業での利用
こうして作られたビデオクリップのうちのいくつかは,今年度の京都市立納所小学校での授業研究の中で利用された。
体育館での授業にコンピュータを持ち込んでいくには,まだネットワーク接続は大変な面がある。今回の企画はCD化してオフラインで使う資料としてできあがったので,コンピュータを1セット持ち込むだけでも充分使うことができる。
素材は同一であっても,学級の実態と担任としてのねらいによってその素材へのアプローチの仕方は異なる。その「異なり」方によってhtmlを担任がそれぞれの立場で作っていけば,学級によりぴったり合った学習材として準備できることになるのではないだろうか。
5 実践を終えて
ビデオ撮影のしにくい教材がいっぱいある。なわとび,マット,鉄棒など移動範囲の狭いものは撮りやすいが,球技のゲームのようにどう動くかわからないものは撮りにくいし教材化しにくい。
長く撮りためておき,その中から短くポイントになることがらを抽出していくには多くの時間がかかる。
また,撮影のタイミングを待ちながら進めてきた企画であるため,ビデオテープからのファイル化が年末にまでずれこんだ。そのため,まだ多くの領域にわたる教材は準備できていない。
6 ネットワークを利用した共同研究
先に述べたように,同一リソース(動画ファイル)を参照しながら異なった教材(html)として組み立てていくことが可能になる。
ほしい素材をML上で交換しあい,提供しあい,検討を重ねるといった研究活動には,ネットワークは欠かせないメディアである。
ワンポイントアドバイス |
利用したURLなど
http://p100.mgt.ipa.go.jp/~d_dic/ath/ (体育教材のページ)