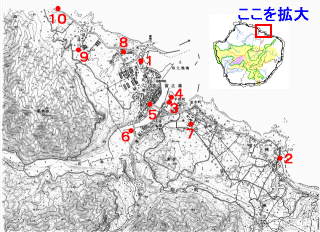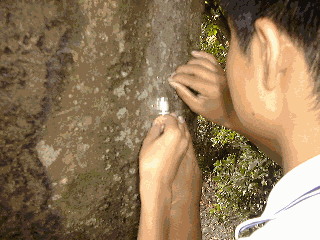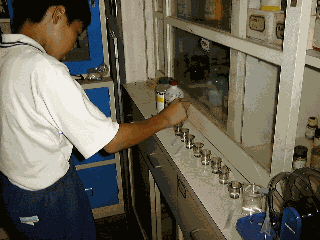酸性雨/窒素酸化物調査プロジェクト
実践報告書
宮浦中学校
1.本企画に参加した意図
生徒とともに屋久島の雨水の酸性度を調べたり,酸性雨の原因物質のひとつである窒素酸化物濃度を調べる活動を通して,環境問題に関する興味・関心を高めたいと考えた。また,全国各地のデータと比較することで,豊かな自然に恵まれる屋久島においても酸性雨が降っていることに気づくとともに,酸性雨をはじめとする環境問題は世界的な問題であることを気づかせたいと考えた。
屋久島では,地域ネットの構築とその学習への活用を目的としたプロジェクトを進めている。そのプログラムの1つとして,島内複数校による気温・気圧・湿度等の気象情報同時観測プロジェクトを実践中で,そのデータおよび考察を補完する意図もあった。
2.プロジェクトの位置づけ
2-1.教育活動の中での位置づけ
(1)プロジェクトを実施した具体的な教育活動( 2,5)
- 理科の授業
- 理科以外の授業(教科 選択技術)
- クラブ活動
- ホームルーム活動
- その他の活動(有志による課外活動グループ)
(2)測定を行ったのは誰ですか。 (3)
- 生徒
- 教師
- 生徒と教師の共同作業
(3)データの送信は誰が行いましたか。 (3)
- 生徒
- 教師
- 生徒と教師の共同作業
2-2.プロジェクトを教育活動の中で実施するとき、ネットワークの具体的な利用場面(1,2,3,4)
- データの送信
- 他校のデータの収集
- 他校との交流
- 他のホームページを使った資料の収集
- その他( )
2-3.プロジェクトの実施にあたり利用できたネットワークの環境。
該当するものを全て選び、その他のものがある場合は具体的にお書き下さい。(1,2,3,4)
- ホームページ
- 電子メール
- 電子掲示板
- テレビ電話
- チャット
-
その他
3.実践の経過と指導計画の概要
実践の経過
1999年09月06日・・・・プロジェクトへの応募
1999年09月30日・・・・第1回気象観測TV会議
1999年10月11日・・・・合同気象観測報告・意見交換会
1999年10月14日・・・・第2回気象観測TV会議
1999年10月21日・・・・NOx/第1回調査(以後週1回計6回)
1999年11月 初旬・・・・酸性雨観測機器の到着
1999年11月12日・・・・酸性雨/第1回調査
指導計画(案)の概要
- 学習活動「酸性雨とは何か」(1時間)
- 観測チームの決定とNOx調査の方法講習(1時間)
- NOx調査カプセルの設置と回収(週1回・6週間)
- 酸性雨調査の方法講習(1時間)
- 酸性雨調査の実施(雨天時)
- NOx・酸性雨データの登録(随時)
- 学習活動「自分たちの地域の酸性雨を知ろう」(1時間)
- 学習活動「他の地域の酸性雨と比べてみよう」(1時間〜)
- 学習活動「酸性雨を無くすアイデアを考えてみよう」(1時間〜)
4.授業(活動)の実践記録
(1) NOx・酸性雨調査
- 校内から有志を募り,NOx・酸性雨調査チームを結成する。 1学期に発足させていた「気象観測チーム」を中心に,15名程度のグループができる。3年生と2年生の混成グループ。
- NOxは大気汚染の程度を測るひとつの指標であることを説明し,観測者の自宅に近い場所ごとに観測地点および設置・観測者を決定する。 設置の注意点(設置条件・設置の方法)をWeb(http://pine.fukuyama.hiroshima-u.ac.jp/nox00/ntop.html)を参考にしながら説明した。具体的な観測点は以下の通り。自宅に近い場所を選択してもらった。観測地は校区のほぼ全域におよぶ。
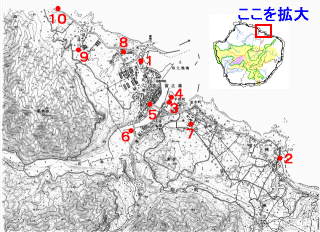 |
1:交通量の多い道路(宮之浦大橋)
2:交通量の少ない道路(楠川神社)
3:学校内で植物の多いところ
4:教室や職員室の中
5:宮之浦大橋(交通量多)
6:唐船峡橋
7:屋久島高校裏手(住宅地近隣)
8:城ヶ平(近くに工場のある団地)
9:深川地区(郊外の住宅地)
10:ゴミ処理場(ゴミ焼却施設近く) |
観測者は,雨の降らない日の登校時にカプセルを設置し,翌日の登校時に回収した。そして,登校後に試薬を滴下し,比色することでNOx濃度を測定した。屋久島は日本一とも言えるほど雨が多く,さらに天候がたいへん変わりやすい土地柄なので天候判断が難しかった。
始めはカプセルをビニールテープを使って固定したが,貼り付けが不十分であると落ちてしまうこともあった。そこで,強力な両面テープを使ってカプセルを壁面等に貼り付ける方法を試してみたが,簡便かつ確実に貼り付けることができた。
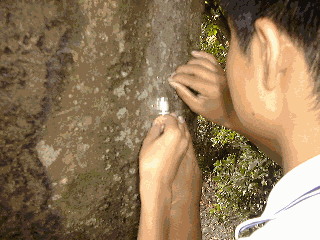
観測結果は以下の通りである。
| No |
観測地点 |
濃度 |
|
1
|
交通量の多い道路 |
0.18
|
|
2
|
交通量の少ない道路 |
0.13
|
|
3
|
校内で植物の多い所 |
0.13
|
|
4
|
教室や職員室の中 |
0.14
|
|
5
|
宮之浦大橋(交通多) |
0.20
|
|
6
|
唐船峡橋 |
0.12
|
|
7
|
屋久島高校裏手 |
0.10
|
|
8
|
城ヶ平 |
0.15
|
|
9
|
深川地区 |
0.15
|
|
10
|
ゴミ処理場 |
0.16
|
数値は6回分の平均値(μg/ml)
NOx調査と平行して,雨天時に第1回の酸性雨測定を行った。この時点ではまだpH計および導電率計が準備できていないこともあり,パックテストで簡易測定した。最初の測定は全員に集まってもらい,酸性雨の簡単な説明と測定方法をWebを使って説明した。
2回目以降の測定はチーム内を3人ぐらいずつに分け,ローテーションを組んで観測することにした。原則として,まる1日以上雨の降っていない晴れまたは曇りの日に雨水分取器(レインゴーラウンド)を設置し,雨の振り出した日の翌日の昼休みに観測した。
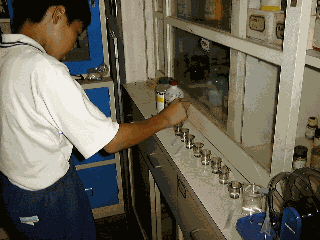
1月27日現在の酸性雨pH値・導電率は以下の通りであった。(測定回数;8回)
| カップ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
平均 |
| pH |
4.9
|
4.4
|
4.2
|
4.3
|
4.6
|
4.4
|
4.1
|
3.8
|
4.3
|
| 導電率 |
70.6
|
46.7
|
114.2
|
70.6
|
24.5
|
41.7
|
60.0
|
139.5
|
71.0
|
本校では,観測開始から3ヶ月程度しかたっておらず,酸性雨測定のサンプルもまだまだ少ないことから,充分な授業実践にまでいたっていない。そこで,次のような活動案を検討している。
(2) 「酸性雨とは何か」(活動案)
一般に,子どもたちの酸性雨についての認識は「髪の毛がぬけるらしい」「植物に悪い影響があるらしい」という噂程度のもので,酸性雨が環境および自分たちの生活に及ぼす影響についての具体的な知識は無いに等しいと考える。そこで,酸性雨についてはもとより,酸についての基礎的な知識を学習する機会が必要である。この活動では以下の学習内容を含むこととする。
- 酸性雨とは何かを知る。
- 酸性雨は環境にどのような影響を与えるかを知る。
- 酸性雨の原因は何かを知る。
- 酸性雨を観測するにはどのような方法があるかを知る。
- いろいろな溶液の酸性度(pH)を調べる。(実験)
(3) 「自分たちの地域の酸性雨と比べてみよう」(活動案)
(2)の実践を通して,子どもたちは自分たちの地域にも酸性雨が降っているのかに興味を持つだろう。また,降っているとしたらどの程度の酸性雨が降るのかも知りたくなると予想される。そこで,酸性雨の具体的な観測・計測方法を,実際の観測を通して学習することが望ましいと考える。この活動では以下の学習内容を含むこととする。
- 酸性雨を観測する各種の方法について知る。
- 雨水分取器の構造と目的について知る。
- 導電率とpHの測定について知る。
- 雨水の酸性度を測定してみよう(実験)
(4) 「他の地域の酸性雨と比べてみよう」(活動案)
(3)の観測データが集まるにしたがって,自分たちの地域に降る雨水の酸性度は明らかになってくる。それと同時に,環境の違う他地域との比較をすることが,酸性雨をはじめとする環境問題のグローバル性に気づく良い機会になるだろう。この活動では以下の学習内容を含むこととする。
- 環境の違う他地域の酸性雨の程度を予測する(都市と地方,気象環境の違う土地等)
- 他地域の酸性雨を調べる。(Internet実習)
- 酸性雨の地域分布についてまとめる。
(5) 「酸性雨をなくすアイデアを考えてみよう」(活動案)
(4)の学習を進めていくと,子どもたちは自然の豊かな環境と都市部の間にはほとんど雨水の酸性度に違いが無いことに気づくであろう。また,酸性雨の原因のひとつである窒素酸化物のその地域における濃度の高低に関わり無く酸性雨は降ることにも気づくと考えられる。そこで,酸性雨を引き起こす酸性降下物の由来を探り,その発生源が国内外を問わず関係しあうことから,環境汚染に国境が無いことを気づかせたい。また,そのことから酸性雨をなくすための具体的な方策もあわせて考える活動としたい。この活動では以下の学習内容を含むこととする。
- 酸性雨は必ずしもその地域の環境だけに影響されないことを知る。
- 酸性雨の原因物質はどこから来るのかを知る。
- 酸性雨を無くす具体的な施策について知る。
- 酸性雨を無くす具体的なプランを考え,発表する(実習)
5.実践を終えて
(1)実践で得られた成果
まず第一に酸性雨観測の機器が手に入り,観測・測定のノウハウが生徒とともに身についてきたことがあげられる。分取器(レインゴーラウンド),pH計,導電率計ともに可能な限り操作が簡便になるように工夫されているが,手際良く正確な測定をするには慣れが必要になる。これまでの測定を通してその技術が身につきつつある。
第2に,コンピュータリテラシーおよびInternetをはじめとするネットワークリテラシーが育ちつつあることがあげられる。観測したデータの処理やそのWebへの登録,資料収集および報告書の作成などをコンピュータおよびInternetを使って行った。
第3に,世界自然遺産の島「屋久島」にも酸性雨が降っている事が確認できたことがあげられる。それも,他地点に比較しても酸性度の強い雨が降っているように思われる。窒素酸化物調査では,ほぼ全地点で目立った汚染は見られなかったので,酸性降下物の起源は屋久島以外にあることが推測される。今後,そのことも引き続き調査していきたい。
(2)反省・課題
酸性雨調査にしろ,窒素酸化物調査にしても地道な観測・計測を継続して行わなければならない。本校の取り組みでは,生徒のグループに自主的かつ主体的に調査を行うことを求めたが,観測回数を重ねるごとに観測の意欲が薄れてきた。
その原因は,酸性雨が環境に,殊に屋久島の森林生態系に深刻な影響を及ぼしつつあることをよく知らない事,酸性雨と自分たちの生活が結びついていなかったのではないかと考えられる。「酸性雨を浴びると,髪の毛が抜けるのではないか」といった子どもたちの意見を見ると,酸性雨に関する知識の少なさと興味・関心の浅さが感じられた。
本来であれば,まず最初に動機付けをしっかりと行うべきであった点を大いに反省している。授業プランであげたような実践を観測・測定の前後に必ず行うことが今後の課題であると考える。
今回のプロジェクトでは,データの収集・蓄積という点では大きな成果があったが,そのデータを活かした学習活動の展開ができなかったのが第2の反省点になった。本格的な計測が始まってまだ3ヶ月程度しかたっていない事もあるが,本校のみならず各地のデータも一般的な傾向を示すにはまだ充分ではないと考えている。もうしばらく観測を続け,データがそろってからあらためてデータを活かした学習活動を展開したい。
(3) 今後の実践にあたってのワンポイント・アドバイス
- 観測する目的をはっきりとさせることが何よりも大切。
- 窒素酸化物/酸性雨の正確な調査・測定にはある程度のスキルが必要なので,測定者には充分な事前トレーニングが必要。
- 酸性雨の観測が環境問題への興味関心を高めるというよりも,環境問題を追及する方法のひとつとして酸性雨調査を使いたい。
- 選択理科や総合的な学習への学習単元としての位置付けをした活動の方が深まりを期待できる。
(4) このプロジェクト実施に当たって利用した資料・Webページ等