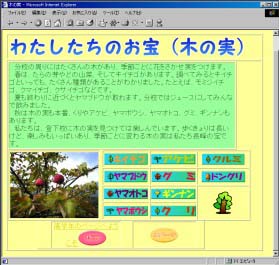
地域のお宝を紹介しあい交流を深めよう
−Webサイト,電子メール(テキスト,HTML)の活用を通して−
小学校・高学年・総合的な学習
宮城県白石市立福岡小学校長峰分校
渡部 敬(nabetaka@human.gr.jp)
http://www.area.city.shiroishi.miyagi.jp/naga-ps/
| 観 点 | 第 5 学 年 | 第 6 学 年 |
| 興味 関心 態度 |
教師の支援のもとに興味・関心に応じた課題を選択し,「長峰のお宝」について進んで調べようとする。 | 自己の興味・関心に応じた課題を選択し,「長峰のお宝」について進んで調べようとする。 |
学び方 |
選択した課題について調べ,資料を整理し,教師の支援のもとにサイトを作ることができる。 |
選択した課題について,見学・取材の計画を立て,調べ,資料を整理し,教師の支援のもとにサイトを作ることができる。 |
表 現 |
作ったサイトをもとに,聞き手にわかるように発表することができる。 |
作ったサイトをもとに,聞き手にわかるように工夫して発表することができる。 |
| 技 能 |
「長峰のお宝」を紹介するWeb サイトをきっかけに,本校児童とメール等で交流し,視野を広げると共に,他地域への理解を深めることができる。 | |
| 次 | 時間 | 学 習 内 容 | 留 意 事 項 |
1 |
<メールについて> | ||
| 1 |
メールの簡単な仕組みやよさを知り,メールの書き方や送信・受信の仕方を体験する。 | 郵便や電話との違いを明 確にする。 |
|
| 1 |
メールの書き方を知り,送信する。 |
できるだけローマ字入力をさせる。 | |
| 2 |
メールを受信し,返信してみる。 |
質問への答え方や感想の書き方を中心にする。 | |
| 2 |
自己紹介のメールを書く。 |
下書きをしてからメールを書かせる。 | |
2 |
<お宝探しからお宝紹介による交流> | ||
3 |
地域のお宝探しをする。 |
お宝として,社会的,自然的,歴史的,人的なものを中心に取り上げる。 デジカメを活用させる。 |
|
2 |
お宝について,詳しく調べる。 |
お宝について,本やインターネット等で詳しく調べさせる。 | |
| 2 |
お宝について,まとめる。 |
レイアウトを考えながら紙にまとめさせる。 | |
3 |
お宝を紹介するサイトを作る。 |
下書きをもとに,ホームページ作成ソフトで作成させる。 | |
| 2 |
作ったサイトを使って,お宝紹介をする。 意見等をもとに修正する。 |
教室でプレゼンをする。 各地のメールを紹介する。 |
|
| 1 |
お宝を紹介するメールを出す。 |
下書きをしてからメールを書かせる。 | |
| 1 本時 |
TV電話を使って本分校間で交流する。 |
お宝のサイトに関するクイズを中心にする。 | |
3 |
<情報ネットワークによる交流の日常化> | ||
| 1 |
画像添付のメールの作り方を知る。 |
写真やイラストの使い方を中心に進める。 | |
| 2 |
画像添付のメールを書いて,送信する。 |
送りたい画像を選択させ,メールを書かせる。 | |
3 |
質問のメールや返信のメールを書く。 メール使用の日常化を図る。 TV電話を使って交流する。 |
メールやTV電話を気軽に使えるようにさせる。 |
|
段階 |
主 な 活 動 内 容 |
教 師 の 手 立 て |
|||||
つ か む |
|
||||||
活 動 す る |
4 TV電話を使い,長峰のお宝を紹介し交流する。 (1) はじめのあいさつ (2) お宝の発表 発表の内容は下記の通り ・Web サイトから考えたクイズ ・Web サイトの紹介 ・本校からの質問・感想など (分校・本校の順に交互に発表を繰り返す。) (3) 終わりのあいさつ |
・テレビ電話では音声が聞こえにくいので,大きな声でゆっくりと話すようにさせる。 ・クイズの答えは写真や絵等で補足し,実体験のない児童にも視覚からとらえられるように工夫する。 ・質問や感想などが多くなった場合は,後日メールで返答する。 ・今後もメールやWeb サイト上にクイズを載せて交流することを知らせる。 |
|||||
広 げ る |
5 まとめと次時の活動予定を聞く。 ・本校のお宝と長峰のお宝を比較して,長峰 のよさや本校のよさを考える。 |
・本校と分校のお宝を比較し,長峰をもっとよい町にするための提案を考えさせる。 |
|||||
3. 学習の展開
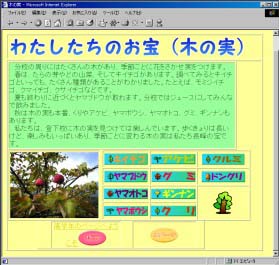 |
| 画像1 分校児童作成のページ |
(1) サイトの作成
9月後半から,本校の5年2組でも,また長峰分校の高学年学級でも地域のお宝のサイトを作成し始めた。本校では,グループを作って校内でお宝を探し,デジタルカメラで撮影していった。集めたものを一太郎スマイルを用いサイト化していった。分校では,木の実を中心にお宝探しをし,本校同様,デジタルカメラで撮影し,ホームページビルダーを使って,サイト化していった。分校ではこれまでにも木の実関係の画像を撮りためていたので,取捨選択していった。(画像1)
児童にとって,サイトを作ることは初めてのことであったが,作り方がわかると,放課後の時間なども活用して,進んで作成していた。
(2) Web サイトとメールでの交流
サイトの作成・交流と並行して,メールの交換も行った。
本校では,20台のパソコンのうちインターネット接続のできるものが5台しかないため,一太郎スマイルの便せんを使ってメール(手紙)を書かせることも試みた。データが大きいため,コンパクトフラッシュに入れ,文書当番の分校職員を通して受け渡しをした。
分校に届いたデータは印刷され,紙媒体の形で児童に配布された。それを読みながら,分校の児童は返信を書いた。分校児童は,Outlook Expressを使ってメールを書き,3人まとめて送信した。
分校では,高学年担任が連絡し,他の学校の親しい先生方やその受け持ちの児童にも見てもらった。北海道から宮崎県まで,各地から届くWeb サイトに関するメールを読んで,児童も担任も喜んでいた。
(3) インターネットTV電話での交流(失敗編)
分校にはTV会議システムがあるものの,本校にはない。そこで,インターネットTV電話を活用して新たな交流に挑戦した。KDDI研究所から出されているもので,USB
接続のCCD 動画カメラとヘッドフォン付きマイク,ソフトで1万円弱で手に入るものである。
何度かの接続実験を試み,昨年の10月23日に本分校間で音声,動画ともに開通した。
早速,5年2組と高学年学級での交流をと考え,10月31日に接続し,児童を登場させたところ,本校児童の勢いに圧倒され,分校児童が萎縮してしまった。本校児童にどう対応したらよいのか迷ったのである。
 |
| 画像2 旧担任との交流 |
 |
 |
| 画像3 分校での様子 | 画像4 本校でのTV電話の画面 |
4. 成果と今後の課題
○ 居ながらにして同学年の児童と交流を深めることができ,特に分校の児童にとっては, 自己を振り返る機会となった。本校や他分校児童に対する仲間意識も高まった。
○ サイト作成やメールの活用といった新たなコンピュータ・リテラシーを高めることが できた。HTML型のメールの必要性は感じなかった。
○ TV電話の活用はまだ始まったばかりである。3学期になり不忘分校にも設置した。 日常の授業や生活の中で今後も活用し,本校や他分校との交流学習を深めていきたい。
○ より深い交流のために,共通体験と結びつけたメール等でのやりとりも実践したい。
| <ワンポイント・アドバイス> | ||
| (1) デジカメは多いに越したことはない。せめてグループに1台は必要である。 (2) お宝探しは1年間かけてじっくりと取り組み,取捨選択するとよい。 (3) インターネットTV電話は簡単なシステムであり,気軽な交流にはとてもよい。 |
||