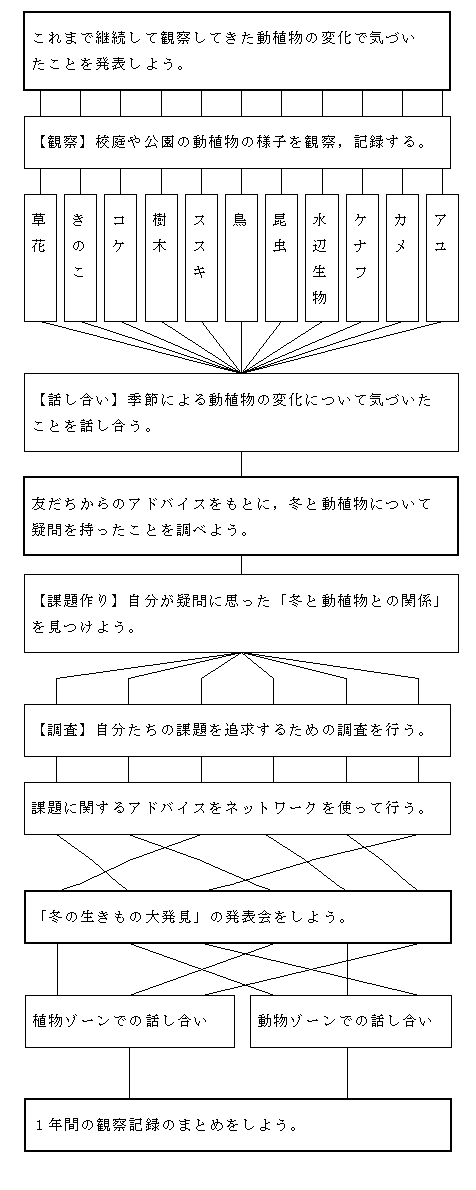
【校庭,並木公園】 ・デジタルカメラ ・ビデオカメラ |
【教室前オープンスペース】 ・グループウェア ・データベース 【校庭,並木公園】 ・コンピュータ 【教室,科学館】 ・電子メール ・ビデオ配信システム ・データベース |
【コンピュータ室】 【体育館】 ・プロジェクター ・マルチメディアボード |
【コンピュータ室】 ・グループウェア |
児童の主体的な活動を保証するための学校の枠を越えた協調学習
ー30以上の課題を同時に進めるためのインターネットの活用ー
茨城県つくば市立並木小学校 毛利 靖
http://wwww.namiki-e.ibk-tt-net.ed.jp
tsukuba@namiki-e.ibk-tt-net.ed.jp
キーワード:小学校,4年,6年,総合的な学習の時間,協調学習,主体的な課題
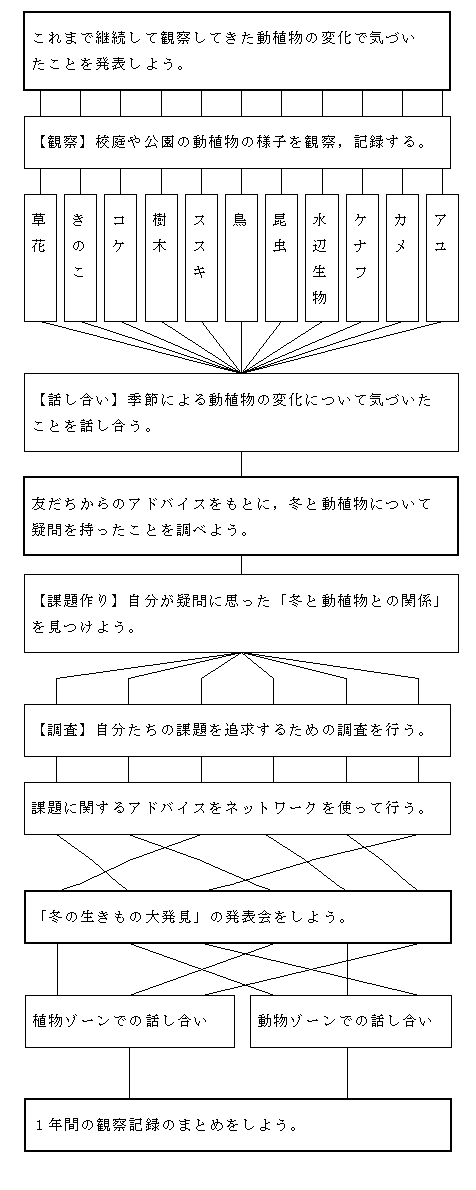 |
|
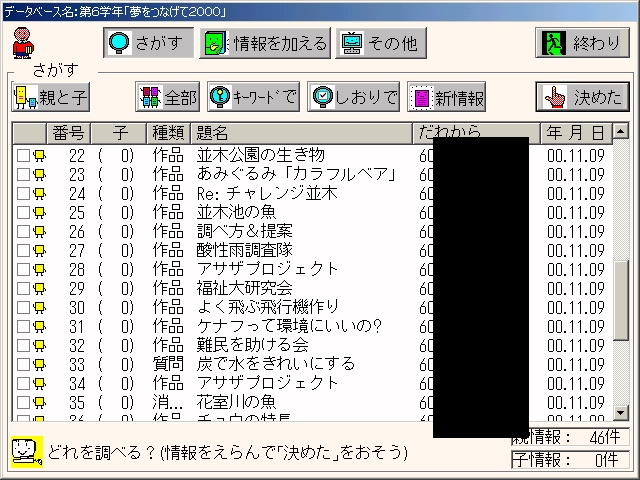
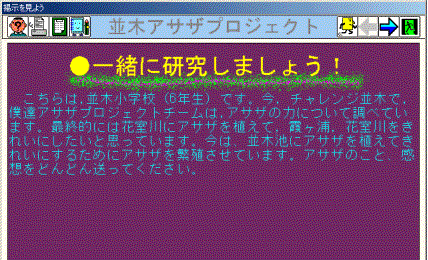 |
|
|
児童が呼びかけたメール |
|
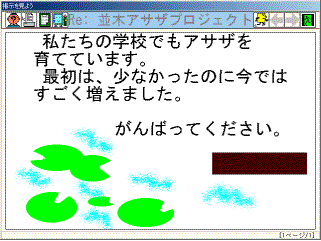 |
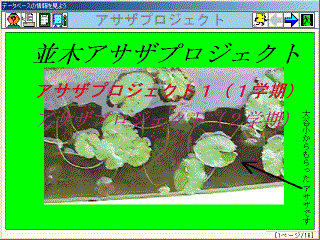 |
|
他校からの電子メール |
実際に育ててホームページにした画面 |
ウ.蛍の発光にも影響を与える光害の研究
夜の光(街灯,ネオン,自動車のライトなど)が環境にどのような影響を与えるのかを調査しようと考えたグループ(2名)は,教師に質問したが「星が見えにくくなる」程度のことしか誰も答えることができなかった。図書資料も探したが,見つからず,インターネットで調べていた。すると,千葉県柏市のプラネタリウムのホームページに関連した内容があることを知り,電子メールを使って交流することになった。(質問ではなく交流としたのは,プラネタリウム側でも児童に対して質問をするなどのやりとりが行われるようになったからである)こうして,光害は,夜に星が見えにくくなるばかりか,植物や昆虫,特に蛍に関しては発光しなくなるものまででてくるほどの被害があることがわかってきた。そこで,他の友だちにもこのことを考えて欲しいと願い,学級の時間で話し合いを持つほどになった。その話し合い活動では,マルチメディアボードを使って,プレゼンテーションを行った。
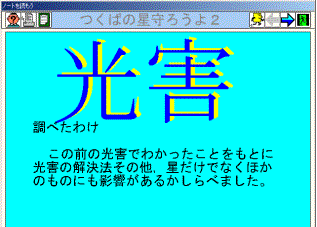 |
 |
| 児童の作った光害のページ | マルチメディアボードを使った発表会 |
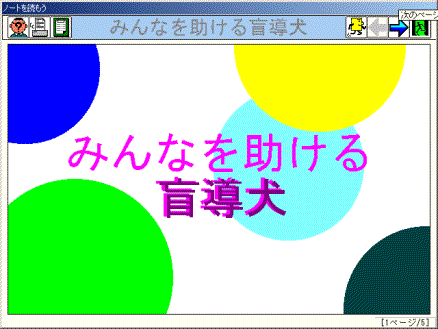 エ.盲導犬訓練士をめざす児童が行った研究
エ.盲導犬訓練士をめざす児童が行った研究
また盲導犬訓練士をめざす子どもは,福祉に興味がある子どもたちと一緒にグループを構成し,盲導犬や介助犬について調べていく中でそこでも専門家や他校との自主的なかかわり合いが見られた。盲導犬や介助犬について調べたことや共同研究の呼びかけを電子掲示板に登録したところ東茨城郡内原町立鯉渕小学校の6年生から質問のメールが届いた。子どもたちは,互いにアドバイスをしながら研究を進めていった。盲導犬や介助犬のすばらしさを知った子どもたちは,ぜひ盲導犬や介助犬に会ってみたいとの願いに達した。そこで日本パートナードック協会に相談をしたところ,つくば市で介助犬教室が開催されるとの情報を得ることができ,本校でも児童主催で福祉体験学習を行うことができた。
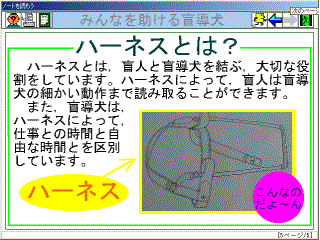 |
 |
| 児童が調べてまとめた画面 | 実際に開かれた福祉体験教室 |
4.成果と課題
 今回の研究では,児童の30以上のプロジェクトを同時に行うための方策を研究してきた。右の写真のように,昼休み,自由に他校とテレビ会議ができる環境も整えてきた。教師の役割も「指導する」ことから「ともに学んでいく」という姿勢に変わりつつある。今後も,児童の主体的な学習の場を保証するための道具として,インターネットを活用していきたいと考えている。今後の課題として,さらに児童の新たな課題に対応できる学校ボランティアなどを充実させていきたい。
今回の研究では,児童の30以上のプロジェクトを同時に行うための方策を研究してきた。右の写真のように,昼休み,自由に他校とテレビ会議ができる環境も整えてきた。教師の役割も「指導する」ことから「ともに学んでいく」という姿勢に変わりつつある。今後も,児童の主体的な学習の場を保証するための道具として,インターネットを活用していきたいと考えている。今後の課題として,さらに児童の新たな課題に対応できる学校ボランティアなどを充実させていきたい。
ワンポイントアドバイス
数多くの課題を同時に進行させる場合,教師がすべてを指導しようと考えず,他の機関との連絡調整にあたったり,児童の進行状況を把握することに力を注ぐことが大切になってくる。児童も「私たちは先生も知らないすごいことを調べているんだ」という意識付けが意欲にもつながってくる。
参加・協力校
つくば市立竹園東小学校http://www.takezono-e-e.ibk-tt-net.ed.jp/
北浦町立要小学校http://www.sopia.or.jp/kaname/index.htm