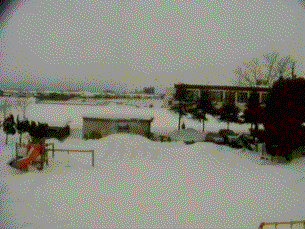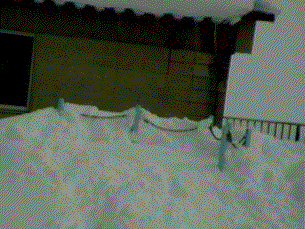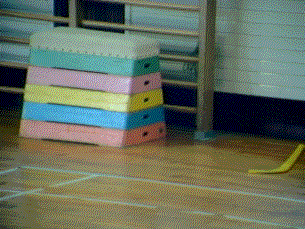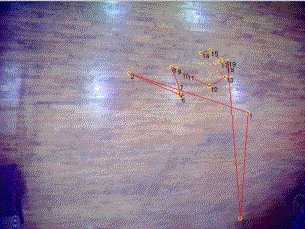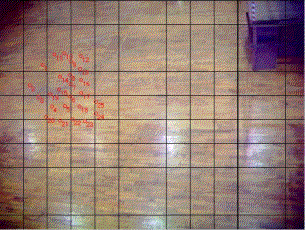「ネットワークを利用した障害を持つ子どもたちの活動分析システムの試み」
-新しい学習観に基づいた集団への参加と相互のかかわりを中心に-
福井大学教育地域科学部附属養護学校 水野雅人
mizuno@smrsrv.fuzoku-smr.fukui-u.ac.jp
キーワード 教育現場のニーズ、ネットワークカメラ、新しい学習観、暗黙知と形式知
LAN、集団への参加による学び
ネットワーク利用の意図
100校プロジェクト以来のネットワークを利用した教育を振り返った時に、メールやWebや会員制のネットワークなどを使った実践などがひととおり出てきつつあると考えた。そこで、本校のような知的障害の養護学校に限らず、特殊教育諸学校、さらには幼児教育をも含めた教育界全般で今必要なものは、現在整備されつつあり、今後より高性能化する情報基盤に対応し、現場のニーズにマッチする既成の実践にとらわれない新たな実践利用事例を模索することではないかと考えた。
そこで、現場を振り返り、学習観の転換と活動の振り返りの問題に着目してみた。
新指導要領に見られるような新しい学習観の背景には、共同体へ参加することが学習であり、子どもは仲間と協同する個人として、先輩や熟練者としての教師の支援を受けながら、共同体における活動で知識を獲得していくという考え方があるようである。その意味で、共同体の活動に参加し学ぶことが注目されると考える。
ところが、学校教育に於いて、集団での活動では、それぞれ個別の動きは見えやすいが、活動全体像は必ずしも見えない場合が存在する。特に特殊教育諸学校に於いては、1対1で支援を必要とする子どもたちも存在し、教員が、場面に応じて指導したり、支援したり仲間として一緒に活動する中で、活動の全体像や子どもたち一人ひとり全員を見ることは難しいのが実状である。活動を確認するために映像等で記録する場合には、人手が確実に一人以上は必要になるが、そこまでの余裕がある場合は少ない。
そのため、活動する子どもたちが多い集団での活動を振り返っても、例えば、教員が支援を分担している活動のコーナーについては、自分の担当分は、よく理解し、各コーナーの担当の教員間では共通理解し、連携をとりやすいが、自分の担当以外のコーナーでの様子や全体像についてや理解しにくいことがあり、活動全体の課題の追求が深まらない場合が多く、そして、環境設定やかかわりを含む次の活動設定につながっているとは言いにくい面がある。ところで、養護学校に於いては、発達の未分化な子どもたちが多いために、一人ひとりに応じた個別の指導と共に、前述したような比較的大きな集団での活動として「遊び」、全校集団活動が設定されている。そして本校の場合、さらに全校縦割り集団による異年齢集団による「選択活動」を週1回設定して教育している。これら活動のうち、学部全員が場を共有して遊ぶ、「合同遊び」では、活動する集団である「生活共同体」への参加と相互のかかわりに着目して活動を分析したい。具体的な成果目標としては、ネットワークカメラを固定し、活動を録画することで活動場面の中での子どもたちの位置を数量化し、位置の変化を分析することにより、環境設定による子どもたちの活動への参加のしかたや、相互のかかわりの中で、どのような行動により、活動が生まれるかを見いだしていきたい。
1 利用環境、稼働環境等
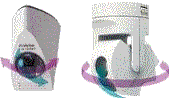 <ネットワークカメラ関係>
<ネットワークカメラ関係>
日本ビクター VN-C3 1台
ネットワークカメラ用専用ACアダプター 1個
壁取り付け型金具「日本ビクター VNBK31」3個
<ネットワークカメラ稼働環境>
利用パソコン PentiumⅢ550Mhz、メモリ256MB、ハードディスク(60GB)に増設
バックアップ用として外付けハードディスク(60GB)
<ネットワークカメラ設置工事個所>
放送室の窓際(本校2階)、遊戯室の天井角付近、体育館の天井角付近の3カ所
<ネットワーク利用可能なパソコン台数> 23台
<校内LAN整備状況>
有線で各学部教官室、各学部教室、会議室、和室、放送室、体育館、保健室、音楽室、 校長室、副校長室、日常生活訓練施設に情報コンセント設置
*なお、撮影した画像を閲覧するソフト(Windows用)は、複数のパソコンで利用可能 なため、複数のパソコンにインストールし利用した。
2 利用場面
前庭での活動・・・放送室の窓際(本校2階)に設置、小学部合同遊びを対象
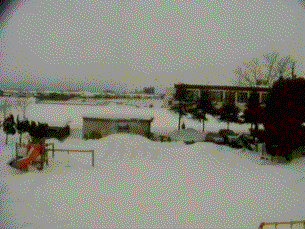 |
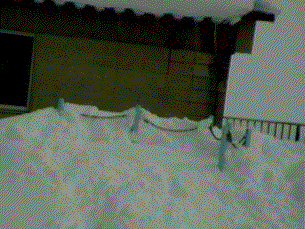 |
| 小学部前庭(広角) |
小学部前庭(望遠) |
遊戯室での活動・・・遊戯室天井角付近の壁にカメラ設置
小学部合同遊び、なかよしたいむを対象
 |
 |
| 遊戯室(広角) |
遊戯室(望遠) |
体育館での活動・・・体育館角の壁に設置、うんどうなどを対象
 |
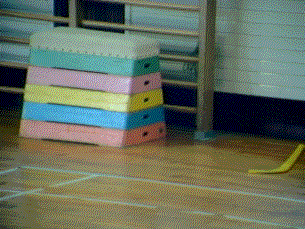 |
| 体育館(広角) |
体育館(望遠) |
3 展開
(1)活動の撮影、再生を通して気付いたこと
今回、利用したネットワークカメラは、パソコンのハードディスクに画像を保存する方式である。撮影諸条件により異なるが、中程度の圧縮で、約1時間の録画で約300MB程度と、ハードディスクの大容量化を考えれば、比較的少ない。また、この程度の容量で、フォルダが一杯になり、保存せずに、録画は自動的に中止されるため、最初に録画ボタンをクリックするだけで良いとも言える。しかし、その反面、画質は劣り、色も実際の色とはやや異なり、残像が残るような画像であり、撮影開始前に、何を撮影するかポイントを絞る必要がある。
広角で撮るほど、誰なのかが、判然としなくなるが、子どもたちによっては特徴な動きや、本校の子どもたちはユニフォーム的なものを着用しておらず、それぞれが独自の衣服を着用しているため、関係者には何とかわかる場合もある。画面は暗く見にくいが、晴れた日の雪のある場面では明るく、子どもたちの雪遊びのためのジャンパー等の服装がカラフルであるため、比較的わかりやすかった。
角や隅の方など、どうしてもカメラの死角ができるため、見えない箇所ができる。
他のメディアのビデオの利点とも共通するが、多少、画質が良くなくても、録画した活動を見ることにより、教師が気がつかなかった子どもたちの動きを知ることができたり、あいまいに捉えていたことを明確にすることができる。
カメラを構えないので、カメラを意識せずに、自然な動きをとらえることができる。
校内LANを利用できるために、活動中に撮影ポイントを修正したい場合には、その撮影現場に近いパソコンからカメラを操作することもできる。
(2)ごく簡略化した活動の経時的変化の概観方法について
今回、利用したネットワークカメラで撮影した画像は、JPEG形式のファイルの集合体である。活動の概観を簡略化するために、ハードディスクに保存された画像の集合体の中から、例えば、最初の画像は001.jpg、次は100.jpg、その次は200.jpgというふうに、等間隔に何枚かに1枚の画像を抜き出し表示させるローカルなHTMLファイルを作成する。つまり、そのHTMLファイルによって、例えば、およそ1分間に1枚や
30秒に1枚程度などの画像群をサムネイル表示、必要に応じて、撮影したスケールで表示することが可能である。これにより、このHTMLファイルで活動経過を一覧することができる。なおカメラは最初の設定で1秒間に1枚から複数枚の間隔で撮影し、ファイル名は、例えば、2001-1-31-9-00-01-040.jpgなどと命名されるが、フリーウエア(カエ太郎Ver.1.40)で、ファイル名を一括して連番に変換し、上記のようにHTMLファイルで表示できる。
(3)ごく簡略化した集団への参加状況の概観方法について
集団への参加から、子どもたちの学びをみるために、撮影された静止画を用い、子どもの位置をパソコンの画面上に置いた透明なシートに記入した後、逆にそのシートに記されたマークの箇所をグラフィックソフト(画像XY座標調査)で撮影画像に記入していくことで、集団への参加状況(活動の軌跡)を見てみている。(図1参照)また、グラフィックソフト(方眼紙2)で子どもの活動の位置を明確にしてみたりしている。(図2参照)これらのデータを事例研究会で利用する予定である。
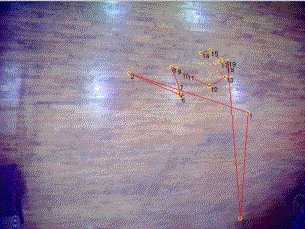 |
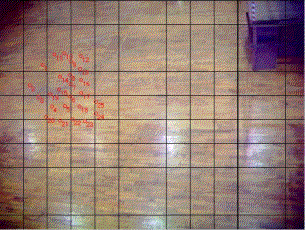 |
| 図1 活動の軌跡のイメージ1 |
図2 活動の位置のイメージ |
4 成果と課題
ネットワークカメラによる活動記録・分析への試みは、大筋であれば、素早く活動を把握できたり、カメラをパソコンから遠隔操作できたり、操作に慣れれば、画像を手早くプリントしたり、撮影画像をそのままソフトを用い分析できたり、撮影画像をLANを利用し複数のパソコンで共有できたりすることが可能な点でお手軽な防犯もしくは監視カメラとは異なる利点があると考える。そして、カメラの画質の点では、他のカメラとは明らかに劣るが、クリック一つで活動の画像を再生できるのは、何より魅力である。
また、以下のことが利点として考えられる。
- 普段は見れない俯瞰的なアングルから、巨視的に活動全体を把握できる。
- 活動を大雑把に把握でき、必要に応じて、撮影時刻を頼りに撮影画像を再生できたりじっくり観察できることは、多忙な教員にとって便利である。
- 固定して設置すれば、定点観測的に活動を捉えることができ、グラフィックソフトで経時的な子どもたちの位置の変化(行動の軌跡)を図示することで、集団への参加による学びを探れる可能性がある。ごく単純で、性能は不十分ではあるが、デジタル的な行動観察的要素を持つシステムへの試みとも言えるのかも知れない。
- 教師がカンで捉えていたことを明確に捉えることができ、また、子どもたちの活動を撮影する中で、結果的に教師の直接的もしくは間接的な働きかけや無意識的な学びの状況を知ることができる可能性がある。(暗黙知と形式知)
- パソコンの性能やネットワークの環境にもよるが、撮影した画像データのフォルダを共有化することでネットワークを経由してデータを再生することができる。
- 現時点では、試行段階であるが、活動を振り返ることは教員にとって誰しも関心が高くニーズのあることであるため、画質や撮影場面の選択の問題はあるものの、利用され、活動の振り返りに利用でき、授業改善の方向へ、教員の関心を向けることができるのではないか。
以下、気になったところや課題として
- 今回利用したネットワークカメラは、残念ながら現バージョンでは、撮影する時には(再生時は問題なし)、パソコンのネットワークの設定を変更する必要があったのが不便だった。撮影ポジションは記憶できるので、できれば、周期的に複数の撮影ポジションを巡回して撮影できると、利用価値は広がるだろう。
- じっくり見る間は、パソコンを占有してしまうことになるが、現場のパソコン台数を考えると、じっくりと利用できない場合もあるかもしれない。
- 多様な利用が可能であるが、プライバシーには十分に留意することが必要である。
- チームティーチングの活動の場合、教員集団の共通理解が必要である。
- 無線LANには対応していないので、対応が望まれる。
今後も大容量化するハードディスクなど高性能化するパソコンの学校での整備および校内LANを中心とするネットワーク環境整備が進むと考えられるが、ネットワークカメラも情報家電の一つとして低価格化かつ高性能化すれば、学校現場でのネットワーク利用方法の一つになり得るのではないかと考えている。
|
ワンポイントアドバイス
- 今回のネットワークカメラは、ネットワーク可能なパソコンとクロスケーブルさえ あれば利用できるカメラである。ハブを用いれば、遠距離でも利用可能である。
- 教員の空き時間がある学校では、パソコンを通じて、カメラを遠隔操作し、リアル タイムに活動を少しでも観察できるようにしてもよいのではないか。
- 校内LANを利用した場合、カメラの利用とネットワークへのアクセスを同時に行った時に、支障が出る可能性に配慮すべきであると思われる。
- 現在、音声対応に向けて開発中のようである。ITにより、消費者の声が素早く開発 現場にも届き、消費者のニーズで製品化される現在、教育現場のニーズをもっと伝
えていってはどうか。
- 別機種のネットワークカメラ(IPカメラ)は、インターネットで遠隔操作でき、限定されたメンバーだけが閲覧可能にすることも可能である。また、外部出力でビデオに直接録画することも可能である。さらに教育的な利用が可能ではないか。
- 今回利用したネットワークカメラは、画像をハードディスクに保存する。今後、予想される常時接続環境で、ハードディスクに保管する場合は、個人情報である画像
に不正なアクセスを受けないような対策も考える必要も出てくるのではないか。
|
参考文献
『コンピュータ』『インターネット』と『視聴覚教育』 岡本 薫
視聴覚教育 平成11年8月号
「コンピュータで変わる子どもの心」大修館書店
福井大学教育地域科学部附属養護学校 第8回教育研究集会紀要
参考にしたURL
画像XY座標検査 http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se164808.html
カエ太郎について http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sgeacnt/
方眼紙2について http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se134426.html
なお、福井大学教育地域科学部附属教育指導実践センターの三島 博之助教授に実践、研究についてのアドバイスを頂きました。
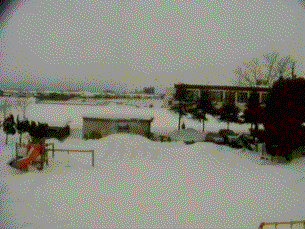
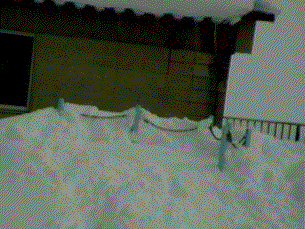
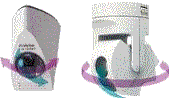 <ネットワークカメラ関係>
<ネットワークカメラ関係>