英語習得のための共同WEBページコンテスト
高等学校2年生・英語
三重県立川越高等学校 英語科 近藤 泰城
yasuki@bebop.gr.jp
http://mie-c.ed.jp/hkawag/
キーワード:英語学習、WEBページコンテスト、コミュニケーション、
必然的なニーズ、メーリングリスト
インターネット利用の意図
正確さと流暢さというバランスがとれて、初めて英語はコミュニケーションのツールとなりうる。どちらかといえば、前者に偏り勝ちな日本の英語教育を変えるために、インターネットは強力なツールとなる。海外の生徒との本物の英語コミュニケーションをたくさん体験させたい。そのため、WEBページコンテストという、必然的なニーズを作り出す仕掛けを考えた。
- 実践のねらい
これまで、二年間、コンピュータ教育開発センターの援助を受けながら、英語学習でのインターネットの実践を積み重ねてきた。1980年代に唱えられたコミュニカティブ・アプローチは、学習者が、英語を、コミュニケーションのためのツールとして使いこなせるようになるためには、実際にツールとして使うトレーニングの場を出来るだけたくさん与えなくてはならないと主張している。そして、トレーニングの場面は、擬似的なものではなく、インフォメーションギャップを埋めるための伝達や、合意や問題解決をめざす、双方向的なやりとりでなくてはならないとも主張している。また、それが、別の言語を母語とする人々との交流などであればなおさら英語によるコミュニケーションの必然性が高まるであろう。インターネットの普及によって、そのような語学学習環境の可能性が大きく広がったと言える。過去二年間、様々な交流を試みてきたが、最も大きな悩みは、「身につく」ために十分な交流量が得られなかったことである。そのため、今回は、共同WEBページ作成、コンテストというコミュニケーションの必然的なニーズを生み出す仕掛けを考え、実行しようとした。
2.実践の準備
交流相手の確保が最も大きな課題であった。筆者が担当する本校二 年生英語科は、2クラス84名の生徒がいる。インターネット上には、インターネット利用の教育プロジェクトの相手を探せるようなサイトが多数あるが、それらに紹介されている交流希望は、ほとんどの場合、20名ぐらいまでの、日本でいう少人数クラスのものである。インターネットを教育利用できるような先進国では、このようなクラスサイズが常識なのであろう。ともあれ、二学期からの実践に向けて、一学期中ごろから、交流相手探しを始めた。利用したのは、http://www.iecc.org/、http://www.epals.com/、で、双方とも大変優れたサイトである。特に、Epalsは、交流相手探しだけでなく、無料WEBメールのサービスも行っており、筆者担当の生徒も利用している。あらかじめ名簿を作成しておけば、84名分のアカウントを作成するのに3分程度で出来てしまう。実践を始めた当時は、これらのサイトに交流希望のメールを投稿するのも全て自分で行っていたが、今回は、ティームティーチングをしている、ALT(アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)にやってもらった。大変助かった。7月に入り、ペルーの高校の先生から、83名の生徒のクラスを持っていて、交流したいという連絡が届いた。こんな素晴らしい話はないとさっそくコンタクトをとりはじめた。一学期から交流のある、ドイツ、韓国、アメリカの生徒に参加してもらうつもりであった。
年生英語科は、2クラス84名の生徒がいる。インターネット上には、インターネット利用の教育プロジェクトの相手を探せるようなサイトが多数あるが、それらに紹介されている交流希望は、ほとんどの場合、20名ぐらいまでの、日本でいう少人数クラスのものである。インターネットを教育利用できるような先進国では、このようなクラスサイズが常識なのであろう。ともあれ、二学期からの実践に向けて、一学期中ごろから、交流相手探しを始めた。利用したのは、http://www.iecc.org/、http://www.epals.com/、で、双方とも大変優れたサイトである。特に、Epalsは、交流相手探しだけでなく、無料WEBメールのサービスも行っており、筆者担当の生徒も利用している。あらかじめ名簿を作成しておけば、84名分のアカウントを作成するのに3分程度で出来てしまう。実践を始めた当時は、これらのサイトに交流希望のメールを投稿するのも全て自分で行っていたが、今回は、ティームティーチングをしている、ALT(アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)にやってもらった。大変助かった。7月に入り、ペルーの高校の先生から、83名の生徒のクラスを持っていて、交流したいという連絡が届いた。こんな素晴らしい話はないとさっそくコンタクトをとりはじめた。一学期から交流のある、ドイツ、韓国、アメリカの生徒に参加してもらうつもりであった。
3.実践の流れ
交流相手が見つかって以降の実践の流れを日記風に綴ってみた。
| 7月21日 |
|
ペルーのガルシア先生からメールが届く。彼女は直接は参加生徒を担当しておらず、我々の投稿を見て、他の先生に紹介してくれるということであっ
た。 |
|
9月
2日
|
|
コンピューターサイエンスのダニエル先生からメールが届く。 |
|
9月
5日
|
|
ペルーの英語教師Perla先生からメールが届く。 |
|
9月19日
|
|
教員用もメーリングリストを立ち上げる。 |
|
9月19日
|
|
生徒のグループの人数を一カ国2人にしようとDaniel先生から申し出がある。
|
|
9月20日
|
|
ペルーから生徒のリストが届く。 |
|
9月22日
|
|
ペルーと日本の生徒のグループ分けが終了、リストを教員メーリングリストに流す。
|
|
9月25日
|
|
このころ、ペルーのダニエル先生が、http://groups.yahoo.com/mygroups
で、42個の生徒用メーリングリストを作成してくれる。この積極性に筆者は非常に喜んだ。

|
| 10月4日 |
|
アメリカ、韓国、ドイツの先生に、参加生徒の確認をお願いする。 |
| 10月12日 |
|
アメリカ、韓国、ドイツの生徒のグループ分けを終了。本校生徒にくじを引かせた。時間がかかりすぎた。これは機械的にやってしまうべきだった。 |
| 10月17日 |
|
アメリカ、韓国、ドイツの生徒のメーリングリストへの登録を終了。
トピックに関するディスカッションを始めるように指示。 |
|
11月1日
|
|
ペルーの生徒がトピックに関するアイデアをメールで送信。同時に、
ペルーの生徒は最終学年であり、11月いっぱいで、学校は終了という
連絡がある。愕然とする。 |
| 11月1日 |
|
トップページと三つの下位ページからなるWEBページのテンプレートを作成し、生徒に見せる。
反省:作成の技術的な面のでの負担が大きく、本来の「英語を使う」 活動に力が回らなくなる。
|
| 11月2日 |
|
映画、音楽、アニメなどをトピックに選んでいる生徒が、オリジナルの写真、画像が使えないということで、自作のイラストを作成し始める生徒がおり、
授業本来の目的からそれるので、課題提出に向け、文章のみに集中する ように指示 |
|
11月6日
|
|
トピックに関する合意に至っていないが、時間がないので、作成に入ると、 教員用のメーリングリストでアナウンスする。 |
|
11月7日
|
|
川越生徒単独で、WEBページ作成に入るように指示。デザイン、 写真はなしで、テキストのみを期末テスト前に作成を終え、電子メールで、
提出するように指示する。期末テスト一週間前までに提出。でないと他の教科の成績に影響を与えるため。 |
|
11月24日
|
|
レポート提出締め切り。電子メールで、筆者とALTに提出。 |
|
三学期以降
|
|
二学期末に向けて、作成したテキストを元にWEBページを完成させ、 海外の生徒からのフィードバックを得るなどしたいと考えている。生徒作品は、42個にもなるので、一覧表を作成し、訪れた人が選びやすいようにしようと考えている。また、そこに生徒自身による宣伝文を掲載し、それも評価と対象とすることとした。海外交流に関しては、エストニアの高校生と、エッセイの交換などをしている。WEBページが完成したら、彼らに評価に参加してもらいたい。 |
4.実践の評価
4.1 コミュニケーション量
|
|
本校生徒 |
海外生徒 |
合計 |
|
平均 |
10.7 |
11 |
21.7 |
|
最大 |
25 |
21 |
34 |
|
最小 |
2 |
4 |
10 |
当初の目的である、多量のコミュニケーションについては、昨年度に比較すれば、交換されたメールは多い。今回は、メーリングリストを利用した交流であったが、グループごとの投稿数は以下の通りであった。同一メールが二回流れていることもあり、また数行程度のメールも多いので、数字の半分ぐらいをイメージしていただきたい。内容を読んでみると、トピックを決めるためのディスカッションなどは、内容の薄いものも多い。やはり、時間をかけて、エッセイのようなものを書かせた方がよいのではという気がする。
4.2 WEBページ作成技術と英語学習のバランス
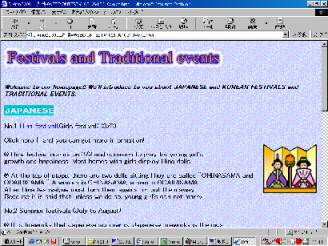 ホームページを作成し始めると、生徒はイラストを描いたり、かわいいアイコンを置いたり、凝ったタイトル文字を作ることに非常に興味を示した。後者二つは筆者が紹介したものなので、筆者に責任があるが、本来の「英語を使う機会」でないところに大きな時間を注ぐことになってしまいそうであった。そこで、「テキストのみを採点します」というアナウンスをした。また、三学期になってからも、授業時間数が少なく、その中で、デザインを意識したWEBページを完成させようとすると、「英語を使う機会」から外れるので、デザインは最低限にし、「自分たちのWEBページのコマーシャル」を書く課題を与えた。このコマーシャルとタイトル、生徒名で、リストページを作り、海外の生徒からもフィードバックを得たいと考えている。
ホームページを作成し始めると、生徒はイラストを描いたり、かわいいアイコンを置いたり、凝ったタイトル文字を作ることに非常に興味を示した。後者二つは筆者が紹介したものなので、筆者に責任があるが、本来の「英語を使う機会」でないところに大きな時間を注ぐことになってしまいそうであった。そこで、「テキストのみを採点します」というアナウンスをした。また、三学期になってからも、授業時間数が少なく、その中で、デザインを意識したWEBページを完成させようとすると、「英語を使う機会」から外れるので、デザインは最低限にし、「自分たちのWEBページのコマーシャル」を書く課題を与えた。このコマーシャルとタイトル、生徒名で、リストページを作り、海外の生徒からもフィードバックを得たいと考えている。
ボタンやロゴなど、豊富な素材を含んだ多機能のWEBページ作成ソフトは、時間をかけすぎる生徒が出る。もちろん、よいデザインのページを作るのは、よいことであるが、英語の授業であること、また、時間が限られていることを考えると問題となった。フリーの単純なソフトウエアのみでよいと思われる。
4.3 生徒自らが交流相手を探す
ミスコンセプション(文化的な先入観)をテーマに選んだ生徒たちは、相手が必要なので、自分で相手を探させることにし、次のようなサイト(http://www.japan-guide.com/penfriend/index_j.mv)を紹介した。幸い、よい相手が見つかり、食事のマナーにおけるゲップについて面白い文を書いていた。このように生徒自身が自分で交流相手を探すことも十分可能である。三重県桑名市立陵成中学校、中川祥治先生は、http://www.englishtown.com/というサイトで、生徒に交流相手を選ばせ、好結果を得ているとのことである。
4.4 課題の提出方法
WEBページの提出については、生徒個人に持たせているフロッピーディスクを提出させる方法をとった。これは教員側で、ハードドライブやMOドライブなどにコピーする面倒な作業が必要なので、ぜひともサーバーに個人フォルダを作るなどの環境を用意したい。現在の筆者の実践環境では、時間的な無駄が多すぎる。高価ではあるが、使い勝手のよいCAIシステムは、不可欠である。
4.5 課題の評価方法
総合的な学習の時間の導入も近いが、こうした授業で、生徒に作成させる作品について、いかに評価するか、検討する必要がある。本実践の対象生徒は、84名であるが、彼らの作る作品の全てを公正に評価するのは、容易ではない。あらかじめ、評価基準などを示したが、評価の段階では、それらを念頭において、全体的な印象で判断した。一度評価した後、点数ごとにグループに分けて、再度チェックし、微調整をした。一回の評価で、成績をつけてしまうのは、問題が多く、三学期は、小さな作品を4〜5個、それぞれは、原則3段階(中央の段階を6割など多めにする)程度の大まかな評価を行い、それを積み重ねるという形にした。
4.6 著作権の問題
自由にテーマを選ばせるとどうしても、映画、音楽、アニメなどを選ぶ生徒が出てくる。ここで問題になるのが、著作権である。WEBサイトや雑誌、本などから、そのまま画像を自分のWEBページに載せてしまうことが問題であることがすぐには分からないようであった。清水寺や金閣寺を紹介したグループがあったが、彼らはそれらの写真があるサイトを見つけ、作成者と、電子メールで交渉した。結果、「作者、URLを明記する」「画像に変更を加えない」などの条件で許可を得た。また、任天堂にピカチュウについては、たまたま筆者の所属するメーリングリストに同社社員がいて、「ユーザーが自分の書いたポケモンのイラストを自分のWEBページに掲載するのは認めている」ということを教えてもらった。企業にしても全て禁止するのが得策ではないと判断する例もあるようである。しかし、これは例外であり、著作権については、しっかりした指導が必要である。
生徒が選んだWEBページのテーマ
各国のスポーツ 伝統スポーツ 子供の遊び
西瓜わり、おりがみ、綾取り、剣玉 和食 いただきますの言葉、はし、てんぷら、すし、レシピ 味噌汁、てんぷら和菓子、季節の和菓子、ダイエット 伝統楽器 尺八、三味線祭り 裸祭り、ねぶた祭り 着物 ひな祭りなど年中行事 観光スポット 雷門、仲見世、金閣寺、清水寺 動物園、水族館 amusement
park日米の学校生活、放課後、日常生活、授業、クラブ、ファッション、ルーズソックス、染髪 制服、先生の紹介 絵本の紹介とオリジナルストーリーmisconception(異文化 ゲップの意味) リサイクル 環境問題 キャラクター エンターテイメント、水戸黄門、ドラエモン、シンゴママ
5.まとめ
共同WEBページ作成コンテストというコミュニケーションの必然的なニーズを生み出す仕掛けによって、実際にツールとして英語を使うトレーニングの場を出来るだけたくさん与える、という当初のもくろみは成功したとはいえない。その原因としては、「(1)ペルーの生徒の卒業で活動が出来なくなった、また、それを知ったのが遅かった。(2)生徒メーリングリスト立ち上げに一ヶ月以上かかってしまった。大変ではあるが、このあたりは迅速に行わなくてはならない。(3)WEBページのトピックについては、望ましいものをリストにして与え、映画、音楽、アニメなど著作権の問題のあるようなものは除いておくという配慮が必要であった。(4)学期制の違いなどを考慮すると、今回のコンテストのような大きなプロジェクトは無理があり、エッセイなどを送信しあう方が、結果的には、英語を使用する量は増えるのではないかと思われる。」などが考えられる。今後の参考としたい。
|
ワンポイントアドバイス
現段階では、海外との学校を授業の中心とすることは、難しいのではないかというのが今の心境である。双方がかなりの授業時間を割くことができ、双方の生徒が、パソコン、インターネットを十分に使える環境、時間が保障されていることが、重要である。もう少し大きなレベルで、プランを示し、それを責任を持って遂行できるクラスが応募するというようなシステム作りが必要ではないだろうか。
|
 年生英語科は、2クラス84名の生徒がいる。インターネット上には、インターネット利用の教育プロジェクトの相手を探せるようなサイトが多数あるが、それらに紹介されている交流希望は、ほとんどの場合、20名ぐらいまでの、日本でいう少人数クラスのものである。インターネットを教育利用できるような先進国では、このようなクラスサイズが常識なのであろう。ともあれ、二学期からの実践に向けて、一学期中ごろから、交流相手探しを始めた。利用したのは、http://www.iecc.org/、http://www.epals.com/、で、双方とも大変優れたサイトである。特に、Epalsは、交流相手探しだけでなく、無料WEBメールのサービスも行っており、筆者担当の生徒も利用している。あらかじめ名簿を作成しておけば、84名分のアカウントを作成するのに3分程度で出来てしまう。実践を始めた当時は、これらのサイトに交流希望のメールを投稿するのも全て自分で行っていたが、今回は、ティームティーチングをしている、ALT(アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)にやってもらった。大変助かった。7月に入り、ペルーの高校の先生から、83名の生徒のクラスを持っていて、交流したいという連絡が届いた。こんな素晴らしい話はないとさっそくコンタクトをとりはじめた。一学期から交流のある、ドイツ、韓国、アメリカの生徒に参加してもらうつもりであった。
年生英語科は、2クラス84名の生徒がいる。インターネット上には、インターネット利用の教育プロジェクトの相手を探せるようなサイトが多数あるが、それらに紹介されている交流希望は、ほとんどの場合、20名ぐらいまでの、日本でいう少人数クラスのものである。インターネットを教育利用できるような先進国では、このようなクラスサイズが常識なのであろう。ともあれ、二学期からの実践に向けて、一学期中ごろから、交流相手探しを始めた。利用したのは、http://www.iecc.org/、http://www.epals.com/、で、双方とも大変優れたサイトである。特に、Epalsは、交流相手探しだけでなく、無料WEBメールのサービスも行っており、筆者担当の生徒も利用している。あらかじめ名簿を作成しておけば、84名分のアカウントを作成するのに3分程度で出来てしまう。実践を始めた当時は、これらのサイトに交流希望のメールを投稿するのも全て自分で行っていたが、今回は、ティームティーチングをしている、ALT(アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)にやってもらった。大変助かった。7月に入り、ペルーの高校の先生から、83名の生徒のクラスを持っていて、交流したいという連絡が届いた。こんな素晴らしい話はないとさっそくコンタクトをとりはじめた。一学期から交流のある、ドイツ、韓国、アメリカの生徒に参加してもらうつもりであった。
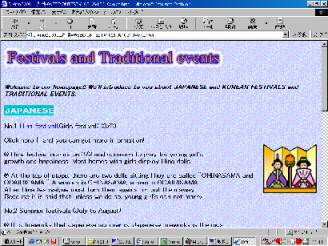 ホームページを作成し始めると、生徒はイラストを描いたり、かわいいアイコンを置いたり、凝ったタイトル文字を作ることに非常に興味を示した。後者二つは筆者が紹介したものなので、筆者に責任があるが、本来の「英語を使う機会」でないところに大きな時間を注ぐことになってしまいそうであった。そこで、「テキストのみを採点します」というアナウンスをした。また、三学期になってからも、授業時間数が少なく、その中で、デザインを意識したWEBページを完成させようとすると、「英語を使う機会」から外れるので、デザインは最低限にし、「自分たちのWEBページのコマーシャル」を書く課題を与えた。このコマーシャルとタイトル、生徒名で、リストページを作り、海外の生徒からもフィードバックを得たいと考えている。
ホームページを作成し始めると、生徒はイラストを描いたり、かわいいアイコンを置いたり、凝ったタイトル文字を作ることに非常に興味を示した。後者二つは筆者が紹介したものなので、筆者に責任があるが、本来の「英語を使う機会」でないところに大きな時間を注ぐことになってしまいそうであった。そこで、「テキストのみを採点します」というアナウンスをした。また、三学期になってからも、授業時間数が少なく、その中で、デザインを意識したWEBページを完成させようとすると、「英語を使う機会」から外れるので、デザインは最低限にし、「自分たちのWEBページのコマーシャル」を書く課題を与えた。このコマーシャルとタイトル、生徒名で、リストページを作り、海外の生徒からもフィードバックを得たいと考えている。