
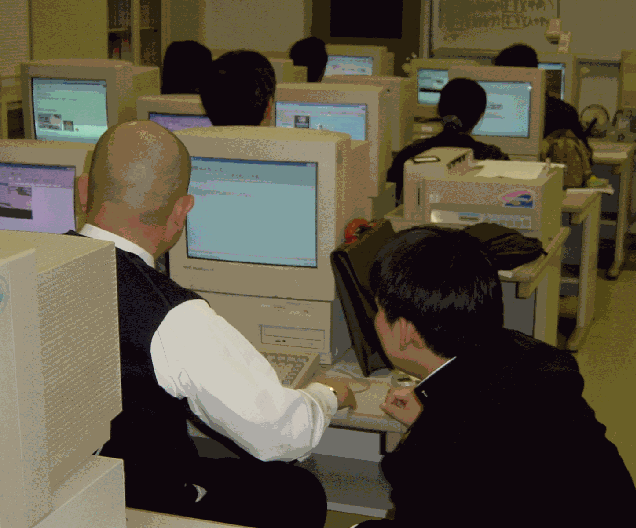

地域社会と連携した情報ボランティア活動
愛媛県立新居浜工業高等学校 宇佐美 東男
usami@ehime-net.ed.jp
キーワード
・情報格差 ・情報インフラ ・インターネット技術研修会
・運用ノウハウ ・情報ボランティア ・「えひめGFDay」
1 はじめに
初等・中等教育のすべてにインターネットが導入されようとしている。国による予算化が進められているが、地方においては、導入される施設・設備を有効に活用できる人材や、そのノウハウがほとんど蓄積されていない。これは地域や組織あるいは個人における「情報格差」に他ならない現象である。このため約2年間に渡り、地域社会を対象に「インターネット技術研修会」の開催と、情報インフラの整備や運用ノウハウを提供する情報ボランティア活動団体「えひめGFDay」への参加を企画実施してきた。
活動の主な目的は「情報格差」の解消に少しでも役立てばとの思いから取り組んできた。また、情報ボランティア活動への生徒達の積極的な参加は、地域社会より大きな評価を得ることができ、素晴らしい結果が得られた。
これらの活動は、結果として、これまでに蓄積したインターネット教育利用に関する知識や経験を存分に生かすことができ、学校教育の情報化や地域社会の情報化に協力することができた。
また、地域の方々と研究会などを通して、地域ネットワークの在り方についても研究を進めることができ、学校教育を含んだ今後の地域ネットワークの在り方についても指針を得ることができた。
以下に地域と連携した教育活動に関する内容と「えひめGFDay」の会則等を紹介する。
2 地域と連携した教育活動
(1) 情報化推進コーディネータを目指したインターネット技術研修会
地域における教育の情報化を推進するために人材育成は欠かすことができない。本校では平成3年から情報通信技術(パソコン通信ホスト局運営と教育利用を開始した。)を含むカリキュラムを展開してきた。また、平成6年から今日にかけて、100校プロジェクト等への参加により、インターネットの教育利用に関するノウハウを蓄積することができた。これらの経験を生かすことと、地域社会へのなんらかの還元をする意味も含めて、教育関係者を対象としたインターネット技術研修会を実施してきた。
ア 研修対象と実施時期
研修は、市内(愛媛県新居浜市:人口約13万人)の小中学校27校の教職員と市教育委員会職員、東予地区県立高校23校事務職員、及び市内の特定の小学校全校研修等が対象となった。実施時期は、平成11年度〜12年度に渡っている。
受講者総数約180人の先生方を6つのグループに分けて実施した。それぞれのグループは、3日間コース2グループ、1日間コース4グループで、合計10日間の研修にチャレンジした。各コースのカリキュラムのねらいは基本的に同じであるが、研修項目についての深度や演習の程度が異なっている。研修時間は午前中に講義・実技が行われ、午後はリファレンスを伴った自由実習が基本的なパターンである。各研修は、学校設備の空いている夏・冬の長期休業中に行った。また、12年度実施の1グループは、会場を愛媛県立総合科学博物館の会場を借り受けて実施された。他のグループは本校の会議室やコンピュータ室を会場とした。
 |
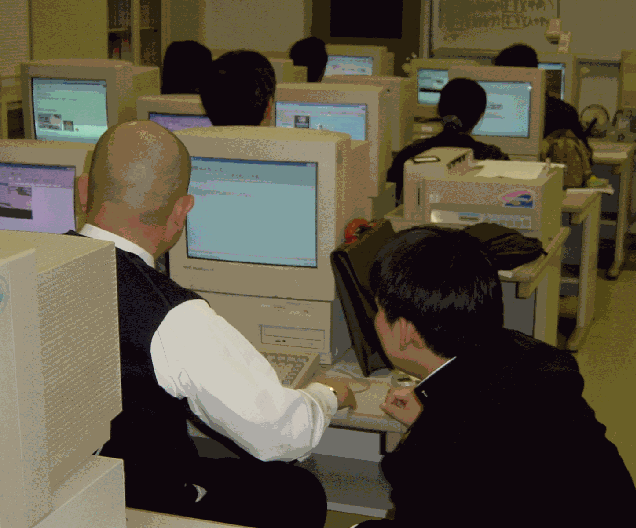 |
 |
|
図1 研修風景
|
図2 「えひめGFDay」のミーティングと生徒の指導
|
|
イ 研修内容
研修は「高度情報通信社会と教育の在り方」を総合テーマに、おおむね以下の項目を研修するカリキュラムとした。
「高度情報通信社会のとらえ方」、「教育の情報化と進め方:ミレニアムプロジェクトについて」、「インターネットの教育利用分野」、「情報倫理」、「有害情報の問題と対策」、「個人情報保護の問題と対策」、「インターネットの仕組みとサービスの種類」などを講義として行い、実技では「基本ソフトとアプリケーションの操作方法」、「インターネットサービスの利用方法」、「教材の作り方」、「ネットワークの構築」、「パソコンの仕組みと組立」、「ソフトウェアのインストール」などかなり幅広い分野の研修が行なわれた。
ウ 研修用教材
(ア) テキストの作成
研修用テキストとしてA4版約100ページのものを自作した。2年間に3回の改訂作業を行った。
講義用の部分約60ページ、実技用の部分約40ページ、また、補助テキストとしてインターネット上の関連情報も補助教材として活用した。
(イ)研修用リンク集の開発
研修内容に即したリンク集を開発した。カリキュラムに関連するコンテンツを探索し、評価したものをリンクしたが、コンテンツが突然消滅したり、変更されるものもある。2ヶ月に一度くらいは再評価する必要がある。
(ウ) Web教材の開発
ネットワークパソコン組み立て研修用のマルチメディア教材を開発し、活用した。
この教材は、動画教材(ムービーとWeb)と関連情報のリンク集で構成されている。
(エ)パソコンの組立キット
組み立て実習用として、ハードウェア及びソフトウェアを5セット分購入し、研修に活用した。3人で1台を利用できる環境とした。
このセットは20回程度の組立・分解によって部品(特にコネクター部分)が損傷し始めるので補修が必要となる。
エ 講師について
講師陣は本校教員、近隣校の教員及び地域社会の専門家、さらに情報リテラシーの高い若干名の生徒たちによって構成した。各コースを10〜8名程度の講師陣で担当し、1グループ当たりの受講者数は30〜40名で実施された。
オ 研修環境
研修室では、受講者1人に対して1台のLAN接続されたパソコン(インターネットアクセス可能)と、指導者からの教材提示用ディスプレイを利用することができる。このシステムは指導者から個別にネットワークを通して指導を受けることもできるシステムである。また各研修者に個人アカウント(1年間有効)および公開ホームページ用ディスクスペース(公的使用を原則として1人20Mバイトまで1年間利用可能)が提供された。この環境の提供は研修後の自己研さんにも活用することができる。
カ 研修の反省
研修終了時に研修内容等についてアンケートを行った。受講者からは充実した研修であったという意見と共に、時間が少なかったという意見も出された。今後の研修会に反映して行きたい。
この研修会は、情報化推進コーディネータの養成を意識したものであり、一般的なインターネット教育利用技術研修会ではなく、当然、参加者は全員教職員あった。研修の中で苦心した点は、学校現場での情報化に対する意識統一の方法や、インターネット教育利用を普遍化する方法など、これまであまり経験のなかったことを研修することに苦心した。
しかし、学校教育の情報化の手順やケーススタディ、パソコン組立研修などはユニークであり好評であった。
また、研修の2次的効果として、学校と地域社会との交流のきっかけとなることや、小中学校の方々の本校に対する理解が少し深まったのではないかと思われる。
(2)一般市民対象IT講習会
一般市民の部は、本校PTA関係者を対象に2年間で約50名が参加した。さらに、国のIT講習国民運動の講習会場としても、12時間のカリキュラムで約80名の一般市民の講習が行われた。この研修は共に夜間を利用して実施された。
IT講習は、平成13年度も約200名の参加が予定されている。
カリキュラムは「情報化社会の捉え方」、「基本ソフトの操作」、「アプリケーションソフトの使い方:主にワープロ」、「電子メールの使い方」、「ホームページの閲覧方法」、「簡単なホームページ作成」、「インターネットビジネスの利用」、「情報モラル」等について研修を行った。
さらに、地域社会の子供達(小学校4年生〜6年生までの児童と保護者)を対象とした、子供インターネット教室を開催した。
この教室では、親子がインターネットを楽しく学ぶことができ大変好評であった。
14時間のカリキユラムとし、インターネットの使い方を中心に、表計算ソフトによるグラフの作成など小学校教育でも取り組んでいるものを対象とした。この教室は土曜日・日曜日・夏休みなど長期休暇を利用して通年で開催されており、本校の生徒たちも参加し指導することがある。
(3)情報ボランティア「えひめGFDay」への参加
高校生のボランティア活動として、情報ボランティアに取組んだ。
本校は専門高校として、生徒達は日常の学習活動の中でIT技術を学んでいる。日頃の学習活動の成果をボランティア活動に役立てることができれば、社会参加の経験として将来役立つことになる。
また、情報ボランティアとして社会参加をすることで、情報モラルや情報社会に積極的に参画する態度も養うことができる。
県内には、情報ボランティア活動組織として「えひめGFDay」と呼ばれる組織がある。
この組織に参加することで活動の機会を得ることにした。
「えひめGFDay」はアメリカにおけるネットディとよく似た活動組織である。
この組織は、県内の民間団体(後述参照)や研究会、学校関係者等によって構成されていて、組織の活動目標に賛同できる団体や個人が自由に参加できる仕組みになっている。
以下に本校生徒と職員が参加した「えひめGFDay」について紹介する。
尚、紙面の関係上詳しい内容は割愛し、実施された項目のみを挙げる。
ア 「えひめGFDay」実施計画検討会(7月29日 新居浜市内S高等学校で実施)
(ア) 参加団体
1)愛媛県情報サービス産業協議会 4)愛媛県立新居浜工業高等学校生徒および職員
2)新居浜インターネット研究会 5)新居浜市内S高等学校生徒および職員
3)えひめマイコンクラブ 6)その他
(イ)検討会の内容
a これまでの活動経過報告
(a) 第1回事前打ち合わせ会・・・・5月18日
内容:「GFDay」事前打ち合わせ会
参加:新居浜工業高校、新居浜市内S高校
(b) 第2回事前打ち合わせ会・・・・6月22日
内容:「GFDay」事前打ち合わせ会
参加:新居浜工業高校、新居浜市内S高校
(c) 第3回事前打ち合わせ会・・・・7月15日
内容:第1回「GFDay」事前打ち合わせ会
参加:新居浜工業高校、新居浜市内S高校
(d) 第4回事前打ち合わせ及び工事(第1回GFDay)・・・・7月26日27日
内容:1)新居浜市内S高校内LAN工事実施(スローガンは「世界は友達」)
参加:新居浜工業高校(生徒・教員)、新居浜市内S高校(生徒・教員)
1) 「GFDay」事務局あいさつ
2) 対象高校あいさつ
3) 作業スケジュールの説明(「GFDay」事務局・S高校)
4) 作業開始
5) 作業終了
6) 活動の評価・反省
約20mUTP天井裏配線、HUB1ヶ所設置など
7) 閉会
b 今後の活動計画「第2回GFDay」について打ち合わせ
イ <第2回GFDay>校内LAN工事実施(実施日:8月5日 9時〜12時)
1) 「GFDay」事務局あいさつ
2) 県立S高校あいさつ
3) 作業スケジュールの説明(「GFDay」事務局・S高校)
4) 作業開始
5) 作業終了
6) 活動の評価・反省
約100mUTP天井裏配線、HAB3ヶ所設置など
7) 閉会
ウ <第3回GFDay>地域社会インターネット研修会実施(実施日:9月予定)
エ <第4回GFDay>地域社会インターネット研修会実施(実施日:11月予定)
オ <第5回GFDay>地域社会インターネット研修会実施(実施日:13年1月予定)
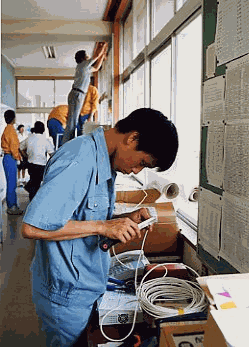 |
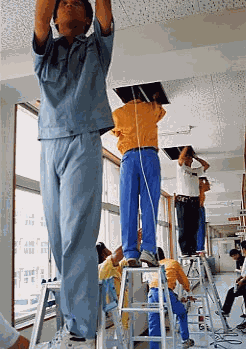 |
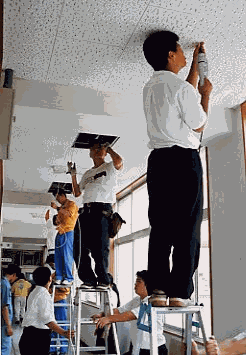 |
|
図3 「えひめGFDay」生徒によるLAN工事の様子(S高校)
|
||
3 えひめ GFDay(Global FriendShip Day)会則
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 えひめ GFDayの活動目的
えひめ GFDay は、インターネットを通して、世界の平和を願う団体であり、そのために役立つ以下の活動を行う。
2 活動内容
(1) 情報ボランティア活動(情報格差の解消)
a 研修会の開催
b 情報インフラ等整備に関する援助
c グローバル・コミュニケーションに関する援助
d 新しい教育システムの開発と運用
(2) 研究会
a 会員相互の研さん
(3) 親睦会
a 会員相互の親睦
b インターネット利用者間の親睦
3 会則(概要)
(1) 会の名称は「えひめ GFDay」協議会と称する。
(2) 会員はGFDay活動に協力できることを条件とする。
(3) 会員の中から会長(1名)・副会長(2名)・事務局長(1名)・運営委員(若干名)・監事(2名)を選任し、運営委員会を構成し、職務に当たる。監事以外は兼任でもよい。任期は1年間とし、再任を妨げない。会長は、事業運営上必要と認めた場合、臨時に総会、運営委員会を招集することができる。
(4) 活動を維持するためにGFDay事務局を設置し、担当者を置く。
(5) 運営費は、寄付および援助を主な財源とし運営費の範囲内で収益事業を行ってもよい。
(6) 入会、脱会は自由とする。
(7) 総会は年1回開催し、事業計画、事業報告、会計報告を行う。役員改選は互選で行う。
(8) 運営委員会の開催は年3回を定例とし、事業計画等を協議する。
(9) 会則改定は総会出席者の過半数の議決をもって行う。
4 その他
この協議会は平成11年10月1日より活動を開始する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 おわりに
高校生のボランティア活動は将来の社会参加にとって、「生きる力」を養うなど大変重要な体験学習となる。国の方針でもボランティア活動を義務づける方向で進んでいるようである。特に、学校で学んだ専門知識・技術を役立てることができれば、生徒たちの将来への自信につながり、校内での学習活動では得られない教育効果が得られる。
また、インターンシップ制度のこともあり、新しい視野で情報ボランティア活動を活発化させていきたい。
|
地域社会を対象としたインターネット研修会の実施は、学校職員の日頃の地域活動(例えば研究会活動等)があれば比較的容易に運ぶことができる。また、地域の教職員を対象にする場合は、地域の教育委員会等の連携は欠かすことのできない条件であろう。 |