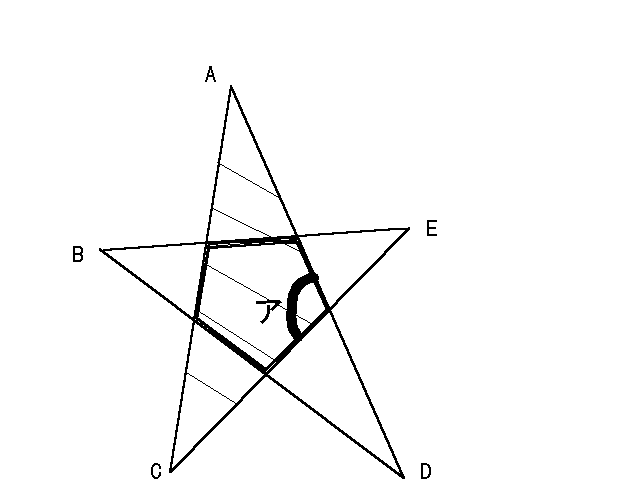 星形五角形を斜線の三角形をかさねあわせて作ってみる。
星形五角形を斜線の三角形をかさねあわせて作ってみる。5.4 数学における多解問題について
慶應義塾普通部 荒川 昭
5.4.1 概要
慶應義塾普通部では、通産省の100校プロジェクトに参加して、インターネットを使用できる環境がサーバー1台、クライアント1台専用線で接続された。1年目は海外とのメールの交換を中心であったが、参加2,3年目はインターネットの教科利用で「数学における多解問題」として2年間実践した。
(1)きっかけ
インターネットでの教科の活用方法を思案中のある時、数学の図形の授業で次のような問題を解いてもらった。
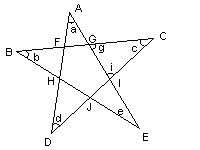
問題 星形五角形の角の和が180゜となる証明を考えよ。
三角形ADIを見ると、外角は内対角の和に等しいということを使って、図1より
∠a+∠d=∠i
次に三角形BEGを同様にして、
∠b+∠e=∠g
∠a+∠b+∠c+∠d+∠eの和が
図1.証明1
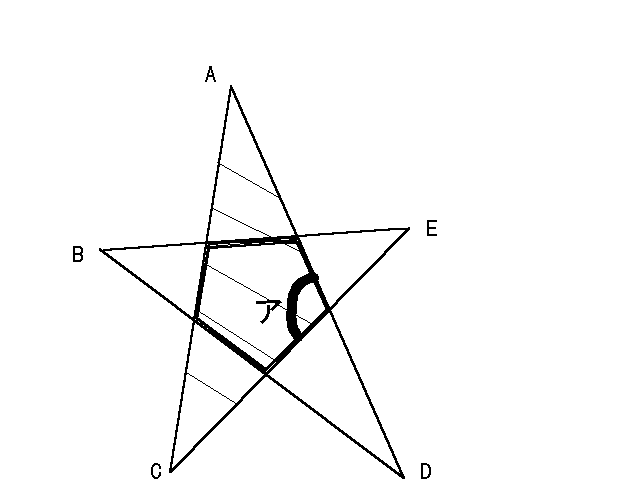 星形五角形を斜線の三角形をかさねあわせて作ってみる。
星形五角形を斜線の三角形をかさねあわせて作ってみる。
図2より三角形に、五角形の1つの内角アと三角形2つの内角A,Cが含まれることになる。
同様に五角形の内角について考えると
∠A+∠C+∠ア=180度
∠B+∠D+∠イ=180度
∠C+∠E+∠ウ=180度
∠D+∠A+∠エ=180度
E+∠B+∠オ=180度
図2.証明2
左辺の和
2(∠A+∠B+∠C+∠D+∠E)+∠ア+∠イ+∠ウ+∠エ+∠オ=900度
2(求めたい角度の和)+(五角形の内角の和)=900度
より 星形五角形の角の和=(900−540)/2=180度
同じ問題をいろいろな角度から考え、解答を発見し喜んで取り組んでいる様子や、1つの解き方に触発されて何通りもの解法を発見する生徒の姿をみた。これこそが日頃の授業では不足しているところで,自分自身で考えることの素晴らしさや発表することの大切さを実感した。既知の学習内容はわずかであるが、同じ規則を使って深く考え込んでいく大切さを感じた。このような取り組みをいろいろな学校で1つの問題をもとに考え,解法を交流しインターネットのインタラクティブな面も生かして新しい教科の授業活用にしようというのが出発点である。
(2)多解問題とは
・数学における多解問題
数学の問題は解が1つと思っている生徒も多いが、まず解法がたくさんある問題に取り組み、学校を超えて交流しよう。「数学における多解問題」ときめた。インターネット上での初めての試みであるので、問題のタイプを絞りすぎないためである。またコンテスト形式は正解がわかってしまうと興味が失われやすい。できるだけ解(解法)が1つではない問題を考えてもらい解法等のプロセスを学校間で交換しあう。
・数学がわかるとはなにか。相手を納得させる説得術
1つの問題をいろいろなアプローチをして考えると、本来の数学の自分で考える楽しさや、自分で考える大切さを実感する。自分の言葉で、低学年の子どもにわかるように既習事項を説明する。この過程において、表面的な理解ではなく自分の言葉で、本当の意味での数学の理解を促し、知識の定着を図ることができる。
・生徒自身にやる気をおこすには
大学生や社会人となった卒業生にあうと「もっとまじめに中学の時に数学をやっておけばよかったです。今大切なのは数学ですよ。」と文科系の卒業生にいわれる。今、教えている生徒にきくと、算数の四則計算は必要だが、関数や方程式などは大切なの?と思っている生徒は少なくない。受験勉強に必要だからとかではなく、数学が本当に必要だという実感する必要がある。そのために社会人の方の経験談を集め学習の動機づけにする。以上のことをインターネット上でおこなう。
具体的にはまず、問題を選定しインターネットのホームページ上に立ちあげ問題を公開する。それによって各自の学校、または個人で取り組み解答を送る。またWeb上に公開して意見交換をする。したがって今回のインターネット上の意見交換で大切なのは、正解を登録することではなくて、意見交換のなかで自分の考えを検討し、成長していくことである。
5.4.2 実施
(1)流れ
・多解問題の募集…解が何通りかある問題を募集する。多解問題の選定(2)問題選定
教科書の問題とは少し違う雰囲気にして、いろいろな分野で考えてみた。
ねらいとしては、表面的な理解では説明しにくい問題を考え、単に数学的な知識を問う問題をいれない。
(3)参加校 今年度このプロジェクトに参加した学校名と代表の先生方。
岡崎市立甲山中学校 稲垣 祐嗣先生(4)問題
など、「数学における多解問題について」のページ http://www.kf.keio.ac.jp
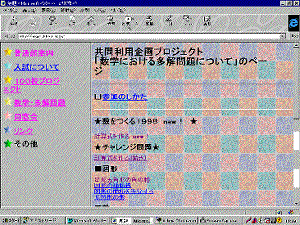 |
|
図3.多解問題ページ
|
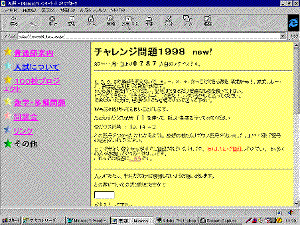 |
|
図4.解答登録画面
|
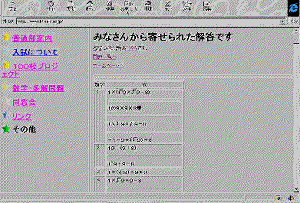 |
|
図5.解答表示画面
|
5.4.3 効果と課題
(1)効果
生徒の感想をみると多解問題を取り組んだ価値があったと答えた生徒が多い。またインターネットを通じて、各学校の先生方と知り合えたことも私にとっても意味があった。これからのインターネット活用で生徒は、教員1人から学ぶのではなく、いろいろな人との交流を通して、成長していくのである。(2)課題
・インフラの整備 教育現場でのインターネット環境の整備が進んできているが、まだまだ生徒にインターネット環境を自由に解放できる学校は多くない。
・数学の記述の問題 インターネットで解法を交換して検討する際に問題となるのは、数学記号の記述と図表などの取り込む作業の煩雑さである。問題や解法の図をスキャナーで読み込みGIFファイルに変換するという作業をしなければならない。
・情報の集約、プロジェクトの周知 サーチエンジンなどでホームページを公開されている先生方の情報が検索できる。個人の数学のホームページはJAVAscript、JAVAなどを使いかなり質のよいものが登録されてきている。
今後に大いに期待したい。
参考文献
○ネットワーク利用環境提供事業(100校プロジェクト)
平成8年度共同利用企画 数学における多解問題
○学校図書教科研究数学No.153
○日数教 長崎大会 インターネットを使った新しい試み
−選択授業と星型五角形と内角の和−