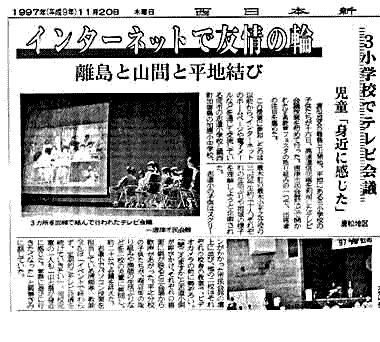5.32 地域に学ぶ学習材の開発とネットワークの構築
佐賀県唐津市立志道小学校 浦郷 孝一
5.32.1 概要
(1)これまでの経緯
唐津市立志道小学校では、1994年秋、コンピュータ21台導入に始まり、1996年5月、唐津市内の小中学校に通信用コンピュータが1台導入されたときに、佐賀県教育センター“EDU−QUKEさが”をプロバイダとしてインターネットへの接続が始まりました。
それまでのコンピュータリテラシー育成の取り組みから、インターネット活用へと研究の範囲を広げ、各教科における道具としての活用の可能性を探ってきました。
本校ではインターネットに接続するコンピュータが1台という環境の中で、多数の児童が同時にアクセスし、情報検索・収集するという活動を行うことはできません。しかし、こうした環境の中でインターネット活用を探る取り組みから現在の活動が生れてきました。
(2)地域情報データベース
各校に通信用コンピュータが導入されたのを機に、各小学校のホームページ作成の段階で、社会科等の調べ学習にも利用できるよう、各学校の地域情報を一元的にデータベース化し、学習に利用できるホームページ「わたしたちの唐津市」を別途作成し、“EDU−QUKEさが”上で運用しながら、利用研究を図ってきました。さらに、本事業の支援を受け、地域学習素材の交流と収集を図り始めたところです。
(3)インターネット活用と授業
1台のコンピュータを28.8モデムに接続して、授業・クラブでのWeb情報の提示や、教材情報の取得、職員のインターネット・電子メール研修、唐津市内職員間の電子メールの交換等に活用してきました。
本事業に選定後、市教育委員会の支援により、ISDN1回線およびISDNルーター機器が導入され、図書館のコンピュータ3台を活用した学習情報センター化を含め、簡易校内ネットワークの構築に向けて活動しています。
(4)テレビ会議システムと遠隔授業
平成8年度より、100校対象校の武雄北中学校の協力を得て、5年社会科「伝統工芸」の学習において、行政に対し伝統工芸を地域で守り育てる提案内容を調べていくために活用。さらに、シカゴの日本フェスタへの参加などに活用して来ました。しかし、これまでは回線速度、回線切断等の問題が起こり、授業での使用には多くの困難がありました。
本事業の機器貸与とISDN回線の設置により、本格的に共同学習・遠隔授業の試みに取り組めるようになり、いくつかの共同遠隔授業の取り組みを試みています。学校の地域情報ホームページと地域ネットワークを活かして、児童がリアルタイムに調べ学習や交流ができ、学習を深めることができる授業実践に向けて現在取り組んでいるところです。


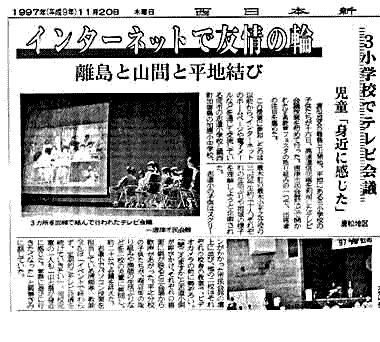
5.32.2 実施
インターネット活用教材の作成と、地域情報ネットワークを活用したテレビ会議システム授業の試み、簡易校内LANの構築に向けた活動に取り組んできました。
- 5,6月、5年理科「天気の変化」の学習において、Web情報を活用したHTML教材を作成し、20台のブラウザ上で天気予想の授業を実施した
- 8月、本校教職員に佐賀県教育センターよりインターネットアカウントの発給を受け、インターネット入門、電子メール運用の研修会を実施した
- 8月、唐津市内小学校のホームページ更新と地域情報データベース「わたしたちの唐津市」へのリンク作業、インターネット研修の支援を図った
- 9月、5年理科「天気の変化(2)」の学習において、Web情報を活用したHTML教材と新聞テレビ情報から、台風の進路予想授業を実施した
- 10,11月、4年社会科「私たちの佐賀県の特色ある地域を調べよう」の学習において、島の生活と商店街について、佐賀県北部地域内の離島、山間地、市街地の各校ホームぺージからの情報検索、電子メール・FAXを使った情報交流を図る。さらに、佐賀県教育フェスタ(11月16日)において、NTTのテレビ会議システムを使って3校同時に遠隔授業を実施した。このテレビ会議遠隔授業では、児童が調べたものの交流だけではなく、地域の人(離島からは漁師さん、市街地からは商店街の人)を呼んで、実演や意見交換、要望を直接伝えることができた
参加校:山間地・佐賀県東松浦郡厳木町立厳木小学校平之分校、渡辺 顕
離島・・佐賀県東松浦郡鎮西町立加唐小中学校、岩瀬 弘憲
- 12月5日から12月25日まで、本事業の支援を受け、CU−SeeMe用機器2台を借用し、テレビ会議システムの教育活用の研究を図る
- 12月、市教育委員会の支援を受け、ISDN1回線とISDNルーター機器をコンピュータ室に新設。校内LAN導入により職員室内と図書館3台のコンピュータをインターネットに接続する準備に入る
- 12月16日,18日、4年社会科「各地のくらしと私たちの国土・山地の人々のくらし」の学習において、ホームページの検索、情報取得、情報交換の最後にCU−SeeMeテレビ会議システムを活用し、それぞれの地域の抱える問題点等について交流授業を実施する
参加校:佐賀県東松浦郡厳木町立厳木小学校平之分校、渡辺 顕
- 12月17日、同一地域内の学級交流を図るため、CU−SeeMeテレビ会議システムを活用して、同時合唱、校区自慢ゲームなどの交流授業を実施する
参加校:唐津市立成和小学校、藤浦 聡文
5.32.3 効果と課題
- 市内小学校の地域情報をデータベース化することで、小学校3,4年生の地域学習に役立たせる土俵ができ、本校児童だけではなく、他校からもホームページ情報を基礎にした調べ学習の交流が始まりだした
- 教師代理の電子メール交流ではあるが、授業の中で生じた疑問等の解決に新しい情報手段を獲得することで、児童の興味関心を高めることができた
- 調べ学習において、従来の書籍、新聞、周囲の人々に聞く情報だけではなく、その地域でしかわからないことは、直接ホームページや電子メールを活用しながら、当事者の生の声を知る情報取得ができるようになった
- 学校ホームページの地域情報から、さらに知りたいことわかったことを直接交流する手段として、テレビ会議システムの活用は、直接相手を見ながら話し合うことができるだけでなく、その場で生じた疑問意見の交流で児童の思考を揺さぶり、さらに深めることができる有効な手段であることがわかった
- 佐賀県北部という同一地域の中でのテレビ会議システムを使った交流であったが、児童は離島山間地とも一度も訪れたことがなく、この交流を通してお互いの特色を知るとともに、自分達の住んでいる地域を知り身近に感じることができた
- インターネット接続1台という中で、社会科や理科の教材情報の取得と、HTML教材化により、コンピュータ室の21台のブラウザ上で児童の調べ・予想学習に活用することができ、コンピュータの活用範囲が広がった
- 年間を通したネットワーク活用の計画がまだ未整備で、今後、教科の中での位置づけや合科・総合の時間等を含めて検討を進めていく必要がある
- 3校で続けてきた共同学習をイベント的なものに終わらせず、教科・単元を考えながら共同のテーマを作り、同一地域内の地域情報を豊かにする取り組みを進める必要がある
- 2月に予定している簡易校内LANの構築を完成し、職員室内のインターネットアクセス、データの共有を図るとともに、図書室を学習情報センター化し、図書や新聞と同じように、インターネットにもアクセスして情報の取得ができる環境を創出したい
- 児童が収集・選択し、加工・表現した学習内容を、ホームページ上に発表できるスペースと、意見・批評してくれる交流の仲間作りの場を準備したい
- 学級交流、授業交流、共同学習、遠隔授業等、インターネットを活用した教師の授業アイデアを活かせるTT活用や、システムの運用支援を本校だけではなく、地域内小学校間でも活かせるシステム作りに取り組みたい