山口大学教育学部付属光中学校 教諭 前原 隆志
同上 教諭 神村 信男
| 月 | 学習内容・学習活動 | コンピュータの利用 |
| 10 | 情報収集,テーマの決定 | メディアキッズ会議室で先輩の話や後輩からの質問を聞く。 |
| 11 | 調査活動,友達からのアドバイス | インターネットの検索ソフトで沖縄関係のホームページを探す。 |
| 12 | 調査・報告活動 | メディアキッズでテーマ別に意見を交わす。調査結果をまとめる。 |
| 1 | 沖縄への提言 | インターネットで全国の類似例を探す。 |
| 2 | 提言の吟味 | 提言者と取材記者になりメディアキッズ上に新聞記事を作る。インターネットで交流相手を捜す。 |
| 3 | 提言をポスターにする中間発表 | 紹介された情報をインターネットで確認する。 |
| 4 | 修学旅行現地調査 | 紹介された情報を現地で確認するデジタルカメラ等を使って記録し,報告会を行う。 |
| 5 | 修学旅行報告会 | 下級生に修学旅行の学習成果を報告する。 |
| 学習内容・教師の問いかけ | 教師の対応 |
| 1 生徒作品の紹介 ・友だちの「沖縄ノート」の優れた点を学ぼう。 |
・生徒作品の中からテーマ設定や調査方法,表現方法で特色ある作品を選び,メディアキッズ上のメールで紹介する。 ・コンピュータ操作の手順を確認する。 |
| 2 友だちからのアドバイス ・自分の「沖縄ノート」に対して,友だちはどんなアドバイスをしてくれているのだろうか。 |
・自分のこれまでの調査が十分だったかどうか,友だちの批評をもとに考えさせる。 ・新しい調査の方向が見えるようなアドバイスがないかメールの中から予想させる。 ・調査に有効なホームページが見つかった場合,そのURLをメディアキッズのメールに記入して,みんなの共有の情報となるように指示しておく。 |
| 3 アドバイスに対する質問 ・アドバイスしてくれた友だちに真意を聞いてみよう。 |
・メールを手がかりにして友だちに直接質問し,自分の今後の調査の方針を探らせる。 ・よかった点や,不十分な点,新しい視点などを獲得できるよう,ワークシートを準備し応答の内容を記入させる。 |
| 4 新たな視点の獲得 ・沖縄県民の立場から見たとき,どんな視点をもつべきだろうか。沖縄県民に 「あなた自身はどう考えているのか」 と問われたらどう答えたらよいのだろう。 |
・沖縄県民が新たな方向を模索していること意識させる。 ・本土とは違った歴史的経緯,地理的環境,国際的立場にあることに気づかせ,異文化に接する際に個人個人が留意しなければならないことについて考えさせる。 ・沖縄県民からわれわれに投げかけられる疑問を想定させて,沖縄を理解することと自分の立場を明確にすることとが表裏一体であることに触れる。 |
| 5 調査活動の方針づくり ・今後の調査の方針を作ってみよう。 |
・メディアキッズでの調査や応答に沖縄県民も直接参加できるようになることを知らせ,そのために意識しておかなければならないことを考えさせる。 |
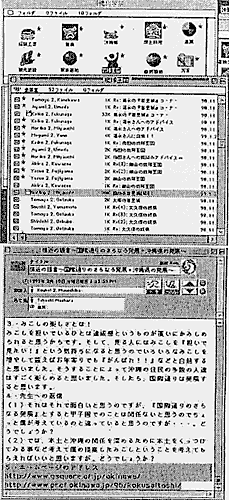 この学習で,生徒達が扱った情報について整理してみると,次のような情報がある。
この学習で,生徒達が扱った情報について整理してみると,次のような情報がある。| メディア活用の環境について 生徒たちが積極的にネットワークで得た情報を学習に生かしていくためには,それらを支援している2つの環境がある。1つは,ハードウェア(コンピュータ,ネットワーク,デジタルカメラ)が生徒たちの身近にあり常に使えるという環境にしておくことが必要である。2つめはメディアの活用を授業の中にどう取り入れたらよいか,あるいはそれらを生徒たちの学習にどう生かしたらよいかを真剣に考え,実行している教師が多数いることが大事である。教師が生徒たちの学びに対しての可能性,有効性を追求し,教官室内で研鑽できる人的環境を備えていることが大切になってくる。これらの環境が常に存在していることが生徒たちや教師が共に学び活動(共動性)する意欲を高めることになると考える。 |