・Windows基本操作を習得する
(起動・終了・スタート・コピー・切り取り・ペースト・削除等)
・表計算ソフト、ワープロソフト、図形作成ソフトの使い方を習得する
・GIFアニメーションの仕組みと作成の仕方,webページへの組み込み方を習得する
・各種タグの編集がメモ帳やエディタを使ってできるようになる
・wavファイルのwebページへの組み込み方を習得する
・タグの編集の仕方支援画面(サーバーに各タグの使い方のヘルプ画面をHTMLで
作っておいて,生徒が必要なときに見に行けるようにした)の作成
・教室内LANでのメールのやりとり(同じチームの生徒同士で,作品の構成や分担,出来具合や制作を進めていく段階での問題点などを打ち合わせるのに使った),ネチケット(メールのやりとりにかかわって)について知る
・日本各地,海外の学校や動物園などの施設とメールを交換して情報収集する
・図書室の資料や地域の素材(祭や文化遺産など),役場の資料やパンフレットなどからの資料収集
・手紙をやりとりしたり,写真を送ってもらったりしながらwebページをより豊かなものにする。 ・ドイツ,イタリア,カナダの生徒とのメールによる交流
・背景画面の作り方(グラフィックソフトを利用して,明度やコントラストなどを調節して,背景として適した画像にする)や入れ方を知り,工夫してページを作る。
・MIDIファイルの作成の仕方 を知る
・マップエディタの使い方を知り,webに組み込むことができるようにする
・グループ作品交流会
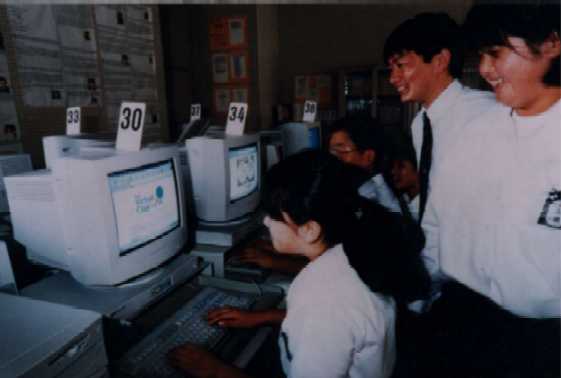
写真1 みんなで作品を認め合う
との交流開始
・メールやチャットを使って,教師同士の自己紹介,学校や生徒についての交流,
今後の活動計画の打ち合わせ
・教師や生徒が使えるソフト,技能の交流
・3校の教師で生徒につけさせたい力,めあての確認と共通理解
・参考例,よく使う言葉の提示など
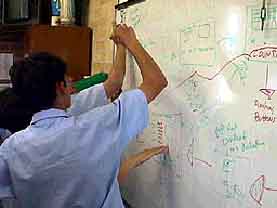

写真1,2 オーストラリアの生徒がサイトマップを考えているところ
・テレビ会議による自己紹介
・プレゼント交換 (旗,色紙,ポスター,硬貨,ビデオテープなど)
・生徒とともに教室掲示(プレゼントや海外の生徒の自己紹介など)


写真3 日本からの送った色紙を見る 写真4 コンピュータ室への掲示
アメリカの生徒
・5つのサブテーマ(恐竜の時代,国の始まり,政治の始まり,災害を乗り越えて生きていく人々,私たちの未来)の決定と各校の生徒のグループ分け(学校間を横切る役割分担の決定)
・サイトマップについての意見交流と改良,それにしたがってwebの制作
・制作したwebページの流れ(オーストラリアの数人の生徒がJAVAを使ったページ移動を作成)についての意見交流,改良
・テーマ音楽の決定

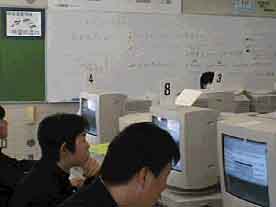
写真1 友達と相談しながら修正したキャラクターを確認する
・テーマ(グループ)ごとの資料収集とwebページ作成開始
・テーマごとのフォーラムでメール交換しながら,ページについて共通理解を図っていく
・web作成のためのデータ収集とweb作成(お互いの文化比較もしながら) ・テレビ会議による海外の学校との交流
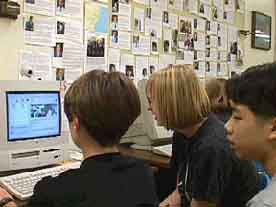

写真2 アメリカやオーストラリアの学校での本校とのテレビ会議の様子
・webページの各テーマ毎の内容作成
・webページのコンセプトの再検討,ページ制作上の問題点と改善