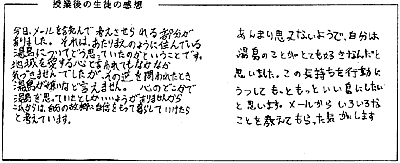湯島を全国の方言で紹介してもらおう計画
マルチメディアで育てるふるさとへの愛と誇り
中学校全学年 特別活動
熊本県天草郡大矢野町立湯島中学校 金井 義明
インターネット利用の意図
本校は,熊本県の有明海に浮かぶ,周囲4kmのたいへん小さな島の学校である。離島という閉ざされた環境のなかでは,小さなころから狭く同じ環境,同じメンバーでの生活であり,いろいろな人と接し,いろいろな考えに触れる機会が少ない状況にある。中学を卒業すると,大きな集団での生活が待ちかまえている。どのような困難にも立ち向かう力をつけてあげたい。そのために,多くの人との出会いの場を増やし,人間関係を深めていく経験の場を多く設定する必要があると考える。
そこで,島外の中学校との交流をきっかけに,島の人,さらにインターネットを使って全国の人との交流が始まった。学習の場を学校内だけでなく,地域へ,そして全国へ広げた交流学習を進めている。
交流を通して,視野を広げ,多面的にものを見たり,考えることができるようになってほしい。そしてそれは,島外へ目を向けるだけでなく,ふるさと湯島を見つめ,自分たちで島を盛り上げていこうという気持ちを高めることにつながる。私は,このように,交流活動を通して「ふるさと湯島を愛する心」を育てていきたい。
1 湯島を全国の人へ知ってもらおう
(1) ねらい及び指導目標
「ふるさとへの愛と誇り」は,次の3つの活動を通して育まれる。
・発見-ふるさと湯島を見つめ,そのすばらしさを知る。
・発信-ふるさと湯島のすばらしさを地域の人,全国の人に伝える。
・発展-ふるさと湯島をさらにすばらしくしようと考え行動する。
本実践は,湯島のすばらしさを発見,発信する取り組みである。
湯島を全国の人に知ってもらうために,湯島紹介のホームページを作成する。その取材のなかで,今までと違う眼で島を見つめ,今まで気がつかなかった湯島のすばらしさに 気づいてほしい。さらに湯島の一員としての自覚を高めたい。
はじめのねらいはここまでであったが,活動はさらに広がっていった。全国の人へ,湯島紹介をその土地の方言になおしてもらおうと呼びかけるなかでの企画力,寄せられたメールから学ぶ「郷土愛」など,活動の広がりとともに,ねらいも広がっていった。
(2) 利用場面
湯島の紹介文の作成,ホームページの公開,方言の募集における電子メールの送受信で,パソコン,インターネットを活用した。
(3) 利用環境(実践当時)
①使用機種 NEC9801 4台 富士通FM-V(DESK POWER)1台
②周辺機器 カシオデジタルカメラ
③稼働環境 インターネットができる環境がなく,教師個人のパソコンにより,ホームページ作成,電子メールの送受信を行った。
④その他の利用ソフト ネットスケープナビゲーターVer3,一太郎Ver3
2 指導計画
(生徒の活動)
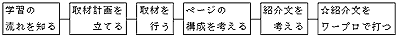
生徒が作成した湯島の紹介文を,教師がホームページにまとめる
ホームページを公開する(★インターネットの活用)
寄せられたメールをもとに考えるふるさとを愛する心(★電子メールの活用)
3 利用場面
 (1) 改めて気がつくふるさとのすばらしさ
(1) 改めて気がつくふるさとのすばらしさ
取材では,島のいろいろな人と出会い,美しい自然にも目を向けることができた。いつもは何も感じないことも,取材をするという意識は,あらたな発見を促してくれた。
自分たちが生まれ育ったところだからこそ見落としていた湯島のすばらしさに気づくことができた。
取材後の生徒の感想
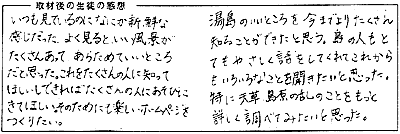
(2) 自分たちにしかできない地域紹介をしよう
多くの方に見てもらいたい。そのためにも,自分たちにしかできない地域紹介にしようと生徒に呼びかけた。みんなで考えるなかで,湯島弁で紹介を行うことにした。おじいちゃんやおばあちゃんに聞きながら,一生懸命に紹介文の湯島弁化に取り組んだ。おかげで,本校ならではの湯島紹介のページを作成することができた。
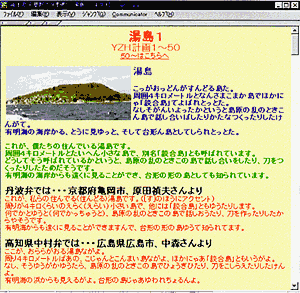
(3) 全国の方言を知りたい
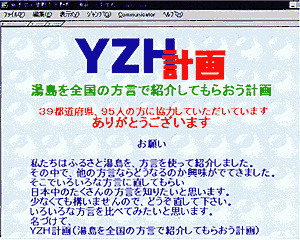 驚いたことに,小さな島の方言でもいろいろな言い方があった。そこで全国の方言を調べるともっとおもしろいだろうという話に進展し,YZH計画(湯島を全国の方言で紹介してもらおう計画)を行うことにした。全国へ協力を呼びかけたところ,現在40都道府県,100人あまりの協力を頂きいろいろな方言で湯島を紹介していただいている。
驚いたことに,小さな島の方言でもいろいろな言い方があった。そこで全国の方言を調べるともっとおもしろいだろうという話に進展し,YZH計画(湯島を全国の方言で紹介してもらおう計画)を行うことにした。全国へ協力を呼びかけたところ,現在40都道府県,100人あまりの協力を頂きいろいろな方言で湯島を紹介していただいている。
(4) 寄せられたメールから学んだふるさとのすばらしさ
方言を教えてもらうだけでなく,生徒の取り組みに対して,多くの励ましの言葉を頂いた。方言を大切にしようと思う方は,同時にふるさとを大切にしようと思う方ばかりである。方言について,さらにふるさとについてみんなで考えることができた。自分たちの湯島のすばらしさについて,あらためて気づくことができたようである。
・寄せられたメールより
最近は中学校でインターネットをされるんですね!。驚きました。そして,生まれ育ったかけがえのない故郷を,こうしてインターネットを通して全世界に紹介されるなんて,とてもすばらしいことだと思います。
私自身も,東京に出てきてから,故郷である大阪がとても愛おしくなってきました。住んでいたときには全く感じなかったのに。それだけに湯島中学校のみなさんの「湯島を愛する心」をひしひしと感じるホームページでとても楽しい時間を過ごさせていただきました。
絶対にかけがえのない「湯島の言葉・風習」を忘れないでください!。そしてもっと多くの方々にすばらしい湯島を紹介なさってください。応援いたします。
ともかく,みなさんは,自分たちが住んでいる地域を愛し,方言について強い問題意識を持っていると見受けました。どうか,その問題意識を大切にしてほしいと思います。
私は,現在東京に住んでいます。仕事の関係で全国さまざまなところに行きます。行った土地行った土地で,そこのよさを発見します。いつの日か,みなさんの住んでいる 湯島に行って,湯島のよさを見つけたいと思います。みなさんも,機会があったら,日本全国,いや世界中,いろいろなところに行ってみてください。そうすると,みなさんの住んでいる湯島がもっとよくわかると思います。
・郷土への愛(寄せられたメールを使って行った道徳の授業)
① 目標
方言のすばらしさに気づくとともに,郷土を愛し,その発展に尽くそうとする態度を身につけることができる。
② 資料
寄せられたメール
③展開
| 学習活動 |
主な発問と予想される生徒の反応 |
教師の支援 |
| 1.日頃使っている湯島弁についてえる |
・意識したことがない。
・都会に行ったら使わない。
・はずかしい。 |
・湯島弁をどう考えているのか,都会という場面を設定して考えさせたい。 |
2.今後方言が残るかどうかを考える
3.ふるさとを愛する心について考える
4.今後どのような行動をとっていくべきか考える
|
今後,方言は残るだろうか,
なくなってしまうのだろうか
|
「残る」
・その土地の特徴だから
・今までも使っているから
「なくなる」
・共通語のテレビに影響されて
・格好悪い。恥ずかしい。
・その場の雰囲気で使えない。
メールの意見の中の,「ふるさとを愛する心」とはどういうことなのだろう
|
・ふるさとのよさを残していくこと。
・ふるさとを活性化させること。
・ふるさとに誇りを持つこと。
|
・方言を使ってよかったこと,悪かったことなどの経験を想起させ,身近なこととしてとらえさせたい。
・「残る」「残らない」どちらかの考えか明確にさせ,深く考えさせたい。
・寄せられたメールを読み,意見を参考にしてより深く考えさせたい。
・湯島のよいところ,悪いところを出し合い,それぞれが持っているふるさとへの思いと関連づけて考えさせたい。
・自分たちもふるさとを愛する心を持っていること,それをどう実行していくかが大切であることに気づかせたい。 |
5.メッセージを書く
6.みんなの考えを聞く
7.教師の話を聞く
|
メールを送ってくれた方へ,
みんなからもメッセージを送ろう。
|
|
・メッセージを送ることにより自分が今後どのような行動をとるべきか考えさせたい。
・今後も自分たちの手で湯島のよさを残していこうという気持ちを高めたい。 |
授業後の生徒の感想
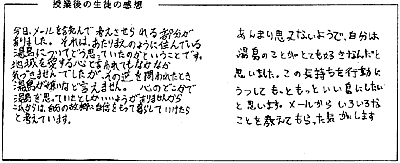
4 実践を終えて
活動は予想以上に広がり,子どもたちの追求意欲も高まってきている。また,相手にうまく伝えようとする表現力や,コンピュータの基本操作も徐々に高まっている。その他の成果は,以下の通りである。
・地域の人たちと接し,地域のことを調べるなかで,「湯島にはこんな人がいたんだ」「歴史的にとても重要なことがあったんだ」と改めて湯島の人や自然,歴史のすばらしさを感じることができた。また,自分が湯島の一員であるという自覚も高まり,自分の手で湯島を守っていかなければという気持ちが強くなってきている。
湯島のことを全国の人に伝えようとする姿からは,自分の生まれ育ったふるさとへの愛と誇りが感じられる。さらに,多くの方からメールを頂き,生徒たちもたいへん励みになったようである。自分が取材し,作成したホームページを発信しそれを多くの人に認められる,インターネットの双方向性という特質は今後も積極的に活用していきたい。
ワンポイント・アドバイス
「自分たちにしかできない地域紹介をしよう」からはじまった取り組みは,全国の人の協力を得て,予想もしていなかった活動に広がった。地域の人と触れあい,全国の人とつながるなかから様々なことを学ぶことができた。今後も,方言データベースとして,充実させていきたいと考えている。小さな島からも,全国へ向けて情報発信ができ,働きかけることができる,インターネットのすばらしさを感じるできごとであった。
しかしながら,ホームページで呼びかけると,たくさんの人が協力してくれるかというと,そうでもない。ホームページが増え続ける今,学校のホームページを見てくれる人は少なくなる一方であると思う。その中で,自分たちの取り組みを知ってもらい,協力していただくよう,働きかけることが大切である。結局,つながっているのは人であり,人と人をどう結び,協力しあっていくかが重要であると考える。
|
 (1) 改めて気がつくふるさとのすばらしさ
(1) 改めて気がつくふるさとのすばらしさ 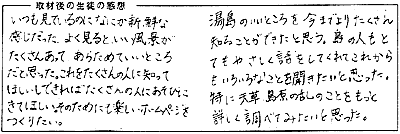
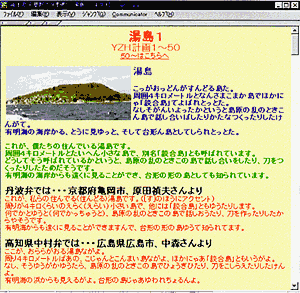
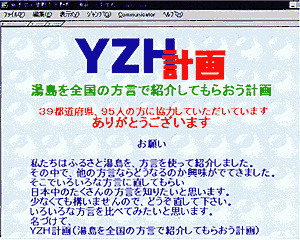 驚いたことに,小さな島の方言でもいろいろな言い方があった。そこで全国の方言を調べるともっとおもしろいだろうという話に進展し,YZH計画(湯島を全国の方言で紹介してもらおう計画)を行うことにした。全国へ協力を呼びかけたところ,現在40都道府県,100人あまりの協力を頂きいろいろな方言で湯島を紹介していただいている。
驚いたことに,小さな島の方言でもいろいろな言い方があった。そこで全国の方言を調べるともっとおもしろいだろうという話に進展し,YZH計画(湯島を全国の方言で紹介してもらおう計画)を行うことにした。全国へ協力を呼びかけたところ,現在40都道府県,100人あまりの協力を頂きいろいろな方言で湯島を紹介していただいている。