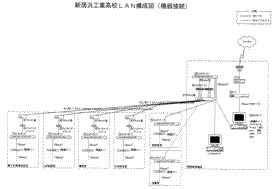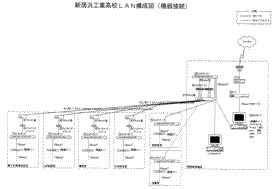光ファイバー網を利用したテレビ会議システムの研究
インターネット利用の意図
情報通信技術のめざましい発展によって,電話回線やインターネットを利用してテレビ会議を簡単に実現することができるようになった。これを利用し,新しい教育方法を開発することを目的として研究に取り組んできた。テレビ会議システムは,マルチメディア・コミュニケーションを実現する有力な道具である。教育にとってコミュニケーションの方法は教育効果にとって重要な要素となる。これまでテレビ会議システムを学校教育の現場で日常的に利用するには,コストや運用技術の面から困難であった。現在は情報通信技術の発展によって意外と簡単に実現できるようになった。
1 ねらい
インターネットによるテレビ会議を教育活動に利用することで,どの程度の教育効果を得ることができるのか,また,実践を通してテレビ会議システムの利用がどのような教育分野に適しているか,更に,テレビ会議システムの技術的な問題や運用を行うためのネットワーク環境の整備等について研究開発に取り組むことにした。
2 指導目標
教科指導や特別活動において,インターネットを学習活動の道具として位置づけ,利用方法の習得や学習目標を達成するための情報収集,意見交換を行うためのコミュニケーション・ツール(テレビ会議システム)として利用させる。
これによって問題解決能力や自ら学ぶ力を育成する。
3 利用場面(テレビ会議システムの利用が効果的な教育分野)
テレビ会議システムは,主に遠隔地あるいは場所的に隔絶されている2箇所以上の場所でマルチメデアなコミュニケーションを必要とする場面に利用するとよい。また,各種実験等で微細な対象物をスクリーン上に拡大投影し,会議に利用するなどがある。この様な場面は,教育の世界には無数にあると思われる。以下に利用可能な分野を例示する。
(1) 学校間の共同研究
例:環境問題における意見交換,課題研究等の共同研究
(2) 地域社会とのコラボレーション
例:リクルート開発,職業訓練
(3) 国際理解教育
例:文化交流,共同研究
4 利用環境
最近,テレビ会議システムとして製品化され,市販されているものも多くなってきた。
機能的に高度で高価なものから,多少映像等の品質を落すなど機能に制限を設け価格を低く抑えているものまで様々である。
学校教育での利用は,特別予算等が手当されている場合を除いて,多くの経費をかけることはできない。この様な条件の下でテレビ会議を実現するには,カメラやキャプチャーボードは市販品を購入するとしても,ソフトウェアはフリーウェアが存在している。これらを利用することで,テレビ会議システムの教育利用は一応可能である。
(1) 技術的な動向
テレビ会議に関する技術的動向としては,動画の符号化技術としていくつかの国際規格(ITU−T勧告)がある。ISDN回線の利用を前提としたH.320(市販サービスとしてマルチポイントサポートのテレビ会議システムが販売されている。),アナログ網やPHSで利用される低ビットレートマルチメディア端末用のH.324,世界の標準的なテレビジョン方式のどれとも直接接続できる機能を持たせたハイブリッド符号化方式を規定したH.261,CD−ROMなどの蓄積媒体での符号化技術として標準化されたMPEG1,更に高画質を追求し,蓄積メディアだけでなく,通信・放送メディアのデジタル化なども含め標準化されたMPEG2などがある。
今後,様々な画質を提供できるMPEG2は幅広い分野のマルチメディア通信に利用されることになると思われる。
また,国際規格の勧告に準拠しない独自技術によるシステムも多く存在する。
(2) テレビ会議システムに必要な環境整備と運用の問題
遠隔地とのテレビ会議を行う場合は,インターネットを利用すると経済的である。一般の電話回線のようなギャランティー形(通信が保障される方法:信頼性が高い・品質がよい)のポイントツーポイントの接続では,料金体系が距離制のため日常的な利用は難しい。しかし,インターネットを利用するならば,世界中のどのような場所ともテレビ会議は可能であり,マルチポイントをサポートし必要経費も,基本的には利用場所に関係なく同じである。だが,問題点もある。インターネット上のテレビ会議に参加するには,複数の地点を結ぶインターネット回線が使われ,ここに流れるトラフィック量に対する回線容量が大きなボトルネットとなる。
これはインターネットが通信方式としてパケット方式が採用され,一般に公衆網を利用するため,限られたユーザだけで回線を占有することはできないところに原因がある。 (したがって通信回線費は安いのだが・・・)
テレビ会議はいわずもがなであるが,映像信号と音声信号,テキストコードの送受信がスムーズに行われて,はじめて成立するものである。
これらの信号は膨大なトラフィック量となる。このトラフィックをベストエフォート(確実な通信は保障されないが回線能力の範囲で最良の通信を行う方法)なインターネット回線を利用しようとする場合,高度な情報インフラの構築が前提であり,現段階ではなかなか困難である。そこで映像信号の圧縮方法やサンプリングに工夫がほどこされ,映像・音声共に実用上差し支えない程度(医療や技術関係では解像度を抑えることはできないと思う。)に品質を抑えて利用することになる。市販のテレビ会議システムもフリーウェアのシステムもこの点では同じ範疇にある。
実際に学校教育で利用するには,インターネット回線を確保し,市販の物を購入するか,フリーウェア(代表的なものでは:CU−SeeMe)を利用することになる。もちろん実験的には大規模な通信システム(マイクロウェーブ回線や高速光ファイバー網を)を利用するケースもあるが,まだ一般的ではない。
(3) マルチメディア利用校内LANの整備
新しく校内LANを構築するに当たり,大きな目標の一つをマルチメディア・コミュニケーションが可能なシステムとして設計することにした。
限られた予算ではあったが,今後の情報通信の発展も考慮し,光ファイバー網で校内LANを構築することにした。
光ファイバーであれば帯域幅を自由にとることができるが,今回の構築は100Mbpsを校内のバックボーンとした。
ネットワーク機器については,スイッチングHUBを中心にできるだけコリジョンドメインを小さく設計し,信号の衝突をさけるようにした。
また,校内LANを通した外部とのテレビ会議は,グローバルIPアドレスを利用するが,各クライアントはDHCPサーバにより管理するため,必要な箇所にNAT機能を持たせ,グローバルIPアドレスでコミュニケーションができる設計とした。
校内LANに接続されるインターネット回線は,光ファイバーによる1.5Mbpsを導入した。これによって,外部とのテレビ会議における映像・音声・チャット等の品質も大幅に改善されるものと思われる。
(4) 校内LAN概要図
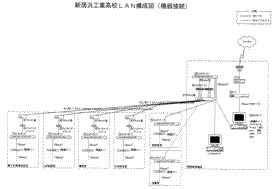 |
現在,図の様に約140台のクライアント及び約5台(必要に応じてサーバを立てる)のサーバが接続されている。
テレビ会議等のトラフィクの発生が大きいクライアントはスイッチングHUBの100BASEポートを利用することができる。
100BASEポートは,校内に教棟別に7箇所16ポートが利用できる。
|
(5) テレビ会議に必要な道具
テレビ会議の方式には,ルーム型,デスクトップ型,モバイル型などがある。
ルーム型はテレビ会議専用の部屋が準備され,多人数での会議に使われるが,カメラの方向などはリモートコントロールで制御される。通信回線も高速のものが使われる。
また,パソコンを利用するものや一体型のものがあるが,パソコンを利用する方が安価である。
ここでは,よく利用されるパソコン利用デスクトップ型について紹介する。
・コーデックボード(ビデオ・キャプチャーボード)
ボード自身にCPUが登載されたものや,使用するパソコンのCPUパワーを利用するものもある。市販されているものは解像度によっ大幅に価格が違っている。
・カメラ及びマイクロホン
カラーCCDカメラにマイクロホンが一体化したものが使いやすいと思われる。場合によってはホームビデオカメラでもよい。
(こちらの方が高性能である。)
・ソフトウェア
フリーウェアで高性能のものがある。(インターネット上に多数存在する)
米コーネル大学で開発されたCU−SeeMeがよく利用される。
リフレクターもフリーウェアで提供されている。
(リフレクターはインターネット上で検索すると,国内の大手民間企業のサイトに存在している。ソースファイルであるので,C++Ver4コンパイラが必要である。サーバにインストールして利用する。)
・リフレクターの立ち上げとセキュリティ問題
リフレクターの立ち上げは,セキュリティの問題から校内LANの外向けサーバにインストールする方がよい。もしイントラネットサーバにインストールして利用する場合は,インターネットにつなげるルーターにパケットフィルタリング等を行い,確実な相手のみが利用できるようにする。
校内に限定してテレビ会議を行う場合(必要がないと思うが)は,イントラネット上にリフレクターを置くと,快適なトラフィクが得られる。
・市販されている簡易テレビ会議システムの種類
CU−SeeMeをベースに開発されたもの
NetMeetingをベースに開発されたもの
Phoenix(デスクトップ一体型)などメーカ独自のシステムも多い。
5 指導計画と授業実践
当初,利用環境として光ファイバー網を計画していたが,諸般の事情により完成が大幅に遅れ,高速回線による授業実践はこれからの課題となった。
したがって,ここでは従来の64Kbpsや一般アナログ回線を利用して授業を行った。
(1) テレビ会議システムの利用実験
課題研究の情報通信技術に関する授業の一環として実験を行った。結果を以下に紹介する。この実験の条件は,一般に市販されているキャプチャーボード(5〜6万円)とカラーCCDカメラ,CU−SeeMeを利用し,遠隔地間3箇所で行った場合である。また,インターネット回線の経路情報に関してはなんら考慮することなく実験を行った。だだし,TCP/IPユーティリティである経路情報取得コマンド(tracertコマンド)を利用し,情報収集は行い,経路及び時間的監視は行ったが,実験結果の分析には反映していない。(普通に実験し体感を評価の中心にしている。)
・3.4KHzアナログ電話回線を36Kbpsモデムで利用したテレビ会議では,音声を利用することは困難である。映像としてもフレーム数(毎秒30フレーム程度送受信できればなめらかな自然映像になる。)を極端に抑え,モノクロでパラパラとした感じのフレーム数(5〜10)で我慢しなければならない。テキストによるチャットは自由にできる状態である。
・INS64電話回線では映像を減色したカラーとして,フレームは10フレーム前後(人の動作状態は充分把握できる程度の映像)で可能である。音声は虫喰い状態で,とても実用性は感じられないが,意味はほぼ理解することができる。テキストによるチャットは自由にできる状態である。
一応,ISN64によるテレビ会議については,総合的に実用できると思われる。
・1.5Mbps光ファイバー回線による実験は,当初計画していたが,光ファイバー回線の工事等導入時期が予定より遅れたため,現在のところ(2月現在)実験に取りかかっていない。
まもなく,工事が完成し,実験可能になるので,実験予定である。
現在までの結論としては,CU−SeeMeを使ったISN64回線によるテレビ会議は,実用できる段階にあるといえる。また,コストパーフォーマンスをあまり気にしないならば,専用テレビ会議システムは操作性等に優れた点があると思われる。今後,情報圧縮技術の発展やxDSL等の既設回線を利用した情報通信技術の進歩により,更に実用に近づくと考えられる。
(2) 環境教育の実践と今後の計画
特別活動の分野で実施した。
校内で発生するゴミの問題を取り上げ,環境全般な地球環境問題へ発展させた。
山口県の高校生,長野県の一般市民の方,市内の他高校生,本校生によってテレビ会議を利用したコラボレーションを行った。
現在,校内の焼却炉が廃止され,生徒たちは自分の出すゴミに対して意識がかなり変化してきている。
焼却炉から排出される有毒物質(ダイオキシン等)に関して,インターネット上から情報収集を行いながら,論議を進めてゆくことができるなど,これまでにない手法で,学習活動に取り組むことができ,大きな教育効果を得られたと思う。
このような手法を発展させ,海外の高校生(経験上かなり困難を伴うと思うが:ただし,適切なコーディネータが存在すれば解決できる問題である。)も交えて,授業実践ができることを願っている。
6 教育実践と問題点
光ファイバー校内LAN工事が遅れたため,これを利用しての実験はこれから取り組む計画である。
既設の校内LAN(10BASE5幹線)から,CU−SeeMeを利用して,環境問題をテーマに,本校と他県の高校,他県の一般市民,県内の高校とテレビ会議を数回行ったが,この時,リフレクターはテレビ会議システムを販売している民間企業のものを利用したこともあり,参加者を限定することができなく,予定にない様々な人が参加する場面もあった。
参加者限定の場合は,会議の大体の流れを事前に想定することはできるが,不特定多数の参加になると,様々な意見も得られ,別の意味で教育効果を期待できる場合もあると思われる。
7 実践を終えて
テレビ会議を利用した教育活動は,まさにネットワーク社会の到来にふさわしい教育のスタイルであるといえよう。
現在のところ簡単に利用できるかといえば,今すこし煩雑な部分があり,更に技術が進歩し,誰もが簡単に利用できるよう進化が望まれる。
また,教育の方法全般に関しても,マルチメディアの活用は,今後の教育の在り方にとっても大きく影響を与える要素である。
インターネットの導入に限らず,マルチメディア教材のデータベース開発やそれらを駆使できる指導者の養成など急がなければならない問題も多い。
ワンポイント・アドバイス
CU−SeeMeを利用して実施を行ったが,このシステムの場合,インターネット上のどこかのサイト(サーバ)にリフレクターを立ち上げる必要がある。すでに公開されているリフレクターを使うこともできるが,予測できないハプニングが起こる可能性がある。できれば自前(自分のサーバか大学等に依頼するとよい。)でリフレクターを立ち上げることをお奨めしたい。リフレクターの在処は本文中に記載済みである。
また,テレビ会議を行う相手校探しには,ネットニュースの関係分野にニュースを投稿すると,様々なアドバイスや紹介を得られると思う。 |