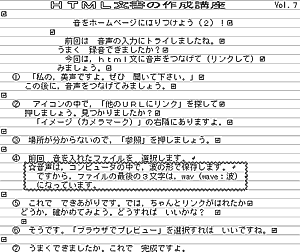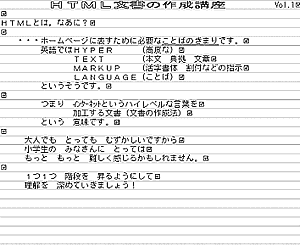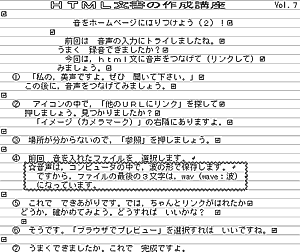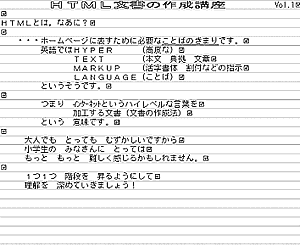インターネット新聞で発表しよう
─調べたことをまとめてみよう─
小学校第5学年・国語
茨城県鹿嶋市立中野東小学校 山田 岳男
インターネット利用の意図
児童は,インターネット上から情報を収集して活用する学習は,今までに数多く取り入れて行ってきた。しかし,この形式では,受け身的な学習になってしまいがちである。そこで,HTML形式の言語について簡単に学習した上で,自分たちが調べたことをホームページ作成を通して情報発信すれば,学習も能動的になり,今まで以上に,より意欲的に活動できるのではと考えて行ったものである。
1 調査したことを「みんなの読書生活」(光村図書出版)
(1) ねらい
グループごとに,調査するテーマを決め,調べ学習を行い,インターネット新聞を作成・発表することにより,物事を深く考える意識を高めさせる。
(2) 授業に至るまでの経過
2学期始めに,子供たちから「ホームページを作りたい。」という声があがり,市販されているマニュアルを参考にして,子供向けのガイドを作成した。学級活動やゆとりの時間を活用して,4~5時間程度でマスターした。そこで,この技術を活用して,本単元と兼ねあわせて,「インターネット新聞」を作成しようと考えた。
(3) 利用場面
エディタを用いて,HTML言語を活用して編集を行った。また,ハイパーキューブ2の作画機能を活用して,アンケート結果を絵で表すようにした。絵などのデータは,添付形式でリンクするようにした。作品の完成したグループから,インターネット上にデータをアップ・公開することにより,子供たちの意欲を喚起するようにした。
(4) 利用環境
①使用機種 富士通FM-TOWNSⅡ教師用1台 児童用20台
②利用ソフト DEKURE社「Hyper Edit」 スズキ教育ソフト「ハイパーキューブ2」
Netscape社「Netscape Navigator ver.3.0」
③周辺機器 内田洋行社・実物投影機
2 指導計画
|
指導計画(10/10)
|
留 意 点
|
① グループで調べてみたい題材について話し合い,テーマを決める。
② 調べたいことを,どのような方法で調査するか,話し合いを進める。
③④アンケートを作成し,分担に従って,調査を行う。
⑤ 調査した結果を持ち寄り,データを集計する。
⑥⑦⑧データをもとにして,インターネット新聞を作成する。
・文書の作成
・画像の作成
・データ処理
☆インターネットの活用
⑨ インターネット新聞発表会を行う。
・1班 ・2班
・3班 ・4班
・5班 ・6班
⑩ まとめを行う。
・データ収集からホームページ作成,発表会までについての感想を書く。
|
・身の回りにある身近なことを想起しながら,テーマを考えさせたい。
・アンケートで調査するか,面接報で行うか,それぞれの利点を考えさせながら,決めるようにする。
・必要なデータが得られるように,選択肢や回答欄に注意して作成するようにする。
・間違いのないように,再度チェックしたり,複数で確認したりするようにする。
・文書を編集する際に,わからないことがあったら,HTMLについてのマニュアルで確認しながら行うようにする。
・画像データについては,著作権の問題があるので,既成のものは活用せず,各自で作画するように助言する。
・編集の際には,閲覧ソフトも同時に開いて,確認しながら編集するようにする。
・各班の発表の後に,質疑の時間を設け,話し合いを深めるようにしたい。
・教師用パソコンから,児童用パソコンに画像データを一斉送出して,発表を行うようにする。
・ホームページに掲載できなかったデータは,実物投影機を用いて提示する。
・工夫した点,苦労した点などを書くようにする。
|
3 利用場面
(1) エディタを活用してのホームページ編集
① エディタについての事前学習
インターネットを用いて学習している中で,さまざまなホームページを見てきた子供たちの間から,「ホームページを作りたいよ。」という声が盛んに聞かれるようになってきた。HTML文を使って作成するので,大人の私でも初めの頃は,とても難しく,とっつきづらかった。時間があれば一人ひとりに個別指導を行うこともできたが,時間的な余裕もなかった。そこで,自分自身が知っている範囲内で,子供たちが自力で作れそうなホームページのテキストを作成することにした。作る際に,注意したことは次のことである。
○テキストを参考にすれば,自力で簡単なホームページが作れること。
○文字の大きさや色について,自由に変えられること。
○画像が添付できること。
○”wab形式”で音声を添付できること。
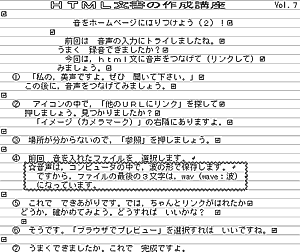 |
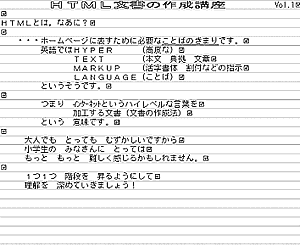 |
|
図1 HTMLの自作テキスト
|
実際に活動する中で,児童用の小さな画面で作ったものを,サイズの大きい画面で見ると,画像と文字のバランスがくずれてしまうことに気づき,また,子供たちからも指摘を受けた。そこで,少々レベルが高いが次のことについても,テキストを作成することにした。
○どんなサイズの画面でも画像がきちんと見えるように,テーブルの切り方をマスターできること。
② エディタを用いての編集作業
各班とも,テキストを参考にしながら編集を進めた。また,編集の際に誤りを少なくするために,エディタで編集を進める場合は,2人組になって行うようにアドバイスした。わからないことがあれば,巡回して指導している教師に尋ねるようにして,作業の効率化を図った。
最初のうちは,文字を入力するだけで,精一杯だった。しかし,ブラウザで確認する中で,「小さいから見づらい。」,「赤くした方が目立つよ。」などの声があがり,文字サイズを変えて大きくしたり,色をつけて,目立たせるような工夫が見られた。
 |
|
図2 エディタ編集の様子
|
(2) キューブ2を活用しての画像編集
算数では,3学期になるとグラフについての学習をする。しかし,この授業を行ったのは,2学期でまだ未習だったので,グラフの活用は行わなかった。そこで,ここでは,テーマに関する絵を描くこと,また必要に応じてアンケート結果を,文字とイラストで表現するようにした。ここでは,ハイパーキューブ2を活用して行った。描く部分を拡大して彩色したり,コピーや貼り付けを効果的に行って,手際よく活動できていた。
 |
|
図3 画像編集の様子
|
(3) データのアップについて
インターネット上に,データを公開するので,校内で決められているネット上のエチケット(ネチケット)に反していないか,また,プライバシーを侵害している点がないか,担任およびwebmasterである研究主任の2人で確認を行った。また,製作者である子供たちからも,データのアップについての了解を確認してから行った。
(4) インターネット新聞発表会
6班のデータが全て完成したので,全体でインターネット新聞発表会を行った。プロバイダーのサーバにあるデータを呼び出して行うため,全てのパソコンでアクセスをかけると,時間のロスが大きくなることが懸念された。そこで,教師のパソコンからのみアクセスをかけた。そして,データを児童用パソコン20台に一斉に送信して授業を行った。
発表については,各班とも5分以内で発表という形式をとった。また,ホームページで載せられなかった資料については,実物投影機を用いて,一斉送信で提示する形式をとった。
発表の後,質問の時間を設けた。それぞれが,各班の質問アンケートに回答していたので,内容が理解できていて,質問も少ないのではと予想していた。しかし,各班の内容について分からない点が多かったようで,質問が多く出されていた。
最後に,webmasterである研究主任の先生に,ホームページ及び発表を聞いての感想,アドバイスをいただいた。資料のデータに信頼性を高めるという点では,学年全体からデータを収集した方がよいこと,ホームページを見る人の立場を考えて,文と絵のレイアウトを工夫するとさらによいことなどを教わった。子供たちも,ふだん中野東小のホームページを作成,管理している先生のアドバイスなので,うなずきながら,またメモをとりながら集中して聞く姿が見られた。
 |
 |
|
図4,5 発表会の様子
|
4 実践を終えて
子供たちが,とても意欲的に活動できていたので,思ったよりもスムーズに活動することができていた。また,わからないところがあったり,疑問点があったりすると,友だち同士で教えあったり,それでも解決しないと,教師側に尋ねてきたりして自らの力で解決しようとする姿が多く見られた。各班ごとの内容では,調査対象が,ほとんどクラス内で行ったので,広がりがあまりなかったように感じた。また,未習のためグラフをほとんど活用できなかったので,この点をもう少し工夫すれば,深まりのある作品に仕上がったのではと感じた。
 |
|
図6 ホームページ作品
|
ワンポイント・アドバイス
「インターネット上にホームページを載せたい。」という子供たちの希望から始まったものである。小学5年生が限られた時間で作成したものであり,内容的には,まだまだである。しかし,子供たちの意欲が喚起され,難度の高いエディタを使ってのホームページ作りを完成させることができた。また,本文には言及していないが,インターネット上からフリーアイコンを見つけて,著作者に許可のメールをいただいてから,アイコンを利用することもできていた。子供たちの情報活用能力は,大きく成長したと言える。
エディタの良さは,作成しながら出来を確認できる点,そして修正や加筆が容易である点である。また,学校予算が限定されているので,インターネット上から,シェアウェアという形でダウンロードして購入した。市販のソフトを店頭で購入するよりも,安い価格で入手できた。試用期間があるので,試してから購入することができる。シェアウェアソフトを活用するのも,有効かと思われる。
|
利用したURLなど
鹿嶋市立中野東小学校(http://www.sopia.or.jp/nees/index.html)
子供たちの自作ホームページ(http://www.sopia.or.jp/nees/1998/5-2/child/9812theme.html)