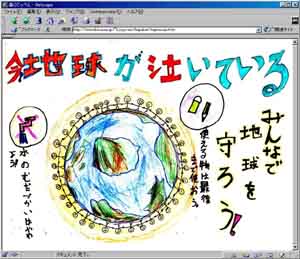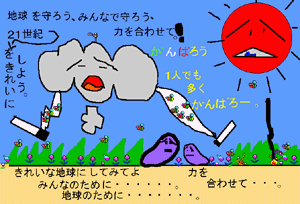インターネットによる情報発信で公民的資質を養う
ぼくたちにできる環境にやさしいこと
小学校第5学年・社会
京都女子大学附属小学校 多川 充
インターネット利用の意図
10年前までは自分の意見を世に訴えるには,現実的には新聞に投書するぐらいしか方法はなかった。ところが今やパソコン通信を使えば,それが簡単にできるし,インターネットを使えば世界にメッセージを送ることさえできる。児童・生徒のこういった世の中に積極的に関っていこうとする行為が,公民的資質の育成をめざす社会科にとって望ましい姿であることはいうまでもない。インターネットを利用し自分たちの学習の結果を不特定多数の人々に発信することを前提に学習を進めることにより,子どもたちはこだわりを持って取り組むであろうし,また情報を受け取った人々から反応があれば,子どもたちは自分に対する評価として受け止め,それは次の追究に大きな意欲となるであろう。
1 ぼくたちにできる環境にやさしいこと
(1) ねらい
本単元は大単元「わたしたちの生活と工業生産」の中の小単元である。子どもたちは自動車工業を学ぶことにより,日本の工業についての社会認識を形成する。次に,便利な自動車が環境に少なからず影響を与えていることから,自分たちの便利な生活が環境に負担になっていることを知り,自分たちなりに環境にやさしいことをしようという認識を持つ。そしてその気持ちを表現活動により作品に仕上げ,世界に向けて発信しようというのである。
(2) 指導目標
・環境問題についてインターネットや文献など多様なメディアを使って調べることができる。
・環境問題を自分自身の問題としてとらえ,解決しようとする。
・環境問題の解決のため,多様な表現活動ができる。
(3) 利用場面
この単元では以下のような場面でコンピューターを活用する。
①環境のために市民レベルで取り組めることを調べる場面
②自分たちの作品をホームページに載せ発信する場面
(4) 利用環境
①使用機種 PC-9821 Xv20 1台 PC-9821Cx13 6台 PC-9821Cu16 16台
②周辺機器 プリンター Canon BJC-455J 6台
③稼働環境
上記のコンピューター及びプリンターがLANによってつながれている。インターネットとは常時つながっている。
④その他の使用ソフト
キッドピクス(INTERPROG) ハイパーキューブ(スズキ教育ソフト)
2 指導計画(全11時間)
| 指導計画 |
目標 |
①②公害の問題
|
公害とはどのようなものかを調べるとともに,四日市ぜんそくについて調べ,自分の考えを持つことができる。 |
③水俣の公害
|
水俣病など日本の公害について調べ,工業による環境破壊が公害の原因となったことに気づき,これらの原因を解決していくことが大切であることに気づく。 |
④⑤よみがえった空と海
|
北九州の例をもとに環境保全への努力が公害を解決するために大切であることに気づく。 |
⑥ふえる自動車と環境
|
自動車の増加を例として文明生活がいかに環境に影響を及ぼしているかについて考えることができる。 |
⑦便利な生活と生活への負担
|
自動車以外にも 文明生活が環境に影響を与えている問題について調べ,考えることができる。 |
⑧⑨わたしたちにできるエコロジー
★インターネット利用
|
環境のために,人々が市民レベルでどんな取り組みをしているかを調べ,自分たちにも環境のためにできることがあることを知る。
|
⑩⑪世界に向けてよびかけよう
☆コンピューター利用
★インターネット利用
|
環境のためにどう行動すればよいか,考えることができる。
自分たちの意見・提案を世に問うために効果的な表現活動ができる。
|
|
3 利用場面
⑦便利な生活と生活への負担
|
予想される学習活動 |
指導内容および指導上の留意点 |
備考 |
導
入 |
わたしたちの生活で昔に比べて便利だなと思うことは何ですか
|
・エアコン・電車
・水洗トイレ
・ビデオ・電話
・パソコン・飛行機 |
・自分たちの生活を振り返らせる |
|
展
開 |
これらの中で環境に大きな負担となっているものはどれでしょう |
・エアコン・飛行機
|
・電気製品については消費電力とそれだけ発電するのに必要な石油の量を知らせる。
・乗り物については消費燃料の量を知らせる |
図書館資料
★
インターネット
|
ま
と
め
|
・便利な生活は環境に負担をかけていることを知る。
|
・自分たちが環境に負担をかけていることを認識させる。
・次時予告 |
|
⑧⑨わたしたちにできるエコロジー
|
予想される学習活動 |
指導内容および指導上の留意点 |
備考 |
| 導入 |
環境を守るために,自分たちにできることはないでしょうか
|
・エアコンを控える
・なるべく公共交通機関を利用 |
・自分たちの生活を振り返らせる。
|
|
| 展開 |
環境を守るために,人々はどんな活動をしているのでしょう |
・リサイクル
・ 節約
・他にないか自分たちで調べる。
・調べたことを発表する |
・図書室の環境問題コーナー,インターネットのサイト等,必要に応じて知らせる。
・自分たちにもできそうだという見通しを持たせる。 |
図書館資料
★
インターネット |
| まとめ |
・調べた感想を書く |
夢物語ではなく,実現可能なことに絞って自分の提案も書かせる。 |
|
⑩⑪世界に向けてよびかけ
|
予想される学習活動 |
指導内容および指導上の留意点 |
備考 |
| 展 開 |
環境を守るために自分たちの意見や提案を世界に発信しよう |
・ポスターを作る
・新聞づくり
・紙芝居を作る
・作文を書く
・思い思いの方法で表現する |
・あらかじめインターネット上の本校のホームページに載せることを知らせる。
・作文は原稿用紙に書いてから子どもがキーボードで入力する。その他はスキャナーで取り込む。 |
☆コンピュータ
スキャナー |
4 実践を終えて
子どもたちは,環境問題に大いに興味を示し,調べ学習にも表現活動にも積極的に取り組んだ。インターネットで調べたがる子が多かったが,分からない言葉などは図書館で調べていた。最近はどこの学校でもそうだろうが,本校の図書室でも環境問題コーナーが設置されている。子供向けの環境問題の本がすぐみつかったようである。
表現活動では作文を書く子が4人,ポスターをかく子が35人であった。ポスターについては手がきの子がの作品例が図1,キッドピクスで表現した例が図2である。
| 図1 手がきのポスターの例 |
|
図2 キッドピクスによるポスターの例 |
子どもたちにはワークシートにおいて節目ごとに感想を書かせた。インターネットを使って調べ学習をした程度では大きな変容は見られなかったものの,発信をした後,そしてそれに対するメールが届いた後では子どもたちの感想は単に事実認識や感想を述べたものから,解決しなくては行けない問題である,そして自分で実行しようと言う認識に移行し,さらには社会に働きかけていこうという認識へと移行していった。子どもたちの認識が大きく変容したことが検証された。
A児の変容を紹介する。第7時の後,「人間は楽しく生活しているが,そのかわりに地球の環境をこわしていることがわかった。」と単に事実認識に終わっているが,第9時の後,「私たちにできる活動が,こんなにたくさんあるなんて,びっくりした。これからはもっともっとできることをやりたい。自分でできることは自分でやりたいと思う。」と自ら解決しようとする姿勢が見られる。さらにその姿勢は第11時の後にも見られ,「私たちはふだん何気なく生活をしているけれど環境のことを考えてみると私たちの生活をもう一度振り返ってみて,私たちにできる環境にやさしいことはできないか,考えていきたいと思います。そして電気のむだづかいなどをやめて,生活していきたいと思います。」と,より積極的になっている。そしてメールをもらった後には,「6年2組のホームページを作って,読んでくれた人が少しでも地球に対して何か考えてくれるようになってくれたらいいなと思う。」と,明確にホームページを読んでくれる不特定多数の人を対して意識していることがわかる。自分の発信が一部の人であっても社会を変えられるという認識が見られる。さらにこの児童は「このメールを読んで,教生の○○先生が努力していらっしゃることがわかったので,ホームページを作ってよかったと思う。」と続けている。メールはなかなか来なかったが,発信しただけでも子どもたちの認識の変容が見られたことから,発信する行為そのものに大きな意義があるものと思われる。
また,今後の課題として次のことが明らかになった。
・どのような内容の発信に対して,レスポンスが期待できるかを研究し,授業に組み込む。
・いつまでも事実認識型に留まっている子どもに対しては,適切な支援が必要である。
ワンポイントアドバイス
子どもたちが自分たちの思いを表現し、ホームページに載せて情報を発信してもなかなかレスポンスが得られない。この原因は①情報の質による②検索エンジンに登録していない③普段交流をしている学校がない,等の原因が考られる。
①については逆に自分たちだったらどんな情報がほしていか,を考えてみるいいと思う。また,②についてはポピュラーなyahoo japanが最近なかなか登録を受付けてくれない,という問題もある。その他の検索エンジンを活用するしかないようだ。③については是非が問われる。交流していれば懇切丁寧なメールが届けられるかしれないが,それはあくまでも知人からのメールであって,不特定多数の人にはならない。しかしそれでもメールは届いた方が、子どもの意欲が増すことはまちがいないであろ |
参考文献
・田中博之・木原俊行・山内祐平(1993)
「新しい情報教育を創造する」ミネルヴァ書房
・田中博之(1995)子どものためのマルチメディア学習「マルチメディアリテラシー」 田中博之編 教育協会
・水越俊行 佐伯胖(1996)「変わるメディアと教育のありかた」 ミネルヴァ書房
・石原一彦 坂本旬 丹羽敦 橋本晃(1997)「インターネット教育で授業が変わる」 労働順法社
・多田元樹(1995)メディアミックスの到来で社会はどう変わるか
「教育科学社会科教育no.403」明治図書
・小川慎一 菅原伸介 小原要(1997)インターネット活用授業に見る実践のポリシー 「教育科学社会科教育no.438」明治図書
利用したURLなど
・YAHOO!JAPAN (http://www.yahoo.co.jp/)
・京都女子大学附属小学校 (http://www.biwa.ne.jp/~kyojo-es/)