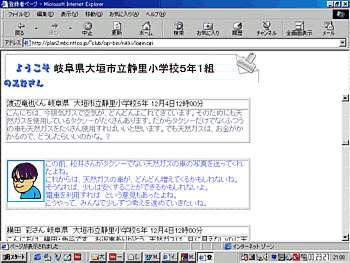 |
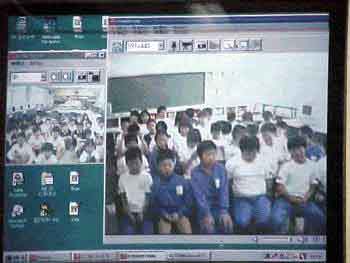 |
|
図1 クラブ日記への書き込み画面
|
図2 フェニックスで意見交流
|
3 利用場面
(1) 目標
テーマ別グループごとに「大気汚染」について調べたことを,「ハイパーキューブ」 でまとめ,ホームページの形にする。見る相手のことを考えながら,よりよい作品づくりに取り組むことができる。
(2) 展開
| 指導計画(7/9) | 留意点 |
| (1)「たった一つの地球」を視聴し,思ったことを話し合う。 ★インターネットの利用 |
・ビデオに収録しておき,もう一度見たい児童が何度でも見られるようにしておく。
・メモをとりながら見ることも認め,自分の意見の書き込みに生かす。 ・自分の思ったことと,友達の思ったことを聞き比べながら話し合いに参加する。 ・疑問点については,本やインターネットなどを利用し調べておくように助言する。 ★「こねっとgoo」の利用の仕方について,指導する。 |
| (2)「クラブ日記」に意見の書き込みをする。(図1) ★インターネットの利用 |
・画像データを必要とする児童にはデジタルカメラ,スキャナなどを準備する。
★他の児童の書き込みやスタッフからの意見も読みながら書き込めるよう助言する。 ・調べたことについても書き込めるよう,時間を十分確保する。 ・全員が書き込みを終えたら,プリントアウトして,教室に掲示しておく。 |
| (3)(4)放送番組「大気汚染」に合ったテーマにもとづいて,グループごとに調べ学習を行う。 ★インターネットの利用 (5)調べたことを学級で中間発表し,仲間のアドバイスを受ける。 |
・調べ活動に入る前に,テーマ別グループごとに小テーマと調べ方まとめ方について相談する時間をとる。
★調べ方は,本・インターネット・取材(聞き取り)などを紹介し,適宜援助する。 ・調べたことをメモする紙と,コピーしたり,プリントアウトした資料を閉じておくファイルをグループごとに準備しておく。 |
| (6)(7)(8)「ハイパーキューブ」で調べたことをまとめ,HTMLに変換する。 |
・「キューブワード」では,「編集」→「コピー」→「張り付け」すれば画像データを入れることができることを助言する。
・イラストや図は「えほんらいたー」を利用して画像データを作成する。 ・Mavicaの画像データは「インターネットエクスプローラ」で表示して張り付けることを教える。 ・まとめが完成したら「ホームページ機能」の使い方を教え,「ホームページ書き出し」をしてファイル保存する。 |
| (9)テレビ会議システム(フェニックス) を利用して意見交流する。(図2) |
・ディベート形式で行えるように,テーマ話し合いの手順などを,相手校と事前に打ち合わせておく。
・児童は自分の考えを持って,話し合いに臨めるようにする。 |
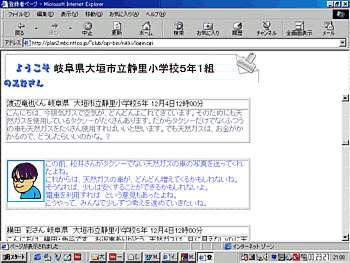 |
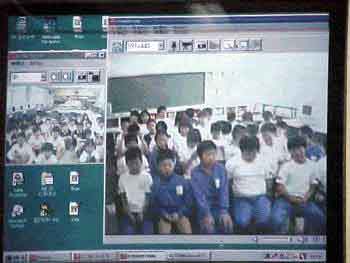 |
|
図1 クラブ日記への書き込み画面
|
図2 フェニックスで意見交流
|
3 利用場面
(1) 目標
テーマ別グループごとに「大気汚染」について調べたことを,「ハイパーキューブ」 でまとめ,ホームページの形にする。見る相手のことを考えながら,よりよい作品づくりに取り組むことができる。
(2) 展開
| 学 習 活 動 | 活動への働きかけ | 備考 |
| 1 本時の学習の進め方を知る。 |
・グループごとに活動の見通しを持たせる。 |
・コンピュータ ・デジタルカメラ ・大型ディスプレイ |
| 調べたことをホームページにまとめ,広く知らせよう |
||
| 2 テーマ別グループのまとめを「ハイパーキューブ」で作成する。 ●大気汚染とは? ●恐ろしい大気汚染 ●自動車の排気ガス ●環境にやさしい車は? ●大垣市では環境を守るためにどんなことをしているか? ●大垣市の空気の様子 ●これから私たちはどうすればいいのか? 3 作成したまとめをホームページの形式に書き出して,保存する。 4 まとめのホームページを見て感想を話し合う。 |
・能率を上げるため,文章入力,画像データ製作などを分担して行うようにする。 ・タイトルの字の大きさや色を見やすく工夫させる。 ・「コピー」→「張り付け」を利用して,グループの作品を一つにまとめる。 ・「ホームページ機能」や「ホームページ書きだし」の使い方を助言する。 ・修正,加除する点について明らかにする。 |
|
 |
 |
|
|
図3 大気汚染調査グループのホームページ
|
図4 グループのまとめを作成
|
今回の実践を通して,インターネットに関連したコンピュータリテラシー(情報検索,情報収集,ホームページ作成など)は,飛躍的に向上した。また,調べ学習やNox調査を通して「大気汚染」さらに「環境問題」への関心は高まった。この取り組みではさまざまなメディアを利用して行われる。メディアがあるから利用するのではなく,これらのメディアを必要に応じて「道具」として利用していくことが大切であろう。放送とインターネット,それに他のメディアや体験をうまく融合したマルチメディア学習の可能性は,今後広がっていくに違いない。
ワンポイントアドバイス
|
こねっと・ワールド(http://www.wnn.or.jp/wnn-s/)には,インターネットを使って学習を進めるための情報が満載である。国内外の学校間交流を呼びかけるコーナーでは,交流希望の学校を検索することもできる。また,プロジェクトに参加することで,共同学習に参加することができる。インターネットを活用して離れた地域の学校と学習を進めたいと考えている学校は,まずここを訪れてみるとよいだろう。本実践は,このプロジェクトの一つに参加したものである。 |