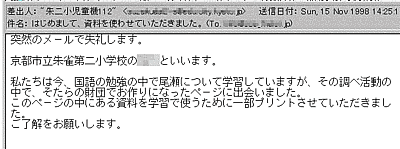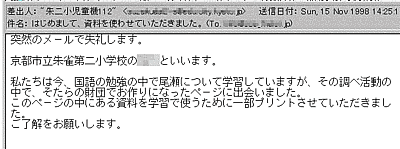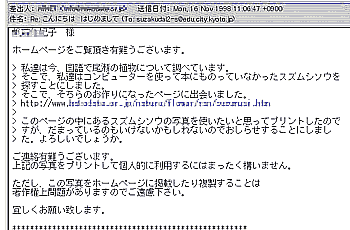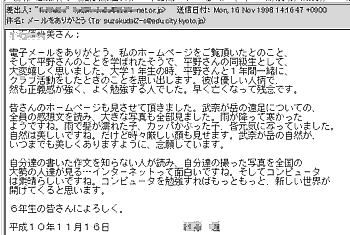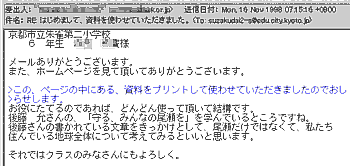学習資料を調べつつ学ぶネチケット
webページ作者との連絡を通じてネットワークの意味について考える
小学校第6学年・国語
京都市立朱雀第二小学校 中嶋 弘行
インターネット利用の意図
2つの意図を持って取り組んだ。
(1) 教科学習のための参考資料をwebページを通じて探るのが可能なことを知ること。
(2) webの資料は作者のものであるという知的所有権の意識とそれを利用する側の礼儀。
つまりネットワーク上のエチケットを実践的に体得していく。
1 「守る・みんなの尾瀬を」
(1) ねらい
6年生2学期の国語科読書・読書教材に「守る,みんなの尾瀬を」という読み物がある。後藤允さんの作品で,平野長靖の生き方を描いている。
後藤さんは尾瀬に一生を捧げた平野長靖の同級生で,98年11月27にフェニックスを通じて直接児童と対話授業をしていただいた。そのときの話によると「快適とは何なのか,生き方の問題としてよく考えてほしい。」ということだった。山に登りたい,登りやすくするために道をいっぱい造る。それは,ほんとうに快適なのか。
平野長靖の生き方を知らせ,それを通じて読む者にも自分の生き方を見つめ直させる教材である。
尾瀬の美しさにふれ,そのことをインターネット上で資料として公開しているサイトもいくつかある。それらを訪ねながら,尾瀬への思いを深めたり「もっと知りたい」という意欲を深め,そのための方法について探ることのできる子に育てたい。
(2) 指導目標
LANにつながったコンピュータを利用して,インターネット上の尾瀬や自然保護に関わるサイトを閲覧する。
児童が自分の興味を持っている課題に出会ったとき,プリントして発表や報告に使ったりたりすることがあるが,その際にそのページの作者に問い合わせたり依頼したりすれば利用の可否についてわかることを知る。
(3) 利用場面
次のような場面でコンピュータを利用する。
①CD-ROMの資料を調べる
図書館の写真集などとともに「尾瀬追憶」のCD(新井幸人)を使い,尾瀬の風景について知る。
②遠足の記録をhtmlで書き,印象を整理するとともにwebページを通じて知人に送る。
Win3.1のコンピュータが多いため,エディタを使ってhtmlを書く。
③教材文を通読し,初発の感想をエディタで書く。(一覧表にするため)担任の側で回収後,ワープロの上で整理してプリントする。
④尾瀬のビデオを視聴し,教材文を通読した後で生まれた各自の課題を元に,webサイトに公開されている尾瀬や自然保護関係の資料を閲覧し,課題にあったものを探し出す。
⑤教室での発表や報告など自分のまとめに使いたいページに出会ったときに,引用やプリントの可否について作者に問い合わせたり依頼したりする。
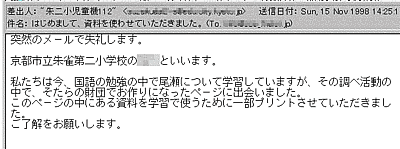 |
 |
| 図1 児童の出したメール |
図2 ページ作者へメールを書く |
(4)利用環境
①使用機種
NEC PC-9821CT16 4台
NEC PC-9821XC16 1台
NEC PC-9821AS2 1台
PB-NEC PB2133L 1台
Sotec Winbook bird 2台
自作 P5-200クラス 2台 (すべてWindows95)
遠足の記録用デジタルカメラ Fuji DS-30 25台
②周辺機器
MN128SOHO(ダイアルアップルータ) 10base-T室内ネットワーク
③稼働環境
校内のproxyを経て京都市情報教育センターを通じてインターネットにダイアルアップ接続し、児童用コンピュータから直接webページにアクセスできるようにする。
尾瀬関係の資料については担任とコンピュータ室担当とであらかじめリンク集を作っておくが,こねっとgooなどの検索エンジンも指導のもとに利用できるようにするため,学習時間にはインターネットに接続しておく。また,個々のクライアント側から電子メールが出せるように室内に中継用のメールサーバをおく。
④利用ソフト
web閲覧/e-mail Netscape 3.04 , Proxyserver WinProxy2.0
MailServer PMS(Personal Mail Server)
エディタ 秀丸エディタ(Win3.1/95とも)
写真整理 Paintshop 4.14 , 作文整理 一太郎8
2 指導計画 ★インターネットの利用
| 指 導 計 画 |
留 意 点 |
|
①人に尽くした人の伝記を読もう |
・生き方・ものの考え方に触れながら読み,メモを残すように心がける。 |
|
②遠足の記録をまとめよう |
・自然への感動をメモに残す。 |
|
③HTMLを使ってメッセージカードを作り,届けよう (★秀丸エディタ) |
★HTMLの書き方を知ろう(テンプレートを利用)
・伝えたい相手をはっきりさせて書くようにする。 |
④ビデオを視聴し感想メモを書こう
(NHKビデオ・「知られざる尾瀬」) |
・尾瀬の美しさや雄大さにふれるよう,大型スクリーンを使う。 |
⑤「守る,みんなの尾瀬を」を全文通読し,初発の感想をエディタで書く。
(秀丸エディタ) |
・後藤さんのメッセージを先に聞き,筆者と主人公の関係や人柄を知らせてから通読する。
・感想の交換と整理のためにエディタで感想文を書く。 |
|
⑥資料調べをしながら,ネチケットも知ろう(★インターネット) |
★webページの探り方とともに,ネットワーク利用のための姿勢についても知る |
|
⑦作者との対話(フェニックス利用) |
・作者の思いや考えを直接聞く機会を持ち,「生き方」について考えるようにする。 |
3 利用場面
(1) インターネット上のwebページにある尾瀬や自然保護に関係する資料を調べ,自分の課題にあったものがあるかどうかを検討する。学習時間に使いたいものがでてきたときにはそのページの管理者に連絡し,許可を取った上で利用するようにするのがエチケットであることを知る。
| 学 習 活 動 |
活動への働きかけ |
備 考 |
| 1 ネットワーク上で調べた資料には自分の課題にあったものがみつかっただろうか。 |
・前時までの検索の活動の中で得た情報を想起し,本時の学習意欲を高める。 |
|
|
2 本時の学習課題を知る。 |
|
・閲覧・メール用コンピュータ
・校内サーバに用意したリンク
(尾瀬関係)
・検索エンジンも利用する
・メールの例を示しておく
・電子メールは初めての児童が多いので,送信する前に助言を与える。
(文体・署名など) |
|
見つけた資料を使うときにはどんな注意が必要だろうか。
|
3 児童用のコンピュータからページの管理者に電子メールが書けることを知る。
4 目的にあったページをみつけて記録したり,電子メールを使って管理者に依頼を送る。
5 各自の資料検索のようすについて簡単に報告し,整理の進み具合について確認する。
|
・webのホームページには多くの場合連絡先が記してあることを知らせる。
・児童用機のメーラから送信できることを知らせる。 |
6 本時のまとめをする。
|
・使いたい資料の作者に連絡が送れたか確かめる。
|
|
尾瀬関係のリンク集(朱二小)
http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/suzakudai2-s/yr98/links/ozelinks.html
4 実践を終えて
インターネットに接続できる環境が爆発的に増え,家庭に浸透していっている一方で,ネットワーク利用をめぐるトラブルが絶えない。
古くから言われているように,ネットワークはひとつの社会であって画面のむこうにはかならず人がいるものであり,webの上で公開されている資料といえども作者がいるのであって,その資料は際限なく引用/転載などしてよいというものではない。そのことに思いをいたさないときにトラブルが発生する。
また,自分の課題や興味にあった資料を見つけることができたならば,その作者に連絡することで,さらに豊かな資料や人に出会うことのできる可能性ができる。
このトラブル未然防止とより豊かな出会いという2つの目標から考えて,電子メールを使って連絡をとるのは大事なことだろう。
実際,連絡したページの作者からはすべて暖かいお返事をいただくことができ,児童も担任もとても喜んだ。そして,作者によって利用許可の範囲が違うことも知り,その範囲の中で(授業に使えなくなることはなかった)不安なく資料をプリントしたり提示したりして有効に利用させていただくことができた。
こうした活動を通じて,ディスプレイの中に表示される資料は生きた人間が作ったものであり,交流をもちながらより深く生き方を考えるために利用できる道具としてコンピュータを位置づけることができるのではないだろうか。
児童へのメールの返事は,早いものの場合は翌日に届いた。そして,幸いなことに,送信した児童すべてがそれぞれに自分宛の返事を手にすることができた。それぞれのページの作者の誠意を見る気がする。
「もう届いたのか」「ほんとうに読んでもらえた」「いくら探してもなかった,絶滅危急種の珍しい花の写真が使わせてもらえる,これでみんなに知らせることができる」というような喜びに満ちていて,指導者としてもとてもうれしく思った。
また,webページの中には,この学習に出てきた平野長靖の大学時代の友人であるという人のものもあって,その方からも許可依頼への励ましのメールをいただくことができたりして,ほんとうにたくさんの出会いを経験できた。
人どうしのつながりを大切にしながら,今後もネットワーク利用を進めていきたいと思える実践であった。
ワンポイント・アドバイス
webサーバに掲載するための「メッセージカード」作りでは初めて本格的にHTMLを書く作業をしたが,タグについても初めてなのであらかじめテンプレートの形でファイルを用意し,その中に文章そのものや改行タグを入れていくというふうにしてみた。こうしてみると初めてでもブラウザの上に写真入りで自分の書いたものが表示できる。
多くの学校ではインターネットへの接続について速度面の問題があることだろう。本校の場合もやはり64/128Kのダイアルアップ接続なので,ダイアルアップルータをNATとしてだけ使うとデータの流量が増えてとても使いものにならない。あらかじめデータをどこかのキャッシュに入れておいて擬似的に接続する方法もあるが,準備にすごく手間取る。そこで,キャッシュを持つproxyを入れて,できるかぎりLAN内でデータが使い回せるようにした。
このようにするで,小学校のようにある程度児童の興味対象が重なってくるような学習環境の中では,ほとんどストレスを感じることもなくインターネット接続が実現できる。
また,児童用のクライアントからは直接外部のメールサーバにアクセスしないようにし,いったんローカルのメールサーバに送っておくという方法をとっている。これはreply-toを学校のアドレスにしていたりするのであまりいい方法ではないかもしれないが,無用なメール発送を避け,小学生のレベルでの電子メール利用の学習という点からは,使える方法であると考えている。
|