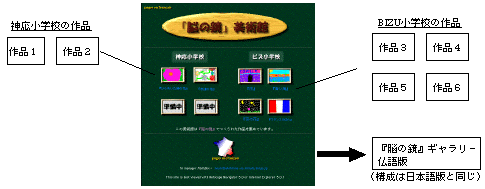
図1トップページ
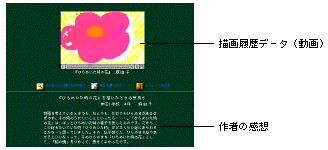
図2 作品紹介のページ
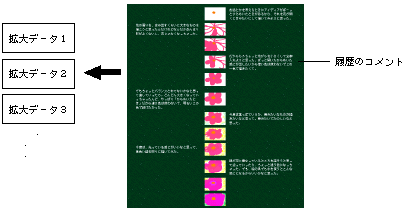
図3 作品の描画履歴紹介のページ
小学校第3学年 図工・国語・学活
港区立神応小学校 杉原 紀子
インターネット利用の目的
神応小学校では,学校間交流としてフランスのビズ小学校と描画用ソフトウェア『脳の鏡』を利用して描いた絵の交換を中心に交流を進めてきた。
そこで,両校の児童の作品に対する関心・理解を深めるため,インターネットを利用し,神応小学校のホームページ上にビズ小学校と共同のヴァーチャルギャラリーを構築し互いの作品をインターネット上で鑑賞し合い,児童の創作意欲を高める。
1 単元名・題材
フランスの友だちに「心の花」を作りながら,考えたことを紹介しよう。
(1)制作の過程を見たり,描き直したりできるソフトウェアを活用して,自分の絵の履歴 を見直しながら,納得感が得られるまで絵を制作できる。
(2)自分の絵の制作過程に込められた心情や工夫などを表現できる。
(3)発表された絵に対して自分と共通した心情や工夫などの意見を共有してすることを 味わう。
(4)フランスの子どもの作品に対しても共感的な心情を持つことができることを味わう。
次のような学習場面でコンピュータを活用する。
(1)コンピュータ・グラフィック画の創作場面
再構成型ソフトウェア「脳の鏡」を利用して,絵を制作する。このソフトウェアを利用することで子どもたちは,絵の制作場面を再現することができ,また,納得が得られるまで,描き直すことができる。
(2)インターネットで作品を鑑賞し合う場面
両校の学習過程で制作された絵を発表し合う場として,神応小学校のホームページに絵を公開するインターネットギャラリーを構築し,お互いの作品を鑑賞し合う。
(1)使用機種 Power Macintosh---4台
(2)稼働環境(推奨) OS---漢字トーク7.5.1以上 CPU---PowerPC 100MHZ以上
メモリ---16MB以上 ディスプレイ---32000色以上
(3)利用ソフト
再構成型描画ソフトウェア「脳の鏡」 「脳の鏡」は, 「再構成型学習」の道具という新しい主張を持ったソフトウェアである。また, 追記性や記録の蓄積性など, コンピュータの持つ特性を教育的に意味づけたソフトウェアでもあり, コンピュータを教育現場で活用する教育的な必然性を持ち得たソフトウェアである。
「脳の鏡」は大きな教育的な特徴として2つの機能がある。
(1)色作り機能
「脳の鏡」は, 水彩画風に描くということを基本においた描画ソフトであるため, 色の透明度というものを機能の大きな柱の一つにしてある。「脳の鏡」では, より直感的に透明度のある色までも再現することができる。この透明度の他に色を混ぜて,自分の納得した色を作ることができる。そして,作った色を登録し自分の名前を付けられる機能もある。つまり自分で名前を付けることによって, より自分が作り上げた自分だけの色であるということを認識させることができる。
(2)履歴再現機能
「脳の鏡」には画面に描き始めてからの履歴をこのソフトウェア上で記憶し再生する機能を持たせている。この機能はいわばビデオのようなもので, 途中で止めてその続きを描き直すことができるのである。つまりこの機能を使うことによって, 何度も巻き戻しをして, 続きを納得のいくまで描き直すことができるようになっている。
ア インターネットギャラリーの構成
1つの作品を多層的に表現するため,インターネットギャラリーでは,完成作品と,その作品の表が履歴の両方を表現することにしたため,ギャラリーの構成は次のAからDのようにした。
A トップページ(図1)
神応小の作品を左側,ビズ小学校の作品を右側に静止画で表現する。フランス語ヴァージョンは,画面下のフランスの地図をクリックする。
B 作品紹介のページ(図2)
トップページから作品を選択すると,動画の描画履歴データ(QT画像)による紹介と,作者の作品への気持ちをテキストで表現する。画面中央には以下の3つのアイコンメニューがあり,選択できる。
(a)どんなふうに描いたのかな 作品の描画履歴紹介のページへのリンク
(b)何かを思ったら 子どもたちが作品の作者に感想を送る 電子メールを送信するためのページ
(c)メニューにもどる トップページへのリンク
C 作品の描画履歴紹介のページ(図3)
描画履歴を静止画で時系列でならべ,作者が作品を制作するうえでの気持ちの流れ をテキストで横に添える。履歴静止画をクリックすると,新ページにその拡大された静止画が現れる。
「履歴機能」を使ったときの子どもたちの様子を紹介する。この任意の場所からやり直せるという機能があることによって, 教室の雰囲気は一変した。つまり, 子どもたちは自分が納得いく作品をつくるということに集中することができたのである。これはいままで子どもたちが作品づくりをするときに, いかに失敗を恐れていたかということの現れでもある。任意の場所から子どもが作品をやり直すことができるということは, 子どもたちにとって, 自分の作品づくりを, その制作過程で何回も見直すことができるということを意味している。これはいままでのように, とにかく白い画用紙を色で埋めていくことに汲々としていた子どもたちを, 解放していったばかりではなく, 絵をつくるということの考え方そのものを大きく変化させていったのであった。
たとえば「あれ!?違うな」と子どもがつぶやき, そして「もうちょっと戻ってやってみよう」と言い, この任意の場所から戻れる機能を活用していく。そして子どもたちがつくり直し始めたときの顔は, これまでになかった, つくるということ描くということ, そのことだけに自分の心を注ぎ込むことができた顔である。実践を共にしていて, 子どもたちにとって, この任意の場所からやり直す機能というのは, これまであった「白紙に戻す」という機能とは全く質的に違う機能なのであるということを改めて知らされたのである。この機能が, これから子どもたちが絵を描くということに対して与えた影響は, きわめて大きいと言える。
また, 子どもたちは, クイックタイム・ムービを再生することで, 自分の作品の制作過程を行きつ戻りつ見ることができ, そのことで次のような会話が生まれてきている。「私が, この作品をつくっていくときに, こんなことをやっていたなんて, あんまりよく覚えていないけど, でも, 何回もこうやって繰り返し見ていくと, ああ, 何となく, このときこんなことをやってたなあ, 考えてたなあということを思い出すことかできるよね」「うん, そうだね。こうやって, 自分がつくってきたことをもう一回見れるって, 何かいろいろ, そのときにあったことや, そのときどんなことを考えていたかって, 人に言いたくなるよね。それに, 何か自分の気持ちがよくその描き方に出てるような気がする。」
このように何度もやり直しができたり, 自分の作品を振り返ることのできる機能に子どもたちは夢中になっていったのである。
D 電子メールで感想をおくるページ
ギャラリーを訪問し,作品を鑑賞した子どもたちは,その作者へ電子メールを使って手紙や感想を送ることができる。翻訳の都合上,メールのアドレスは神応に設置されたサーバーに全て集められ,日本語,フランス語の翻訳を行う。翻訳されたテキストはB作品のページの「作者の感想」の下に逐次,掲示板のようにホームページ上に公開し,紹介していくことにした。
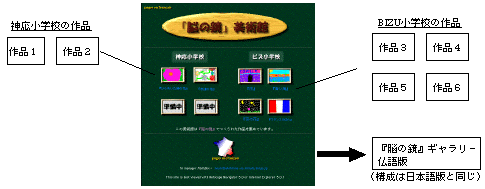
図1トップページ
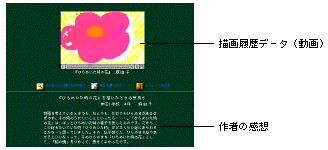
図2 作品紹介のページ
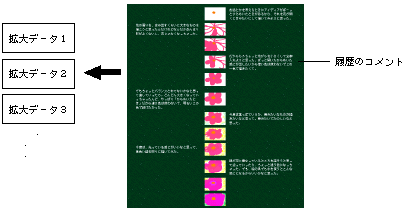
図3 作品の描画履歴紹介のページ
イ インターネットギャラリーの利用環境
Netscape Navigator 3.0以降,Internet Explorer 3.0.1 以降が必要である。また,作品の動画(クイックタイム形式)を鑑賞するため,Quicktime Pluginが必須である。
2 指導計画
|
指導計画(4/4)
|
留意点
|
| (1)「脳の鏡」で自分の心情を表した「心の花」を描く。 | ・児童に最近のできごとで心に残っていることを話し合わせる。そして,そのときに喜怒哀楽などの心情 について感想を述べ合わさせる。
・自分の心情にあった色を作らせる。 ・「心の花」は具象的なものだけではなく,抽象的なものもあるを知らせる。 |
| (2)納得感が得られるまで,描き直しをしてみる。 | ・履歴再現機能を利用して,自分の描きたかった心情はどんなことなのかを考えさせる。
・児童が作った色に名前を付けて,保存させておく。 ・児童にいくつかの派生的な作品を作らせてみる。 |
| (3)クラスで「心の花」ができるまでの過程を心情や工夫を中心に表現させる。 | ・児童に自分の心情を素直に表出できるように受け 手の聴き方を考えさせる。
・児童に共感的理解という視点を持たせる。 ・友達と自分の共通点や差違点を考えさせる。 |
| (4)フランスの子どもたちの「心の花」の過程を知り,その心情に共感できるところを見つける。 | ・児童に共感的理解が拡大できるという視点を持たせる。
・フランスの子どもと自分の共通点や差違点を考えさせる。 |
3 利用場面
(1) 目標
インターネットギャラリーで友達の絵の作り方の秘密を知ろう。
(2) 展開
|
|
|
備考
|
|
①フランスの子どもたちから「心の花」と一緒にきた電子メールを読む。(図1)
|
・これまでの交流の作品をもう一度思い起こさせる。
|
|
|
②インターネットギャラリーを開いて,送られてきた作品を見る。
|
・自分たちの作品も新しいものがあれば,フランスの子どもの作品を見る前に紹介し合わせる。
・自分と友達の共通点や差違点を考えさせる。 |
|
|
③作品の過程や説明などの和訳を読み合って,感想を述べ合う。
|
・和訳をして下さっているボランティアの方の苦労について話し合わせる。
・絵から受けた印象,絵の制作過程から受けた印象,和訳から文章から受けた印象など,それぞれに違った印象を持つことがあることを理解させる。 |
|
|
④それぞれ絵を手直しをする(図2)
|
・共通点や差違点を話し合い,作品と生活を結びつけさせる。
|
|
|
⑤本時のまとめ
|
・作品の表現の仕方や作品の見方でよかった点を話し合わせる。
|
 |
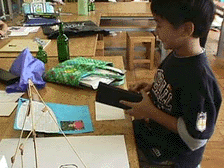 |
|
図1 ビズ小学校からの手紙を読む
|
図2 『脳の鏡』で絵を描き直す
|
実践を終えて
子ども同士の交流の場としてのインターネットギャラリーは,主張を持ったデータベースとして機能という展望がある。このインターネットギャラリーは,より多くの作品を持つことを目的とした既存のデータベースとは,一線が画してきた。つまり,「見渡せるだけのデータベースというコンセプトを基に,一つの作品を多面的に味わうことができるデータベースで,何回も見直すことで作品に対する味方や考え方が吟味されたり,自分では気づかなかった自分の制作のスタイルを知ることができた。
フランスの児童の作品を鑑賞した際に,同じ描画ソフトウェアを利用しているにもかかわらず,色の使い方,描き方などに日仏で大きな違いがあることに気づく児童も多かった。それぞれの文化に対する認識が高まったと言えるだろう。インターネット上で異国の児童の作品を作品に添えられた感想文と共に鑑賞することによって,絵に込められた作者の思いを共有し,電子メールを通じて手紙を出し合う場面も見えることができた。このように,インターネットギャラリーは,単なる作品の展示場ではなく,学習の再構成の場として,また,インターネットが,新しいコミュニケーションメディアの道具として活用できる可能性を多分に秘めていることが分かった
・インターネットギャラリーで再構成型の学習に取り組もう
「再構成型学習」とは, 今までの授業以上に子どもたちを個性的な存在として捉え, その良さを子どもたち自身に確認させていく, つまり自分らしさを気づかせること(自己発見・自己理解・自己実現)を目的としている。「再構成型学習」の中で子どもたちが自分らしさを見つけていくためには, 子ども自身の自己評価能力の必要性がこれまで以上に高まってくる。子どもの自己評価を実現するには, 子ども自身が学習の履歴をどのような形で省みていくかということが大切なのである。たとえば, 自分の創った作品を何回も作っては壊し, を繰り返していくことなどである。
利用したURL
神応小学校 ( http://www.shinno-es.minato.tokyo.jp)
ビズ小学校 ( http://www.ecolebizu.org)
三谷商事株式会社(http://www.mitene.or.jp/mitani/jkikaku/bizu/index.html)
指導
苅宿俊文(大東文化大学文学部教育学科)
協力
学習環境デザイン研究工房