『日本を知り、日本を伝えよう!』
|
日本の中で生活し、日本のこと知っているつもりになっていた子供たちが、諸外国へと情報発信するためには、まず、自分たちのことを知らなければいけないことに気づく。そして、6年生で歴史学習を行う上でも、もっと自分たちの住む日本の文化について、興味・関心をもったり、世界の中の日本を考えたりする活動へとつなげていくことをねらいとした。
|
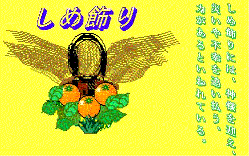 |
---インターネットを活用し、教室の枠を広げていくための試み---
小学校第5学年・特別活動・道徳(総合的な活動)
横浜市立神大寺小学校 安冨 直樹
『日本を知り、日本を伝えよう!』
|
日本の中で生活し、日本のこと知っているつもりになっていた子供たちが、諸外国へと情報発信するためには、まず、自分たちのことを知らなければいけないことに気づく。そして、6年生で歴史学習を行う上でも、もっと自分たちの住む日本の文化について、興味・関心をもったり、世界の中の日本を考えたりする活動へとつなげていくことをねらいとした。
|
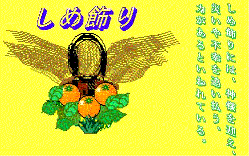 |
お正月に行われる活動が、どのような背景で生まれ、受け継がれてきたのかを調べることを通して、日本文化について、興味・関心をもつことができる。
| ・動画編集コンピュータ | SONY VAIO-S510 | 1台 |
| ・ネットミーティング用コンピュータ | GATEWAY solo9100 | 1台 |
| ・ホームページ作成用コンピュータ | IBM THINKPAD 370C | 7台 |
| ・デジタルカメラ(静止画・動画)作成 | SANYO DSC-X100 | 3台 |
| ・教室内でのインターネット接続用PHS | +32Kカード | 1台 |
| ・8mビデオカメラ | SHARP VL-HL50 | 3台 |
| ・ビデオプロジェクター | EPSON XV-E500 | 1台 |
| ・カラープリンター | CANON BJC600 | 2台 |
| ・CD-R作成 | I・O DATA CDRW-vx26 | 1台 |
| ・ネットミーティング用カメラ | ヴィヴィダーUSBカメラ | 1台 |
| CCDカメラ | 1台 |

④その他の利用ソフト
・CUBE for windows(文章作成・絵作成)
・メディアルーム(アニメーション作成ソフト)
・デジカメール (ホームページ作成)
・ネットスケープナビゲータ(ホームページ閲覧)
・AL-MAIL(電子メールソフト)
・ネットミーティング(簡易テレビ電話)
・訳せ!ゴマ(日英・英日双方向翻訳ソフト)
2 指導計画
| 指導計画(全6時間) | |
| ① | 日本の『お正月』について、どんなことを伝えればいいのか、本町小学校と話し合う。 |
| ②③ | 日本の『お正月』を伝えるために、特徴的な慣習を調べよう! |
| ④⑤ | 調べたことをもとに、ホームページにまとめよう! |
| ⑥ | 英語のホームページを作成するために、主語や述語をはっきりさせた文章に書き直そう! |
| 学習活動 | 活動への働きかけと支援 | ||
|
○きっかけ |
|||
|
1 日本の『お正月』を外国に伝えるためには、何を伝えればいいのか本町小学校と話し合う。 |
・ネットミーティングを使い、横浜市立本町小学校の友達にインタビューする。 |
||
2 「日本の正月」について、インターネットで調べる。 |
・『お正月』に行われる遊びや食べ物、飾りなど、自分の調べたいことを調べる。 |
||
|
3 調べたことをホームページにまとめる。
|
・ネットミーティングを使い、ニュージーランドの子供たちとも会話をしたかったが、回線速度が出ず、断念。子供たちは、映像や説明を郵便で送ろうということになる。 ※ニュージーランドと日本では、ビデオの形式が違うため、子供たちが撮ったものをそのまま送っても見ることができない。しかし、コンピュータならば、世界共通の規格がある。そこで、教師は、画像をコンピュータで処理し、aviファイルに直し、CD-Rに焼き付けて送付することを子供たちに伝えた。
・写真やお絵かきソフトを活用し、グループごとにまとめていく。また、家族も巻き込み、初詣やおせち料理を写真に収めてきたり、冬休みの自由研究としてノートにお正月調べをしてきたりした子供もいた。
|
||
|
4 英語のホームページに書き直す。 |
・英語には、必ず主語と述語があり、翻訳ソフトを使うときには、照応を正しくしなければいけないことを知る。 ※翻訳ソフトで英語にした文に、「主語なし」という日本語がたくさん書かれていて驚く。
凧について紹介文を書く。
|
||
4 実践を終えて
日本のことをニュージーランドに伝えようということから始まった活動であったが、子供たちは、自分たちが日本を知らないということに気がついた。このことが、活動のエネルギーとなっていった。
「なぜ、門松を飾るのか」「おせち料理にはどんな意味があるのか」などの疑問を調べ、問題を解決することによって、昔の人々の思いや願いを感じ取ったことも、大きな収穫であった。
また、今回の活動で、子供たちは、発信するからには、正しい情報を分かりやすく伝えていくこと、そして、その内容に責任をもつということを意識しながら、ホームページを作成していった。
|
「先生、私たちの『お正月』のページを見て、ニュージーランドの子供たちは日本に来てみたいと思うかな?」
|
 |
このつぶやきの中には、自国の文化に対する誇りの芽生えも感じられる。この子供たちが、「子供外交官」となって、教室の枠を越え、インターネットを通して、世界とのかかわりを深めていってほしい。
最後に、まだまだインターネットの回線速度は十分でない。今後、動画を送り合うことが増えると予想されるが、それに耐えうるだけのインフラの整備を社会が行っていく必要がある。
| ワンポイント・アドバイス |
| 教室から子供たちにインターネットを使わせる場合、PHSでネットワークにつなげることは、とても便利であり、子供たちもつながっていることを容易に意識できる。まだまだ通話料は高いが、春から64Kになれば、もっと快適に使えそうである。 英語翻訳ソフトは、精度も高くなり、瞬時に英語へと変換する。しかし、きちんとした英語に翻訳するためには、きちんとした日本語を使わなければいけないことを、子供たちと考えていくことは、有意義であった。 |