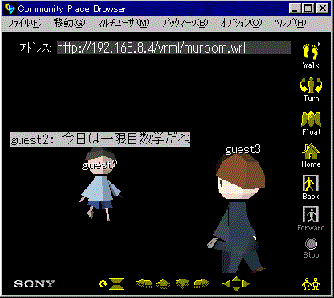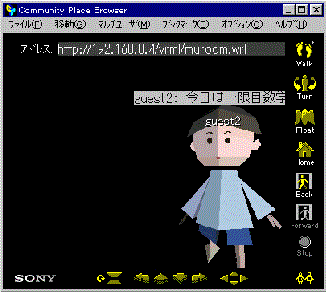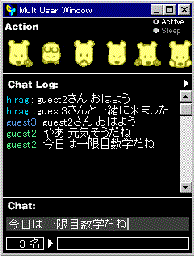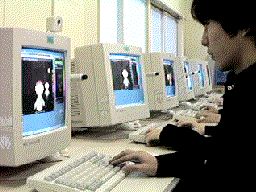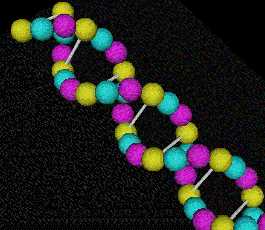46 Virtual Class Room の実践
インターネット利用の意図
日頃コンピュータに関連した工業技術を学んでいる点を生かしながら,4校の生徒がインターネット上で情報交換や共同作業を行う。その中で,同じ分野を学習している他校の様子を把握したり,学校内の限られた生徒間では解決できないような問題を相談しあう。これにより,生徒自身が良い意味での刺激をうけてコンピュータ技術への興味関心を増し,ひいては学習の整理につながることをねらいとしている。また,各県の枠をこえて共同企画を実施するにはどのような内容が望ましいのかを探ることも目的としている。
1 参加校および参加生徒数
バーチャルクラスルームはいろいろなタイプの生徒が集まることを前提としているため,各学校の担当教員を中心に学年および学科を問わず参加生徒の募集を行う。
石川県立小松工業高等学校 12名(1年:8名,2年:2名,3年:2名)
熊本県立小川工業高等学校 3名(1年:1名, 3年:2名)
大分県立津久見高等学校 4名( 3年:4名)
山梨県立甲府工業高等学校 8名(1年:6名 3年:2名)
2 実践の概要
WWW による情報発信のなかで,グラフィック的な表現やインタラクティブな環境などの実現をめざし,Java言語やVRML言語等のプログラミングおよびグラフィック関係の開発ツールについて学習する。具体的には,インターネット上のバーチャルクラスルーム内に以下の3コースを設け,参加生徒にコースを自由選択させる。
・Javaエントリーコース:Java Studioを用いたプログラミング入門
・Java実用コース :Java Work Shopを用いた実践プログラミング
・Java活用コース :VRMLによるJavaを活用した3次元世界の作成
更に,生徒はそのコース内で生徒自身の目標を定め,その目標の実現に向けて作業を進める。その際,行き詰まった点や疑問点をバーチャルクラスルームへ投げかけ,各コースの担当教員や参加生徒同士でその問題を共有し,お互い検討し合う。
参加生徒は制作物をバーチャルクラスルームのホームページへリンクし,活動状況や活動結果が参照できるようにし,参加者全員で制作物を評価し合い,その研究内容を全員で共有する。
以上の流れの中で各学校の担当教員は,環境の整備,進捗状況の調整および管理・指導,カリキュラムの検討を行う。
3 実践のための準備
(1) バーチャルクラスルームの構築
インターネット上のバーチャルクラスルームには,各学校の黒板や参加者全員のノートおよび全体の黒板が準備されている。参加者が抱いた質問事項や意見は,そのバーチャルクラスルーム内の各自のノートあるいは黒板に記述することにより,指導教員や他の参加者に伝えることができる。この環境を小松工業高等学校のネットワークサーバ上に構築し,その構築と運用を小松工業高等学校で行った。
(図3.1) |
 |
| |
図3.1 バーチャルクラスルームのホームページ
|
(2) メーリングリストの構築
担当教員同士のスケジュール調整や情報交換手段としてメーリングリストを活用した。また,生徒用の情報交換手段としてのメーリングリストも構築した。これらのメーリングリスの構築と管理を小川工業高等学校で行った。
(3) 各学校での環境構築と事前学習
選択したコースの内容により,それぞれの開発環境を学校毎に構築する必要がある。また,生徒たちはバーチャルクラスルームに参加するための基本的なマナーや操作について各学校の担当教員を中心に事前学習する必要がある。
①Javaエントリーコース
JavaStudio:(株)サンマイクロシステムが提供しているJavaの統合環境システムで,各種コンポーネントが準備されており,初めてJavaを学習する人に適している。
下記URLで無料提供されている。
http://www.sun.co.jp/market/academic/freejava/
②Java実用コース
Java WorkShop:Javaの統合環境システムで,Java Studioに比べソースコードを記述してより細かで柔軟なプログラミングが可能である。
下記URLで無料提供されている。
http://www.sun.co.jp/market/academic/freejava/
③Java活用コース
Community Place Conductor:VRML空間作成ソフトで,ブラウザと連動して動作する。これも無料で以下のURLから入手できる。
http://vs.sony.co.jp/index-j.htm
④メーリングリスト
初期の交流手段として電子メール及びメーリングリストは有用であり,且つ交流のマナーを学習するのに適している。そのため,これらの活用方法等について各学校で事前指導を行った。
4 各学校での実践および評価
(1) 石川県立小松工業高等学校(http://www.komastu-ths.komatsu.ishikawa.jp)
アプレットの制作とVRMLマルチユーザ空間の制作に分かれて活動を展開した。VRML空間とは,あるVRML空間を複数の端末で同時に共有し,その空間内で相手の存在や動作の確認,さらにチャットで会話できるものである。図4.1から図4.3は,2台の端末で今回制作したVRML空間を共有している様子である。
チャット画面は各ユーザのディスプレイ上に表示されるが,ここではユーザguest2についてのみ載せた。各ブラウザ画面では,自分の姿は表示されず,視界内の相手の姿が見えている。ユーザguest2が「今日は一限目数学だね」と入力すると,他ユーザのブラウザ画面にそのメッセージが表示される。図4.4 は生徒がマルチユーザ空間での動作を確認している様子である。
①実践環境
使用機種:NEC PC-9821xv13(Windows95,WindowsNT4.0)
稼働環境:校内LAN,FireWall,インターネット(64K専用線)
使用ソフト:ブラウザソフト(CP Browser),
VRML空間作成ソフト(CP Conductor)
マルチユーザサーバ(CP Bureau),
VRMLモデラートソフト(Breeze Designer2.0)
②実践結果
|
計画では他校の生徒が作成したVRML空間やアバタとリンクしバーチャル空間でのコミュニケーションを目標としていたが,残念ながらそこまで到らなかった。このマルチユーザ空間はVRMLで記述されたファイルとJavaプログラムが密接に連携して実現されている。VRMLで記述した物体の動きや連携をScriptノードを媒介にしてJavaプログラムで操作した。3次元空間での挙動を確認しながら純粋なオブジェクト指向言語Javaの基礎的な学習を生徒とともに行うことができた。
|
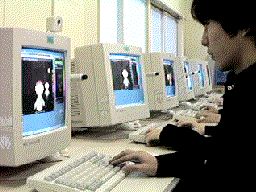 |
| |
図4.4
|
(2) 熊本県立小川工業高等学校
(http://www.ths.ogawa.kumamoto.jp)
Java に関しては初心者ということで,参加者全員Java Studioへ挑戦した。分かり易いソフトウェアであると思い生徒たちに実践を試みさせたが,マニュアルが少ないこともあり,またバーチャルクラスルームを利用した有効な課題解決方法を生徒が主体的に見い出しきれないまま時間不足となっている。
今回は,取り組み開始が遅く十分な成果が得られたとは言えないが,Javaを学習させるためには極めて有用なソフトウェアであり,今後は早めの取り組みを行い,時間をかけてやっていけば良いことがわかった。
|
 |
| |
図4.5 JavaStudioを操作中
|
①生徒の感想
・基本的な使い方が未だに解らない。
・イメージの動作ができずに様々なアイデアがボツになってきた。
・いろいろなサンプル等も参考に制作してきたが,サンプルはとてもシンプルなので複雑なものには応用できなかった。
・java studioは便利だけれども,簡単なプログラム作成しかできなかった。
・モグラたたきの案も結局”モグラの出現”及び”たたく”の動作ができぬまま終了と
なってしまった。
・同時にプログラムが一つしか開けない。
・メーリングリストを旨く活用できなかった。
(3) 大分県立津久見高等学校 (http://www.tsukumi-hs.tsukumi.oita.jp)
電子科3学年課題研究「インターネット班」の下記の研究テーマで取り上げた。
・Community Place Conductorによる3次元仮想空間の作成
・Macromedia Flash 2J による教育ソフトの作成
・ホームページの作成「音楽と画像のリンク集」
・Java Studioによるゲームの作成
・ホームページの作成「電子科のあゆみ」
・Java WorkShopによる動画の作成
・Digital Locaによる3D製作
・Digital Locaを使った3次元の表現
|
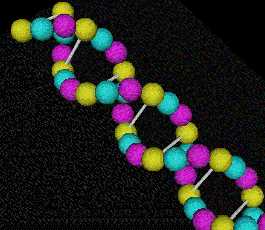 |
| |
図4.6 生徒の作品
|
①成功した点
同じような研究をしている仲間たちが地域の枠を超えて存在していることに気がつくことができた。学校の中だけでは解決できなかった点を,掲示板を利用して疑問点に答えてもらうことで課題研究を完成させることができた。
②反省点
・生徒からの質問項目があまりなかった。
・共同作業による課題研究を期待していたが実現できなかったことが残念であった。テレビ会議システム等を通してお互いの学校間交流をもう少し深めておく必要があった。
・バーチャル教室の黒板に,課題研究に必要なデータのあるWeb のページや,関連の企業のページをリンクしておくことで,より使いやすいシステムに生まれ変わることが期待できる。
③生徒の感想
バーチャルクラスルームは卒業研究をやっている時など,わからないことがあったりしたらその場ですぐに質問することができるのでとても便利だと思いました。でも,質問してもすぐに答えがかえってこないのでその辺りは良くしてもらいたいと思います。
(4) 山梨県立甲府工業高等学校 (http://www.kofu-ths.hun.ne.jp)
放課後の時間を使用して,生徒は自由参加の方法をとった。プログラミングはある程度経験しているが,JavaやVRMLは初めてという生徒が多かった。当初 Java Studioの環境を構築し開発を行ったが,現システムではパフォーマンスが悪く時間がかかるため,急遽VRMLを用いたプログラムの作成に切り替えた。
生徒達はソースコードを1行ずつ書いていくという手間のかかる作業にも,新しいことを他校の生徒と一緒に学習しているのだという動機付けと好きな学習のため,お互い相談しながら課題を遂行していった。作業を進めていくうちに本校の参加者全員で1つの作品を完成しようという雰囲気になった。3年生が中心になり,作品の立案から計画書の作成まで生徒たちで行った。期間は短かったが,
12月に実施された県下プログラミングコンテストにその作品を出展することができた。最初まとまりの良さを発揮したものの,なかなか計画どおりに進まない様子で,1つの物をみんなで分担して製作していくという共同作業の難しさを体験した。
|

|
| |
図4.7 共同作業で制作中
|
①反省点
活動前に趣旨を理解させたつもりであったが,期間が短かったためか生徒達は自分達の作品制作に夢中になってしまい,他校との交流を十分果たせなかった。また交流するためには,事前の準備をしっかりしておく必要があり,その時間も計算して交流計画を立てる必要がある。
②生徒の感想
・放課後の限られた時間で行うには無理があったのではないか。
・参考にするマニュアルが少なくプログラミングに時間を要した。
・自分のことが精一杯で,もう少し他校の生徒と交流をしたかった。
・普段交流が少ない他科の生徒や先輩達と共同作業ができて励みになった。
・計画通りに作業が進まず,未完成のままコンテストに出品したのが残念だった。
・今度は他校の生徒と共同作業で1つの作品を作ってみたい。
5 課題と今後の展望
実施した期間は短かったが,今回の実践で参加した学校ではバーチャルクラスルームを展開するための環境がほぼ整った。しかし,バーチャルクラスルームを効率よく実施するためには事前の準備が大切である。特に教員間の事前の打ち合わせを十分に行わないと,途中で各々の学校がそれぞれやりやすい方向へ走ってしまい収集がつかなくなってしまう恐れがあり,そのため十分な成果を得ることができない。今回,教員間の連絡はメーリングリストを活用したが,準備におよそ200通ものメールが交換された。しかしながら生徒間の交流があまりなされなかったため,今後事前の準備は電子メールだけではなく直接資料等持ち寄り,指導方法や交流方法も考慮した打ち合わせを行い,具体的な計画を立案する必要がでてきた。
本来バーチャルクラスルームは,時間・空間・資源を考慮せずに自由に学べしかも共同作業ができる環境である。その実現に向け実践を積み重ねながら少しずつ問題を解決していく必要がある。それが可能になれば学校間交流はもとより,生徒個人の主体的な学習にも十分貢献できると思われる。