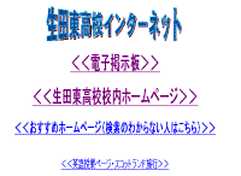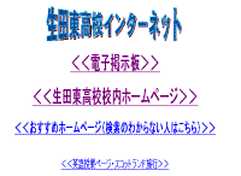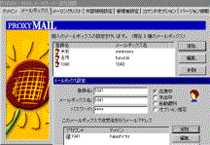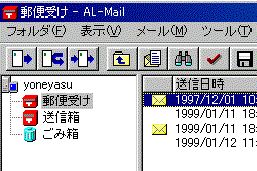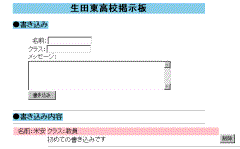48 校内メールからインターネットメール発信
インターネット利用の意図
手作りの校内インターネット網により校内電子メールを実践し,その発展型として校内のインターネットメール利用を計画した。その一環として,一つのインターネットメールアカウントで100人規模の校内メールアカウントを管理する方法の研究と実践もあわせて行った。
1 校内メールからインターネットメールを発信
(1) ねらい
インターネットでホームページを閲覧させるだけでは,情報を受けるだけであり教育効果は半減する。情報発信の発信方法として,ホームページによる発信とインターネットメールによる発信が考えられる。本校では校内インターネット網構築により,ホームページ(WWW)による情報発信はすでに体験可能である。そこで,今回は電子メール・インターネットメール体験が可能なシステムの構築と実践を行った。
あわせて,インターネットを利用した授業を計画する時の利用環境整備を行った。
その環境とは,
①コンピュータがある
②コンピュータがネットワークで接続されている
③ネットワークが外線電話と接続されている
④プロバイダと契約し,インターネットメールアドレスを持っている
⑤インターネット利用の設定が完了している
⑥複数のコンピュータで同時にインターネット接続が可能で,その利用速度に問題がない
⑦インターネットメールのアドレスが利用生徒分確保されている
⑧その他,校内での利用規定・利用講習の立ち上げが完了している
以上のような条件を,ごく普通の高校が満足させるのは予算・人員の確保などでかなり困難がある。本校は,人員の確保は可能であったので,予算的な面は研究助成などを利用して上記の条件をなんとか乗り越えた。個人がインターネットに接続する環境とほとんど変わりがないダイヤルアップ接続システムでも,工夫次第では20台以上のコンピュータから一斉にインターネットやインターネットメールが利用できるシステムの構築を目指した。
|
(2) 指導目標
生徒の情報リテラシー能力の向上は今後必要とされるであろう。その一環である情報発信能力向上の一手段として電子メール・インターネットメールを体験させる。
(3) 利用場面
①電子掲示板体験
②校内メール体験
③校外メール体験
④海外とのメール体験
|
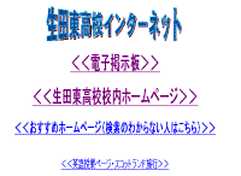 |
| |
図1 校内インターネットメニュー
|
(4) 利用環境
①生田東高校情報ハイウェイ計画により設置された,手作りの校内ネットワーク(10BAST-2/T規格の併用)
②ネットワーク網に接続されたコンピュータ(Windows95)が25台
③ISDN回線を2系統使用
・ホームページ(WWW)利用は3台のルータを経由してインターネットプロバイダにダイヤルアップ接続で使用,1台のルータ(64Kbps)ではコンピュータ8台の接続が同時利用の限界で,これ以上ではタイムアウトが続出し授業が成立しない。
・インターネットメールは専用コンピュータ(Windows95)からTAを経由してインターネットプ ロバイダにダイヤルアップ接続で使用した。
④電子掲示板-NTサーバ上のIISプログラムとデータベースソフトのAccess97で構築した。
⑤校内メールサーバ専用コンピュータ(Windows98)の設置
グループウェアソフトウェアのPROXY-MAIL(ブレーン製)を使用して校内メールボックスと校外メールアドレスからインターネットメ-ルアドレスへの自動変換に使用した。
⑥校内メールアドレス変換システム
PROXY-MAIL(ブレーン製)を使用した。
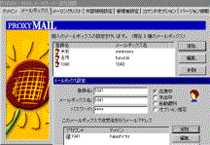
図2 PROXY-MAIL設定メニュー
機能
・校内メールアカウントの設定
・校内メールの送受信
・校内メーリングリストの構築
・ひとつのインターネットメールを校内生徒のメールボックスに振り分け転送
・ひとつのインターネットアドレスで複数パソコンの同時インターネット接続
・インターネット端末型ダイヤルアップ接続で自動ダイヤリング,自動切断
・個々のアクセス記録を残すログ管理機能
がある。
校内メールアドレスの発給法
大学などで実施されている学籍番号をメールボックス名にする方法を採用
↓
利用生徒分のメールボックスをPROXY-MAILで設定
↓
下記のように生徒の校内メールアドレスを登録
学籍番号(4ケタ)+@higashi-hs
↑
下線の部分を校外へのインターネットメールではhigashi@kw.netlaputa. ne.jpとPROXY-MAILが自動的に変更してくれる。
以上から,下記のようなアドレスを持っている生徒は
校内アドレス 0040@higashi-hs
校外アドレス 0040<higashi@kw.netlaputa.ne.jp>
⑦校内メールの送受信
校内アドレスを使用
⑧校外メールの送受信
送信は発信元を校内アドレス(0040@higashi-hs)で発信するとPROXY-MAILが上記の校外アドレス(0040<higashi@kw.netlaputa.ne.jp>)に自動変換してくれる。
受信は0040<higashi@kw.netlaputa.ne.jp>のように返信者が送信先を入力することで,生田東高校にメールが到着次第,PROXY-MAILのメールボックス分類機能によりそれぞれの生徒のメールボックスに振り分けられる。
⑨メールプログラムの選定と導入
Windows95に付属するインターネットメールはアドレスがひとつしか設定できず,複数ユーザーでの利用を想定していない。予算的な面で市販 のソフトウエアを購入することはできず,シェアウェアのソフトウェアを検討した結果,AL-MAIL32が,教育関係は無料で使用可能な点,さらに1台のコンピュータ上でメールアドレスを複数設定可能で生徒がメールボックスを別々に設置可能な機能を持っていることから,本校では使用している。このソフトは利用してみると,機能がシンプルなために操作が容易であり,生徒にも好評である。
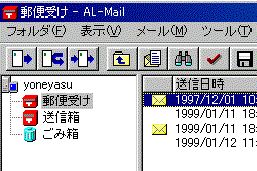
図3 メールプログラム(AL-MAIL32)
2 指導計画
(1) 段階を追った情報発信
実技科目では3年のコンピュータ演習A,普通科目では3年の英語Ⅱの授業の一環として実施した。コンピュータ演習Aではホームページ作成実習の次の課題としておこなっている。ホームページ作成も情報発信であるが,そこで扱ったプライバシーの尊重や著作権やネチケットの知識がより直接的に関係してくるメール体験は意義がある。しかし,外部とのメール交換をすぐに行うことは,生徒のプライバシー保護上の問題もあり段階的に行うことを計画した。
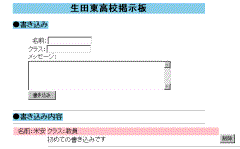
図4 電子掲示板メニュ-
| 指導計画 |
活動内容 |
電子掲示板体験
(コンピュータ演習A,
英語Ⅱ) |
自分の発言をリアルタイムに電子掲示板に掲載し,その掲載結果をみて,友人の反論や意見が掲載される。これら,発言のキャッチボールを経験させることで,情報発信体験と発言のエチケットを学ばせる。 |
校内メール体験
(コンピュータ演習A,
英語Ⅱ) |
自分あてのメール発信と受信
↓
仲間同士のメール交換
↓
指導教師へのメール発信と返信の受信
以上の手順で行うことで
・メールプログラムの利用方法
・新規メールの作成法
・メールアドレスの記入方法
・パスワードの設定
・返信メールの作成法
・到着メールの振り分け方法
の技術が習得できる。 |
校外メール体験
★インターネット利用
(コンピュータ演習A) |
指導教師のプライベートメールアドレスへインターネットメールを発信させる。これによりインターネットメールアドレスの記入方法を習得させる。 |
海外メール体験
★インターネット利用
(英語Ⅱ) |
3年時の英語Ⅱの授業で異文化体験の一環としてインターネットメールの送受信を経験させる。 |
注:★インターネット利用の概念は校外に発信したときに限定した(イントラネット利用は含まず)。
3 利用場面
(1) 目標
英語3年英語Ⅱで異文化体験でインターネットメールを送信してみよう。
(2) 展開
| 学習活動 |
働きかけ |
備考 |
| 準備1 |
HotList of K-12 Internet School Sites - USA.(全米の小中学校,高校のホームページが網羅されたサイト)で,オレゴン州とデラウェア州の高校のホームページを見て6校にe-mail交換のメールを出す。 |
教員 |
| 準備2 |
Sussex Tech High Schoolでは校内のホームページの一面に,こちらのe-mailの内容をそのまま掲示してくれた。世界史担当の先生が担当のクラスの生徒を紹介してもいいと返事があった。 |
教員 |
| 準備3 |
Valleyvue high school の生徒から1人返事があった。 |
教員 |
| 準備4 |
メール交換のめどがたったので,生徒3人一組で英文の手紙を書く準備をする。 |
教員 |
コンピュータ使用法の
練習 |
コンピュータの使用方法およびワープロソフト使用法の説明を実施した。 |
生徒(1時間) |
| 英文メールの文章作成 |
ワープロソフト(Word)を使って英文を書く。 |
生徒(2時間) |
| 英文メールの入力と添付ファイルの作成 |
メールプログラムの使用練習,デジタルカメラで写真を撮り,それをメールに添付する練習。 |
生徒(1時間) |
| 英文メールの送信 |
生徒の書いたメール,16通の中から5通を選び,準備2,3で述べた先生と生徒にe-mailをだす。 |
生徒,教員 |
| 英文メールの受信 |
生徒からは名前を指定して返事がきたので,その生徒に返事をださせる。
現在進行形。(受信3,返信2) |
生徒,教員 |

図5 英語2授業風景
4 実践を終えて
(1) 1クラス全員(40人)でのメール交換は物理的に不可能であったので3人1組で対応した。しかし,その中でも積極的な生徒には個人で対応させた。
(2) アメリカの高校の先生のメールによると,アメリカの高校生は国内の出来事には興味は持つが,海外のことにはほとんど興味をもたない。その先生も海外の高校生とe-mailの交換をさせるよう努力してきたが失敗したとのことであった。ちなみに返事をくれた高校生には,日本から留学している友人がおり,日本語を勉強中であり,そのことが今回のメールの返事を書く原動力になったという状況がある。
(3) 生徒の英文を書く能力が低く,生徒の書いた手紙の半数は内容が稚拙で,致命的な文法的の誤りが多くe-maillの交換は無理であり,教員による文法チェックが必要であった。このことが,16通のメールが5通に減った理由でもある。
(4) 何回かメールの交換がないと効果的ではないので,継続的に実施する方向で考えている。
(5) 携帯電話・ポケットボード・ポケベル等でメールを経験している生徒の対応を見ると,あまりにも世の中の変化のスピードが早く,生徒にとってインターネットメールの送信・受信体験は感動を与えるものではなさそうだ。
(6) PROXY-MAILは,性能的には本校の生徒全員にメールアドレスを与えても十分対応できる性能を持っているようだ。メーカーによると500人規模で運用している学校がすでに存在しているとのことであった。
(7) 生徒個人のメールボックスはコンピュータのデスクトップ上の個人フォルダに設置している。そのためにパスワードによるプライバシー管理が必要である。しかし,PROXY-MAILで設定したメールボックスのパスワードは利用者から変更できず,管理者がメールサーバーから変更する必要があり,この点が使いにくい。
(8) 2002年には,全部の学校にインターネットが接続する計画であるが,今回の校内メールボックスの設置と校内メールアドレスの配布は生徒のプライバシー保護の点からも非常に安心感がある。やみくもに外部に接続するのではなく十分校内で経験をつんで校外のメール体験を実施することで事故も防げるのではないかと考えている。
| ワンポイント・アドバイス |
本校では,外部からのメールは現在すべて上記のPROXY-MAILで作成したメールボックスに保存するようにしています。そのために本校の正式なメールアドレス(たとえば0040<higashi@kw.netlaputa.ne.jp>)で送られてきたメール以外は,すべてエラーメールとして管理者のメールボックスに保存されます。この機能により,メールの送受信のエラーや不適切なメールなども管理できます。
インターネットメールの授業への導入は,生徒のインターネット検索の導入時よりも,電話代の高騰・ホームページに生徒が同時にアクセスするために発生するタイムアウトの心配等もなく,比較的容易であったというのが実感です。インターネットメールの授業への導入は比較的簡単です。仲間がふえれば,校外メール体験はもっと楽しくなると思います。 |
生田東高校ホームページ (http://www.netlaputa.ne.jp/~higashi/)
生田東高校メールアドレス (higashi@kw.netlaputa.ne.jp)