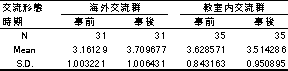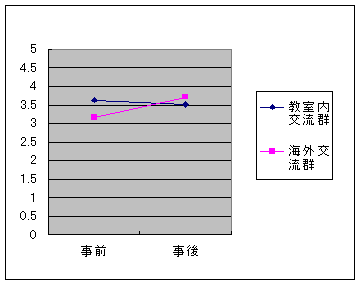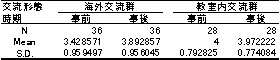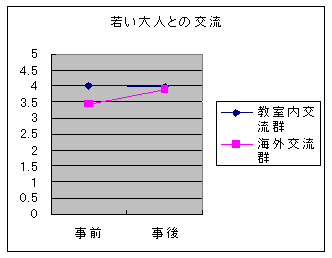50 英語の4技能を総合的に高める電子メールを利用した海外交流授業
---コミュニカティブな言語習得環境 ---
高等学校2年生・英語
三重県立川越高等学校 英語科 近藤 泰城
三重大学教育学部 下村 勉
インターネット利用の意図
言語習得に関して,オーセンティック(本物の)なコミュニケーション体験が重要である。インターネットによる海外の学校との交流で,それが瞬時に可能になった。言語をツールとして用い,「学ぶ」という意識なしに,身についていくような環境がインターネットにより可能になる。また,マルチメディアの発達により,「読む」「書く」だけでなく,「聞く」「話す」の領域に関しても,「習得」の機会を提供できる。
1.企画の目的・意図(日本の英語教育の問題点とコミュニカティブ・アプローチの視点)
1970年代,EC諸国間の交流や国際化時代を迎えて,「文法的には正確な文を作る能力を持つ学習者が,単純な意思伝達さえできないという実態は,世界各国の言語教育者がかかえている悩み」(安藤昭一 1991 英語教育現代キーワード事典p.147)であった。そこで,提唱された語学教育理論が,コミュニカティブ・アプローチである。中でも,インプット理論はそれ以後の英語教育に多大な影響を与えたが,その主張は,現在の日本の英語教育の改善に寄与するものが多くある。その中から,筆者の実践に関連あるものを挙げる。①成人が第二言語を身につけるには,子供が母国語を無意識的に身につける「習得」と,学校などで系統だてて文法規則などを意識的に学ぶ「学習」とがある(習得学習仮説)。②第二言語でのコミュニケーション能力を身につけるためには,「習得」を可能にするような,学習者の能力より少し高度な適切なインプットを多量に与えることが必要(インプット仮説)。③「学習」による知識は,アウトプット(話す,書く)の際のモニター機能(誤りを正す)を担い,言語の生成には,「習得」された知識が必要である(モニター仮説)。<渡辺時夫 1988 インプット理論の授業 p.1>日本の英語教育は,高校,大学入試が大きな目標となっており,これまでは,客観テストで測ることが可能な「学習」による知識が重視されてきた。もちろん,「習得」と「学習」は車の両輪のようなものであり,「習得」だけで,コミュニケーション能力の全てが得られるわけではない。ただ,日本の英語教育では,「習得」の視点が軽視されてきたと考える。そのような状況を少しでも改善し,コミュニカティブな言語習得環境の提供をできるように授業を進めることにした。
2.実践の準備
この実践の準備では①交流校,②交流テーマ設定,③授業手順検討を重視した。
(1)交流相手を探す。
交流相手を探すには,様々な方法があるが,カナダのストラフ大学の運営するInter-cultural E-mail Classroom
Connections <http://www.stolaf.edu/network/iecc/>へ交流校募集の投稿した。WEBページのフォームからの投稿が可能で,世界中の二千人以上の先生へ配信される。結果,20通以上の返事を得ることが出来た。
(2)交流テーマの設定を工夫する。
交流テーマの設定についても,かなり悩んだ。様々な先行実践に目を通した。結果,身近な話題がよいであろうと下記のようなテーマを用意した。
①将来の職業 ②環境保護のために何をしている,出来る? ③おこずかいの入手方法,使い道
④家事の分担 ⑤たばこについてどう思うか ⑥男女同権について ⑦学校のランチの内容
(3)授業の手順の検討
授業の手順については,研修中に学んだことを基に,以下のような手順を定めた。
①コンピューターを使った英作文授業(自己紹介,身近なテーマによるエッセイ)を行う。②インターネット(電子メール)によって,米,露,西の生徒と作文を送りあい,コメントしあう。③個人対個人の交流ではなく,多対多の交流を行う。返事が来ずに動機付けが下がる生徒が出るのを防ぐと同時に,情報を共有化し,多読のトレーニングにもなる。④授業の指示,コンピュータ操作の解説などを,日本人英語教師(筆者)も英語によって行う。⑤生徒は,日本人英語教師に対して,英語で,話さなくともよい。発話を強制しないインプット理論に基づく。⑥研究上の比較の必要と,コンピュータ環境の不足の問題で,2クラスを,海外交流群と教室内交流群に分けて,前者は海外と交流を行うが,後者は,教室内で,クラスメートの作文を読んで,そこにコメントを入力するというような活動を行った。⑦画像を用いて,交流を深める。⑧画像と音声を組み合わせて送信できる「With
Voice Multi」というソフトウエアを用いて,この授業で英語の4技能のうち不足している「話す」活動を増やす。
3.企画の実践
(1)企画の実践について,日記風にまとめてみた。
|
98年1月10日ごろ |
カナダのストラフ大学の運営するIECCに交流校募集の投稿をする。 |
|
98年1月20日ごろ |
上記の投稿への返信が相次ぐ。実際交流に発展したCeil先生,Dolorsさんを含め,約25通のメールをいただいた。 |
|
98年4月14日 |
第1回目授業:コンピューター教室でなく,ホームルーム,LL教室において,オリエンテーションを行った。まずAssistant Language TeacherのJacob Togo先生が英語で,今後の予定,授業中の活動などについて説明。その後,筆者も補足の形で,ほぼ同様の内容を英語で説明した。Input理論のredundancy(母親が幼児に語りかけるように繰り返し,言い換えを多用する)を意識した。 |
|
98年4月21日 |
全ての授業をパソコン室で行う。パソコンの操作等を説明。全て英語。アダムス高校の自己紹介のWEBページをプリントアウトして見せる。 |
|
98年4月27日 |
自己紹介文を作成開始 |
|
98年5月26日 |
海外交流群:ロシアからの自己紹介文を読ませる。15分で読んで,返事を書かせようと考えたが,読むだけで,40分費やした。
教室内交流群:クラスメートの自己紹介文をプリントアウトして見せる。思ったより真剣に読んでくれ,20分ほど静寂が続いた。 |
|
98年6月2日 |
海外交流群:ロシアからの自己紹介文への返事を書かせる。6名完成。
教室内交流群:エッセイテーマを将来の職業,こづかい,家事の分担などから生徒に選ばせる。クラスメートの自己紹介へのコメント作成継続。 |
|
98年6月4日 |
海外交流群:アメリカ,ロシア,スペインへ,自己紹介文をやっと送信。 |
|
98年6月9日 |
海外交流群:ロシア,スペインからの自己紹介へのコメントを書く。
教室内交流群:「エッセイ」の概念の説明に苦労した。 |
|
98年6月10日 |
海外交流群:ロシアとアメリカからのメッセージが到着。見せる。喜んでいる。誰宛てのメールか分からず,返事の送信で困ることが判明。
教室内交流群:エッセイのタイトルをつける。brain stormingを試みる。 |
|
98年6月14日 |
海外交流群:返事が届きはじめる。宛て先不明メールのトラブル多発。
教室内交流群:エッセイ作成開始。アイディアない生徒は図書館学習 |
|
98年6月15日 |
海外交流群:返事を配布。返事の来ていない生徒がいる。これ問題。 |
|
98年6月24日 |
海外交流群:返事の来てない生徒の表情がさえないのが気になる
教室内交流群:期末テストの内容について説明。 |
|
98年7月初旬 |
海外交流群:返事が来てない生徒に,返事が来るように腐心する。 |
|
98年8月 |
下旬に,各交流校に交流再開のメールを送るが,アダムス高校Ceil先生のみ返事があった。集中した交流ができると考え,交流校が1校になることは,マイナスでなくプラスであると考えた。 |
|
98年9月 |
これより後は,比較する二群を設けずに,全ての生徒が海外と交流。。 |
|
98年9月8日 |
新しいAssistant Language TeacherのTrisha Strodeさんの自己紹介(約10分)。その後,Trishaに手紙を書こう!という課題を与える。 |
|
98年9月9日 |
Trisha先生への手紙が終わったものから,一学期に作成した自己紹介の書きなおしを始めるように指示。 |
|
98年9月16日 |
アダムス高校の新しい生徒の自己紹介を読ませる。 |
|
98年9月29日 |
アダムス高校の新しいクラスの生徒の自己紹介を読む。 |
|
98年10月13日 |
日本的なものを紹介するためのBrain Stormingを行う。今回は画像を利用することを伝える。出てきたアイディア:Daibutsu,
Graves, Origami, Ikebana,Yukata, Kimono, Sushi, Shrine, Buddhist Family
Altar, Sumo, Kite, Uchiwa, Mochi, New year's gift of money,Karate, Festival,
How to make rice, How to grow rice, New year's day, judo, onsen(図1~3)
|
|
|
|
|
図1ルーズソックス
|
図2こけし
|
図3てるてるぼうず
|
|
|
98年10月15日 |
本校生自己紹介をアダムス高校へ送信。 |
|
98年10月27日 |
アダムス高校生徒自己紹介へのコメント,川越高校コマーシャル,「日本的なもの紹介」の課題を順次こなしていく。 |
|
98年11月2日 |
14時間の時差があるため,夜12時までに送信すれば,アダムススクールの午前中の授業に間に合うため,完成した「日本的なもの紹介」を自宅から送信しようとするが,プロバイダー話中で不可。翌朝起きると,Ceil先生から,「Send them!!」というメールが来ていた。残念。 |
|
98年11月10日~ |
生徒が興味を持つような課題の設定に行き詰まる。この日朝,アダムス高校から,11通の画像付きのアメリカの高校生の文化の紹介メールが届く。当初計画を変更,プリントアウト。生徒に読ませた(図4~7)。 |
|
98年11月10日~ |
 |
 |
 |
 |
|
図4バックパック
|
図5免許証
|
図6駐車違反証
|
図7ピーコート
|
|
|
98年11月11日~18日 |
「日本的なもの紹介」作成継続。アダムス高校からの画像付きメールへの返事を書く。 |
|
98年11月19日 |
コンピュータ教育開発センターの自主企画の助成で,DOSV機2台とカラープリンタ1台,デジタルカメラ1台他購入。パソコン室にも,外線電話が使える環境をいただき,交流の幅が広がった。音声多機能メールソフトの使用が可能になり,生徒がメールソフトから直接メールを読む,プリントアウトする,送信することが可能になった。 |
|
98年11月24日~ |
音声多機能メールソフト With Voice Multi によるメッセージの作成 |
(2)With Voice Multiの紹介
 |
|
図8 With Voice
Multi 画面
|
11月後半から,”With Voice Multi(ボイス多機能メールソフト)”というソフトウエアを交流に導入した。これは,画像を複数枚並べておき,ナレーションを録音しながら,画像を切り替え,ポインターを動かし,グラフィックソフトのように,線や図形などを書き足したりできるソフトウエアで,できあがったファイルは,高率で圧縮され,メールに添付して送ることが可能になる。生徒が自分で作成した原稿を手に,嬉々として録音をおこなっている姿を見て,英語学習の新たな可能性を感じた。このソフトウエアは,新100校プロジェクトなどで活躍されている名古屋市立西陵商業高等学校教諭の影戸誠先生からご紹介いただいた。影戸先生は,「リアルタイムの交流は,技術的に困難な点が多く,マルチメディアを利用したインターネットによる交流の一般的な普及には限界がある。より手軽に,マルチメディア+インターネットを教育分野で使ってもらうのによいものはないか」と望まれて見つけられた。筆者は英語教師の立場から,「聞く」「話す」の領域でも,マルチメディア+インターネットで生徒の活動を促す要素を導入したいと考えていたので,渡りに船であった。
生徒によるWith Voice Multiの作品をアダムス高校に送った時の反応は素晴らしく,Ceil先生は,以下のようなメッセージをくれた。”These are just FABULOUS! You are ahead of us.”「すばらしい!そっちの方が進んでるわね。」アダムス高校でもこのソフトウエアを利用したいというメールが届き,販売元であるメディアカイト株式会社に問い合わせたところ,米国ソフトリンク社のPowerlinkというソフトウエアが,同一の機能を持つと分かり,さっそくアダムス高校に連絡した。
5.実践の評価
(1)英語学習への動機付け
海外との電子メールによる交流の有効性を確かめるために,いくつかのアンケート調査をおこなった。その中で,英語学習について,「学校での英語学習,受験のための英語学習」と「自分の英語力を高めるための自主的な英語学習」とに分けて,それぞれへの動機付けの高さをたずねた。筆者は,前者が「企画の意図目的」で述べた「学習」,後者が「習得」に相当すると考えている。以下に結果を述べる。まず,「受験のための英語学習」についてたずねた。質問項目を以下の通りで,5段階で,回答するようになっている。
この授業(筆者の授業)以外の学校の英語の授業,あるいは,受験ための英語の勉強についてのやる気について答えてください。
この項目については,交互作用(設定された条件の差が効果の差を生み出したかどうか)は見られず,本実践は,この面の動機付けに影響を与えなかったようである。
続いて,コミュニケーションのための英語学習への動機づけの実践前後の変化を調査した。質問項目は,「学校の英語の勉強や受験のための英語の勉強以外の,自分の英語力を高めるための自主的な英語の学習についてのやる気を教えてください。」で,上記同様の5段階評価で回答を求めた。調査の結果,平均値,標準偏差は,図9のようになった。図10に変化を図示する。
分散分析の結果,交互作用(設定された条件の差が効果の差を生み出したかどうか)は,1%水準で有意(差が偶然の揺れの範囲ではなく,意味がある。)であった(F(1,64)=7.802,p<.01)。時期の主効果は,有意傾向であった(F(1,64)=3.348,p<.1)が,交流形態の主効果は,有意ではなかった(F(1,64)=0.453,p>0.5)。この項目については,設定された交流形態の差が,動機付けに差を生み出したと判断できそうである。
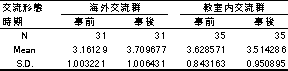 |
|
図9 コミュニカティブ英語動機付け統計
|
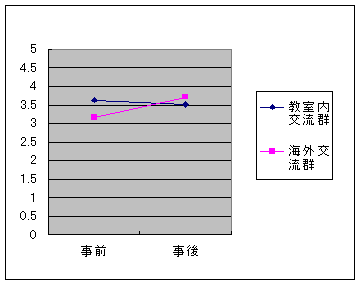 |
|
図10コミュニカティブ英語グラフ
|
(2)異世代交流欲求調査
筆者は常々,日本では,世代間のコミュニケーションが少なすぎると考えている。高校生であれば,家族以外では,同世代のものと過ごす時間が非常に多い。結果,視野が狭くなる。筆者は,海外の異文化との交流が,身近な異文化とも呼ぶべき異世代の人々との交流への積極的な態度につながり,豊かな人間性の形成につながると考えた。世代の区切りは,予備調査を行い,平均値をとり,年齢を設定し,次の質問項目により,調査を行った。「あなたは,中学生以下(14才以下)の子供たちと話してみたい,あるいは,もっと話したいと思いますか?」 これに対して,5段階で答えてもらった。以下,次のような世代に分けて,調査を行った。①中学生以下(14才以下)の子供たち ②同世代(高校生,あるいは15~18才)のすでに知っている人 ③同世代(高校生,あるいは15~18才)のまだ知らない人たち ④若い大人の人たち(だいたい19~27才) ⑤大人たち(だいたい28~60才) ⑥お年寄り(だいたい61才以上)
このうち,「若い大人の人たち」と,「お年寄り」について,交互作用が確認できた。
ア.若い大人の人たち(だいたい19~27才)(図11,12)
分散分析の結果,交互作用は,有意であった(F(1,62)=5.920,p.<.05)。時期の主効果も,有意であった(F(1,62)=4.659,p.<.05)。,交流形態の主効果は,有意傾向であった(F(1,62)=2.851,p<0.1)。
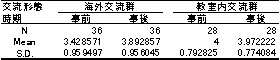 |
|
11 若い大人統計
|
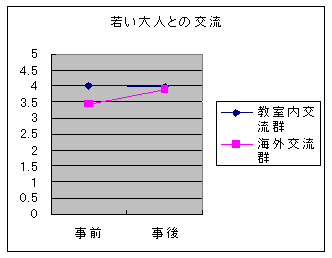 |
|
図12 若い大人グラフ
|
イ.お年寄り(だいたい61才以上)
分散分析の結果,交互作用は,有意であった(F(1,63)=4.011,p.<0.05)。時期の主効果(F(1,62)=20.094,p>.05),交流形態の主効果(F(1,62)=2.464,p>0.05)とも有意ではなかった。
以上の結果,海外交流によって,「若い大人の人たち(だいたい19~27才)」「お年寄り(だいたい61才以上)」という二つの世代に対する態度の変容が見られると思われる。この結果を信頼すれば,海外交流が,「若い大人」という「先輩」たちに心を開き,アドバイスを受け入れ,高齢化社会へのレディネスを持った生徒の育成になんらかの効果あると思われる。
6.実践を終えて
設備,時間の不足,筆者の計画性のなさ等,様々な問題にも関わらず,大半の生徒が授業を楽しんでいてくれることが,何より嬉しい。交流校のCeil
Jensen先生,両校の生徒,理解支援いただいた同僚、東海スクールネット研究会,コンピュータ教育開発センタはじめ多くの方々のバックアップを受けて,初めてできた実践である。交流が,文字⇒画像⇒音声とステップアップしていったのが良かったように思う。常に目新しさを維持できたことが動機付けを保つのに役立った。ただ,情報の共有化ということで,あちらからのメールを皆で読み,こちらからも,不特定多数に向かった発信になった。このことが,動機付けを低下させたように思う。海外交流を伴う授業については,国際的な協力によるカリキュラム開発の必要性,多国間のコーディネーターの必要性を感じる。今回研修中ということで,この交流実践に十分な時間を割くことができたが,初めて交流を始める時はかなりの不安がある。それらを軽減する努力が必要である。最後に,LAN環境なしの教師の代理送信による交流には問題が多すぎる。学校までだけでなく、学校内での環境も含めた施策を一日も早くお願いしたい。
| ワンポイント・アドバイス |
| 今回の実践で,ここまでやってこれたのは,交流相手校の教師の力量や親切,寛容に負うところが大きいと考えている。この種の実践を進めていく場合,「良い交流相手に出会う」ということが最も大きな助けとなる。交流相手との良好な関係を維持するために,筆者が心がけたことは,「それぞれ事情があるので,要求は『可能なら』という形で出し,応えてもらえた場合には,思いきり感謝の言葉を書く,応えてもらえなかった場合には,『だいじょうぶ』というコメントを送る。」「近所の風景の写真など個人的な情報をやりとりする。」「できるだけ速いレスポンスをする」「相手の要求へ可能な限り応える(アンケート調査の依頼があり,翌朝の授業で行った。)」などである。また,相手の反応により,次の授業の展開が異なるものになる。それを肯定的にみていくことが必要である。よほど,綿密な計画を立てない限り,それぞれの側の事情もあり,こちらの思惑通りには,ことが運ばない。「何をやっているか分からない」という生徒のコメントに打ちひしがれた日もあったが,交流の中で起こる出来事を肯定的に受け止め,面白がる態度が重要であると感じた。 |