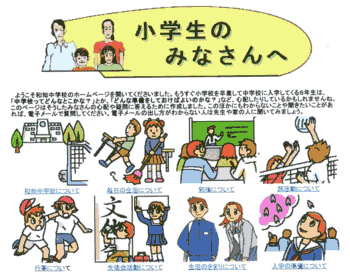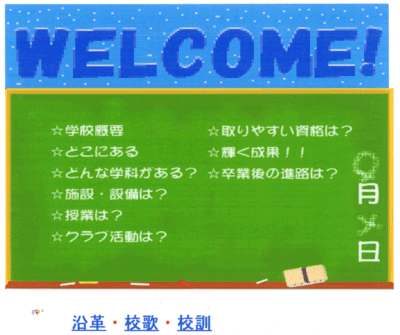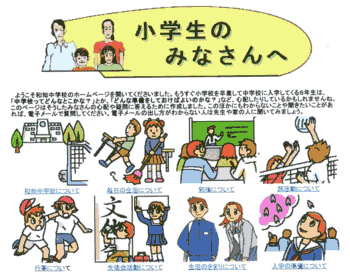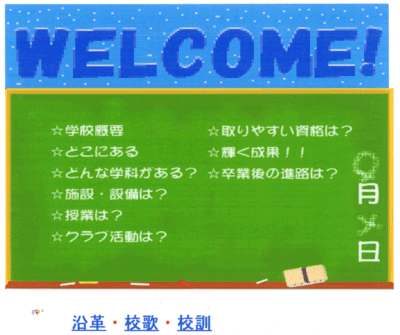67 小中高の連係による進路学習のインターネットの活用研究
小学校・進路学習
中学校・進路学習
高等学校・進路学習
福知山市立雀部小学校 塩見 昭
福知山市昭和小学校 芦田 誠
綾部市立豊里中学校 小林 治
福知山市立南陵中学校 細谷 恵滋
三和町立三和中学校 清水 雅登
和知町立和知中学校 中村 澤三
京都府立工業高等学校 田中 邦明
インターネット利用の意義
進路指導で使用する資料は,従来,ほとんどが印刷によるものであった。そのため,どうしても情報の一方通行になりがちで,児童・生徒は,細かい質問に答えてもらえる機会があまりなかったといっても過言ではあるまい。確かに,進路先の学校の先生を招いた「進学説明会」は持たれているが,時間的にも内容的にも,制約は多くあった。
ここ2・3年間に,学校教育現場のインターネットなどの環境は整備されつつある。そこで,相互に情報交換が可能なネットワークを利用した進路学習が展開できないか,また,小中,中高にとどまらず,小中高の関係者(教師・児童・生徒など)も含めたシステムが構築できないか実践してみた。
1 進路指導
(1) ねらい
小中高各学校で,進路指導で使用することができる資料をWeb上に公開する。ブラウザで資料を閲覧し,質問があれば,その学校へ電子メールで質問する。質問の内容に応じて,教師や生徒が電子メールで回答したり,Web上に提示したりする。
Web上に公開する資料の決定にあたっては,事前に関係各校から情報(質問事項など)を電子メールなどで集めておくこととする。
以上の流れの中で,小中高の連係による進路学習におけるインターネット活用の有効性について検証する。
(2) 指導目標
小中高各校種で共通しているのは,それぞれの学校にあるブラウザや電子メールソフトの使い方である。また,電子メールを発信するにあたっての情報倫理(いわゆるネチケット)の指導も必要となる。
中学・高校では,上記に加えて,Webページ作成(デザインや構成面など)に関する指導も行う。ただし,Webサーバへの登録は教師(Web管理者)が行う。
(3) 利用場面
次の場面で利用する。
①進路指導の資料として,それぞれの学校のWebページを閲覧する。
閲覧方法は,後述しているとおり利用環境に大きな差があるので,児童・生徒が個々のコンピュータを使う場合や全体で1つの画面を見る場合,プリントアウトしたものを見る場合と,まちまちである。
②感想や質問などがあれば,それぞれの学校に電子メールで送る。
③質問などの回答を,Webページに載せたり,電子メールで返信したりする。
①の場合と同様,実際の環境に応じていろいろな方法を採る。なお,「2 指導計画」「3 利用場面」は,回線接続校を例に挙げて記述する。
(4) 利用環境
各学校によってまちまちであるので,学校別の詳細は略す。
・コンピュータ未設置 ・・・・ 1校
・回線未接続 ・・・・・・・・・・・・ 1校
・ダイヤルアップ接続 ・・・・ 4校
・専用線接続 ・・・・・・・・・・・・ 1校
2 指導計画
| 指導計画 |
留意点 |
| 進学する上でどんな情報が必要か,(あるいは,どんな情報を希望するか,)意見を発表させる。 |
・小中学校で児童・生徒・教師にアンケートをとり,まとめたものを電子メール(今回は,参加校のメーリングリストを使用)で送信する。送信は教師が行う。 |
ブラウザの使い方を知らせ,各学校のWebページを閲覧させる。
★インターネット利用 |
・閲覧させるWebのアドレスは,教師が予めブックマークの設定をしておくか,アイコン化しておくなどする。
★Webページの閲覧 |
電子メールについて知らせる。
|
・情報倫理面(ネチケット)について指 導する。 |
Webページを見た感想や質問を電子メール(用のテキスト)にまとめさせる。
★インターネット利用
|
・今回は,学級や学年単位で質問事項などをまとめさせる。電子メールの発信は教師が行う。(小学校)
★電子メールの発信 |
質問の回答を電子メールにまとめ,発信させる。
★インターネット利用
|
・中学高校への質問の中で,生徒が答えた方が効果的なものについて回答させる。発信前に教師が内容を確認する。
★電子メールの発信
|
3 利用場面
(1) 目標
ブラウザの使い方を知り,目当ての学校のWebページから,必要な情報を得るとともに,Webページについての感想や疑問を持つ。
(2) 展開
| 学習活動 |
活動への働きかけ |
備考 |
| 1 本時の目当てを確認する。 |
|
各校のブラウザソフト
|
目当ての学校のホームページにアクセスし,
必要な情報を手に入れよう。
|
|
2 ブラウザの使い方を知る。
3 目当ての学校にアクセスし,Webページを閲覧する。
4 Webページを見た感想や疑問(質問したいこと)について話し合う。
|
・スクロールバーやバックボタン,ハイパーリンクについて知らせる。
・学校のアドレスは,ブックマークなどに予め登録しておく。 |
使い方を書いたプリントなど
|
今回利用した学校
和知町立和知中学校
小学生向きの学校紹介ページ(図1)
京都府立工業高等学校
中学生向きの学校紹介ページ(図2)
|
|
・学級や学年の意見などを箇条書きにまとめておく。
・必要に応じて,Webページを印刷したり,保存したりしておく。
|
プリンタ
Web保存ソフト |
5 次時の予告を聞く。 |
・電子メールについて
|
|
図1 和知町立和知中学校 小学生向きの学校紹介ページ
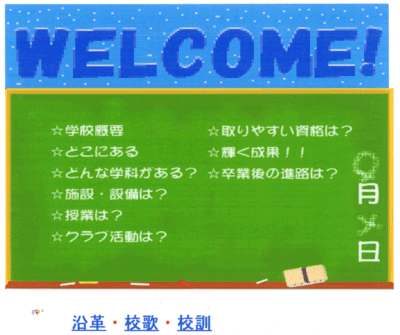
図2 京都府立工業高等学校 中学生向きの学校紹介ページ
4 実践を終えて
「進学先の学校について知りたいこと」というアンケートをとるとき,小学生の場合,ほとんどが地元の中学校に進学するため,知りたいことは近所の先輩に聞けばよく,アンケートの意味がわからない児童が多かった。それで,「自分が今まで知らなかった中学校に急に進学することになったとき」という条件を付けた。
Webページを実際に見た児童・生徒は,通常の進学説明会や学校訪問のときより,活発に資料を見,情報収集を楽しんでいた。この理由として,次の3点が考えられる。
・ イラストやクリッカブルマップを使用した,興味や関心の高まるWebページが用意できていたから。
・ メニュー形式にまとめられていて,自分が見たい順序で,また見たい項目を中心に見ることができたから。
・ 少人数で一つの画面を操作できたので,気楽にのびのびと操作できたから。
このことから,Webページを作るときには,見る側の意見や希望を取り入れ,視覚的に訴えるものを作ること,Webページを見せるときには,目当てを持たせた上で自由にできる時間を確保することで,効果が上がると思う。
1単位時間の授業の中で,児童・生徒たちは,「知りたいことがよくわかった。」「思い通りに自由に見ることができて楽しかった。」「もっとほかの学校のことも調べたい。」というような声が多く聞かれた。
今回の取組は,各参加校がメーリングリストを使って連絡を取り合いながら進めていったが,取組期間が短くなり,電子メールでの質問などのやりとりが,この原稿の執筆時までにできなかったのが残念であった。さらに取組を続け,進路学習でのインターネット利用の有効性や実用性を確かめていきたい。
| ワンポイント・アドバイス
情報を公開していく上で考慮しなければならないこととして,個人情報や写真などのプライバシーの保護があげられる。
Web上に公開する情報は不特定多数の人々に見られるという意識を持って,作成していかなければならない。電子掲示板を使ったやりとりも同様である。作る方は進路指導に活用してもらうつもりであったとしても,見る方が公開情報をどのように活用するかはわからないのである。
個人やグループに限る情報の伝達方法としては,電子メールやメーリングリストがある。もっとも,電子メールでも,秘匿性が完全に保たれるわけではないことを,回答者は知っておかなくてはならない。進路学習の資料という観点から考えると,例えば質問事項やその回答などWeb上に公開した方がよいものもあるので,公開の意志を予めはっきりさせることや教師による児童・生徒の質問・回答メールの内容確認などのルールを作っておいた方がよい。
|
利用したURL
和知町立和知中学校
(http://www.kyoto-be.ne.jp/wachi-jhs/guidance/child.htm)
京都府立工業高等学校
(http://www.kyoto-ths.fukuchiyama.kyoto.jp/school/gakindex.htm)