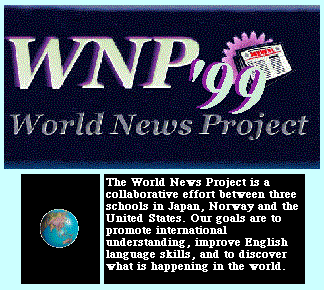2.1.3.3.World News Project (WNP)
兵庫県立神戸商業高等学校 坂東英敏
① プロジェクトの概要
このプロジェクトは昨年の9月から始まり、日本、ノルウェー、アメリカの参加国の生徒が毎月県立神戸商業高等学校のサーバー上にあるホームページのニュースを更新し、そのニュースについて、それ以外の国から参加する生徒も含めてコメントをBBSを使って交換するというものである。ニュースはそれぞれの国の特徴が伝わるものか生徒が他の国に伝えたい内容のものということで、それぞれの参加校からメールで本校に送り、WNPのホームページに載せている。BBSは、各ニュースごとに分かれており、コメントが書き込めるようにつくられている。
② クラスのねらいと特色
このプロジェクトのねらいの一つは参加者がそれぞれの国のニュースを持ち寄り、それについての意見交換をすることによって、お互いの共通点や相違点に気がつき、国際人としてのセンスとコミュニケーションの方法を身につけることである。また、ニュースがテーマになるため普段新聞を読む機会の少ない生徒が、このプロジェクトに参加することでその機会が増えるきっかけとなればと考え、企画した。
③ 参加者のプロフィール
ニュースの提供は
・県立神戸商業高校 3年生 情報科 課題研究 15名
・アメリカワシントン州ケネウィック高校ESLクラス 10~12年生 20名
・ノルウェー Joepeland Ungdomsskole 9年生 media class 6名
上記の学校以外でBBSに参加したのは
韓国 新亭女子商業高等学校
日本 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校
富山県立高岡商業高等学校
④ 交流の実際
9月の開始時は日本とノルウェーの2カ国のニュ-スでスタートした。日本のニュースとして掲載したのは和歌山のカレー事件で、ノルウェーのニュースは駅に赤ん坊が捨てられた事件であった。ニュースを考えた生徒がまずコメントを書き込み、これに対して同じ学校の生徒も、それ以外の学校の生徒からもコメントがあった。
これまでに掲載されたニュースは6件でコメントの数は32であった。10月にはアメリカで原始人と思われる化石がケネウィックで見つかったニュースが加わり、3カ国になった。また、そのニュースに対して、韓国やほかの日本の学校からもコメントが寄せられた。11月の日本のニュースで商品券(地域振興券)を配布することについては、コメントが多く寄せられた。ニュースそのものについての自分の考えを述べることは単なる感想にとどまったケースが多かったが、そのニュ-スの内容についての質問があったものに答える場合は交流が続いた。2月に配られる商品券の額がどのくらいになるかということを他の国の生徒にわかってもらおうとコメントを考える過程で生徒は相手の文化や生活の様子について考え、表現や内容について工夫していた。
コメントの書き込みは一般的なメールの交換と異なり、性格上文章が短く表現が簡単であったため、参加しやすかったという感想の生徒もいた。また、反対にもっと詳しくやりとりをしたかったという生徒もいた。
⑤ 継続するために
参加各校によってコンピュータの利用できる環境が異なるため、最大公約数的にホームページの利用が適当と考えた。また、共通の言語としての英語の能力の差が心配であったため、ニュース、コメントともその長さが障害にならないように短くした。
元になるニュースは5行以内と言うことにした。アメリカの高校生は英語が第二国語(ESL)となる生徒のクラスであり、ノルウェーでも英語は外国語であるため、比較的差は少なかったかもしれない。夏休み明けからすぐに始められるように以前から交流のあった学校から始め、その後希望があれば枠を広げるという形を取った。
実際にはパスワードによって参加が制限されていたせいか、当初の学校以外からの参加申し込みはなかった。参加に制限があること(パスワ-ド)には、プラスとマイナスの両面が考えられる。安全にメッセージやサーバを管理するためには参加者が制限されているほうが問題が少ないが、より多くの交流をすることで生徒が学ぶチャンスを増やす観点からいえば問題があると思われる。
今後、参加者の範囲やパスワードの設定については更に議論が必要であると思われる。
コメントの記入は生徒の全くの自主性に任されているときには躊躇があったようであるが、各校で担当の教員がコメントの発信を課題としたり、ニュースの原稿をクラスの提出物に組み入れたりしたときは参加が増えた。或る程度カリキュラムに組み入れる形でプロジェクトを運営した方がスムーズな交流になるかもしれない。誰がどのくらいの回数BBSにアクセスしているかが分かれば、自分の書いたメッセージに反応がなくても生徒の意欲は減少しない。このような情報が自動的に表示されるものが必要かもしれない。
また、始めて早々本校の生徒がなかなかニュースをうまく英語に直せないということと、そのためにニュースの更新に時間がかかりすぎてはいけないという心配から週刊の英字新聞の記事を利用することを考えた。The
Japan Times Weeklyと交渉し、快く転載の許可を得た。実際にはその記事をそのまま使うことはなかったが、記事の中の単語や言い回しを使ってニュースを載せることになったが、生徒はそのサポートがあって安心してニュースの原稿を考えることが出来た。
⑥ 評価と展望
まだ始まったばかりで、全体を評価出来るだけの情報が集められたか。まず第一にこのプロジェクトの性格上、継続すれば次第にコメントを書く生徒同士がそのコメントから相手の人間としての様々なものを感じ、より深い交流へと変化すると考えたのであるが、なかなかその数は多くなっていない。その障害としては、言語、学校のスケジュールの違い、コンピュータを利用できる環境の違いが考えられる。そのいずれもが簡単には解決できない要素を多く含んでいる。まだまだ工夫する要素が残っていると思われる。すべての参加者が少なくとも容易に一日一回はBBSにアクセスできるような環境が整えられれば更に多くのものを得ることができると考える。
技術的な問題としては、ニュースの更新に手間がかかるということを改善する必要がある。メールで送られてきたものが自動的にホームページにのせられ、以前のニュースと、それに対するBBS上のコメントがバックナンバーとして保存されるようなしくみがあれば、よりスムーズに更新できると思う。
た、BBSのしくみは基本的には必要な要件を満たしていたが、アメリカの学校で使っていたモニターはサイズが小さく、画面全体が表示できなかったため当初自分達の投稿した部分が見られなかった。コンパクトに表示できる工夫も必要かと思われる。
⑦それぞれの学校でのプロジェクトへの取り組み。
神戸商業高校の生徒にとっては全く新鮮な試みであったため、積極的に参加出来たと思う。また、ニュース原稿の作成や質問に答えるために新聞を読む回数が増えたことに驚いている生徒もいた。実際の授業はメールの交換が中心になっているが、このプロジェクトに参加することで、より広い視野を持つことができた生徒が多かった。また、ICPの他のプロジェクトに参加する余裕はなかったが、その点についても考える余地が残されていると思う。
アメリカのケネウィック高校の生徒は14才から20才までの生徒が参加した。うち11人が女子で、14人が男子である。彼らはESL(English as
Second Language)クラスに所属し、まだ十分に英語が使いこなせない生徒もいる。このプロジェクトで知り合った日本の生徒とのメールやニュースの交換は、彼らにとって他の世界で起きている事柄について学ぶことのできるチャンスにもなった。彼らはニュースからアメリカと同じような問題が他国でも問題になっていることを知るとともに、考え方の違いについても学ぶことができた。
(Sara MaCraynoldsのメッセージから)
ノルウェーのジョプランド中学は選択のメディアのクラス(週2回)のなかの希望者が参加している。14才から15才までの女子ばかり6名で、このプロジェクトに参加したことで、日本の生徒との交流の希望が高まり、担当の先生から、継続してメールの交換ができる生徒を見つけて欲しいという申し入れがあった。
プロジェクト全体が当初の目的を達するためにはさらに多くの交流が必要と思われる。