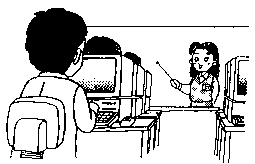 (1)コンピュータに関する研修の指導
(1)コンピュータに関する研修の指導 |
学校側の活動内容と留意点 |
・ハード、ソフトの設備一覧の作成を行う。 ・参加教職員のレベル調査およびグループ分けを行う。 ・教職員の欲している研修内容の把握 ・多くの教職員が参加出来るように日程の調整を行う。 実施 ・集合あるいは個別研修を受ける。 留意点 ・開始時刻を守り、安易に予定を変更しない。 ・参加される教職員が偏らないようにし、全員が幅広い知識の習得が出来るようにする。 ・SEだけに頼るのではなく、技能の高い教職員は補助にあたる。 ・研修目的以外のサービスを要求しない。 |
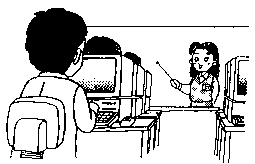 (1)コンピュータに関する研修の指導
(1)コンピュータに関する研修の指導 |
SE側の作業内容と留意点 |
・設備の把握やシステム(ハード、ソフト)チェックをする。 ・教職員のスキル、活用状況の把握をする。 ・研修内容の検討、確認を学校側と綿密に行い、意見交換を積極的にする。 ・研修目的、形態に応じた指導実施の準備、作成 実施 ・操作等の説明及び操作実習での指導、助言を行う。 留意点 ・SEはわかりやすい言葉での説明を心がける。 ・研修開始の少なくとも1時間前には学校に入りソフト・資料の準備をする。 ・特に初級レベルの教職員に対しては、時間的余 裕を見て、コンピュータアレルギーにならない よう注意する。 |
|
学校側の活動内容と留意点 |
・事前に学校のシステムをSEに伝えておく。 ・児童生徒のコンピュータに関する技能や学習経験について知らせておく。 ・指導案で、授業のねらいや流れを明確にし、SEが補助しやすいように配慮する。 ・SEの授業での役割などを確認しておく。 実施 ・授業等において支援を受ける。 留意点 ・SEはあくまでも補助であり、児童生徒に対しての指導は、教師が行うということを忘れないようにしたい。 ・児童生徒へSEを紹介し、「○○先生」あるいは「○○さん」と児童生徒が質問しやすい雰囲気づくりをする。 |
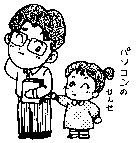
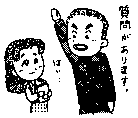
|
SE側の作業内容と留意点 |
・事前に学校のシステムを点検確認しておく。 ・授業者と連絡を取り合い、授業での役割を確認しておく。 ・学習のねらいや流れを授業者と確認し、授業に関する基礎的な知識を身につけておく。 実施 ・児童生徒の技術的なつまずきに対し助言する。 留意点 ・児童生徒の年齢を考えた、わかりやすい言葉で説明する。 ・児童生徒へは明るく声をかけ、技術的なつまずきで落ち込ませないよう配慮する。 ・クラブ活動では、活動内容について事前に確認し、わかりやすく説明できるようにしておく。 |
|
学校側の活動内容と留意点 |
|
|
|
SE側の作業内容と留意点 |
・事前に学校のシステムを点検確認しておく。 ・部活動の指導者と連絡を取り合い、指導内容や役割を確認しておく。 実施 ・生徒への技術面での指導を行う。 ・個々の生徒への助言を行う。 留意点 ・わかりやすい言葉で説明する。 ・内容が広く、高度になることも考えられるため、それらに対応する知識が必要である。 |
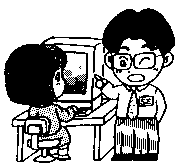
|
学校側の活動内容と留意点 |
・学校に導入されているオーサリングソフトを利用したソフトウェア開発について、校内で事前に検討する。 ・授業での活用場面や活用方法 ・コースウェア 実施 ・ソフト作成に関する助言を受ける。 留意点 ・学校に導入されていないソフトの準備をSEに依頼しない。 ・教職員ごとの個別相談はしない。質問事項は代表者が取りまとめSEに問い合わせるようにする。 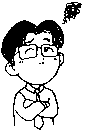 ・プログラム入力はSEの仕事ではない。 ・プログラム入力はSEの仕事ではない。 |
|
SE側の作業内容と留意点 |
|
|
|
学校側の活動内容と留意点 |
・希望する内容を具体的にSEに伝える。その際、学校の設備で説明が可能かどうかを確認する。 実施 ・最新技術動向について説明を受ける。 留意点 ・内容は授業実践に結びつくものとする。 ・説明方法は講演形式にするのか、デモ形式にするのかを確認しておく。 ・SEから入手した情報は、パソコン担当者が占有するのではなく、全教員に公開する。 ・事前に学校にある機材(OHP・パソコン等)の状況を知らせておく。説明の内容によってはSEに手配を依頼することも必要である。(機材の手配には日数を要するので早めに) ・説明を受ける時には、常に授業での活用を念頭において聞くよう心がける。 |
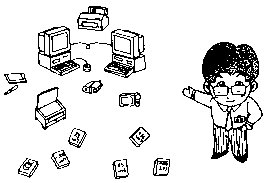
|
SE側の作業内容と留意点 |
・資料を収集し、必要に応じてFAXを利用して学校に送付する。 実施 ・コンピュータ分野における最新技術動向を教員に対して紹介する。 留意点 ・最新情報を紹介する時には一つのメーカーに偏ることがないように配慮する。 ・紹介の方法として、講演形式なのかデモ形式なのかを事前に打ち合わせておく。 ・説明をする際には専門用語を少なくし、できるだけ平易な言葉で説明するように心がける。 ・機器の手配が必要となる場合があるので、機器手配のルートを確保しておく。 ・授業に結びつけた内容説明を行うよう心がける。 ・各種展示会には積極的に参加し、常に最新の情報を入手するよう心 がける。 |
|
ライブラリ側の活動内容と留意点 |
・次のことについて内容を明らかにしておく。 ・保存ソフト一覧 ・施設概要(LANが組んである場合その形態) ・所有機器の台数 ・SEに指導してほしい内容 実施 ・施設設備を整えたり、運営したりする中で生じた疑問等について支援を受ける。 留意点 ・来訪者への対応はセンターの職員が行い、SEには技術的な面での援助を受ける。 ・設備、環境面について、全てをSEに任せるのではなく、センターの職員が施設設備を十分活用できるようになろうとする意識を持つ。 |
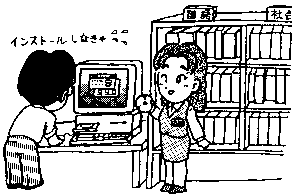
|
SE側の作業内容と留意点 |
|
|
|
学校側の活動内容と留意点 |
・学校における日常の利用状況を把握しておく。 ・相談したい内容を明確にし、SEに伝える。 実施 ・学校で困っていることについて助言を受ける。 留意点 ・あらかじめ相談内容を決めておく。可能な限り事前にSEに相談内容を知らせておく。 ・学校にある機材の不具合をSEに解決してもらうのではなく、コンピュータの活用方法や活用のための技術について相談する。 ・SEは資料の提供や知識の提供をすることが作業であり、それをどのように活かしていくのかは学校が考えることである。 ・学校に導入されているコンピュータをどのように活用するのかを相談することであって、決して個人持ちのパソコン等の相談の場ではない。 |
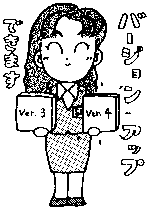
(7)その他技術面に関する相談
|
SE側の作業内容と留意点 |
|
実施 |