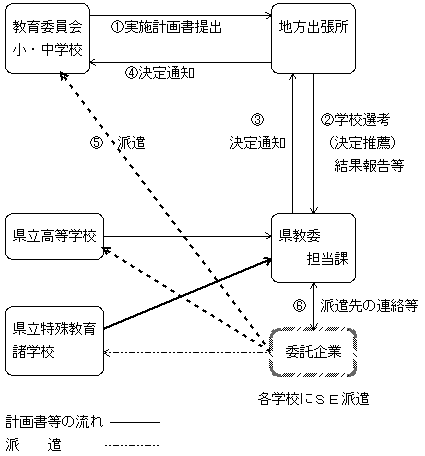参 考 資 料
1.「情報処理技術者等委嘱事業」の現状
本事業がスタートして3年が経過した。各自治体ではコンピュータの導入が進む中、コンピュータ教育に関する教員への研修も盛んに行われている。それに伴って、情報処理技術者等の活用も進み、多くの自治体で本事業が実施されるようになってきた。また、未実施の自治体についてもほとんどが今後実施していきたいと考えている。
1)実施自治体の推移
平成6年度 2自治体
平成7年度 28自治体(政令指定都市4を含む)
平成8年度 42自治体(政令指定都市5を含む)
2)平成8年度の実施状況
① 地区別の実施状況
北海道・東北:7(1) 関東 :4(1) 東海・北陸:9
近畿 :3 中国・四国:9(1) 九州 :10(2)
(括弧内は政令指定都市)
② 活用方法
コンピュータに関する研修(県や市主催) 65%
コンピュータに関する研修(各学校で) 56%
コンピュータの環境面に関する相談、支援 49%
最新の技術動向等についての情報収集 44% など
3)データベースの状況(平成9年3月末)
①企業数及びSE数
企業数 : 510社 SE数 : 5533名
(地区別企業数及びSE数)
| |
地 区 |
企 業 数 |
S E 数 | | 北海道・東北 | 139社 | 734名 | | 関東 | 455社 | 2999名 | | 東海・北陸 | 235社 | 1398名 | | 近畿 | 216社 | 1233名 | | 中国・四国 | 120社 | 613名 |
| 九州
|
151社
|
822名
|
| |
(都道府県別勤務可能数を合計した延べ数)
②SEの年齢及び経験年数(平均値)
|
|
|
|
人 数
|
年 齢
|
SE経験
|
インストラクタ歴
|
|
男 性
|
4192名 |
36才 |
8.1年 |
3.9年 |
|
女 性
|
1341名 |
31才 |
4.8年 |
3.2年 |
|
全 体
|
5533名 |
35才 |
7.3年 |
3.7年
|
|
|
③(財)コンピュータ教育開発センターから教育委員会への情報提供
平成8年度中に25の自治体に情報提供を行った。
本県では、平成8年度より次のような事業計画のもと、「情報処理技
術者等の派遣事業」を実施した。
1.授業の目的
民間の情報処理技術者等を県内の小・中・高及び特殊教育諸学校へ派遣して教員研修やコンピュータを利用した授業等の技術補助・助言を行い、もって、情報教育の推進を図る。
2.派遣する情報処理技術者等
「情報処理能力の促進に関する法律」に基づく資格を有する者等
3.平成8年度派遣計画(240校に派遣)
(1)小中学校
前期( 6月10日~11月 1日) 105校に派遣
後期(11月 4日~ 3月14日 105校に派遣
(2)高等学校及び特殊教育諸学校
通年( 6月10日~ 3月14日) 30校に派遣
4.派遣日数
1校当たり、1週間の内3日間(6時間/1日)とする。
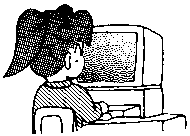
5.派遣校の決定
県教育委員会が次の事項をもとに決定する。
・市町村教育委員会が推薦する学校
・学校より提出された実施計画書
・コンピュータの整備状況(2人に1台以上)
6.情報処理技術者等に委託する業務内容
(1)コンピュータを利用する授業の補助
(2)コンピュータ操作に関する教員の校内研修の指導
(3)コンピュータの操作の支援及び相談、インストール等の技術支援
7.具体的な活用例
(1)授業補助、コンピュータを利用する授業の補助又は操作に関する指導の補助(導入機器及びソフト等を用いた授業の補助)
(2)研修の主な内容
・授業におけるコンピュータ操作の支援
・市販ソフト(音楽ソフト等)を使っての実技指導補助
・導入ソフトウェアの検証、操作支援
・基本的応用ソフト(統合型)の基本的操作実習
・教育用ソフトウェアの効果的な活用方法の紹介及び実習
・簡易プログラム言語を利用したプログラミング操作指導及び支援
・専門学科(商業、情報基礎等)の基礎学習に伴う補助
・OS講習(初心者向け)
平成8年度の実施内容から
実施内容の1つである「コンピュータを利用した授業の補助及びコンピュータの操作に関する指導の補助」において、次のような内容で実施した。
1.学校に導入されている学習用ソフトを活用した授業補助
(小学校)コンピュータに慣れ親しむといった感覚で実施した。
(中・高)情報基礎を活用した授業展開ができるように実施した。
2.学校に導入されているアプリケーションソフトを活用した授業
(小学校)それぞれの機能がよく分かるように工夫しながら実施した。
(中・高)アプリケーションソフトの特性を考慮に入れながら実施した。
3.授業に伴うコンピュータの操作に対する教員の補助
(小学校)教員一人一人にきめ細かく操作補助を行った。
(中・高)教員相互のモチベーションが上がるように工夫し、実施した。
4.コンピュータシステムの基礎構成、各部の機能説明等補助
(中学校)メーカーにとらわれることなく基本機能を重点に実施した。
(高 校)メーカーごとの特性を考慮して最近の動向も踏まえ実施した。
5.プログラミング学習補助
(中学校)プログラミング技術の考え方、方法などを効果的に実施した。
(高 校)言語の基礎的技術とコーディング規約などを補助し実施した。
成 果
1.コンピュータに対する関心が深まった。
今までコンピュータに触れたことがない教員が興味を持つようになり、コンピュータに畏れを抱いていた教員の意識改革に効果的であった。また、教員がコンピュータに触れる機会が増加した。
2.操作技能が向上した。
各学校で研修計画を立てることができ、教員個々の空き時間等に個別指導を受けたり、実態に応じた丁寧な指導を受けたりすることも可能であった。そのことにより、教員個々の操作技能の向上につながった。
3.学校にあるソフトウェアが使えるようになった。
学校に導入されているものの、今まであまり使われなかったソフトウェアを使って、操作の仕方や授業での活用方法について研修を行ったことにより、授業に活かそうとする意欲が高まった。
4.コンピュータを活用した授業に安心して取り組めた。
情報処理技術者等が授業の補助として教室にいてくれることにより、コンピュータの操作に自信のない教員も安心して授業に取り組むことができた。また、児童生徒も専門的な助言や援助を受けることができ、意欲的な学習態度が見られた。
課 題
1.情報処理技術者等との十分な事前打ち合わせが必要である。
各学校の担当者と情報処理技術者とで事前の打ち合わせを行うことになっていたが、十分な打ち合わせが持てなかった学校では、研修内容と学校の希望とにズレが生じた。
2.研修に対して教員の共通理解を図っておくことが大切である。
「情報処理技術者等の派遣事業」について、全職員への周知が不足していたため、研修の目的等が定まらず、十分な活用ができなかった学校もあった。
3.研修成果を授業に生かすような学校体制作りが必要である。
研修を行ったことにより、教員個々の技能向上は見られたものの、個人研修の域を出ないままに終わっている学校も見られる。学校全体でコンピュータ教育に取り組むことが研修成果を生かすことにつながる。
4.派遣日数を増やす必要がある。
1校当たり3日間の派遣であったため、教員がコンピュータに慣れたところで終わってしまうという状況が見られた。そのため、研修により新たに生じた疑問等が解決しないままになってしまった学校があった。
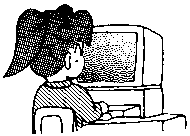 5.派遣校の決定
5.派遣校の決定 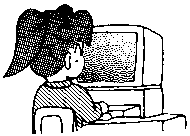 5.派遣校の決定
5.派遣校の決定