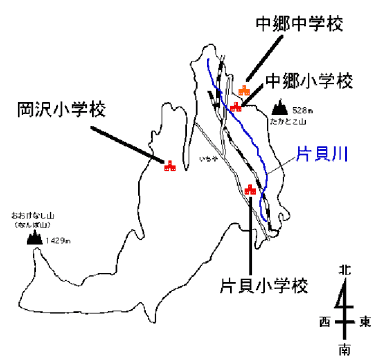
「共同で取り組む川調べ」
〜新潟県中郷小学校の実践より〜
○はじめに
本校(児童数250名、11学級、山本雄徳校長)は、新潟県の南部、長野県境近くに位置している。夏は蒸し暑く冬は寒い日本海側特有の気候をみせ、四季の変化が非常にはっきりしている。特に冬季間は、2m以上も雪が積もる豪雪地帯である。学校の周りにも緑が多い。校庭に続く夕日が丘と呼ばれる村所有の小高い丘は、雑木林が茂り、学校のがけ下を片貝川が流れ、子供たちが自然に親しむのに格好の場所である。このような恵まれた自然環境を教育過程の中で取り入れることによって、子供たちの心にみずみずしい感動を与えることができると思われる。
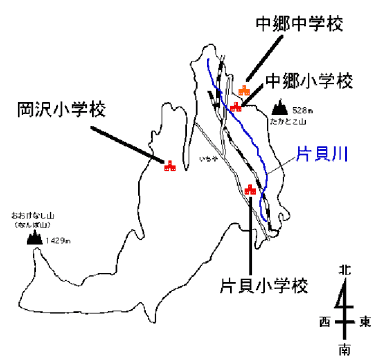
村内の小学校との連携
共同調査や共同学習を行うためには、事前の打ち合わせが大変重要である。昨年度からの実践で、インターネットを利用した交流では、距離的隔たりから意思の疎通がうまく行かず中途半端な交流で終わることが多かった。
そこで、同じ村内の学校の強みを生かし、お互い顔を見合わせて話し合いを行った。片貝小学校もすぐ下を片貝川が流れており、簡単に川の調査ができることが分かり、両校で負担のない程度に川の調査をおこなっていくことにした。
・既存メディアを用いて情報交換
中郷小学校と片貝小学校との情報のやり取りは、ファックス、電話、教育委員会ポスト、インターネットを利用した。両校にはインターネットに対する習熟度に違いがあった。そこで、電子メール以外のファックスや委員会ポストを利用して情報交換を積極的に行った。情報交換の手順は以下の通りである。
①本校の児童が調べた川の情報をホームページに載せる。
②本校のホームページを見た片貝小学校の児童が感想をファクスで中郷小学校に送る。
③片貝小学校から送られた写真や感想を中郷小学校の方でホームページ化し、本校のサーバーに載せる。
・共同調査の概要
7月に上越マルチメディアフェスティバルが行われた。その中で上越市内の小学校が川の共同調査を行なった。その動きに合わせて片貝小学校、中郷小学校も川の共同調査を本格的に行うことにした。また、本校のホームページを見た新潟県松之山町の松之山小学校も共同調査校として参加した。共同調査は、「水の汚れ」、「かわらの鳥」、「かわらの植物」、「土手の様子」、「川の周りの様子」、「流れの様子」の7項目で行った。
本校の児童は、自分たちの片貝川がきれいであると思っていたが、片貝小学校のある上流域の方が、たいへん水がきれいであること、自分たちの流域では見られなかった魚が上流域にはたくさんいること、川原の様子が大きく変化することなどを知った。また、上流の片貝川のきれいな水が、下流の中郷小学校までくるとかなり汚れてくることから、人家や工場などの影響で水質が悪化することも知った。
2 今後の予定
○村内小学校3校による積雪量共同調査
中郷村の中郷小学校、岡沢小学校、片貝小学校の3校は、同一村内でも地理的条件にかなり差がある。そのため降雪期の積雪量にかなりの差があることが予想される。そこで、3校の児童が毎日調べた積雪量結果をインターネットで送り合い、本校のホームページにデータを載せることを計画している。本校ではWEB-TVが稼働中なので、他校に本校の積雪状況をリアルタイムで知らせることも可能である。
3 最後に
川や雪など地域に関係が深いものを共通のテーマとして、ネットワークを利用した共同調査を村内の小学校と行い、自分たちの住む地域を見つめ直していきたい。そのような活動を図りながら、他地域との交流を今後図っていく予定である。