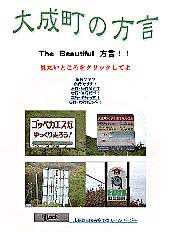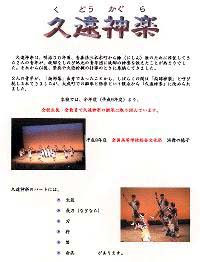丂杮峑偺儂乕儉儁乕僕偼丄暯惉俋擭侾寧偵偼偠傔偰岞奐偝傟偨丅偙傟偼丄僥僉僗僩宍幃偺俫俿俵俴僄僨傿僞傪巊偭偰巹偑嶌惉偟偨傕偺偱偁偭偨丅帺暘偱幚嵺偵儂乕儉儁乕僕傪嶌惉偟偰傒偰丄乽偙傟偼庼嬈偱巊偊傞乿偲敾抐偟丄憗懍丄俀寧偐傜庼嬈偵庢傝擖傟丄梻擭偵傑偨偑偭偨宍偱庼嬈傪峴偭偨丅
丂儅僔儞偺惂栺傕偁傝丄僼儕乕僂僃傾偺俫俿俵俴僄僨傿僞傪巊偄丄僞僌傪慻傫偱嶌惉偟偨丅杮峑惗搆偵偲偭偰丄娙扨側塸扨岅偱偁傞僞僌傕旕忢偵擄夝側傕偺偱偁傝丄榑棟揑偵僾儘僌儔儉傪慻傓傗傝曽偺巜摫偼旕忢偵崲擄偱偁偭偨丅
丂偙偆偟偰惗搆偑嶌偭偨儂乕儉儁乕僕偼丄暯惉俋擭俇寧偵岞奐偝傟偨丅偙偺儁乕僕偺拞偵偼乽戝惉挰偺曽尵乿傗嫿搚寍擻偱偁傞乽媣墦恄妝乿偺儁乕僕傪惙傝崬傒丄抧堟怓朙偐側傕偺偵偟偨丅
|
丂 |
|
丂摉弶丄儊乕儖偺岎姺偼僀儞僞乕僱僢僩愙懕婡侾戜偺傒偱偟偐偱偒側偐偭偨丅偦偺偨傔丄惗搆偺棙梡偼傎偲傫偳柍偔丄愱傜嫵堳偑帠柋揑偵僀儞僞乕僱僢僩儊乕儖乮埲壓儊乕儖乯傪棙梡偟偰偄傞偵偲偳傑偭偰偄偨丅
丂偟偐偟丄僀儞僞乕僱僢僩傪嫵堢偺尰応偵摫擖偟傛偆偲偡傞応崌丄乽惗搆偵懱尡偝偣傞乿偙偲偑昁恵偲側傞丅偦偙偱丄傑偢暯惉俋擭搙偵偼俴俙俶偺側偐偱惗搆摨巑偺儊乕儖岎姺傪偼偠傔偨丅庢傞偵傕懌傜側偄儊乕儖偺撪梕偱偁偭偨偑惗搆偵偲偭偰偼偄偒偄偒偲妝偟偔儊乕儖傪岎姺偟丄惗搆偼儊乕儔乕偺憖嶌偺巇曽丄僱僠働僢僩偵偮偄偰傑偢俴俙俶偺拞偱妛傫偩傢偗偱偁傞丅
丂偦偺屻丄恄撧愳導棫戝巘崅摍妛峑偐傜儊乕儖岎姺傪娷傔偨妛峑娫岎棳偺埶棅偑偁傝丄惗搆偼偼偠傔偰奜晹偵儊乕儖傪弌偡婡夛偵宐傑傟偨丅杮峑偺傾僇僂儞僩偑堦偮偟偐側偄偨傔丄惗搆偑彂偄偨偄偔偮偐偺儊乕儖傪巹偑侾捠偺儊乕儖偵傑偲傔丄戝巘崅峑偺戙昞傾僪儗僗偵憲怣偡傞庤抜傪偲偭偨丅偙偺曽朄偩偲丄惗搆偑弌偡儊乕儖偺撪梕傪僠僃僢僋偱偒傞偙偲偼儊儕僢僩偩偑丄戝恖悢偺応崌嫵堳偵憡墳偺晧扴偲側傞丅
丂廬棃偺僀儞僞乕僱僢僩儊乕儖岎姺偼丄杮峑偺惗搆A偲憡庤峑惗搆B偺乽侾懳侾乿偺傗傝庢傝偱偁傞偨傔丄俀恖偺榖戣偼懠偵廃抦偝傟偵偔偔丄懡偔偺惗搆娫偱嫟捠偺榖戣偑帩偰側偐偭偨丅傑偨丄帺暘偑嫽枴傪帩偭偰偄傞偙偲傪榖戣採嫙偟偨偔偰傕丄扤偵摉偰偰儊乕儖傪弌偟偰傛偄偐傢偐傜側偐偭偨傝丄榖戣傪帩偪偐偗偰傕丄偦偺儊乕儖傪庴偗庢偭偨恖偑嫽枴傪帵偝側偄応崌傕偁偭偨丅偙偺応崌丄惗搆偼帺傜偡偡傫偱榖戣傪採婲偡傞偙偲偵掞峈姶傪帩偪丄徚嬌揑偵側偭偰偟傑偭偨丅偙偺傛偆側揰傪夵慞偡傋偔丄戝巘崅峑偱怴偨偵奐愝偝傟偨儊乕儕儞僌儕僗僩傪棙梡偝偣偰偄偨偩偔偙偲偲側偭偨丅
丂儊乕儕儞僌儕僗僩傪棙梡偡傞偲丄惗搆偑榖戣採婲偡傞偲嫽枴娭怱偺偁傞嶲壛幰偑斀墳偟丄偡傋偰偺儊乕儖偼偡傋偰偺嶲壛幰偵攝怣偝傟丄妶敪側堄尒岎姺丒摙榑傊敪揥偟偰偄偔丅惗搆偼嫟捠偺榖戣傪帩偮偙偲偑偱偒傞偺偱偁傞丅
丂帺暘偺搳偘偐偗偨榖戣偵丄偨偔偝傫偺恖偨偪偑斀墳傪帵偟偰偔傟傞偲惗搆偼偆傟偟偔側傝丄傑偨偝傜偵偦偺僥乕儅偵偮偄偰榖傪怺傔丄愊嬌揑側僐儈儏僯働乕僔儑儞偵敪揥偟偰偄偔傛偆偵側偭偨丅
丂偙偺傛偆側儊儕僢僩偑偁傞堦曽丄帺暘偺彂偄偨儊乕儖偑偡傋偰偺嶲壛幰偵尒傜傟傞偲偄偭偨柺偱徚嬌揑偵側傞惗搆傕弌偰偒偨丅懡偔偺恖偨偪偵帺暘偺峫偊傗婥帩偪傪揱偊傞偙偲偑戝愗側僐儈儏僯働乕僔儑儞側偺偩偲偄偆堄幆傪帩偨偣傞巜摫朄偺岺晇偑昁梫偲姶偠偨丅