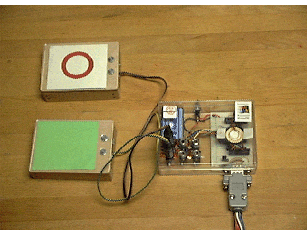
4.9.4 インターネット利用におけるアクセシビリティの研究
肢体不自由児がパソコンなどの情報機器を利用するときの大きな課題は、運動障害があるため標準のキーボードやマウスの操作が困難であるという点にある。肢体不自由児の運動障害の状態は多様であり、一人一人の子どもにより要求されるアクセシビリティはすべて異なる、と言っても過言ではない。また、子どもたちの運動障害の状態は時間の推移とともに変化する。すなわち、操作の巧緻性が向上する子どもたちもいれば、低下する子どもたちもいる。なかには、パソコンの操作を開始してしばらくすると、疲労等のため操作の巧遅性が低下し、細かい配慮を必要とする子どもたちもいる。したがって、肢体不自由児のアクセシビリティは、子どもたちとかかわり手(支援者)の両者がよりよいアクセシビリティを求めて試行する過程(フォローアップ)が重要となる。
このような肢体不自由児に対するインターネット利用におけるアクセシビリティは、(A)端末機のアクセシビリティ(運動障害がある子どもたちが利用できるパソコンの操作環境)と、(B)提供データのアクセシビリティ(インターネットで提供されるデータの提供の仕方)、の2面を検討する必要がある。
(A)端末機のアクセシビリティ
インターネットを利用する場合、現状では、パソコンを使って接続する場合が多い。したがって、運動障害のある子どもたちがインターネットに接続されている端末機(パソコン)を使用して、インターネットを利用するときに要求されるアクセシビリティは、スタンドアロン環境のパソコンを利用するときのアクセシビリティとほぼ共通であると考えてよい。
(1)パソコン利用のアクセシビリティ
従来、肢体不自由児のパソコン利用において要求されてきたアクセシビリティは、文字の入力に関するアクセシビリティ、すなわち 「キーボード操作のアクセシビリティ」が中心であった。しかし現状では、GUI 環境の普及と共に「マウス操作のアクセシビリティ」 が大きな課題になっている。
現在、配慮されている肢体不自由児のアクセシビリティの対応方策の概要を、以下に挙げる。
①標準キーボードのアクセシビリティ
同時に2つのキーを押さえることができない場合、修飾キーをロックし次の打鍵を待って入力文字を確定する順次入力機能。不随意運動があり正確にキーを押さえられない場合、キーボードに装着するキーガード。他に、キーリピート条件設定機能、キー入力確定条件設定機能がある。
②入力エミュレーションによるアクセシビリティ
〔ソフトキーボード〕
画面上にキーボードが表示され、ジョイスティックやタッチパッド等のポインテ ィングデバイスで選択する。あるいは、外部スイッチでスキャン選択する。
〔マウス入力のエミュレーション〕
マウスをキーボードのテンキーを使って操作する。また、1~2個の外部スイッチで操作する。
③代替入力装置によるアクセシビリティ
〔キーボードの代替〕
小~大型の50音配列ひらがなキーボード、小~大型の標準キーボード等の入力装置を用いる。
〔マウスの代替〕
数個の外部スイッチの操作でマウスを代替する入力装置、トラックボールやタッチパネル等の入力装置を用いる。
④操作スイッチの工夫によるアクセシビリティ
指、瞬き、視線等スイッチを操作する部位、引く、触れる、曲げる等の操作方法他、スイッチの数、形態、特性を工夫する。
⑤入力方法によるアクセシビリティ
〔直接法〕
操作スイッチ(キー)の数と選択肢の数がほぼ同数の場合の選択法。手の指や足の指、口にくわえたスティック、レーザー光線などで直接文字等を選択する。
〔間接法〕
操作スイッチの数が選択肢の数より少ない場合の選択法。以下の選択法がある。
・オートスキャン(自動走査)方式
・ステップスキャン(逐次操作)方式
・コード入力方式(モールス信号入力など)
これらの対応方策のうち、①と②の項目の大部分は市販のOS(Macintoshの「Easy Access」やWindows95/NT4.0の「ユーザー補助」)がサポートするアクセシビリティの機能や市販・フリーソフトウェアとして供給されている「入力支援ソフトウェア」などを利用して対応することできる。
③のキーボードやマウスの機能を代替する「入力装置」は、市販の障害者用入力装置を利用して対応することができる。しかし、現在市販されているこれらの入力装置は、パソコンのキーボード端子やマウス端子に接続する仕様となっているため、パソコンの機種が異なると使用することができないという不都合が生じている。このような不都合を改善する手だてとして、GIDEI(The General Input Device Emulating Interface)という規格が提案されている。Windows95/NT4.0 がサポートしている「シリアルキー」はGIDEI を実用化した支援ソフトウェアであり、Windows95/NT4.0やMacintosh の日本版での動作が確認されている。GIDEIに対応したキーボードやマウスの代替入力装置であれば、パソコンの機種が異なっても利用することができる。
④と⑤については、子どもたちの運動機能の状態や利用するアプリケーション・ソフトウェアにより他の対応方策と相互に関連した対応が求められることになる。
(2)インターネット利用のアクセシビリティ
〔現状〕
肢体不自由児におけるインターネット利用のアクセシビリティの現状を、電子メール及びWWWの利用という視点から考察した。
①電子メール
(a)メールの受信
最近のGUI 環境で動作するインターネット・メーラー・ソフトウェアの多くは、マウスによる操作だけでなく、キーボードによる操作(ショートカット・キー)で受信メールを開いて読むことができる機能を有している。このような機能は、マウスの操作やマウスの機能を代替する入力装置の利用は困難であるが、キーボードの操作が可能な子どもたちには、アクセシビリティの向上をもたらしている。
また、キーボードの操作が困難な子どもたちに対しても、ショートカット・キーに対応した数個の外部スイッチを接続し、これらのスイッチを操作することにより電子メールを読むことが可能となる。
(b)メールの送信
電子メールを書くには、前項で述べた「文字の入力に関するアクセシビリティ」が課題となる。文字の入力のアクセシビリティは、前述した「代替入力装置」や「ソフトキーボード」で対応する必要がある。なお、書いた電子メールはショートカット・キーの操作で送信することができる。
②WWW
(a)情報の発信
WWWで情報を発信するには、HTMLスクリプトを作成しなければならない。最近市販されているHTMLツール・ソフトウェアは、マウスによる操作だけでなくショートカット・キーでも操作できるが、文字の入力が必要な場合もあるため文字入力のアクセシビリティも要求される。
また、画像や音声などのマルチメディア情報を含めて提供(発信)しようとするときには、これらのアプリケーション・ソフトウェアのアクセシビリティが要求される。
(b)閲覧
WWWの閲覧には、WWWブラウザの画面に提示されるホットスポット(ボタン)にマウス・カーソルを合わせ、マウススイッチをONする操作が必須である。一般に使用されているポインティング・ディバイス(マウスやトラックボールなど)の操作が困難な子どもたちには、マウスカーソルの移動をスイッチの操作に置き換える前述②の「マウスキー」や③の「マウスの代替入力装置」を利用することができる。
しかし、これらの入力方法は、数個のスイッチ(あるいはテンキー)を操作してマウスカーソルをホットスポットに合わせる操作(ポインティング操作)を必要とする。このため、数個のスイッチの操作が難しい子どもたちや、不随意運動が強い子どもたちには利用することが困難である。
このような困難を改善するために、「キーボード・ナビゲーション(Keyboard Navigation) 」と呼ばれる操作方法が提案されており、すでに一部のアプリケーション・ソフトウェアで実現されている。「キーボード・ナビゲーション」はWWWの閲覧のようにGUI やハイパーテキストを利用するとき、マウスカーソルをホ ットスポットに合わせる操作(ポインティング操作)を必要としない操作方法である。
以下に、あるWWWブラウザでサポートされている「キーボード・ナビゲーション」の一部を紹介する。
1)〔Tabキー〕 を入力すると「キーボード・ナビゲーションのカーソル(ホットスポットを枠で囲む)」がホットスポットを示す。続けて〔Tabキー〕を入力すると、「キーボード・ナビゲーションのカーソル」が次のホットスポットに移る。
2)〔Shift+Tabキー〕を入力すると、「キーボード・ナビゲーションのカーソル」が逆方向に移動する。
3)〔Enterキー〕を入力すると、「キーボード・ナビゲーションのカーソル」が示すホットスポットが選択されハイパーリンクが起こる。
4)〔Ctrl+Tabキー〕を入力すると、次のフレームに進む。
5)〔Shift+Ctrl+Tabキー〕を入力すると、前のフレームに戻る。
6)〔Ctrl+Pキー〕を入力すると、カレントページを印刷する。
このように「キーボード・ナビゲーション」は、標準キーボードの特定のキーを操作するにより、WWWの閲覧を可能にしている。また、前述したGIDEI(シリアルキー)の機能を併用して、「キーボード・ナビゲーション」の操作キーの機能を設定した「外部スイッチ」を接続して利用することも可能である。すなわち、(マウスをもちろんのこと)キーボードの操作が困難な子どもたちであっても、子どもたちが利用できる1~2個のスイッチを操作することにより、WWWを閲覧することが可能となる。
〔課題〕
①肢体不自由児がインターネットを利用して、電子メールを作成したり、WWWで情報を発信したりしようとするときには、スタンドアロン環境でパソコンを利用するときと同様に、文書や画像、音声などを作成するアプリケーション・ソフトウェアのアクセシビリティが要求される。これらのアプリケーション・ソフトウェアがマウスによる入力操作のみの偏らない、例えばキーボード・ナビゲーションのような肢体不自由児の入力を援助する操作機能をサポートすることが期待されている。また、文書作成に関しては肢体不自由児が入力しようとする単語や文章を予測して入力操作の軽減をサポートする機能の開発とその供給が期待されている。
②GIDEI(シリアルキー)は、最近提唱されているユニバーサル・デザイン(Universal Design )の一環として位置づけられ供給されている。ユニバーサル・デザインは「製品や生活環境など可能な限りすべての人が利用することができるように設計し、供給しよう」とする理念である。しかし、我が国で普及している一部のパソコン機種では、標準機能としてサポートされているはずのGIDEI(シリアルキー)が動作しない。また、GIDEI(シリアルキー)が動作する機種であっても、日本語キーの一部が動作しないなどの不都合がある。このような状況が、GIDEI(シリアルキー)が利用できる英語圏などの国々と比較して、我が国の肢体不自由児により大きなハンディキャップを負わせる結果をもたらすことが懸念される。関係企業の早期対応が求められている。
③前項のような状態が、関連企業に対してGIDEI(シリアルキー)に対応した入力デバイスを開発しそれを供給しようとする意欲を削ぎ、結果としてユニバーサル・デザインの理念などが社会に浸透することを阻むことになることも懸念される。
(B)提供データのアクセシビリティ
前述のように、肢体不自由児はマウスやキーボードなどの操作が困難な場合が多く、子どもたちが操作できる代替入力装置や外部スイッチなどを使用してインターネットを利用することができる様々な工夫がなされている。しかし、多くの肢体不自由児はこれらの入力装置を利用しても操作に時間を要し、また疲労も大きい。したがって、データ提供の仕方についても、肢体不自由児が簡単な操作や手順で、容易に必要とする情報を入手できるような配慮が求められる。
例えば、WWW を閲覧するときなど、連続してスクロールしなければ必要な選択肢(ホットスポット)得られない場合がある。スクロールバーの操作が困難な肢体不自由児を配慮して、できる限り1画面で提示することがのぞましい。また、脳性まひがある肢体不自由児は視覚障害を合併していることが多い。図と地の色やコントラスト、文字の大きさなどの配慮も必要である。
(1)2点スイッチでWWWが閲覧できる入力ディバイスの試作事例
前述したGIDEI(シリアルキー)とキーボード・ナビゲーションの機能を利用して、2つの外部スイッチでWWWを閲覧できる入力ディバイス(以下、Wing-SKと呼ぶ。)を試作した。
Wing-SKはBASIC Stamp II(後述)と呼ばれる小型のマイコンのような物を利用して作った。これは比較的容易にプログラムを組むことができ、RS-232Cのインターフェースなどを搭載している。このため、スイッチのコネクターなど数個の外部部品を配線するのみでWing-SKのハードウェアを作製することができた(図4.9.1)。
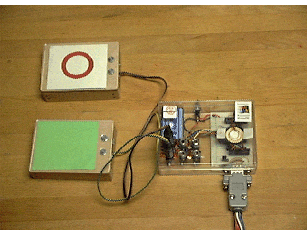
これに2個のスイッチをつなげ前述するような「キーボードナビゲーションを実現するWWWブラウザ」が入っている「GIDEI(シリアルキー)が動作するコンピュータ」に接続することで、マウスを使わなくとも2点スイッチを操作することで自由にWWWのホットスポットをクリックすることができた(図4.9.2)。
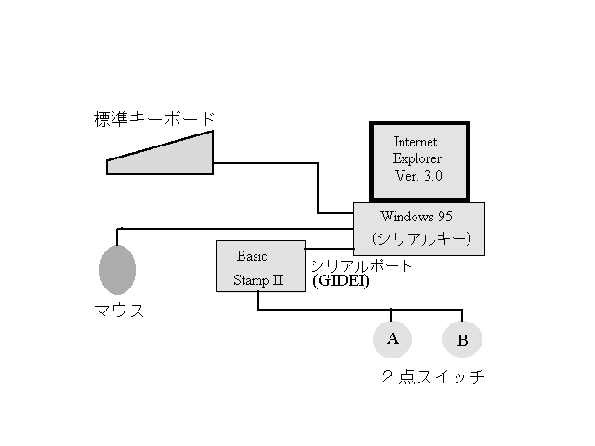
試作したWing-SKでは以下の2通りの操作方法でキーボードナビゲーションするようにした。
(a)2点スイッチ逐次スキャン
図4.9.2において、Wing-SKに接続したスイッチ〔A〕をONすると、逐次〔Tabキー〕の信号が送出される。(スイッチ〔A〕を押し続けても、〔Tabキー〕の信号は1度しか送出されない。)すなわち、スイッチ〔A〕を押すごとに、「キーボード・ナビゲーションのカーソル」が提示フレームのホットスポット(ボタン)に逐次移動する。選択したいホットスポットに「キーボード・ナビゲーションのカーソル」を移動させたときに、スイッチ〔B〕をONすると〔Enterキー〕の信号が送出され、ハイパーリンクが起こる。
(b)2点スイッチ自動スキャン
スイッチ〔A〕をONし続けると〔Tabキー〕の信号が約1秒間隔で送出され、OFFするとその信号が止まる。すなわち、スイッチ〔A〕を押すと「キーボード・ナビゲーションのカーソル」がホットスポットをオートスキャン(自動走査)する。選択したいホットスポットに「キーボード・ナビゲーションのカーソル」が移動したときにスイッチを離し、スイッチ〔B〕をONすると〔Enterキー〕の信号を送出されホットスポットが選択される。
このように、Wing-SKは制御ソフトウェアにより子どもたちに要求される多様な入力方法に対応できる可能性を有している。
※BASIC Stamp II
Wing-SKは、Parallax社の小型モジュールBASIC
Stamp IIを使用した。BASIC StampIIはBASICインタプリタを内蔵したCPUと2KバイトのEEPROM、16ビットの双方向I/O、RS-232Cのインターフェイスなどを搭載している。このため、スイッチのコネクタなど数個の外部部品を配線するのみでWing-SKのハードウェアを作製することができた。BASIC
Stamp IIは消費電力が少く、乾電池で動作させることができた。また、BASIC
Stamp IIの制御ソフトウェアはBASIC言語が利用できるため容易に作成、変更することが可能であり、制御ソフトウェアは簡単な操作でBASIC
Stamp IIにアップロードし、作動させることができる。Wing-SKはGIDEI(シリアルキー)に対応にした仕様とし、図4.9.2に示すようにパソコンのシリアルポートに接続して使用した。
(2)今後の展望
肢体不自由児の運動機能の状態は多様であるため、インターネット利用のアクセシビリティも多様な仕様が求められている。このような要求に対応するには、肢体不自由児のアクセシビリティを細部にわたり援助する自由度の高いハードウェアやソフトウェアが数多く供給されることが必要である。そうなれば、学校現場の援助者はこれらのハードウェアやソフトウェアを子どもたちの実態に沿うよう選択し、組み合わせて対応することが可能となる。
GIDEI(シリアルキー)やキーボード・ナビゲーションは、肢体不自由児のアクセシビリティを援助するための有効な選択肢として、その存在意義が大きい。インターネットを利用するときに使用するWWWブラウザやインターネット・メーラ、そして文書や画像、音声などを処理するアプリケーション・ソフトウェアが、キーボード・ナビゲーションのような機能をサポートすることが求められる。特に文書作成については、機種が異なっても利用できる GIDEI(シリアルキー)に対応した「50音ひらがなキーボード」や、単語入力予測や文書校正などの援助機能をサポートした「ソフトキーボード」などの供給が求められている。
最近、キーボード・ナビゲーションに対応した教育用ソフトウェアやGIDEI(シリアルキー)に対応した入力ディバイスを開発、供給しようとする企業があることは、インターネットのアクセシビリティについても明るい展望をもつことができよう。
このページの先頭へ
目次へ
(1)障害児の抱える情報不利
横須賀市の人口は三十数万人である。日本全国で手帳を持っている視覚障害者の人口とほぼ一致する。仮に、視覚障害者がすべて横須賀市に引っ越してきたら、どうなるだろうか?横須賀の新聞はすべて点字や拡大文字になり、コンビニエンス・ストアでは、点字用紙や白丈が売られ、お隣さんと新しい音声合成装置のことを相談できる。学校でも視覚障害者に関連した情報がどんどん交換されるだろう。
ところが、30万人の視覚障害者は、日本全国ばらばらにちらばっているのである。全国版の新聞には、視覚障害者の専用ソフトの話はまず載らない。全体の人口からすると、割合が少なすぎるのである。これは、つとに指摘されているマイノリティ問題であって、本来は障害者かどうかという問題ではない。
WHOによって、「障害」という概念には3つの異なるものが含まれていることが指摘されてきた。最初の2つは、いわゆる障害に直接関係している、身体的な特徴としての障害であるImpairment と、その結果生じる機能障害、Disabilityがあるが、最後の障害 Handicap は、社会的不利であり、これは、障害者がマイノリティであるために生じる問題と言える。
マイノリティは常に自分たちに有用な情報が流通しにくいという問題を抱えている。マジョリティと共有できる情報については問題ないが、マイノリティだけに必要な情報は、流通が極端に困難である。マスメディアが発達した現代では、情報はマスに対して流通しているので、マジョリティに対してだけに傾斜して情報が流通しやすくなっているわけである。顕著な例を挙げると、たとえば阪神大震災のとき、テレビでは、震災の後まだ1~2カ月のうちに、東京でもし同じクラスの地震が起こったらというような特別番組を流していた一方で、被災地の中の情報交換にはほとんど無力であった。言い換えると、マスメディアは震災の情報を被害者のためでなく、極端なことを言えば東京に住む人のために流したのである。つまり、被災者は、マイノリティであったために、マスメディアからの情報サービスの恩恵がわずかしか受けられなかったわけである。パソコン通信やインターネットといった新しいメディアがボランティアと連携して情報ボランティアの活躍場所として、もっと被災者と被災者の救援をするためのメディアとして活躍したことはあまり知られていないが、インターネットがマイノリティ問題の解決に有効であることを示す良い一例と言える。
マイノリティは、マスメディアのように流通コストの高いメディアは利用しにくい。つまり、流通コストの低いメディアでないと利用しにくいのである。マスメディアでは、マスに対して情報を提供しているために、高い制作・流通コストがペイしているが、少数派のための情報はマスへの報道の意味が少ないために抑制される。もし同様のシステムで全国に少数が散在しているマイノリティに対して報道する場合は、マジョリティに対するよりも流通コストは余計にかかってくる。マイノリティに対する情報提供は、このようにこれまでのメディアでは基本的に解決困難であった。この問題を解決するのが、インターネットやパソコン通信という新しいメディアである。パソコン通信にも同じ利点があるが、インターネットはパソコン通信よりもずっとオープンで、パソコン通信同士を結び付けることができるため、ユーザが情報の流通にかけるコストはさらに低い。
以上の点をまとめると、障害児にとってインターネットは健常児よりもずっと意味が大きいということができる。自分と同じ趣味や悩みを持つ子どもを探すのに、健常児なら自分の学校だけで足りてしまうかもしれないが、障害児の場合、隣の学校か、あるいは隣の県になってしまうかもしれないのである。障害児を担当する教員にとっても同じで、自分の担当の子どもと同じようなケースを抱える教員が同じ学校にいない可能性が高いのである。
このような情報不利が、すばらしい実践やアイデアに関する情報流通をはばみ、障害児やその教員が学習するために必要なコミュニケーションの機会を著しく奪っている。インターネットは、それを補償するメディアになりうるのである。社会的統合を目的としてインクルージョンされていながら、かつ障害児に手厚い専門的な教育をしていくチャンスが、インターネットで社会と繋がった特殊教育諸学校の教室にはあるといえる。
(2)技術的問題-視覚障害者のWWW利用
視覚障害者がインターネットにアクセスする場合、技術的問題もまだまだ残されているが、解決できない問題ばかりではない。むしろ、インターネットに世間一般の情報資源が移転するか、別のメディアと重複するように流通してくると、インターネットが視覚障害者にとって比較的バリアフリーに近いメディアであるだけに、視覚障害者のできることのレンジはずっと広がってきていると言える。視覚障害者にとって、インターネットに提供されている情報と、通常の印刷物として提供されている情報とどちらがバリアフリーかという議論はそれほど難しくない。通常の印刷物は、目で読むことを前提として作られた書き文字のメディアであり、そのままでは触覚や音声でアクセスできない。最近のアクセス・テクノロジーを用いて、たとえば OCR で触覚や音声という目以外の感覚で理解可能な状態に変換することは可能だが、OCRの変換効率は、印刷物のレイアウト、用紙の色や透け具合、印刷のかすれ具合、フォントのつぶれ具合などに著しく影響を受ける。その結果、自分だけでは変換できず人手を要する場合が相当程度残される。ところが、インターネット上に提供されている情報は、すでに変換済みなので、工程が1つ少ないという意味や変換効率100%であるという意味で、ずっとバリアフリーに近いのである。視覚障害者のための情報提供サービスが、伝統的に点訳や音訳であったことを考えると、そのサービスそのものがインターネットではすでに終わっているとも言えるわけである。また、最近では、視覚障害者のためのボランティアの仕事が、点訳や音訳から、電子化に移ってきていることも、このことを如実に表していると言える。
さて、そのバリアフリーの情報サービスも視覚でしかアクセスできないのでは、新たなバリアを産んでしまう。インターネット上の情報サービスに視覚障害者はどのようにアクセスすればいいのか?そこに、どのような技術的な手段があり、困難があるのか?ここでは、比較的最近に現れたサービスであり、かつマルチメディア型のサービスとして、一見困難に見えるWWWの利用だけに問題を絞って述べる。
視覚障害者のうち、ロービジョンないし弱視による利用の場合は、
1) Netscape Navigator などのブラウザに装備されたフォントサイズの調整や背景色とテキスト色の変更の機能で、かなりの部分をカバーできる。WWWによって提供された情報のうちテキスト部分については、個人個人の障害の程度に合わせて見やすいように、自分のclient software 側で調整するか、
2) inLarge/CloseView (MacOSの場合)や、ZoomText (MS-DOS/Windowsの場合)などのPCシステムレベルの画面拡大ソフトを利用することで、テキスト部分だけでなく、グラフィック部分も拡大できる。ロービジョンでは、もともと目をある程度利用できるので、アクセシビリティは、比較的容易に確保されると言えるかもしれない。
これに対して、全盲のネット利用者の場合、WWWブラウザとして有名なもの-Netscape Navigatorや Microsoft InternetExplorer-が使えない、と思われるので、WWWそのものを利用できないと思われる場合も多いかもしれない。しかし、これにもいろいろな手段がある。以下に列挙する:
3) OS/2 Screen Reader2
IBM OS/2 warp で使える Screen Reader 2 は、Netscape Navigator で表示されているテキスト部分やリンク部分の読み上げができる(IBM SNSセンター, 1996)。ただ、日本語入力に難点があり、ページから情報を読みとるのには便利だが、インターアクティブに検索したり、フォームに日本語を入力したりすることには、問題が残されている。また、OS/2 そのものが利用者が少ないという困難がある。
以下には、テキストベースでアクセスする方法を述べる:
4) UNIX 上で Lynx というテキストベースのブラウザが利用できる(浅田, 1996)
5) UNIX host で動作している Lynx をパソコンから telnet して利用できる
ので、音声や点字で UNIX を使ったり、あるいは、音声や点字で利用しているパソコンから UNIX につなげられれば、Lynx を利用して、WWWのテキスト情報を利用できる。点字でUNIXを直接利用するソフトは(Linuxに限定されているが)すでに、Nikhil Nair による brltty があり、日本にも輸入されているAlva Braille Terminal やTeleSensory PowerBraille を使って日本語環境でも実績がある(南谷, 1996)。また、TeleSensory のPowerBraille を使ってFreeBSDやLinuxを含めたUNIX汎用でアクセスするものに、Screen3.6 がある。これは、元来点字ディスプレイ用のものではないが、複数の端末画面にUNIXのタスクをマルチプレクスするソフトである。その端末画面の1つに点字ディスプレイが追加されている(Bargi, 1997)。これは、ISO-2022 コードに対応しているので、日本語への拡張も可能であると思われる。また、
6) Voice Net
VoiceNet という MS-DOS ベースの製品が最近開発されて、音声でWWWを含めたインターネットの情報サービスを利用できるようになってきた。ただ、TABLE や FORMへの対応は不完全である。
7) Lynx-Mail
福島県立盲学校などでは、電子メールでホームページの URL を送ると、内容を電子メールで返してくれる、Lynx-Mail サービスをネットワーク利用企画「特殊教育」の一貫として提供している。これは、視覚障害関係のメーリングリスト、jarvi-mlでの議論から、そのメンバーの浅田氏が開発したperl プログラムである。浅田氏は、上述したLynxの日本語版の製作者でもある。Lynx-Mail だと、パソコン通信から、メールが出せる人なら、だれでも利用できるし、メールと同じように届いてからじっくり読めるので、視覚障害者が情報を読みとるのに晴眼者よりも時間がかかって、利用上のコスト問題があるという部分もかなり解決する。その方法を以下に詳述する:
lynx@fukumo-sfb.fukushima.fukushima.jp 宛にメールを書き、本文に、以下のように書くと中身をテキストで送り返し、
dump 中身を送ってもらいたいホームページの URL
また、以下のように書くと、中身をHTML ソースコードで送り返す。
source 中身を送ってもらいたいホームページの URL
Lynx-Mail は、ユーザから送られた情報をLynx に送っているだけなので、限定付きながらFORMも利用できる。たとえば、以下のような1行を送ると、検索エンジンとして著名なYahoo が、TVというキーワードに関する検索結果の21番目から20個を送ってくれる:
dump http://search.yachoo.co.jp/bin/search?p=TV\&b=21
この他に、現在開発中のもの、海外で開発されたもの-たとえば、The
Productivity WorksのpwWebSpeak という読み上げ機能付きWWWブラウザ(Closing
The Gap, 1996)-がいくつかあり、視覚障害児のインターネットへのアクセシビリティは、技術的な意味では、着実に前進しているし、現状でも一部の視覚障害者は、UNIX+brltty
やLynx-mail などを利用して、すでにWWWによる情報提供を積極的に活用していると言える。
[参考文献]
・Hadi Bargi Rangin, 1996. SCREEN and its
Braille Interface to UNIX.
http://dots.physics.orst.edu/~bargi/projects/screen/thesis.html
・南谷 1996. Japanese Linux Access page.
http://www.gakushuin.ac.jp/~95011245/jplinacc.htm
・IBM SNS センター
1996. スクリーン・リーダー/2.
http://www.ibm.co.jp/kokoroweb/chap14/kkr14039.html
・あさだだくや 1996. Japanized Lynx Home
Page.
http://www.three-a.co.jp/~asada/lynx/
・あさだだくや 1996.Lynx-mail. http://www.three-a.co.jp/~asada/lynx-mail.html
・Internet access for visually impaired and
dyslexic opens up new Internet application areas. Closing The
Gap, Aug/Sept, P. 18-20
http://www.prodworks.com/
このページの先頭へ
目次へ