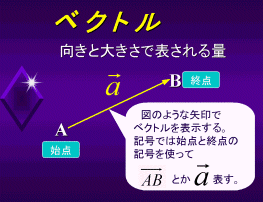
図にあるような説明のスライドと,練習問題のスライドを作成し,説明の後で練習問題を行わせ,生徒が大体終わった後で,練習問題の解答をスライドのアニメーションを使って解説した。
生徒の理解が不十分だと思われるところでは,書画カメラ等で随時,説明の図をその場で書き,補足説明を行った。
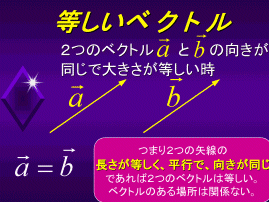
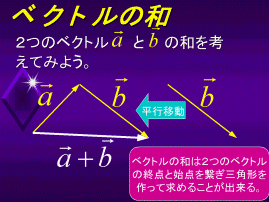
【1】 <実践事例>
【2】 タイトル:コンピュータを視聴覚器材として利用した数学の学習
【3】 概要(箇条書きとし、特徴を含む):
・ プレゼンテーションソフトを利用し,数学のベクトル・図形など,板書によるわかりやすい説明が困難な単元をよりわかりやすく説明する。
・ スライド構成による,図形の動き等を活用し,視覚的に生徒が理解できるよう工夫する。
・ 教材提示機能だけではなく,生徒自らがソフトを操作し,復習用の教材としての活用も考える。
・ 教材の再利用・修正が簡単である点を生かし,一度利用した教材を再検討し,次回の授業でより良いものとして活用できるよう工夫する。
【4】 キーワード(学校区分や、学年、教科などを含めない):高等学校,数学,図形,ベクトル,プレゼンテーション
【5】 学校区分:高等学校
【6】 学年:第3学年
【7】 教科・領域区分(いずれかを○で囲む):(数学)
【8】学校名(URL):千葉県立印旛高等学校(http://www.d1.dion.ne.jp/~sawarako/)
【9】 授業者名:吉田 圭介
【10】 授業実施期間(月日,時間):なし
【11】 単元・題材名:ベクトル・平面図形
【12】 単元の目標:ベクトルの基本的な性質を理解する。
平面図形の性質を理解し,具体的な問題の解法を習得する
【13】 メディア活用の意義:
ベクトル・空間図形などを始め,関数のグラフ・微分・積分等,数学の指導において図を用いる場合は非常に多いが,これらを黒板の板書だけでわかりやすく説明することはかなり困難である。OHPなどの活用も一つの手段であるが,パソコンと液晶プロジェクターが利用できる場合には,動きのある絵を使ったスライドで説明できるプレゼンテーションソフトを用いることが最も効果を上げやすい。
正確な図を描け,一度作成すれば何度も使える上に,問題点があった場合の修正が容易である。また,慣れれば図の作成はOHPにくらべはるかに容易であり,似たような図形は色々な問題で繰り返しコピーして利用することができる。
動画・写真・音声等の利用も可能で,動きのあるわかり易い説明が可能である。
また現状では全ての生徒がパソコンが利用できるパソコン教室を使うことになるので,単に板書の代わりとしての利用だけではなく,プレゼンテーションソフトで作成したスライドを実際に生徒にも操作させ,生徒の理解の速度にあわせた復習用の教材としての利用価値も検証してみた。
【14】 メディア環境
a) 使用機種:NEC PC9821Xv-13 42台 PC9821Xv-20 1台
b) 稼動環境:WindowsNTファイルサーバ
クライアント NEC PC9821Xv-13 42台
液晶プロジェクター
c) 利用ソフト:Microsoft PowerPoint97
【15】 単元の指導計画
指導計画(時間) |
留意点 |
ベクトルの基本的性質(1) 平面図形の基礎(1) |
視覚的に理解できるよう工夫する 基本的な性質を問題の解法に役立てられるように指導する |
【16】 授業展開
学習活動・内容 |
留意点(活動への働きかけ・支援等) |
(1)ベクトル |
動きのある図形で,生徒に興味を持たせ,視覚的に理解させる。 基本性質を生徒に質問しながら再確認し,具体的な問題への対応方法を考えさせる |
【17】 学習活動の実際:
(1) ベクトルの授業
|
図にあるような説明のスライドと,練習問題のスライドを作成し,説明の後で練習問題を行わせ,生徒が大体終わった後で,練習問題の解答をスライドのアニメーションを使って解説した。 |
|
|
これらの図は全て動きのあるスライド形式のものであるが,紙面ではその内容を十分表現できないので正六角形の問題の(1)と(4)について説明の流れを以下の図に示す。
|
|
(2) 平面図形
実際に利用したスライドを参照して頂きたい。
【18】 授業の成果(生徒の反応、メディア活用の効果等):
生徒の側はこのプレゼンテーションソフトを利用した授業をどのように捕らえているのかを調べるために,昨年度ベクトルの授業を行った生徒と今年度平面図形を行った生徒に対して簡単なアンケートを行ってみた。
もともと本校の生徒は文を書くことを非常に嫌がると言うことと,生徒によってはアンケートに必ずふざけた解答を行う生徒もいるのでアンケートだけから断定的な判断はできないがある程度の傾向は掴めたと思う。
(1) アンケートの結果
右のようなごく簡単なアンケートを取った。 |
|
【ベクトルを受けた生徒】 【平面図形を受けた生徒】 |
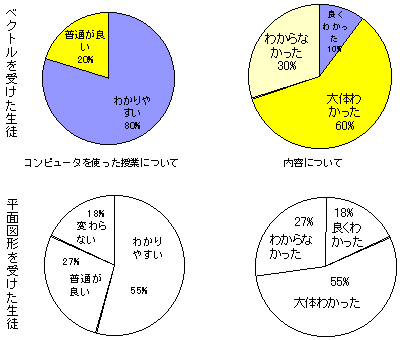 |
(2) アンケート結果に対する考察
全体を通して言えることは,おおむね普通の授業よりは好評なようである。またベクトル・平面図形共に一番多い感想は「きれい」「みやすい」であり,この点でもプレゼンテーションソフトの利用効果は確認できる。またベクトル・平面図形共に「早く進んで良かった」「短時間で色々な問題ができた」という感想があり,ある程度理解力のある生徒にとっては短時間で効率的に指導する手段として役立つようである。
しかし,ベクトルでは一人もいなかった「変わらない」が平面図形では18%,正確な意味での「普通が良い」もベクトルでは皆無に対して平面図形では27%もいた。これは生徒の授業に対する姿勢の差の影響も多少あると考えられるが,扱った単元の特性の向き不向きにも大きく関係しているように考えられる。やはり動きを必要とする単元で最も効果を上げやすいのではないだろうか。
【19】 ワンポイントアドバイス(今後の課題等):
実際に行って見て一番感じたのは,スライドはきれいだがスクリーンのスライド上に板書のようには自由に書き込めないという点であった。マウスで自由な色で書き込めるのだがなかなか思い通りにはいかなかった。
スライドを用意してない所を急に説明するのはかなり大変であった。紙に急遽書いて書画カメラを使って表示したが,教室の設計上ホワイトボードとスクリーンを同時に使えないので機器の操作に慣れていない職員だとかなり大変かもしれないと感じた。ただ慣れていれば書画カメラでの説明とスライドでの説明をうまく使い分けることでそれなりの効果はあがった。書画カメラの価値を再発見した。
最初の授業ではパソコンを完全に視聴覚教材として利用したがやはり生徒がパソコンで直接操作できる教材がないと長続きしないと感じた。本校の生徒は机に座って授業をただ聞くというのは非常に苦手である。しかし,自ら何らかの操作を行うことは割と積極的に行う。一度見せた説明のスライドを自分の手で操作させるだけでも効果があった。
ただ二回目に自然科学コースの生徒に対して行った時は,ベクトルについてはパソコン教室を使える時間の問題から最初と同様,完全に視聴覚教材としての利用しかできなかったのであるが,生徒の学習意欲が比較的高かったためかパソコンの操作無しでも十分に一時間の授業ができた。このあたりは生徒の学習意欲の問題も関係しているようで,比較的意欲の高い生徒が揃っている場合には目の前にパソコンがあっても,完全に視聴覚教材としての利用だけで十分に効果が期待できるようである。
自然科学コースの生徒に対する数学Bの授業で板書で行った昨年度とプレゼンテーションソフトを利用した今年度を比較すると,昨年度は同じ内容で倍以上の時間をかけたが理解度は低く,考査での同じ問題の正答率も今年度に比べかなり低かった。他の単元の考査結果から生徒はほとんど同じ程度の理解力を持つ生徒と考えられるので,プレゼンテーションソフトの利用はそれなりの効果が認められると考えられる。
またスライドの利用は板書の時間が要らないため短時間でより多くの内容が教えられると感じた。特に今回,比較的理解の早い生徒からは「授業が早く,無駄な時間がないためかえってわかりやすい。」という声を聞いた。これは期待していなかったことで一つの収穫といえる。
通常の授業の方が多くの時間をかけたにもかかわらず効果が上がらなかったのは授業に対する集中度の違いも大きく影響している。一度パソコン教室での授業を受けた生徒たちは,再三「今度は何時パソコンで授業をやるの?」と聞いてくる。生徒たちはパソコン教室での授業を非常に喜んで受けているのである。最新の機器を使うことで生徒の授業への意欲がより高められていることは明らかである。無論,単に新しい機械にさわれる,操作できるという好奇心がその大部分を占めているのかも知れないが,この点も積極的に利用して良いのではないかと考える。
【20】 参考資料・参考URLなど(協力者,協力団体含む):なし