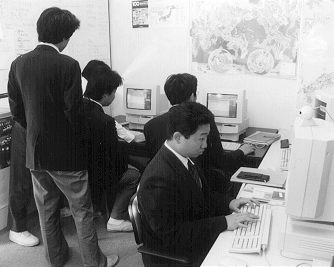現在実践中の事例経過報告及び今後の展開について
課題研究「ネットワークの研究」での取り組み
山梨県立谷村工業高等学校
手塚 芳一
今年度、電子情報科3年生の課題研究の一つに「ネットワークの研究」を取り上げ、実際のネットワークを利用して生徒達に社会参加させてみることにしました。その理由として、
- 基本的なネットワークの構造とかプロトコル等については座学の中で実施できる
- 既にネットワークは特定の人達のものではなくなってきている
- ネットワークの良さや注意しなければならないこと等は利用してみなければわからない
- 積極的な実習参加への動機付けになるのではないか
- 生徒達の授業への取り組みに、何がしかの変化がみられるのではないか
- 「使い方を学ぶ」ということから「何かの目的に活用する」という主体的な学習活動がみられるのではないか、等が考えられました。
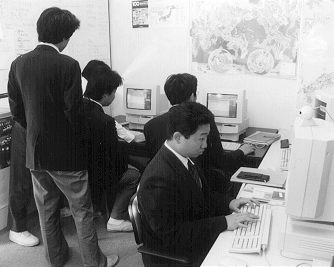
インターネット接続されるまでの間、県情報教育センターが行っているパソコン通信を用い電子メールの交換をしました。メールを
通し他校の先生方から、電子メールの書き方や返事の出し方それに電子メールに流す内容について指導していただきました。インター
ネットの導入は、カラー画像の情報交換ができること等パソコン通信と異なり、生徒達に非常な感動を与えました。生徒達自ら学校のホームページを作りたいという提案がなされ 、6月末にな
んとか初版のホームページを仕上げました。この様子は、NHKやローカル紙に取り上げてもらい、このことも生徒達にとって、やっていることへの自負と自信につながってきました。また11月の学園祭では、県外の高校及び大学の4校とCU-SeeMEを使った一時的な交流を行いました。これをきっかけに参加校と交流を深めていこうと考えていたのですが、具体的な形で行動が移せなかったのは残念でした。課題研究発表会では、インターネット接続されたパソコンを大型プロジェクタに接続し、ブラウザを用いて解説を行いました。このプレゼンテーションの方法はとても斬新で効果がありました。
【得られた成果】
- ネットワークの世界は広いということを肌で感じ、情報がダイナミックに変化し、世界は生きていると思うようになった
- メールが生活のなかの一つの道具として位置付けるようになり、メールの交換を通して相手の気持ちを考え相手の必要としていることを的確に伝達する習慣がついた
- 共同で制作活動を行ったが、お互いの情報をメールを通して活用するようになり、共同作業で協調性がでてき、時間の有効利用にメールが有用であることに気づいた
- 自分だけのリンク集をつくり、必要な情報を必要な時に呼び出せるようにようになった
- HTMLを使った効果的なプレゼンテーションができるようになった
- メディアに取り上げてもらい、生徒達だけでなく学校全体のイメージアップに貢献した
- 教師主導型の授業形態が、生徒主導型に近づき生徒が授業を楽しむようになり、自ら問題解決する傾向がみられるようになった
反省として】
- クライアントの数が少なく、自由に使える時間が少ない
- 電子メールやCU-SeeMeによる交流をもっとやりたかった、またCU-SeeMeでは進行役として全体をまとめるコーディネータが必要である
- 回線が細く、複数台のクライアントからのアクセスに時間を要した
- ただ覗いているだけの授業になってしまいがちになるので、生徒へインターネットを使用する目的をはっきり明示しておく必要がある
- ネットワークを覗いていると時間が思っている以上に速く過ぎてしまうので、スケジュール管理をしっかりしておく必要がある
- 効果的な指導を行うため、チームティーチングが必要であり、またマシンを使用してないときの指導内容を明示しておく必要がある
来年度の活動に向けて、職員のインターネットへの意識調査を今年の2月に実施しました。その結果を見ると、インターネットの教育利用について、約70%の職員がその必要性を感じており、そのうちの30%の職員がなんらかの形で既にインターネットに関わっています。活動の方法として、先ず環境の整備と使い方の指導を行って欲しいという意見が多く、課外活動で生徒主体に活動させたいと考えているようです。企画への参加や積極的な活動を望んでいる先生も多くいることがわかり、企画の提供や研究授業を通した活用方法についての援助等を積極的に行っていきたいと考えています。