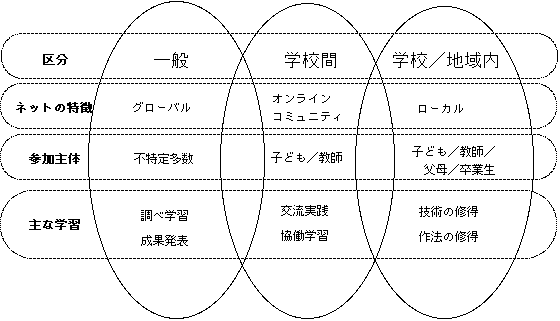
図1.1 学校をとりまくネットワークの3つの利用形態
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター
新谷 隆
shintani@glocom.ac.jp
キーワード インターネット,広場,コミュニティ,学校間交流
本章では,学校におけるインターネットの活用形態をグローバル・コミュニティ・ローカルの3局面に分類し,そのうちのコミュニティ的な活動に焦点をあてながらインターネット上における子どもの広場の有用性を述べる。
全ての人がインターネットを活用する時代が訪れようとしている。当然,インターネットは全ての学校に導入される。関係省庁間の横断組織である「バーチャル・エージェンシー」においては,2005年までに全ての教室からインターネットを活用できるような整備事業が提案されている。そして近い将来は,全ての子どもたちや先生がインターネットを日常的に活用する機会が提供さる日がやってくるであろう。
これまでにいくつもの学校において多様なインターネット活用実践が繰り広げられてきた。ホームページを利用した調べ学習,学校ホームページを通じた情報発信,電子会議室やテレビ会議などを用いた学校間交流,家庭と学校とのメールでの連絡など,さまざまな形態の実践が試みられてきた。そして今後も総合的学習や情報関連授業などにおける新しい活用の仕方が多数提案されることになるであろう。
インターネットを活用した実践事例を整理するために,企業等でよく使われるインターネット技術の以下の3つの利用形態に分けて考えてみることにしたい。
- インターネット
- イントラネット
- エキストラネット
いくつもの企業においては,グローバルなネットワークとしてのインターネット技術の活用サービスのことをインターネットと呼んで,他と区別することがある。企業内に閉じたローカルなネットワークをイントラネットと呼び,さらに取引先や顧客などを含めたビジネスのやりとりを支援するネットワークの仕組みをエキストラネットと呼ぶことがある。いずれもインターネット関連技術をベースにしているという共通点があるが,その利用目的も,活用内容も,参加主体のグルーピングも異なる。
同様な利用形態の分類を学校における実践にあてはめて考えると,次のようなシステム的な特徴を持つものとして理解できる。
- インターネット = グローバルなネットワーク
- イントラネット = ローカルなネットワーク
- エキストラネット = コミュニティをベースとした
そして実際に,それぞれのタイプの活用実践が行われている。我々が普段,単にインターネットの活用実践とよんで一括りに議論している実践事例は,上記の3つの形態にあてはめると,いくつかはイントラネットの,いくつかはエキストラネットとしてのインターネット技術の活用である。
先にあげた活用実践のパターン例を分類するとおよその以下のようになる。なお,上記は厳密な実践事例の分析に基づく結論ではなくて,説明のための便宜的な分類である。個々の活用実践によっては複数にまたがるケースもあるし,解釈によって別の分類枠に納められることもありうだろう。いずれにせよ,学校におけるインターネット技術の活用実践においては,異なる形態の活用が実際になされている。
- インターネット = グローバルなネットワーク
- ホームページを利用した調べ学習
- 学校ホームページを通じた情報発信
- イントラネット = ローカルなネットワーク
- 家庭と学校とのメールでの連絡
- エキストラネット = コミュニティをベースとしたネットワーク
- 電子会議室やテレビ会議などを用いた学校間交流
重要なポイントは,インターネット,イントラネット,エキストラネットという3つの利用形態のそれぞれにおいて,学校における活用の際に「留意すべき点が異なる」ということである。それぞれのネットワークの形態ごとの特徴を説明しながら留意点を説明してみたい。
インターネットは,「グローバルな双方向ネットワーク」という特徴をもっている。インターネットにより,世界中の人々がコンピュータのネットワークを通じてコミュニケーションをはかることができる。学校にとってみれば,児童・生徒や教師がグローバルなコミュニケーション手段を手に入れることができるということである。 「学校」がインターネットに接続されるということは,児童・生徒や教師が地球規模の双方向ネットワークの利用者の仲間入りを果たすことに他ならない。インターネットの利用端末を操作すれば,ホームページを見ることができ,有益な情報を見つけだすことができるかもしれない。
一方でグローバルなネットワークとしてのインターネットの活用においては,学習成果の上がった事例がいくつも報告されているものの,他方でこのタイプのインターネットの活用場面にの有害情報への懸念が集中しているのも事実である。世界中の不特定多数の人々と情報のやりとりができる,というインターネットの優れた特徴が,学校にとっては,有害情報への懸念を高めることにつながっている。このグローバルな双方向ネットワークとしてのインターネットの活用場面において,すなわち一般公開されたホームページへのアクセス,不特定多数向けの情報発信や,特定できない人との電子メールの交換やチャットの利用などにおいて,有害情報への対処法の実施を検討すべきである。
但し,生徒に対して一律の制限のを加えるのではなく,発達段階に応じて,その制限を緩めることも考慮すべきである。例えば,インターネットを初めて活用する生徒に対しては,若干強めの制約をかけることになるとしても,十分なネットワーク・リテラシーの獲得がなされた段階では,情報発信やメール交換などに関しての制約を緩めるといった対処法が望まれる。
インターネットは,グローバルであると同時に「ローカルなコミュニケーション手段」でもある。インターネットの技術を用いると,例えば児童・生徒が校内はもとより,近隣の学校同士でメールの交換をしたり,教師が父母とメールのやりとりをすることが可能である。このようなイントラネットないし地域ネットワークとしてのインターネット技術の活用については,既に多くの実践例が報告されており,教育上の成果が認められている。
学校内や地域をベースとした活用は,グローバルな活用と比べると地味であるが,だからといって,グローバルな活用の方がローカルな活用よりも「優れている」というわけではない。学校において,子供たちや先生が,電子メールなどを活用することで,日本にいながら海外の人々とのコミュニケーションをはかることができるようになる。しかしながら,そのことは,国内の人々との交流よりも海外の人々との交流をはかることの方が「望ましい」ということを意味するものではない。「電話」もインターネットと同様にグローバルな双方向の通信手段であるが,国際電話と国内電話に優劣の差があるわけではない。むしろ,グローバルな活用においても,またローカルな活用においても,それぞれに利点が存在すると言うべきである。
学校では,ローカルなコミュニケーション手段としてのインターネットの特徴を生かした活用実践を積極的に推進すべきである。とりわけ,インターネットの活用実践をスタートしたばかりの学校・学級においては「校内イントラネット」の活用が有効である。さらに一歩進んで,父母の方々なども巻き込んだ学校を中核にした地域ネットワークは,関係者の理解を深め,子どもたちが近い将来にインターネットの世界をひとりで歩くための技術や作法を学ぶために有効である。
ローカル・ネットワークが有効であるという理由はいくつもあげられるが,ここでは,3つのポイントを指摘したい。
まず,子どもたち一人一人が自ら積極的に情報を受信・発信するタイプの実践を組み立てやすい,という利点がある。ローカルなネットワークでは,グローバルな活用よりも有害情報への懸念が少なくて済み,より安全であるので,利用に関する強い制限を加えずに,自由度の高い教育実践を組み立てることができる。
また,ローカル・ネットワークは,失敗が許される場所である。初心者の練習の場所としての活用が可能で,そこでの経験によりネットワークのリテラシーが育ってゆくと期待される。
さらに,地理的に近いところに居る人々が参加するネットワーク実践であるので,実際に会う機会を実現しやすい。インターネットを活用した教育実践は,ネットワークの中だけで完結せずに,実際に会うオフライン活動との組み合わせによって,より有意義な実践が可能であるというケースが多数報告されている。ところがオフラインの実施は,交流相手が遠方であればあるほどコスト的に実現が難しい。その点,地域ベースのネットワークであれば,子どもたちや先生同士の対面型のコミュニケーションの実現が容易である。
インターネット技術を活用すれば「コミュニティをベースとしたネットワーク」を実現できるという特徴がある。これは,不特定多数を相手にするのではなく,しかし地理的ローカルな集団ではなく,興味関心や問題意識などを共にする人々同士がネットワーク上で出会い,交流を実現できるようなネットワーク上の広場を構築し,運用することができる。
とりわけ学校においては,異なる学校同士の積極的な交流の場としての「学校間ネットワーク」の活用が極めて有効である。全国の学校の子どもたちや教師が参加するネットワークは,有害情報の観点から言うとローカルなネットワークと同様に安全である。かつローカルな場面で練習をした子どもたちにとって,次の学びのステップ,すなわち「協働学習」の場を用意する。他にも,ネットワーク社会に生きていく子どもたちにとって欠かせない重要なリテラシーの多くを学校間交流ネットワークを通じて獲得することができる。
日本全国を見渡せば,インターネットを活用した学校間交流プロジェクトである「メディアキッズ」(URL=http://www.mediakids.or.jp/)のような先行事例はあるものの,オンライン・コミュニティの活用は,まだ途についたばかりである。しかし全ての学校へのインターネットの接続が徐々に達成されてゆくにつれ,また新しい学習指導要領により情報教育の実施が必須カリキュラムとして位置付けされてゆくにつれ,学校間交流を実現するためのネットワーク型学習環境の必要性が高まってきている。
各自治体単位で,ないしNPO的な組織が,地域ないし全国規模の学校間交流のためのオンライン上の広場を用意し,そこでの活発な交流実践をサポートするための仕組み作りに尽力する必要があるだろう。そして学校側も,豊かな実践を繰り広げられるように,オンラインコミュニティへのかかわりを前向きに検討すべきである。
3つのネットワークの特徴と留意点を踏まえて,学校をにおけるインターネット技術の活用の分類を試みたのが図1.1である。
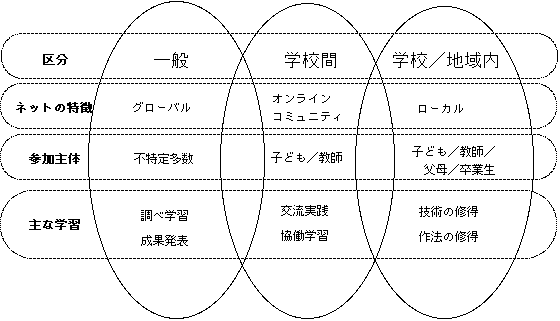
図1.1 学校をとりまくネットワークの3つの利用形態
学校がインターネットに接続されることによって,グローバルなネットワークとしてのインターネットの活用をはかることができる。それは,不特定多数の人々が参加する世界であり,有益な情報が多数存在する。そうしたネットワークにおいては,ホームページの検索による「調べ学習(=ナビゲーション)」などを実践できる。さらに,自分の学校のホームページを開設することにより,多くの人々の目に触れる形で子どもたちのアイデアや作品などの「成果発表(=プレゼンテーション)」が可能となる。但し,有益な情報だけでなく,有害な情報も飛び交う世界であるので,しかるべき配慮が必要である。
こうして考えると,学校におけるインターネットの活用実践は,ローカルな場面からスタートして,コミュニティ的な広場に移行し,さらにグローバルな世界へと離陸してゆくという段階的な活用が有効である。それは,有害情報への前向きな対処法として有効という側面もあるが,それよりも肝心なのは,それぞれのネットワークの特性を生かした優れた学習の組み立てにもつながることである。
|
|
次へ → |