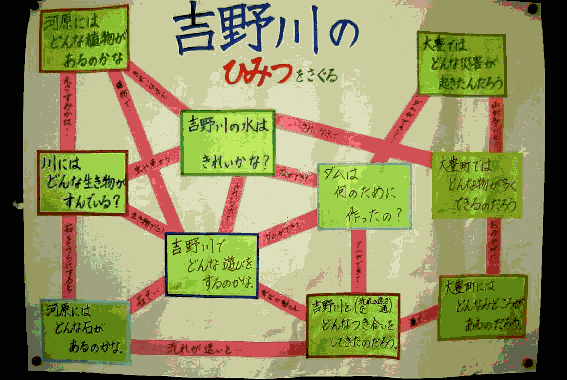
交流相手校の選定は,共同学習を進めるときの最も大切な仕事の1つと言ってよい。校内であらかじめ決定したテーマを元に、「交流相手校になってくれないか」と呼びかけても,簡単に応えてくれる学校はそう多くはない。学校の規模,学校が取り組む研究内容や時期,地域の状況や特色,人的背景などの条件を相手校とすり合わせ,あまり理想を高くすることなく,共同研究を進めていく過程で,調整していく姿勢が必要である。ここでは,そのような観点から主なものを4つ紹介する。
(a) 場所で選ぶ(テーマに関連のある地域やものに近い位置にある)
(b) 人で選ぶ(その学校に知り合いがいる,協力してくれそうな学年がある)
(c) 学校で選ぶ(同じようなテーマについての学習がすでに進められている)
(d) インフラで選ぶ(テーマ追求に必要な物品やインフラがそろっている)
1)場所で選ぶ場合
自分の学校でこれから研究しようとしているテーマが,何らかの形で相手校にあるとか,地形,気候など必要な条件が整っている学校であるとかということである。または,その地域にいろいろな特産物あるといったように,テーマに深い関連がある場所という視点で選定するパターンである。
川や森林,海等の自然や生産地をテーマにする場合は,この基準で学校を決めるとよい。
2)人で選ぶ場合
3)学校で選ぶ場合
現在,同じようなテーマで研究が進められており,情報を寄せてもらえそうな学校ということであるが,研究の進んだ学校では,特に担当者が,ポリシーを持って実践研究を続けている場合が多く,積極的に協力してもらえる場合と,形だけの協力に終わる場合とがある。
自分たちの学校と同じようなスタンスで研究が進んでいる学校が,よい場合もあるし,自分の学校が新しい研究をしている場合は,逆にその実践を広める意味でも,これから始めようとしている学校を選ぶこともできる。
4)インフラで選ぶ場合
テーマ追求にあたり,どうしても必要になってくる設備や機材を中心にした学校選定である。例えば,TV会議システムがあるとか,子ども用のEメール端末が必要な台数分揃っているとか,インターネットを同時に何台も利用できる環境にある,等という条件である。さらに,その活動に必要な活動費の融通が利くかどうか,電話代などに問題を抱えている学校は,少々苦労するかもしれない。また,TV会議システムなどは,機器を利用しなければならないからという,形を重視した利用に陥る場合があるので注意したい。
学校の選定に欠かせないのが,学校が開設しているホームページである。地域を探す場合もあれば,その学校でどんな研究が行われているかを調べるときにも使える。ただ,本当の意味でこれらの情報をきちんと載せているホームページを開設している学校はまだまだ少ない。更新が1年以上もなされていないホームページもある。
現在,各教育関連団体で,さまざまな学校をリストアップしてリンク集をつくったり,交流希望校などの情報を掲載しているサイトもある。こまめに情報を集めるようにするとよい。
また,全国展開している研究会へ積極的に参加し,知り合いを増やしておくことも効果的である。Eメールアドレスを持って,全国レベルでの教師同士の交流に常時参加して各方面からの支援を仰ぐのも1つの方法ではないか。
交流相手校の数は,何を目指すかという目的によってかなり変わってくる。情報を相互に交換し合うことが前提ならば,多くの学校との交流は難しいだろう。スタート時点から学校数を限定しておくこともあると思われるが,テーマ設定によっては,交流校の数を交流学習の進展に従って増やす方法もあるのではないか。
単なる情報の交換というだけの交流ならば,3校以上でもなんら問題はないと思う。しかし,子ども達の心情的な交流も重視するならば、3校が限界ではないだろうか。3校でもそれぞれが三角形の形で交流できれば望ましいが、中心校をはさんで両側に参加校という直線的な交流では,参加校同士がやや疎遠になってしまう。これには,各参加校のインフラの違いも大きく関係してくる。TV会議システムの配備や,Eメール端末の数などの環境整備の状況が,特に大きく関わってくる。
また,学年による「交流」の意識のずれも生ずる。例えば,中学年の子ども達にとって,立場の違う複数の相手を認識するのはわりあい難しいかもしれない。本当の意味での交流を成功させるためには,学習以外の「お互いがお互いをわかり合えるための交流の時間」がかなり必要である。特にバーチャルな交流では,自分たちが相手にしなければ,意図的に相手を忘れることができる。単に情報の送り合いだけの交流であれば,利用するだけ利用してということになりかねない。返事を書かないとき「申し訳ない」という気持ちにさせる心情面での指導と工夫がはじめに必要である。これは「交流のための交流の仕方のルールづくり」の時間といえる。
ただ交流は,交流校という学校単位で考えるというよりは,結局は,特定のクラスを指している場合が多いので,それぞれの人数比をよく考えておかないと,相手が人数の少ない学級であると,かなりの負担をかけてしまうことになりかねない。しかし,そのような場合でも,大規模校は,自分たちの環境とはかなり違う相手の学校の様子を見て,相手の良さを学んだり,自分たちの良さを再認識したりできるわけだから,交流に消極的になるこはないだろう。
学校という組織は,行政区によってものごとの進め方がずいぶん違う。自分の学校で当たり前のことが,相手の学校では考えられないことになっている場合もよくある。そのことを教師側が意識しておかないと,同じ言葉を使っても意図が十分に伝わっていない場合がある。
特に,同じ学校で勤めている場合と,ネット上で同じ作業を進めている場合とでは,情報の伝達の密度が違う。相手校が,どのくらい忙しいのか,何か困っていることがあるのではないだろうか等,「思いやり」が行き届きにくい。交流のみをしていればいいのでなく,互いにクラス内での様子などをわかり合える,共同学習体としての意識を培う努力は欠かせない。
こうした点を考えると,交流校の数が多くなると十分な成果が上がらなくなるおそれがある。実際,10校以上の交流では,お互いにいくつかのグループが組みはじめると,新たに入っていきづらくなるようであるし,何らかの問いかけに対して,誰かが返事をするだろうという安易な気持ちにさえなってくる。そうなると単なる交流校のリストに名を連ねているだけで,もはや交流は成り立たなくなる。学校間交流といっても,子ども同士で交流がスタートしなければ,完全なものとはならないであろう。
遠隔交流学習では,電話やファクスによるメディア活用が中心のように思われるが,相手校の状況と関係なく情報の送受信ができるメーリングリストを開設して,その特色を生かして利用するとよい。これを補う形で電話やファクス,ビデオレターなどを組み合わせて活用する発想がよい。
指導者間を一気につなぐことのできるメーリングリストは大変便利である。特に,遠距離校間の交流ほど、その有用性が発揮される。関係者がたびたび集まって対面会議を行うことは、時間的また物理的に困難である。メーリングリストは、同時双方向通信でないため,相手を拘束することがなく自分がEメールを出せる時間を見つけては,メッセージを打ち込み送ることができる。その上、交流の記録も残り、学習成果のまとめに活用できる。
また、必要なときだけにEメールを送るのでなく、用件がなくても定期的に連絡を取り合うことも大切である。実際,研究に関することだけでなく,お互いの近況や現在考えていることなどを交信し合うことによって,指導者同士の連帯にもつながる。できる限り密に交信し合うとよい。
メーリングリストは,サーバがある場合にのみ開設できる。協力研究委員などが10人,20人にもなるような場合には,メーリングリストを開設し情報交換などを行うことが必要であるが,数名程度の場合,またはサーバーを持たない場合には,メーリングリストでなくEメールで代用できる。
<Eメールの送受信のルールづくり>
Eメールを活用して連絡を行う場合には,頻繁にメールチェックを行わないと連絡が不徹底になる場合があるので,最初にルール化しておくことである。
(a)毎日メールのチェックする。
(b)メールを読んだら必ず返信メールを送る。
(c)メーリングリストでなく,Eメールの場合は,CCによって自分自身にも送って置く。
こうしておくとプロバイダーに故障等があった場合,相手に届いていなことが,発信側でも即座に確認できる。(d)緊急を要する内容については,電話やファックスなど他の通信手段を併用する。
交流相手が遠距離にある場合,直接対面会議を行うことは無理があるため,主としてメディアを利用せざるを得ないが,やはり人間同士,直接顔を見ながら話す機会があれば,相手校の状況など詳しく情報交換できるし,不安が少ないのではないかと思う。
同じ学習内容でも,指導者によって視点が異なるので,実際に何回か会って話をすることは大切である。時間的な問題もあるが,隣の県同士程度の距離であれば,交流学習開始前2回,学習早期1回,中間まとめ1回,学習総まとめ時1回ぐらいは必要かと考える。
また,可能な範囲内で指導者の交流校への相互訪問を行いたい。交流相手校がどんな環境にあるか実際に見ておくと,互いの共通点や相違点がわかり,教材研究になり,TV会議などの交流学習でティームティーチング的な指導ができるように思う。さらに,交流校の環境に応じた情報交換・学習の内容や方法を選定することもできるだろう。
指導者の相互訪問は対面会議を兼ね,会場校を交替しながら実施するといいだろう。
調べたことを学校間で伝え合う交流学習のツールとして必須のメディアである。
しかし,現在では,学校の環境整備が,必ずしも同一水準でないため,教師や児童生徒の活用技術を身につけながらの交流となるので,その使い方が難しい学年では,交流学習の障害になる場合がある。早めに環境整備と利用技術の向上に取りかかるようにするとよい。
以上の他に,内容や目的,緊急性に応じて,TV会議システムや電話,ファクスでの打ち合わせも適宜,併用する。
まず,複数校で同一テーマを学習材として取り上げる場合,そのテーマが学習材としてどのような価値を持っているのか,教師がそのテーマをどのようにとらえているのか,共通理解を図る必要があろう。例えば,川や街道は,環境・歴史・くらし・自然などいろいろな面で,学習として成り立つ要素を持っている。それらを洗い出し,交流学習に取り組む先生方すべてがその川の価値を理解する必要がある。
この共通理解を図った後に,交流のプログラム作成に取りかかることになるのだが,効果的な交流を行うために,互いに理解しておくべきことや,理解する上で望まれることを次にまとめる。
1) 学校の立地環境や規模など
学校と学習材(例えば,川,道路,・・)との位置関係や学校の規模によって,児童・生徒が実際に活動できる範囲の可能性は変わってくる。また,交流学習では,オンラインの交流だけでなく,直接交流することが,学習上より有効であると考えられる場面もある。実際,オフラインミーティングは,直接的な交流学習であるため大きな成果を上げることは言うまでもない。直接交流学習を実現するためには,学校と学習材(川など)との位置関係はもちろん,地形や交通手段,近くの利用可能な施設,安全性等,周辺の状況も相互に理解しておくことが必要がある。
2) 学校の行事予定
交流の計画を提案する際には,相手校の会議や行事の予定を考慮することは,交流を行うタイミングを決定し,長期的な予定を立てる上での重要なポイントである。
3) 情報機器の環境,ソフトの整備状況
交流学習を進める上では,情報機器が,相互の資料の交換,意見交換に大きな役割を担うツールとなる。それらの情報機器が,交流校同士,同じように整備されていることが望まれるが,学校の環境はかなり違うことが一般的である。コンピュータが複数台あり,コンピュータ室から児童が自由にインターネットを活用できる環境の学校もあれば,職員室にしかインターネットを使えるコンピュータがない学校もある。したがって,同一の方法で交流を考えることはできない。
ワープロの文書や図面1つを取り上げても,作成に利用したソフトが異なれば,相手校は読めなく,利用できないことすらある。相互の情報機器環境を理解し,「できることから始めよう」の体制で無理なく進めていくことが大切である。
4) 現在,取り組んでいる学校の研究の状況
総合的な学習の視点,情報教育の視点,環境教育の視点等から,各学校の研究の進行状況をよく理解することが大切である。進行の度合いにより,交流として可能なこと,相手校にお願いできることは違ってくるからである。
5) 各学校の指導体制(T・T,ゲストティーチャー,時間の確保等)
交流プログラムを作成する上で,教育ボランティア(ゲストティーチャーなど)の存在は大きい。交流学習では,それらの方々の力を,1校だけではなく,交流校全体で活用することができるからである。活用できる教育ボランティアの情報を相手校に知らせておくことは重要である。それに併せ,学校内の指導体制として,T・Tの体制が取れるのかどうかを伝えておくことも重要である。これらによって考えられる児童の活動内容や範囲が変わってくる。
また,総合的な学習を試行している現段階では,それに当てる時間数は,学校のカリキュラムの構成によってかなり違ってくる。お互いの学校がどれぐらいの時間を活用できるのかについても理解しておく必要がある。
1) 推進的な役割を果たす学校(リーダー校)を決める
交流学習では、それぞれが自由に交流プログラムを提案したのでは,なかなかまとまらない。中心となる1校が,全体を見渡した上で交流のプログラムを作成して提案したり,活動の状況を見ながら,プログラムの修正・調整案を提案したりする方がうまくいく。
この中心校は,交流学習の経験豊かな学校が担うことが望まれるが,いずれの学校もその経験がない場合は,各学校の研究の状況や人的環境等を鑑みて決定するのがよかろう。
2) コーディネートできる人材の確保
コンピュータに代表されるメディアの活用に関する教師の理解度・スキル等は,学校間や教師間によって差があるのが現状である。この差を埋める役割をしてくれる人が,これからの交流学習には欠かせない。
このような立場の人をコーディネータと呼ぶが,コーディネータには,新しい機器についての情報提供,機器を導入する際の在り方,各種メディアの活用法についての助言,維持・管理,トラブルへの対処を主導的に行うことが要求される。また,交流学習の方法や進め方について助言したり,教育ボランティアの活用に関する企画,連絡・調整を支援したりすることも重要な任務である。
実践の場に,コンピュータ等のメディアに堪能な教師がいれば,交流時に発生する様々なトラブルに即応でき,学習がスムーズな展開できる。今後,このような立場の人材が学校や地域に配置されることが必要であることを,実践を通して痛感した。
以上,交流前に伝え合うべきことを述べたが,これらを意識しすぎて,交流がなかなかスタートできなくなったり,活動内容を最初から固定的に考えてしまったりすると,かえって逆効果である。「まず,できることから始めよう」という姿勢も必要ではないかと思う。
交流の場を設けようとすると,何をするにも各学校との間で連絡調整が必要になる。Eメールでの連絡だけでは,お互いの学校の忙しさがわからないし,それぞれの学校で予定されている行事ごとなどの様子もわからない。そのため,日程調整には,かなり前からの準備作業が必要である。
これらの作業では,中心校のリーダーシップが問われる。中心校の提案を参加校が吟味し意見を述べ,順次調整していくのがよい。どちらにしても少なくとも1年間を通した大まかな計画が年度当初にないと,行き当たりばったり的な急遽の実践に終始してしまう恐れがある。
特に,オフラインミーティングでは,子ども達や資材の移動のための諸経費は,大きな額になる。事前に予算を確保しておく必要がある。そのためにも,年間の計画とその意義を各学校で確かめておかなくてはならない。行政区によっては急な輸送費もままならないことは多くのケースであり得る。その場合,例えば校外学習に替えるなどの融通も考えられよう。
まず,中心校の担当者が,相手校を訪問。正式な依頼と,通信環境について調査をする。例えば,TV会議システムのカメラの位置や,インターネット端末の台数,利用しているメーラーやブラウザの種類などを確認する。これにより,どういう形式で交流を進めていくか考える。
同時に,その学校の周りの様子や,テーマに関係ありそうな情報を,学校の職員や子ども達から聞く。また,道中をVTRにおさめながら移動し,後日子ども達に見せて,交流の意識を高めさせる。
お互いに学校やクラスを紹介し合うためのイベントで,自分たちの学校を相手に紹介するためには,自分たちの学校や地域のことをしっかり知っておかなくてはならない。そのためにも,この機会に子ども達自身が自校や地域の情報を集めるようにしなくてはならない。
交流においては,お互いの学校の授業時間やカリキュラムを変更せずに実施できることが望ましいが,実際問題として,そのあたりが一番むずかしい点である。ある程度の教師の裁量と準備が必要となるので,そのことを相手校に十分伝えることができない場合は,期待通りの成果は得にくい。TV会議は,当然のことながら双方の時間を指定するメディアであるため計画的な活用が必要だろう。
また,TV会議の場合は,顔と名前を相手に覚えてもらうための工夫も,子ども達に考えさせたい。例えば,名前を大きく書いた名札を見せながら自己紹介をする。よく似た名前の子,同じ誕生日の子などがいれば,紹介し合う。聞く相手が退屈しないようにクイズを取り入れるなどの工夫で,画像が使えるメリットを十分生かした時間にしたい。
当然,学級対学級の大がかりなものでなく,数回に分け,小さなグループ同士で話をしたり,休み時間に「かけてもいいよ」という形でお互いに回線を開放することもいいと思う。
情報を共有することと,手軽に発言できるということで,掲示板を設けるのも有効である。しかし,すぐにはテーマに関する内容についての記述が始まるわけではない。雑談をする中で,交流へのステップをつくる。そのために,2種類の掲示板(交流用,テーマ用)を用意し,子ども達の反応を見る。お互いに名前を少し覚えた頃,テーマへとつないでいく。
相互に時間を制約しない交流を進めるためには,やはりEメールが便利である。日に何度もメールチェックができるような環境でありたい。そのためにも職員室や教室でEメールが常時見られるようにすべきである。また,届いたEメールにすぐに返事を送るという基本的なマナーを教師自身が身につけることも大切である。
オフラインミーティングは,各校の学習者同士の心情的なつながりを持たせるために必要なものであるが,その実施は,実践はじめの段階(友だちになる),相互訪問(実際に行って各校の様子を肌で感じる),まとめの段階(共同作業とまとめの発表会)の3回程度は必要であろう。例えば,1回だけのオフラインミーティングでは,調べたことの交流というより,友だちを作る,行くことを楽しむという意識が強くなるだろう。やはり1度だけではセレモニーになってしまうので,できる限り繰り返し行うことが大切である。
実際に各学校でテーマを決定するわけであるが,共同学習である以上
(a) 同じテーマで内容を深める
(b) 分担して調べる
という二つのテーマ設定の方法がある。このとき,中心校の決めたもののうちから,交流校が協力できそうなテーマに賛同するという「下請け型」では,よい共同学習はできない。それぞれの学校がギブアンドテイクになるようなテーマになっていなければならない。当然地域性の大きい内容に関しては,「違う」部分と「同じ」部分という二つの観点から,テーマをつくることができ,交流も順調にいく。
しかし,その地域に固有のものをテーマにした場合,相手に同じことを調べてもらうことはできない。したがって,テーマの一般化がむずかしい。各校のテーマは変えずとも,共同学習にふさわしいテーマに,ある程度絞り込んで進めることも必要である。
|
各 校 |
「川」に触れる(川遊び,ビデオ鑑賞など) |
|
各 校 |
子ども達から「調べてみたいこと」を提案 |
|
TV会議など |
各グループが,調べてみたいテーマを発表し合う。 |
|
各校(妥協) |
それぞれの学校にある同じテーマ,違うテーマが,異なる場合 は,関連のあるテーマから,中心校のテーマに合わせるようにした。 「川」という大テーマは同じであるので,各テーマごとの関連がわかるよう,図式化して,子ども達の意識を高める。 |
↓
|
各校 |
テーマの再検討。相手のテーマを聞いて,いっしょにできそうな もの,さらに考えついたテーマなどについて,子ども達で話し合 う。共通な部分を強調し,いっしょに調べるという意識を持たせ る。 |
ただし,このテーマのすり合わせに関しては,それぞれの学校の総合的な学習の時間の実施状況によって多少変わってくる。どの学校も慣れていれば,単独テーマを共通テーマに合わせなくても,それぞれの学校で実施できる。各校の学習形態の慣れによって,この部分は多少変化する。
ただ,児童の主体的な決定を大切にしながらも,中心校に可能な限り合わせる方向で調整することにより,全員の交流が図りやすいのは事実である。つまり,共通項を取り出して交流テーマにすると,交流できない,または,できにくいグループが出てくるので,相手校のテーマに合わせるような配慮が必要である。
学校間の人数規模の違いから,少人数の学校では,テーマが増えると,負担の大きい形のように思えるが,テーマ間にできるだけ関連を持たせ,共通する観点を与え,それぞれが孤立せず協力して学習ができるようにする。したがって,相手校グループとの関連を図ることがもできる。この際,テーマ関連図を掲示して,各グループ間,相手校グループとの関連づけがわかるように,また自分のグループの本来のテーマを見失わないように配慮する。
学習が進むにつれ,複数人数のグループではテーマのある部分を焦点化していったり,逆に関連の出たグループ同士は合同で調査を進めていったりするようになる。また,それぞれの学校から依頼された調査項目もどんどんふくらみ,それに時間を費やすグループもできはじめる。その経験から,今度は,自分たちがその学校へ調査依頼をし,互いにまとめ合ったりする。
児童数の少ない学校では,各テーマに1人という状態でなく,1テーマに複数人で当たったり,一人に複数テーマといった形も考えられる。様子を見ながら,時には全員で1テーマといったように,各テーマ同士の関連と交流を図り,自分が調べたいことは何かを常に認識しておくようにするのもひとつの方法である。例えば,「テーマ関連図」を作成し,常時目につくところへ掲示しておくことも必要である。
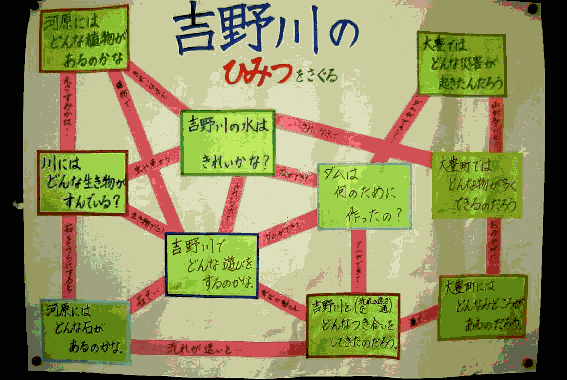
例:「吉野川のひみつ」テーマ関連図
|
|
次へ → |