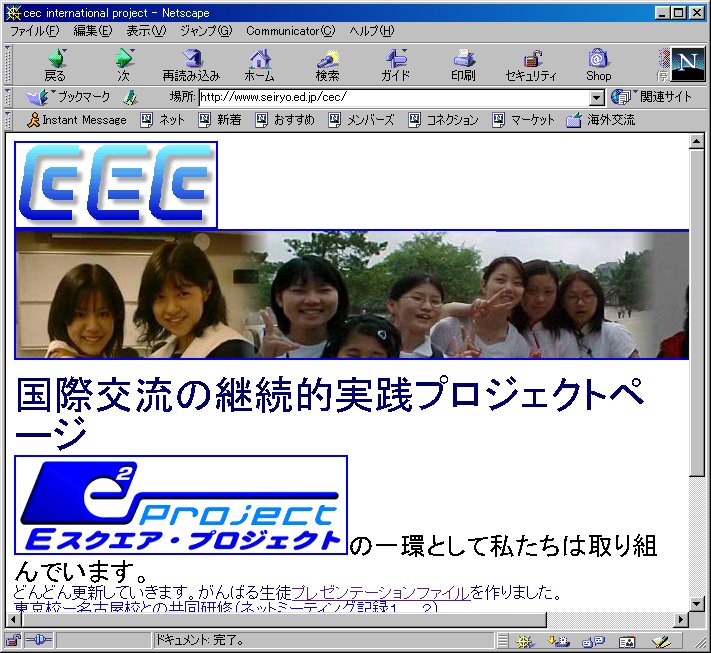
名古屋市立西陵商業高等学校 影戸 誠
CECの100校プロジェクトをベースに日本のインターネットの教育利用が進んできた。この国際化推進プロジェクトに対して本校は96年アジア交流から参加している。当初は共同企画としてスタートした。その後重点プロジェクトとしてアジア高校生交流を推進してきた。またこれらの経験をCEC国際交流ガイドブックにも記載しこれから始めようとする多くの学校に情報提供を行ってきた。
これらの実践のなかでなによりも「人的パワー・人的ネットワーク」が国際交流をささえることを学んできた。
これらの経験を元に、名古屋地区の幹事校として何らかの貢献ができればと考えた。
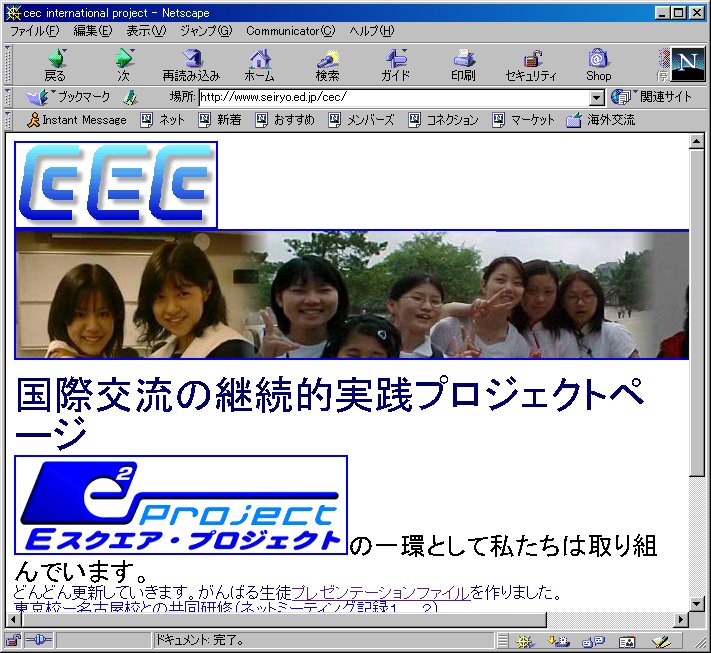
今回のプロジェクト推進にあたってそのサーバを本校webサイト内に作ることもあって、名古屋校のみならず、全体の連絡調整に当たる必要があった。
(1)メーリングリストの運用
すべての先生方をCEC@seiryo.ed.jpのメーリングリストに参加していただき連携をとっていった。
大阪、東京校の先生方と共にプロジェクトを推進している事が実感でき、名古屋校各校のエネルギーとなった。自分の参加している組織の全体像を把握することができている。

また生徒は生徒独自でst@seiryo.ed.jpを設定し卒業後も利用している。
(2)名古屋地域における連絡
名古屋校のメンバーは主にメーリングリスト try@seiryo.ed.jpを活用した。また協力して12月12日本プロジェクト仲介発表会に取り組む必要があり、それぞれボランティアで5回程度の打合会を行い、企画準備にあたった。
またメールを打つ前の連絡はほとんどが携帯電話となり、それぞれの先生方に負担をおかけすることとなった。
(3)活用事例発表会の開催
12月12日に本プロジェクトの中間発表会を行うこととなった。
1999年12月12日
 |
教育とインターネット活用発表会 「さあ広げようインターネット!」 ―実践・国際交流編 児童・生徒の声を交えて― |
基調講演 東京工業大学教授 赤堀侃司先生
「2001年全国の学校接続」 ーー期待と提言ーー
主催(財)コンピュータ教育開発センター
CEC継続的交際交流の実践報告について
参加人数
212名 (生徒 40余名 CEC関連教師 20名 一般教師120名 その他 32名行政・企業)
概要
会場には212名の参加を得て、熱気のこもった発表が行われた。今回は生徒の発表を網羅し、共に作り上げるインターネット実践事例発表会とした。
午前の実践事例も小中高に分かれ発表が行われた。
午後にCECの「継続的国際交流」中間発表会が行われたが、席を立つ人もなく、生徒の堂々とした発表に大きな拍手が送られた。
(参考資料 当日アンケート)
資料など

200名あまりの参加者 日曜というのに熱心な参加
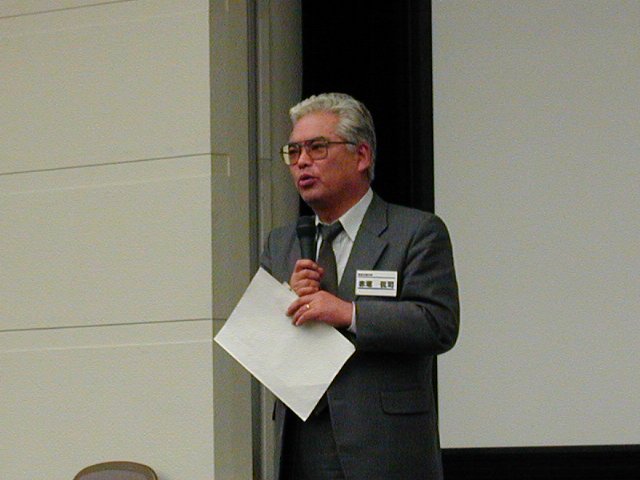 |
赤堀先生 基調講演 午後の発表の講評と多忙な一日をお願いしました。 |
|
三重県立員弁高校の発表 「ワールドユースに参加して」 |
韓国からの報告 新亭女子商業高校より
|
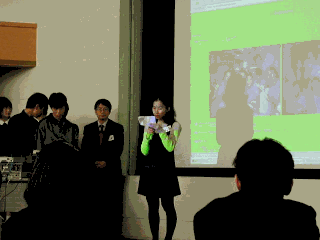 |
大阪校の発表 |
| 感動を呼んだ東林小学校の朗読 | 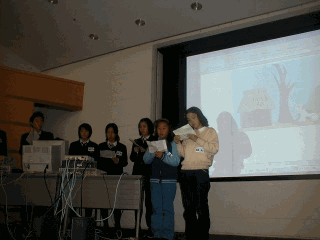 |
|
水越先生も終日参加 |
堂々とした発表の神奈川大学付属中高等学校の生徒さん |
小中高の連携
東林小学校の生徒が朗読を行い、神奈川大学付属中高等学校の生徒がアニメーションを作成し、さらに大阪校の高校生が英語版を作成するなど、縦の共同プロジェクトとして実践できた。
また3地域のネットワーク有効活用し「共同作品」を作り上げることができたことは今後のそれぞれのレベルでの総合学習に関するパイロットプロジェクトともなった。
生徒同士の交流
これまでメーリングリストでしか知らなかった他地域の生徒と直接話し合うことができ、 今後の活動へ大きな力を得ることができた。
当日のプログラム
| 10:00 |
開会 挨拶:(財)コンピュータ教育開発センター 今井正一 |
|
10:10 |
基調講演 東京工業大学教授 赤堀侃司 「2001年全国の学校接続」 |
| 11:10 |
実践事例 小学校 豊橋市立羽根井小学校教諭 鈴木 康弘 |
| 11:30 |
中学校 三重県三重郡菰野町立菰野中学校教諭 大立目佳久 「気楽にやろう!!?中学生の学校間交流(菰野、滝、南山国際編) |
| 11:50 |
高校 三重県立川越高等学校教諭 近藤泰城 「 インターネット交流によるコミュニカティブな英語学習 ==総合的な学習の時間を視野に入れて== 」 |
| 12:10 | 休憩 (インターネットの教育利用に関するソフトウエア、ハードウエア等 の紹介あり) |
| 13:00 |
学校向けのネットワーク基礎講座 (南山大学教授 後藤邦夫) 機器 web アライド 山本さんパソコンーー画面 |
| 13:30 |
滝高校 教諭 栗本直人 生徒 森 えり 発表 タイトル「国際交流のあり方 --- ネパールの学校との交流の中から」 |
| 13:50 |
国際アクティビティ 10分 アジア交流の紹介 影戸 韓国の報告 「日本の生徒を迎えて」 ーーインターネット事前・事後交流ーー 韓国新亭女子商業高校 教諭 ジョン・ジン 韓国九老情報高校 生徒 Ji-youn Kim |
| 14:15 |
ワールドユースミーティング CECサポートイベント 「世界7カ国の高校生 インターネットを駆使!」 ―――名古屋でのワールドユースミィーティング――― 三重県立員弁高校教諭 近藤多寿子 |
| 14:35 | 休憩 |
| 14:45 |
CEC 国際交流の継続的実践 中間報告 インターナショナル スクール on the Netの報告 |
| 14:45 | 大阪校発表 参加校教諭 生徒 |
| 15:05 |
東京校発表 参加校教諭 生徒 1、東京校の実践の説明(2分)-----------小林 Web会議室の紹介(8分)-------神大附属生徒 2、「アニメとゲーム」の説明(5分)--------早稲田生徒 3、「日本の昔話」の説明(5分)----------神大附属生徒 4、今後の活動の展望(5分)--------早稲田生徒 www |
| 15:30 |
名古屋校発表 参加校教諭 生徒 影戸 10分 生徒発表 |
| 15:55 |
小中高生徒の共同作品「日本の昔話 on The Web」の紹介 1、企画主旨(3分) 小林 2、制作にあたって(3分) 神大附属生徒 3、「はなさかじじいFLASH版」デモ(10分) 神大附属生徒、東林小学校児童 読み 4、まとめ(4分) 小林 |
| 16:15 | 講評 東京工業大学教授 赤堀侃司 |
名古屋校の研修会は4度開催され、それぞれに技術を習得していった。
11月7日のマルチメディア研修会は東京校のグループと時間を合わせ開催された。
研修項目
ビデオキャプチャボードの挿入とドライバのインストール

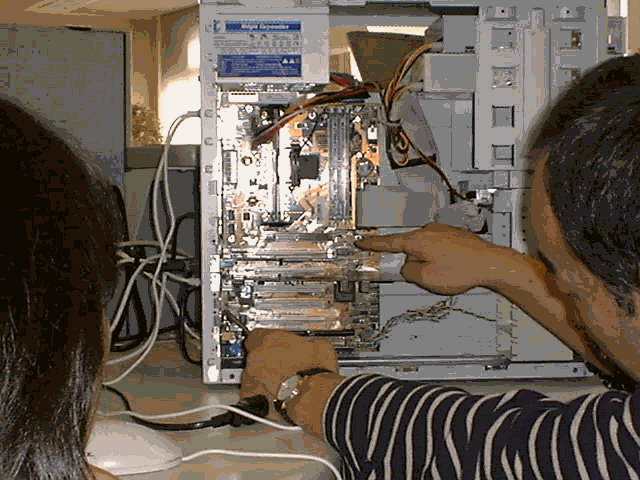
音声、動画、静止画は国際交流において「英語を日常語としない」日本の先生生徒にとってコミュニケーションをサポートする大切な手段である。
今研修は特にインターネットを始めたばかりの先生の研修としてせっていした。
カードを差し込んだもののなかなか設定が進まず、困惑したが、ボードがしっかり刺さっていなかったという事実が判明した。
このような失敗を繰り返しながらの研修であったがこれによって名古屋校7校のネットミーティングはすべて開通し、現在では他校のサポートに回るまでの技術を高めている。
この日は東京校研修会場(神奈川大学付属高校)と結び、ネットミーティングの体験と利用研修を行った。
画面の向こう側からよびかけてくれる小学生や、先生方に励まされ研修を行うことができた。
またCECのこのプロジェクトが大阪・東京とともに進められているということが実感でき大きな力となった。
これらの交信はweb上に置かれ、その後の講習会でもその機能について解説するときに利用されている。
ネットミーテイングなどのリアルタイム交信ソフトへの関心は深く
http://www.seiryo.ed.jp/kageto/soft/netmeeting.html
にダウンロードの方法、さらには利用方法のページを作成し、これを元に名古屋校各校で実験を行った。

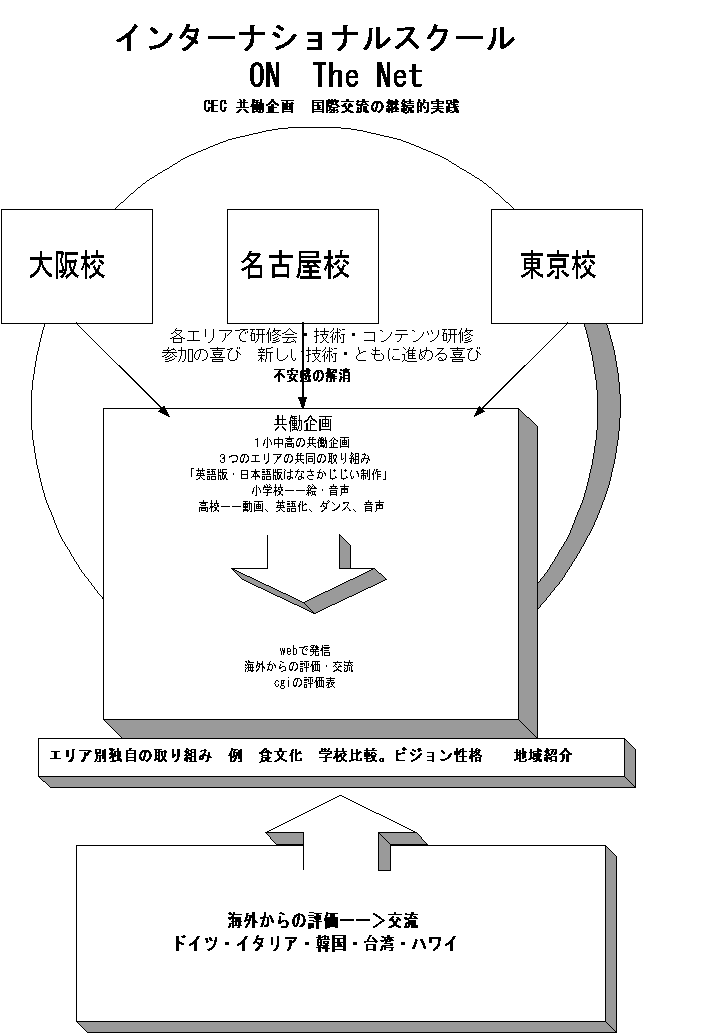
今年度は研修を通して、参加校が国際交流における基本的なリテラシを身につける研修と国内での交流に力点が置かれた。何よりも参加校の不安を取り除き、さらに技術的にも自信を持って欲しいと願ったからである。しかしながら参加校ではこれらの研修を元に、ドイツ、台湾、アメリカと交流が展開している。研修の技術を実際の授業場面の役立てつつある。「授業でのインターネット・国際交流」2つの側面が強化されつつある。
2000年もインターネットによる国際交流がさらに加速されていくことと思う。
しかしながら、各校に置いての取り組みもさることながら、「国際連携」を意識した組織作りが必要とされる時期になりつつあるように思う。
これまでの国際交流も一校相手ではなく、各国のネットワークと連携をとりながら進めていったものについては、継続性があり、レスポンスも確実である。
CECには、連携のための枠組み作りへの支援をお願いしたい。
とはいっても実践は各校の創意と工夫によってなされていく、各校の先生方はCECの支援に答えるべく、ネットワークを活用し、他校で利用できる実践事例と経験の共有を進めていくことが期待できる。
|
|
次へ → |