ネットデイサミット’99ワークショップin滋賀を終えて
ネットワークサポートセンターinかんさい(NeS-K)
ネットデイサミット'99ワークショップin滋賀
〜ネットでラン・ラン・ランデブー〜
日時: 平成11年12月18日(土)・19日(日) 【実施技術講習会】 18日午後2時30分〜午後6時 【ネットデイ】 19日午前9時30分〜午後4時30分 会場: 滋賀大学教育学部附属小学校・中学校 主催: ネットデイサミット'99ワークショップin滋賀実行委員会
滋賀大学教育学部附属小学校・中学校
滋賀大学教育学部教育実践研究指導センター
ネットワークサポートセンターinかんさい(NeS-K)共催: 財団法人コンピュータ教育開発センター(CEC) 参加人数: 18日・154名 19日・146名
ネットデイサミット'99ワークショップin滋賀・その背景
平成11年8月、群馬・愛知・福島・千葉・関西をはじめ、各地でネットデイ活動を実施・支援している8つの団体が夏の前橋に集結、『ネットデイサミットin群馬』が開催された。参加各団体がそれぞれ行ってきた、これまでのネットデイやそのノウハウ、その他ネットデイに関する情報が発表・交換され、人的な交流も大いに行われた。
ネットデイサミットin群馬の大きな成果として、「ネットデイの一つの意義は、地域社会の方々が「学校へ行こう」という気持ちを持つことである」という一文で始まる「ネットデイサミットin群馬共同宣言」が採択されたことがあげられよう(詳細は http://www.nes-k.gr.jp/summit/statement.htmlを参照)。この共同宣言では、現状において、地域の人々が学校へ足を運ぶことや、ネットワークを通じて先生や生徒と自由に対話することも難しいと指摘した上で、ネットデイをはじめとするボランティア活動を契機とし、学校のオープン化、行政・企業による支援、地域社会と学校との連携などが進むことを期待している。

写真:開会式で挨拶する宮田先生。聴覚に障害のある参加者のためにマイク付きヘッドセットをかけている。ネットデイにおけるアクセシビリティへの配慮は、今後の課題となるだろう。
このネットデイサミットin群馬とその共同宣言を受けて、ネットワークサポートセンターinかんさい(以下NeS-K)では、地域・保護者・その他ネットデイに関心を持つ人々との連携を視野に入れたネットデイを、ワークショップとして開催することを企画した。果たして、サミットにおけるNeS-Kのノリの良さが、関西での開催となる契機だったのかはともかく、滋賀大学の宮田先生、小中の情報教育担当の先生方をはじめとする多くの方々の協力を得て、今回のワークショップin滋賀はその形を成していくこととなる。
ネットデイまでの道程 〜下見・設計・案内
「良いネットデイは良い下見から」という言い回しが存在するかどうかは定かでないが、滋賀大附属小学校、そして中学校という2校同時ネットデイはNeS-Kにとっても初めての経験であり、その下見は必ずしもスムーズとはいかなかった。
NeS-Kはこれまで、兵庫県氷上郡を主なネットデイ支援地域として活動してきたが、ほとんどの学校は1学年1学級、都市圏とは違い比較的小規模である。校舎の建築時期によって工事難易度は異なるものの、学校の先生を交えての下見・ルート検討会の回数は比較的少なく済んできた。今回の滋賀附では2校同時、また各フロア毎に別々の工法を検討する必要があり(例えば、中学校の3Fヨコ系統通線では、廊下の天井に塩ビ管を取付て、そこにネットワークケーブルを通線するが、2Fでは教室TV横にある壁の穴を利用、1Fでは教室をつなぐ小窓の枠に切込)、小学校では普通教室など一部にはLANケーブルが既に設置してあり、それらの確認と調整、校舎のつなぎ目部分のルート確保など、難しいポイントが多く存在した。しかし、今回の大きな反省点は、都合4回にわたる下見で、各回ごと、特に1回目と2回目でNeS-Kからの下見参加者が異なってしまい、下見結果の伝達が上手く行われなかった点で、結果的に下見回数が増加することとなった。人数の少ないボランティア団体の宿命であるが、メンバーそれぞれが仕事を抱えており、下見の日程と自分の都合がちょうど良く重なるとは限らない。情報をどう伝達するか。必要なフォームはどんなものか。大きな検討課題となって残った。
また、各建物毎に工事全体をまとめる責任者(NeS-Kでは『棟梁』と呼んでいる)をおいて、下見段階の情報のまとめ、当日の全体的な指示を担当するのだが、今回は2校の棟梁を1人が兼ねることとなったために、情報の集約が十分に出来ず、また負担が集中したために、全体の混乱に拍車がかかった。

写真:下見時のひとコマ。中学校でフロア間をつなぐために利用した通称「スチーム管」を下からあけるところ。旧暖房設備のスチーム配管を再度あけ、タテ系ケーブルを通す。当日の作業が進むように、下見時にある程度下工事をしておくのも、重要なポイントである。
作業の分散という点から見れば、各フロア毎のリーダー(ボランティア側、学校側からそれぞれ人を割り当ててペアとするのが望ましいか)を下見段階から決めておいて、そのフロアの下見・ルート検討などを一貫して担当、責任者は全体を統括して部材の割り当て、特にフロアをつなぐタテ系統の配線など、全体に関わる作業の流れについて責任を持つのが良いように思われる。
とはいえ、毎回の下見で集まった情報を集約し、一般も含めた参加者に知らせる必要はあり、今回は「オンライン・マニュアル」の制作を行った(http://www.nes-k.gr.jp/shiga-fu/manual/)。この「オンライン・マニュアル」には、工事の手順だけでなく、当日のスケジュールや班分け、全体の配線図(Microsoft Excelの罫線機能を駆使した通称エクセルCADで作図した)、一般的な注意事項(ネットデイで知り得た情報の守秘、個人で持参する工具や用品の案内など)も含まれている。8月中旬から、既に準備用の実行委員会メーリングリストが立ち上がっていたが、一般からの参加申込受付開始後は、一般の参加者もこのメーリングリストに登録、「オンライン・マニュアル」の更新に際しては随時ここで情報を提供した。なお、このワークショップの案内は、教育関連のメーリングリスト、Webページ、地域の新聞(取材があった)、小中の保護者に対する案内の配布、宮田先生の講義受講生に対する参加案内など、多くの手段によっている。ワークショップ当日は、この「マニュアル」をもとに印刷枚数を減らせるよう編集・印刷したものを、参加者全員に対して配布したが、「オンライン・マニュアル」は、一般の参加者よりもむしろ、当日の作業リーダーがあらかじめ予備知識をつけたり、実行委員会内で作業の検討を行うのに役立ったようだ。
ワークショップ1日目・実施技術講習会「ネットデイの実施に必要なもの」
【プログラム】
司会=宮田仁(ワークショップin滋賀実行委員長)
- ネットデイで学校はどう変わったか
大西毅正氏(兵庫県氷上郡青垣町立遠阪小学校)
- ネットワークの基礎知識とネットデイLANのデザイン
佐藤高生氏(群馬インターネットつなぎ隊)
- コーディネートの進め方
岸田隆博氏(兵庫県立人と自然の博物館)
- 検討会「滋賀大学附属小学校・中学校ネットデイについて」
山城新吾氏(大阪大学大学院人間科学研究科)

午後から行われた1日目・実施技術講習会の参加者は154名。小学校の大きな多目的ホールが一杯になる程のみなさんが集まった。この日は座学で、実行委員長・宮田先生の挨拶に引き続き、NeS-Kがネットデイを支援した氷上郡・遠阪小の大西先生(遠阪小ネットデイについてはhttp://www.nes-k.gr.jp/tosaka/参照)、前橋で活動中のインターネットつなぎ隊より佐藤先生、氷上郡教育委員会で長らく情報教育、そしてネットデイと関わってこられた岸田先生がそれぞれ講演された。活発な質疑などで時間がオーバーしたため、最後のNeS-K『棟梁』による検討会では、検討というよりは配布されたマニュアルに沿って、翌日参加者に向けた注意事項の伝達が行われた。
NeS-Kのメンバーは、講習会の裏番組で、翌日に先駆け既に一部の工事を始めている。いくつか存在している難工事箇所の下工事、一部の基幹回線をあらかじめ引いておくなどの作業を行っておき、ネットデイ当日の負担を軽くし、作業をスムーズに行うためである。残念だったのは、時間的な制約もあったのだが、氷上でのネットデイで実施してきたように、ネットデイ前日の段階でフロア間をつなぐタテ系統のケーブルを総て通しておくことが出来なかったこと。これが翌日の作業の遅れにつながることになった。
実施技術講習会終了後は、滋賀大学附属のセミナーハウスに移動して、実行委員会メンバーと参加者有志が会議という名の夕食会兼宴会に臨む。ここで翌日に向けた検討が行われているのだが、カゼによる高熱でダウンした棟梁が、その検討に参加できなかったのは痛かった。リーダーの体調不良は作業効率のダウンを招き、やはり宜しくない。
ワークショップ2日目・ネットデイ
【プログラム】
附属中学校は、普通教室(9教室)など20箇所に配線し、情報コンセントを設置。
附属小学校は、特別教室など12箇所に配線し、情報コンセントを設置。
(普通教室へはすでに配線済み、モール処理のみ実施)。
09:00 受付開始
9:30 - 09:45 あいさつ
09:45 - 12:00 作業(小学校・中学校)
12:00 - 13:00 昼食休憩
13:00 - 14:00 LANケーブルの成端技術講習会(両校合同)
指導=三輪吉和氏(株式会社ジェプロ)
14:00 - 16:00 作業(小学校・中学校)
16:00 - 16:30 開通式
16:30 終了予定

いよいよネットデイの当日である。146名の参加者が集まり説明が行なわれた後、各フロア毎の班に分散、作業にとりかかる。
ある程度の下準備をしていたとはいえ、前日までの下準備の遅れ、難工事の連続(特に中学校1F)、室内での大量のモール貼りと、モールカッターや振動ドリルの運用のまずさ(振動ドリルは各フロアに1つずつ、確保出来たのだが、各フロアでドリル専属の人間を置かなかったために、空いているドリルを他フロアの参加者が持っていって結果的に行方不明になってしまう、堅いコンクリートに手回しドライバーでネジを入れることも。反省点)、情報コンセントなど小学校と中学校で使用する部材が異なっており、さらに部材に通じた部材管理専門のNeS-Kメンバーをおかなかったために起きた局所的な部材不足、小中の先生方を、あらかじめNeS-Kのネットデイに招待し、ネットデイとはどのようなものかを体験して頂けなかったことなど、後日、反省点は山のように出てきた。しかしながら、地元の方が大量の脚立を貸して下さったこと、電気工事や室内工事に慣れた方が少なからず参加して下さったこと、保護者の方々の協力など、多くのみなさんの協力があって、全教室への配線が終了(後日、配線のチェックと修正のために、NeS-Kメンバーが改めて訪れる必要はあったけれども)したことは間違いない。宮田先生の言を借りれば、「ネットワークケーブル自体は、か細い線ですが、その電子的なネットワークの向こうには人間の絆、太いヒューマンネットワークがある」ことに気づいた方も多かったのではないかと思うし、現にネットデイ終了後のメーリングリストで、参加者からのレスポンスを読んでいると、それぞれの地域でこのネットデイで得たものを活かしていこうとされている方が沢山おられたり、今回のワークショップ形式での開催は、大きな成果を得られたのではないかと思う。また、ネットデイに向けた準備、そして当日の人的交流などをみれば、ネットデイは決して安い配線業者のかわりではない、むしろそこから地域・そして地域を超えて拡がっていく人の輪にこそ、ネットデイの真の意義があると言えるだろう。

写真:昼食後のケーブル講習会。当日は中学校の生徒も参加している。コネクタを自分で成端し、テスタで性能を計測。測定値の上位入賞者には学校から賞品もプレゼントされた。
最後に。附属中学校では先生方が現在、ネットデイで整備された校内LANを利用した実践を計画されており、また、小学校でも研修が行われる予定であると先日お伺いした。ネットデイを機会に、子どもたちが学ぶ環境がより良いものになりつつあること、そして今後の展開が期待されることを知り、『棟梁』を勤めさせていただいた者としては、この上ない喜びである。ネットデイサミット'99ワークショップin滋賀の実現に尽力して下さったみなさん、そしてワークショップに参加して頂いたみなさんに、心から感謝したい。
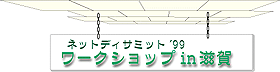 |
山城 新吾 |
|
|
次へ → |